| 連載 第18回 |
再生医学・医療のフロントライン | ||
末梢神経の再生
| |||
 事故などによる末梢の損傷は,修復しきれない例が多い。その他,一般的手術に伴って,末梢神経を切断せざるを得ない臨床例も多い。末梢神経の損傷では,直接吻合以外は自家神経移植が唯一の対策であった。しかし,その成績は決して満足できるものではなく,知覚,運動能力の回復も悪く,過誤支配による後遺症もみられる。また,採取部の痛みや知覚の欠損などの後遺症ばかりでなく,患部の知覚異常,特に「cold tolerance」と呼ばれる疼痛に悩まされている患者さんが多い。
事故などによる末梢の損傷は,修復しきれない例が多い。その他,一般的手術に伴って,末梢神経を切断せざるを得ない臨床例も多い。末梢神経の損傷では,直接吻合以外は自家神経移植が唯一の対策であった。しかし,その成績は決して満足できるものではなく,知覚,運動能力の回復も悪く,過誤支配による後遺症もみられる。また,採取部の痛みや知覚の欠損などの後遺症ばかりでなく,患部の知覚異常,特に「cold tolerance」と呼ばれる疼痛に悩まされている患者さんが多い。
人工的な材料による接合チューブを用いて,末梢神経のギャップを連結して神経を再生させようという試みは,1980年代初め頃から盛んに行なわれてきた。
しかし,非吸収性の合成人工材料による接合チャンネルの研究は,ことごとく失敗に終わっている。その解決のためには,神経束の再生の間,(1)外部からの結合組織の侵入を防ぐ,(2)チャンネル内外の物質交流あるいはチャンネル壁に毛細血管の新生が必要,(3)チャンネル内に軸索やシュワン細胞の増殖に適した足場となる物質が必要,(4)再生後は材料は分解吸収されたほうがよい,などのことが考えられている。これらの条件を考えて,生体内分解吸収性材料による人工神経接合チューブの研究が行なわれるようになった。
人工神経接合チャンネルの開発
生体内分解吸収性材料としては,これまでに,天然材料であるコラーゲンや合成材料であるポリグリコール酸など,いずれも生体内で分解を受け,吸収消失する材料が検討されてきた。しかし,いずれの報告も自家移植を超えることはできていなかった。そこで筆者らは,臨床に応用できる人工神経接合チャンネルの開発をめざして,抽出コラーゲンと分解吸収性人工合成材料とのコンポジットチャンネルの研究を行なった。
生体内分解吸収性のポリグリコール酸(PGA)のメッシュチューブに,豚皮由来の酵素抽出I型コラーゲンをコーティングし,150℃,24時間の強力な熱脱水架橋処理を行なって,人工神経接合チャンネルとした。これは,PGAが生体内で約3か月以上形を保ち,結合組織の防壁となりうること,および,これにコーティングしたコラーゲンが組織再生を促進する活性基に富んでいることを利用したものである。
ネコの坐骨神経25mmのギャップを接合し,チャンネル内に成長因子をふくんだコラーゲンゲルを充填して検討した。シュワン細胞,有髄軸索を含む神経構造が確認され,HRP染色で再生坐骨神経と脊髄および延髄間の軸索輸送の回復も証明された。知覚電位が4週間後に出現し,筋電図が8週間後に出現したが,正常神経に比べて反応の遅れが見られた。歩行パターンは14週間頃から歩行し始めたが,正常の歩行パターンを示すには7か月を要した。回復期間があまりにも遅いため,さらにしっかりした足場を導入することを考えた。
そこで,コラーゲンコーティングPGAチューブ内にI型コラーゲンを微細線維化したスポンジ構造として充填し,しっかりとした3次元の足場を組みこんだ。イヌの総腓骨神経の80mmギャップを接合した。その結果,80mmの長さにもかかわらず,1か月で知覚電位,筋電図が出現し,再生した軸索の数,太さは十分正常に近い像を示し,3か月で正常歩行を開始した(図1)。
臨床での応用
この成績を得て,十分臨床に使用しうると判断し,2002年3月から臨床患者さんに試験的に適用し始めた。現状でも約30例の患者さんに使用し,いずれもきわめて良好な結果を得ている。例をあげると,直腸癌の手術で合併切除された下腿の閉鎖神経25mmの接合例では,1か月で運動と知覚を回復して退院された。
外傷例では,手指,下肢などの陳旧例で長年,接合部に激痛が続き,手指運動や歩行が不能であった患者さんに,再手術を行なって疼痛は即刻消失し,1か月-1か月半には知覚運動を回復されている。長年変性に陥っていた神経がこの方法で正常化することは予想以上の効果であった。
今後は,10cm以上の長い欠損の修復,引き抜き事故のような神経根部からすべて損傷を受けている例の治療法,さらにはまだ未解決の自律神経系の修復が可能となる方法などの大きな課題が残されているが,基本的には見通しはついたと言える(図2-4)。
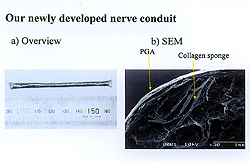 図1 コラーゲンPGA人工神経接合チューブ |
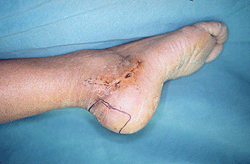 図2 下肢をショベルカーで削り取られた持続性の疼痛のため片足歩行になっていた(再手術前) |
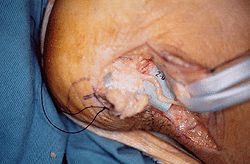 図3 再手術,術中写真。巨大な神経腫となっている |
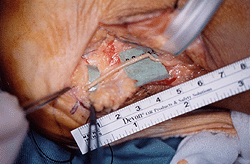 図4 同例で神経腫を切除し,人工神経接合チューブで再接合したところ,末梢側が変性している。術後,両側歩行となる |
