| 連載 第19回 | 再生医学・医療のフロントライン | ||
ES細胞
| |||
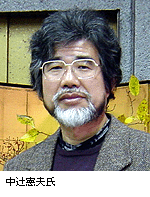 京大再生医科学研究所では,国内で唯一ヒトES細胞株の樹立計画を進めている。多能性幹細胞としての優れた性質を持ち,ウイルス感染などの問題のないヒトES細胞株を国内で樹立することによって,権利関係などの制約のない形で自由に研究に使用できるES細胞を国内の研究者に分配して広く利用できることをめざしている。
京大再生医科学研究所では,国内で唯一ヒトES細胞株の樹立計画を進めている。多能性幹細胞としての優れた性質を持ち,ウイルス感染などの問題のないヒトES細胞株を国内で樹立することによって,権利関係などの制約のない形で自由に研究に使用できるES細胞を国内の研究者に分配して広く利用できることをめざしている。
海外から輸入したヒトES細胞を使用する場合には,権利保有者との契約によってさまざまな制約を受けることになる。政府指針によれば,ES細胞株の樹立機関は,作成したES細胞を,政府から使用研究の承認を得た研究機関に対しては,無条件で無償または実費のみで分配する義務がある。
ES細胞を利用した治療法
ES細胞は無限の増殖能と多分化能を持つことから,体をつくるすべての種類の細胞を無尽蔵につくることができる。傷害を受けたり欠損した組織細胞を修復するために必要な,あらゆる種類の細胞を大量に供給できることになる。ES細胞を未分化な多能性幹細胞の状態で増殖させ,目的とする細胞種へと分化させた後に,必要な機能を果たす分化細胞を選別して,患者への移植治療に使うのが目標である。脳内のドーパミンを分泌する神経細胞が死滅するパーキンソン病,神経細胞が死んでいくアルツハイマー病,脊髄の中の神経繊維が事故などで断ち切られた脊髄損傷,インスリン分泌細胞が正常に機能しない糖尿病,肝臓細胞の機能が低下する肝硬変,心筋細胞が死滅して心臓機能が低下する心筋梗塞などがあり,その多くは社会の高齢化とともにますます増加している。画期的な治療法として,ES細胞からつくり出した正常機能を果たす健康な細胞を必要な部位に移植して機能を回復させるのが細胞治療である。もっとも早期に実用化が期待されるパーキンソン病については,3-5年後に臨床試験が始まると予想される。課題は免疫拒絶反応
ES細胞を使った細胞治療の場合,同種異個体(異系統)間の免疫拒絶反応の問題が存在する。脳内への移植は免疫的隔離が存在し,拒絶反応を臨床的に克服できると思われるが,その他の組織や臓器に関しては拒絶回避が必要である。ES細胞に内在するMHC遺伝子の一部を破壊したES細胞株をつくることは可能であり,免疫拒絶反応を完全に抑えることは不可能としても,免疫抑制剤と共用することによって対処できるかもしれない。移植免疫の問題を根本的に解決するために,患者の組織から採取した体細胞の核を除核卵子に移植することによって初期胚をつくり,患者本人のゲノムを持つES細胞株を樹立する可能性が考えられるが,倫理的問題に加えて,成功率が実際の治療にとって許容される範囲なのかは不明である。
テイラーメイド型幹細胞の可能性
著者の研究室の多田高・多田政子らは,ES細胞の中にも卵子と同様に体細胞の初期化を引き起こす能力があることを見いだした。マウス体細胞とES細胞で4倍体の融合細胞をつくったところ,ES細胞と同様の多能性幹細胞の性質を示した。体細胞に由来する染色体やゲノムは,分化後の体細胞の状態からES細胞の状態へと変化していた。これを利用することによって,拒絶反応を起こさない多能性幹細胞が現実のものになる可能性がある。融合細胞は長期間増殖可能で多分化能を持っていた。同様のことがヒト細胞でも可能であれば,患者の体細胞とヒトES細胞を融合させた場合に,半分のゲノムは患者本人のものであるES様細胞をつくることができる。残りの半分はES細胞由来であるが,拒絶反応を引き起こす原因となる抗原遺伝子を壊しておけば,細胞表面抗原が患者本人のものにきわめて近い4倍体ES様細胞を,各々の患者に適合するテイラーメイド型幹細胞としてつくることが可能となる。つまり,ヒト卵子を必要とせずクローン胚もつくらない方法で,拒絶反応を起こさない多能性幹細胞をつくることが可能になるはずである。
ES細胞に関して,京大再生研ES細胞作成プロジェクト(編集室註:責任者=中辻氏)では,今年1月に国内初の人間の受精卵を用いたES細胞作成実験に着手した。
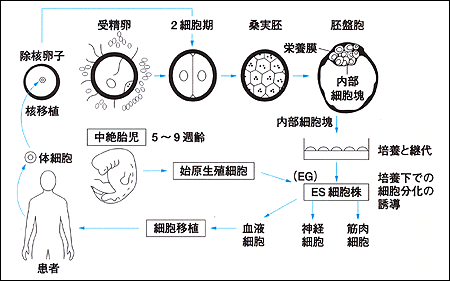 図 胚盤胞からのヒトES細胞株の樹立,機能細胞への分化,および細胞治療への応用。中絶胎児から採取した始原生殖細胞からはES細胞と類似のEG細胞をつくることができる。体細胞核を除核卵子へ移植したクローン胚からES細胞をつくる可能性も検討されている |
