新春随想
2003
次世代の医療を支える医師を育てるには
星 北斗(日本医師会常任理事) インターン制度が廃止されて以来,細分化された専門領域にそれぞれのフォーカスを持つ医局講座が,社会が専門医を希求していたことを受け止めて,医師養成の責任をある面で愚直なまでに果たしてきたと言えるだろう。しかしながら,さまざまな方面からの弊害の指摘に関してはことさらに説明を要しまい。ある意味で,われわれ医療界全体が社会からの要請の変化を受け止めきれなかったのかもしれない。
インターン制度が廃止されて以来,細分化された専門領域にそれぞれのフォーカスを持つ医局講座が,社会が専門医を希求していたことを受け止めて,医師養成の責任をある面で愚直なまでに果たしてきたと言えるだろう。しかしながら,さまざまな方面からの弊害の指摘に関してはことさらに説明を要しまい。ある意味で,われわれ医療界全体が社会からの要請の変化を受け止めきれなかったのかもしれない。
平成16年以後に医師免許を取得した者は,2年間一定の要件を満たす施設で研修に専念し,これを終了していない者が診療所を開設する場合や病院の管理(病院長)をする場合の制限が定められ,この問題に関して現在もなおさまざまな議論が行なわれているところである。
大学病院で行なうことの是非
ある大学では関連病院の囲い込みに勤しんでいると聞く。わが大学が近在唯一の研修医療機関の総本山として君臨したいのだろう,関連病院に医局からの医師の派遣を打ち切ることを仄めかしながら忠誠を誓わせているその姿は,間違いなく時代遅れの封建主義の再来と嘲笑の的となろう。厚生労働省の検討会において日本医師会は,「大学病院が特定機能病院となっていることを踏まえ,ここでの臨床研修を原則禁止すべし」とぶち上げて物議を醸したが,この方針は同省の臨床研修に関する文書に明記されている。いつまでも大学や医局がすべての医師養成に関する責任を持ち得ようか,答えは簡単,「ノー」である。それなら誰がこれからの主役になるのか。第一線で医療の実践に打ち込んでいる地域の医師が,先輩として後輩の育成にあたるべきではないのか。これが答えである。
費用の問題を第一に言うなかれ
地域における臨床研修を考える時,まず話題に上がるのがその費用負担の問題である。曰く「国が研修を義務化したのだから,すべての費用は国が負担すべきである」と。司法修習生に倣ってそうあるべきだとする意見は根強い。もちろん,国が多くを負担すべきとする意見には賛成するが,全額,しかも研修医の給与,指導医の手当をもすべて支払えというのはいかにも乱暴である。インターン制度の問題点を踏まえて,研修医も医師である限り医師として法的にも取り扱われる(例えば医療法上の医師数にカウントされる)ことや,保険医としての登録については,重要な身分上の取り扱いとして主張していて,一方で認められていることであるのだ。次世代を担う医師の養成に先輩医師であるわれわれが何らかの形で力を注ぐことは,当然のことであり,対価が得られないから協力しないという専門集団が本当に社会から認知されるであろうか。研修医がすべて国家公務員のように取り扱われて,金さえくれるなら厚生労働省が求めるような医療を実践する医師の養成を皆が好んでするというなら話は別である。
誰が教えるのか
大学の主張の1つに,地域の医療機関にはろくな指導医がいないというものがある。厚生労働省の規定では臨床研修の期間を含めて7年以上のプライマリケアに関する臨床経験があり,十分な指導の時間が取れる者と定義されている。大学の臓器別医療の実践がこれに相当するとは思えないし,大学にこそ適切な指導医がいるのかと疑いたくなる。地域医療に熱意を持って大学を離れた者を落伍者と決めつけて指導能力がないということが誰にできるであろう。当然,地域医療の実践者であるというだけで指導医として適任だとは思ってはいない。指導医の研修は不可欠であり,日本医師会生涯教育の制度に,近く指導能力開発のプログラムを加えることを検討していることも付け加えておく。
私は大学や医局と喧嘩し,争うことが本意ではない。大学には大学の使命を全うしてほしいからこそ敢えて苦言を呈しているのである。世界レベルの研究開発や優れた専門医の養成は大学にしか担えない重要な機能であろうし,その担い手も必要であることは疑う余地がない。また,今回の義務化は過渡期の産物であると信じたい。大学での学部教育に多くの要素が吸収され,地域医療との共存が大学で実践されるようになれば,自ずと消えていくものであろう。
日本の大学医学部どこへ行く
西岡 清(東京医科歯科大学附属病院長,全国医学部長病院長会議会長)変革の大波が押し寄せる日本の医学部
 この十数年間,日本の大学医学部に変革の大波が押し寄せている。医学教育の共通カリキュラムが作成され,共用試験の施行が行なわれるようになり,卒後臨床研修の義務化,医療費支払いに対して包括評価の導入,また,国立大学では国立大学法人化と矢継ぎ早に改革の波が押し寄せてきている。
この十数年間,日本の大学医学部に変革の大波が押し寄せている。医学教育の共通カリキュラムが作成され,共用試験の施行が行なわれるようになり,卒後臨床研修の義務化,医療費支払いに対して包括評価の導入,また,国立大学では国立大学法人化と矢継ぎ早に改革の波が押し寄せてきている。
共通カリキュラム,研修義務化,包括評価の導入
共通カリキュラムの導入に対して,必ずしもすべての大学人が賛成しているとはいえないのが実情である。一定の基本カリキュラムで学習することはよいが,そのカリキュラムの範囲をもって医学の基本的知識を習得したとする教員,学生が増加することに危機感を覚えているからである。医学部に入学する学生は,柔軟な受容体と許容力を持っているはずである。共通カリキュラムには,アドバンスドコースが付加されているが,アドバンスドコースがどの程度内容豊富なものとなるかは各大学に委ねられており,いかにすばらしい医療人,医学者を育成するかが,これからの課題となろう。平成16年度から義務化される卒後臨床研修制度は,「プライマリケアの基本的臨床技能を身につける」ことが目的とされ,研修医を大学病院から離し,一般病院に配置させることが施策として考えられている。これまでの大学の研修医教育が十分でなかったことに対する反省はあるが,研修医を一般病院に移すだけで問題が解決されるのだろうか。研修医問題の一番の根源は,研修医に対する処遇の確保であったが,この問題についてはいまだ未解決のままである。
国民は,何でもできる医師を要求し,同時に,それぞれの分野における最高の医療を提供できる医師を期待している。この期待にどのように応えられるのだろうか。
大学病院が中心となっている特定機能病院に対する包括評価方式の導入が決定されている。包括評価とは,医療費の必要度を中心とした疾病を分類して診断群を作成し,その診断群分類に従って医療費支払いを行なおうとする制度である。同じ疾患であってもその診断・治療経過が個々の患者で大きく異なるのが大学病院の医療である。このような患者を扱うことが義務づけられている大学病院に,平均化した形の医療費支払いを行なおうとすることが,医療を受ける患者にとってどれだけメリットがあるのだろうかという疑問が残る。
大学のあり方を根本的に考え直すべき
昨年の11月24日の産経新聞に興味ある記事が掲載されていた。ワシントン支局の古森義久氏の記事と京都大学の吉田和男氏の記事である。古森氏は,ジョージタウン大学でのダライ・ラマの代理人である台湾在住のツエジャム氏の講演会について報じている。台湾の李登輝氏が慶応大学で講演することを拒否した日本に比べて,大学の開放度がいかに大きく異なっているかを示すものである。吉田氏は日本の高等教育に対する力の入れ方の少なさを指摘している。義務教育に対する支援は,この10年ほどの間に2倍に増加したにもかかわらず,高等教育に対する支援はそのまま放置され,何らの支援も行なわれていないことを指摘している。日本は,プロフェッショナルを大切にしない国である。日本の医療技術をはじめとする科学技術に対する評価は,非常に低いものとなっている。2002年のノーベル賞受賞がすべて科学技術に対するものであることから考えると,この国が,どこかおかしい状態に陥っているとしか言いようがない。科学技術大国を自負する日本が,古い伝統を持つ欧米の大学と伍するためには,大学のあり方を根本的に考え直すべき時期にきているのでなかろうか。
新しい年と新しい仕事
名郷直樹(作手村国民健康保険診療所)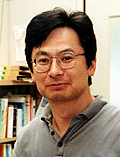 この春,長年勤めた僻地診療所を離れ,臨床研修指定病院に移動することとなった。山間僻地から都市部へと生活環境の変化だけでなく,臨床を中心とした活動から教育を中心とした活動へと,仕事内容も大きく変化することになりそうだ。そのうえ,娘の高校進学,下の息子の中学進学も重なり,自分自身の家族ライフサイクルにとっても大きな節目かもしれない。しばらく腰をすえて僻地医療に打ち込もうと考えていた自分自身にとって,大きな決断だった。ただ大きな決断だったというわりには,あまりよく考えずに決めてしまったような気もする。
この春,長年勤めた僻地診療所を離れ,臨床研修指定病院に移動することとなった。山間僻地から都市部へと生活環境の変化だけでなく,臨床を中心とした活動から教育を中心とした活動へと,仕事内容も大きく変化することになりそうだ。そのうえ,娘の高校進学,下の息子の中学進学も重なり,自分自身の家族ライフサイクルにとっても大きな節目かもしれない。しばらく腰をすえて僻地医療に打ち込もうと考えていた自分自身にとって,大きな決断だった。ただ大きな決断だったというわりには,あまりよく考えずに決めてしまったような気もする。
強く認識した教育の重要性
ここ数年,僻地医療の実践の傍ら,学生教育,研修医教育,生涯教育に携わってきた。その中でもEBMの実践と教育という部分にはとりわけ力を入れてきたが,その中で教育の重要性,さらにその教育内容よりも形式の重要性についてはっきりと認識するようになった。臨床だけでなく,教育もやりがいのある楽しい仕事であることを実感した。ただ臨床を実践する中でしか教育できないという思いと,臨床の片手間に十分な教育はできないという相反する思いの間で常に引き裂かれ,いつまでも今の状況でやれるわけでないことは何となく感じていた。とりあえず今やっていることが臨床中心なので臨床中心にやってきた,それだけだったかもしれない。そして少々臨床に疲れてきて,今度は教育中心にやってみたい,何となくそんな気持ちが強くなってきた。そんなところである。
やりたいことは1つ
ただ臨床,教育といっても,やりたいことは1つ。私自身医師として,必要なほとんどすべてを僻地医療で学んだ。もっと正確に言えば,僻地医療の中で出会った多くの患者さんから学んだ。にもかかわらず医師過剰といわれる中でもまだまだ僻地での医師不足は深刻だ。都市部の過剰に反比例して,僻地ではますます不足している感じもある。そうした僻地の医師不足に対し,自分ががんばるというだけでなく,単に医師を送り込むというだけでなく,最高の僻地医療を提供するために,最高のトレーニングを積んだ,最高の僻地専門の医師を,日本全国の僻地に派遣したい。そしてそのような教育システムが定常的に動き出したら,自分自身ももう一度僻地医療の現場で働きたい。春を待つ気持ち
新しい年と新しい仕事,自分自身の僻地医療に対する壮大な思いはしばらく封印しよう。発想は大胆に,着手は慎重に。まずは,臨床研修病院で,臨床医とは一線を画す教育専門の医師としての立場を確立すること,眠くならないカンファレンスを企画すること,論文がどんどん読みたくなるようなジャーナルクラブを開催すること,指導医も研修医も6時か7時には夕食がとれるような職場環境を作ること。不安と期待が入り混じった,進学を控えた子どもと同じ気持ちで,そんなふうに言うと子どもは怒るかもしれないが,そんな気持ちで,この春を待っている。夢で終わらせない
伊藤隼也(写真家・医学ジャーナリスト協会会員) 20XX年。ホーム印刷の朝刊を読んでいて,ある記事が目についた。「心臓手術後院内感染で患者死亡!」久しぶりに目にする医療事故報道だった。いまどき術後に感染による死亡とは……よほど重大な問題があったに違いない。誰かの陰謀かな?
20XX年。ホーム印刷の朝刊を読んでいて,ある記事が目についた。「心臓手術後院内感染で患者死亡!」久しぶりに目にする医療事故報道だった。いまどき術後に感染による死亡とは……よほど重大な問題があったに違いない。誰かの陰謀かな?
同時に,医療事故防止や医療改革に情熱を燃やし,今想うと気恥ずかしくなるような青臭い日々を過ごしていた遙か20年以上前の日々を思い出した。
「改革」は成功した
多くの病院で院内感染による患者死亡が当たり前のように起こり「手術は成功しましたが合併症でお亡くなりました……残念です」という言い訳が平気で通用していた酷い時代。振り返って「いい時代になったなあ」と実感した。あの当時,戦後50年以上続いてきたわが国の医療制度は,国民皆保険という世界に冠たるシステムを持ちながらも,財政問題ではその存続が危ぶまれ,その他にもマンパワーや医療の質など多くの問題を抱えていた。疲弊した制度が時代の変化に追いつかず,抜本的な改善をできないままに国民医療が彷徨っていた時代とも言えよう。それらの歪みは医療にとって最も大切な医療者=患者という「癒しの出発点」にも大きく暗い影を落とした。
99年1月・2月に相次いで起きた,横浜市大・都立広尾病院での医療事故をきっかけに,それまで少しずつ蓄えられた医療不信へのエネルギーは倍増され,東京女子医大事件で臨界点に達したようだ。
病という同じ目標に向かう者が互いを尊重できない……なんて悲しいことだろう。その後の数年も,いろいろな混乱が生じた。特に,印象深いのは2004年から始まった臨床研修医の制度改革だった。
当初は,さまざまな問題と混乱が生じたが,10年ほどが過ぎると,改革と呼ぶに相応しい成果もあがり始めた。
今でも,あの旧態然とした時代が懐かしいという医師もいるが,かつてあれほど権勢を誇った旧医局講座制度は今や影も形もない。医局支配を終焉させるきっかけになったといわれる研修制度は,多くの自由で優秀な医師を生み,その後の日本医療の発展に大いに貢献した。今日の患者と医師の関係を考えればいまさら語るべくもないだろうが。新鮮な教育理念の実践は,21世紀医療におけるグローバルスタンダードと言われた説明責任と透明性の確保も十分理解し実践した。
世界一の医療産業国に
その後,欧米医療機関の日本上陸,医師免許の国際標準化,など時代の激変を乗り切るために,医師免許更新制,医療のQC(品質管理)コントロール,患者中心の医療理念の実践,医療事故救済機関の設立,看護師や医師などの人的資源や,必要にして十分な財源の投入など,多くの改善を国家レベルで実践したことが見事に結実した。かつて,世界の誰も経験したことのない高齢化社会突入をもってして,なお,世界一の医療産業国として,数万人を越える来日患者や国際医師免許養成国家などで奇跡の復活を遂げた日本医療の姿を振り返ると複雑な想いも去来する。医師免許更新不能な医師,淘汰された多くの病院や診療所,閉鎖された医学部,潰れた医大,倒産・統合した薬品会社,保険制度破綻で救えなかった命……。
しかし,当時の改革で,国民的コンセンサスを得るため,医療界が自ら進んで行なった大英断こそが日本医療改革の求心力になったのは疑うべくもない。また,それらが多くの命や医療者に未来を見せた。まさしく歴史に残る決定だ……う~ん。
「パパ,朝だよー」 また,息子が布団の上で暴れている?
何と2003年の初夢だった!
(想いはそれぞれですが,医療を良くしたい気持ちは一緒。患者と医療者の団結こそが改革に繋がると信じて疑わない)
ホスピスケアからコミュニティケアへ
山崎章郎(聖ヨハネホスピスケア研究所長/聖ヨハネ会桜町病院ホスピス科部長) 私は,2001年10月から2002年9月末までの1年間休職し,ホスピス現場を離れた。理由はいくつかあるが,その1つについて触れてみたい。
私は,2001年10月から2002年9月末までの1年間休職し,ホスピス現場を離れた。理由はいくつかあるが,その1つについて触れてみたい。
ホスピスのあり方への疑問
ここ数年間,私はわが国のホスピスのあり方に疑問を感じるようになっていた。それは,患者さんたちの尊厳を守ろうとし,またご家族も支援していこうとするホスピスケアが,ほとんど癌末期の患者さんやご家族だけに提供されているという事実に対してであった。これには,厚生労働省の施設基準を満たし,緩和ケア病棟としての認定を受けたホスピスは,医療保険の制度上,主に癌とエイズの末期患者さんがケアの対象になるというやむを得ない理由もある。けれども,慢性疾患の患者さんも,その末期になれば癌末期の患者さんたちと同じような心身の問題に直面するのだし,さらには高齢の方も,たとえ病気がなくとも,その人生の終わりの頃には誰かの助けがなければ,その尊厳を保つことが難しくなる。痴呆症の方たちだって同じだろう。
全人的ケアをめざすホスピスケアは,そのような方々にも必要なはずなのに,そして,私たちはそれらのニーズを感じているのに,それに応える努力があまりにも少なかったように思い始めたのである。
そして,それらの問題を放置したまま,今までのように主に癌末期の方を対象にしたホスピスケアを続けていくことは,私にはもはやできないと思い始めるようになったのだ。これが休職を決意した理由の1つである。
それでは一体どうしたらよいのだろう。
この問題が頭を占めるようになってから,ケアハウスやグループホームなどに取り組んでいる高齢者福祉の世界に解決のヒントがありそうだ,と考えるようになっていた。
デンマーク型の「ケアタウンたかのす」に学ぶ
そこで休職中に,北欧,特にスウェーデンの福祉事情を視察してこようと考えた私は,昨年5月に北欧の福祉事情に造詣の深い前朝日新聞論説委員で現大阪大学大学院教授である大熊由紀子氏に相談してみることにした。大熊氏は,北欧に行くのであれば,今はスウェーデンよりもデンマークのほうがよいと言い,デンマークに行くのであればその前にデンマークをモデルに高齢者福祉に取り組んでいる,秋田県鷹巣町を訪問するように薦めてくれた。6月になって,私は鷹巣町を訪問し,行政と住民が作り上げた「ケアタウンたかのす」という福祉の複合施設などを視察した。そこには痴呆老人の方も,高齢独り暮らしの方もそれぞれプライバシーを保証され,生活を楽しみながら,十分な介護や看護を受けて暮らすことのできるコミュニティが出現していた(もちろん鷹巣町はケアタウン内だけでなく,町内の在宅で暮らしている人々の手厚い支援もしている)。
私はこれだと思った。つまりこの「ケアタウンたかのす」の機能と聖ヨハネホスピスの経験を活かした往診中心の有床診療所が合体することで,末期癌のみならず,他の疾患の方に対しても,また高齢者の方に対しても,在宅や在宅に近い療養環境の中で本来的なホスピスケアが提供できるのではないかと考えたのだ。
高齢者福祉・在宅ケア・ホスピスケアが融合するコミュニティケア
その後の9月に,幸いにも大熊氏とともにデンマークを訪れる機会があり,そこでの福祉や医療の取り組みを視察することができた。そして,高齢者福祉と在宅ケアにも重点を置いたホスピスケアとの調和のとれた融合が,私が直面した問題の解答であると確信するようになったのだ。私はこれをホスピスケアをも含む地域としてのケア,すなわち「コミュニティケア」と位置づけ,このコミュニティケアの実現が今後10年の私の仕事であると考えるようになった。このことが昨年1年間休職をした中での最大の収穫であったと思っている。今後は,この新しい視点で社会に貢献していくことができればと願っている。


