〔連載〕医者が心をひらくとき
A Piece of My MindJAMA(米国医師会誌)傑作エッセイ集より
|
(前回2513号)
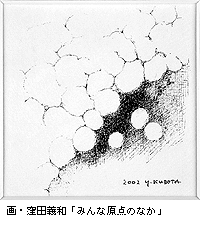 「前の医者も本当の間抜けだったけれど,あんたもそうに違いない!」
「前の医者も本当の間抜けだったけれど,あんたもそうに違いない!」
これが,私と最初に話したときのフィルの結論だった。インターンになって2か月目,癌病棟の1日目だった。私は病室から病室へと,自己紹介をして歩いていたのだが,フィルはぐっすり眠っていた。枕元には「注意――昼は熟睡中」と書かれた紙が貼られていた。私はフィルの身体を揺すって起こしたが,すぐに自分が間違いを犯したことに気がついた。
「あんた,字が読めないのか,ばか野郎」
と彼は叫んだ。「この紙を貼ってあるのには理由があるんだぞ」
彼は,さらに,医者全般,とりわけインターンに関する彼の評価は非常に低いものであることを私にはっきりと理解させた。
「僕は,毎日,少なくとも正午まで眠るんだということを,絶対に忘れるなよ!」
フィルは6フィート2インチ,青く,透き通るような目をしていた。19歳だったが,急性リンパ性白血病の再発で再入院したのだった。化学療法の結果,金髪の髪はわずかしか残っていなかった。日にちがたつにつれ,私は彼の病室でできるだけ長い時間を過ごすようになっていた。私は彼の質問に答え,数え切れないほど施行された検査の結果を説明した。
ある日,私は,病気になる前はどんな生活をしていたのかとフィルに聞いた。
「白血病にやられる前は,ハーレーを乗り回し,毎晩パーティさ」と,彼は言った。
「ビール6缶を3分で飲み干したものさ」
確かにフィルは夜になると元気になった。ガンズ&ローズのお気に入りのTシャツを着て,M-16に似せた強力水鉄砲で武装し,看護婦たちを襲うのだった。ある夜,私が他の患者を診察しているとき,廊下から叫び声が聞こえた。病室から顔を出してみると,看護婦の1人のずぶぬれの顔に,フィルが最後の一撃を加え,さっと自分の病室に隠れるところが見えた。
フィルの母親は近くの工場で働いていたが,空いている時間は必ず彼の病室で過ごした。病室の片隅に簡易ベッドを置き,夜はそこで眠ったのだった。
「ママ」ある夜,私は,フィルが母親に泣きついているのを聞いてしまった。
「吐き気がどうしても止まらないよう。吐き気止めの特別の薬も,ちっとも効かない」
「つらいわね。目をつぶって。何も考えないようにするの」彼女は,フィルの耳元にささやいた。「眠れるように,おでこに冷たいタオルを置いてあげるわね」
細くか弱い腕で,彼女はフィルの巨大なからだを抱きしめた。やがて,フィルの嘔気は治まった。
2週後,目を奪うようなブルネットの美人がフィルの病室を訪れた。背が高くすらっとした,緑色の目をした女の子だったが,午後の間ずっとビルの病室で過ごしたのだった。いったい誰なんだろうと私は興味を持った。
見舞客が帰った後,フィルは疲れてぐっすり眠っていた。私は,枕元に掲示してある警告の内容が変わっているのに気がついた。
「インターンは,見つけ次第,射殺する!」
私は身体をそっとつついてビルを起こすと,
「あの緑色の目をしたかわいい子は誰だ?」と聞いた。
「先生,あんたは初め考えたほど大間抜けではないかもしれないけれど,俺にも言えないことってのはあるんだ。あんたの知ったことではないし,あの子は誰なんだと夢でも見てうなされるんだな」
「新しい警告に変えたようだね」
と,私は枕元の掲示を目で指した。
「そう,そして,意味は書いてあるとおりだ!」フィルはベッドの下からいきなり水鉄砲を取り出した。私は部屋から逃げようとしたが,冷たい水が頬に命中し,フィルは大声で笑った。
その日の遅く,私は,病室を訪れた女の子は誰だったのかを,フィルの母親に尋ねた。
「ルーシーといって,フィルのガールフレンドなの。あの子は,ルーシーが病室に来てくれるときが一番幸せなんだと思うわ」
1週間後のある朝,指導医との回診で,フィルの病室を訪れた。
「今日のご気分はいかがですか?」と,指導医が尋ねた。
「インターンが字が読めないのはわかっていたけれど,あんたも字が読めないようだな!」
「いま,何と言ったのかね?」
指導医が語気を強めた。返事をする代わりに,フィルは巨大なラジカセのスイッチを入れた。病室にAC/DCの「ハイウェイ・トゥ・ヘル」が最大音量で流れ出した。フィルは曲に合わせて歌いだしたが,指導医の顔は怒りで真っ赤になった。私は笑いをこらえようと賢明だった。その日遅く,私はフィルの病室に戻った。
「今朝は,羽目をはずしてごめん」
と,彼は言った。「ただ,病院での暮らしを続けていると退屈でしかたがないから。友だちも見舞いに来なくなったし」
「ガールフレンドはどうなんだい?」
と私は聞いた。
彼は,一瞬,言葉に詰まった後,静かな声で言った。
「死んでいく人と付き合うのは難しすぎるって言うんだ」
彼は,視線をそらし,手を頭に持っていった。
「俺には,髪の毛もないしね」
そのときになって初めて,私はフィルがどんな青年なのかということを理解したのだった。無作法で怒りっぽい外観の下には,死を恐れる,孤独な少年がいたのだった。私は,フィルが私の腕を払いのけないよう望みながら,やさしく彼の肩を抱いた。
「白血病を治す方法があったらいいのに」
と,フィルがつぶやいた。
「僕もそう思う,フィル。僕もそう思う」
そんなことがあった後,フィルは私を病室に招いてテープを聞かせてくれるようになった。
「前からずっと,ギターを弾きたいと思っていたんだ」ある日,フィルが打ち明けた。「バンドに入れてもらったと思った途端,病気になったんだ」
フィルは,大音量でラジオをつけ,目をつぶってギターを弾きならすのが好きだった。病気とは縁のない世界で,満員の聴衆を前に,ステージで演奏している自分を想像していたのだろう。私は,その世界をフィルに与えたかった。そして,2度と私の世界には戻ってきてほしくなかった。
フィルがようやく退院できるようになったのは,私の癌病棟でのローテートが終わる最後の週のことだった。私が病室にお別れを言いにいくと,フィルが水鉄砲を取り出すのが見え,私はとっさに隠れる場所を探した。
「心配しないで」と,フィルは言った。
「撃ちはしないから。今日家に帰るし,もうこれにも用はないから。でも,この水鉄砲のおかげで,先生は運動不足にならずにすんだでしょう。先生にこれをあげるから,看護婦たちが無茶を言ったら,撃ったらいい」
私は,水鉄砲を大事にすると彼に約束した。
それから,3日後の,とりわけ忙しい当直の夜のことだった。ようやくベッドで横になれると思った15分後にポケットベルが鳴った。
「近くの病院から電話があったんだ,ジョン」腫瘍科のフェローだった。
「フィルが,発熱と白血球減少で救急に来たそうだ。こちらに転送するということだが,1時間もすれば着くと思う」
私は眠い目をこすり,コーヒーを飲むと,白血球減少に伴う発熱についてすべきことを思い出そうと努めた。45分後,看護婦が,興奮して走ってきた。
「救急からの電話です。15分前にフィルが救急車の中で心停止を起こして,いま,ERで蘇生中です」
「お母さんは知っているの?」
「いいえ,まだこちらに向かっている途中です」
フィルは,挿管されていた。心マッサージを受けるたびに,彼の若い身体が跳ね上がった。一瞬,自発呼吸をしたかのように見えたが,呼吸が戻ることはなかった。心電図に目を向けたが,波形はまったく平坦だった。彼を生き返らせようとあらゆる処置が試みられたが,すべて無駄だった。
私は,消耗しきってERを後にしたが,突然,フィルの母親がまだ到着していなかったことを思い出した。お子さんは亡くなられたと,どうやって母親に告げたらいいのだろうか?
数分後,ナースステーションにいた私に,フィルの母親が歩いてくるのが見えた。私の険しい顔つきを見て,何が起こったかを彼女がすぐさま理解したことがわかった。
「お気の毒ですが,フィルは亡くなられました」私は言った。
「息子さんのために,もっとできることがあればよかったのですが……」
「先生,息子のことをかわいがってくださってありがとうございました。あの子も,わかっていました。どんな薬よりも,先生にかわいがってもらったことが,あの子にとっては一番助けになったのです」
フィルの母親がゆっくり歩き去るのを見送っていると,誰かが私の肩をたたいた。婦長だった。
「こんなときに,ごめんなさい。でも,ビリーという患者のことなんです」
婦長は言った。
「導入化学療法のために入院した患者です。看護婦全員であれこれ手を尽くしたんですが,泣きやもうとしないんです」。
ナースステーションの奥にしまってあったプラスティック・バッグを手にすると,私は婦長について,ビリーの病室へ行った。ベッドでうつ伏せになってしくしく泣いていたのは,8歳の男の子だった。
「こんばんは,ビリー。僕はジョンだ」
私は声をかけた。
「こんなとこ大嫌いだ!」ビリーは顔をさらに深く枕に埋めて泣くのだった。「遊ぶ道具もないし,白い服を着た女の人,僕の手におっきな針を刺したんだ。どうして,ほっておいてくれないの?」
「ビリー」私は言葉を続けた。「僕には特別の友だちがいたんだけれど,その人が退院する前にプレゼントをくれたんだ」
「それがどうしたって言うの?」
ビリーは,口をつぐんだが,好奇心には勝てなかった。彼は指の間から私のことをのぞき見たが,私がフィルの水鉄砲を手にしているのを見ると,大きく目を見開いた。
「僕の友だちだったフィルは,看護婦が変なまねをしたら,この水鉄砲でいつもお仕置きをしたんだ。ときどきは,僕のことも撃ったんだよ。つらかったけれど,この水鉄砲のおかげで,がんばれたんだ。フィルは,君にもこれを使ってほしいと思っているに違いないよ。試しに使ってみるかい?」
●本連載終了のお知らせ今回をもって本連載は終了とさせていただきます。ご愛読ありがとうございました。なお,本連載の原作の書籍『医者が心をひらくとき』(上下巻,各2000円+税)は,弊社より好評発売中です。 |
