| 連載 第15回 | 再生医学・医療のフロントライン | ||
聴覚機能の再生
| |||
難聴治療への挑戦
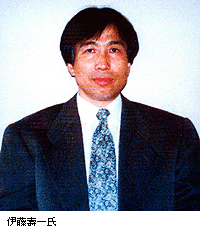 内耳感覚細胞(有毛細胞)の障害は音響暴露,各種薬物,加齢などによって生じる。この内耳有毛細胞は1度障害を受けると再生することは困難で,このため1度生じた感音難聴は治癒しないと考えられている。現在日本には補聴器を使用しても言葉の聞き取りが困難な高度難聴者が約30万人いると推定される。
内耳感覚細胞(有毛細胞)の障害は音響暴露,各種薬物,加齢などによって生じる。この内耳有毛細胞は1度障害を受けると再生することは困難で,このため1度生じた感音難聴は治癒しないと考えられている。現在日本には補聴器を使用しても言葉の聞き取りが困難な高度難聴者が約30万人いると推定される。
しかし,薬物などで感音難聴をきたした動物の蝸牛を検索すると,障害の比較的初期の段階では内耳の形態はほぼ正常に保たれており,内耳有毛細胞のみが障害を受けていることが多い。つまり,内耳有毛細胞の機能が何らかの方法で回復すれば,感音難聴も回復するのではないかと期待を抱かせる所見である。
一方,再生に関し,最近特に注目を受けているのが「幹細胞」である。幹細胞は自己増殖能と多分化能を持ち,種々の器官の元になる細胞であり,幹細胞の中でも神経幹細胞は神経細胞,グリア細胞の元になる細胞である。神経幹細胞はこれまで幼若な動物にのみ存在すると考えられてきたが,最近,成動物の中枢神経系,特に哺乳動物の脳室近辺や海馬でも見つかり,抽出・培養が可能となってきた。海馬由来の神経幹細胞を嗅球,網膜などに移植すると,移植部位の細胞に分化するという報告もある。つまり,この神経幹細胞は順応性,可塑性を有すると考えられ,内耳への移植ドナーの候補とも考えられる。
幹細胞移植による内耳有毛細胞の再生
この海馬由来神経幹細胞を内耳への生着,有毛細胞への分化への期待をこめてラットおよびマウスの内耳(蝸牛)に投与した。図に実験の概要を示す。蝸牛に神経幹細胞を投与して2-4週後,蝸牛の各部位に海馬由来神経幹細胞が一塊となって見出された。このことは,海馬由来神経幹細胞が移植後数週間経っても生着し続けることの証明となる。ある動物では海馬由来神経幹細胞が有毛細胞層上に生着し,また一部有毛細胞に置き換わっているのではないかという所見も見られた。これらの事実は,海馬由来神経幹細胞であっても,内耳有毛細胞に対する移植・再生のドナーの候補となりうることを意味する。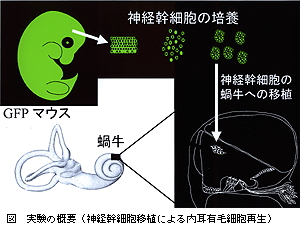
今後の臨床応用へ課題と方向性
近年,幹細胞を移植のドナーとして使用しようとする試みは非常に多くなされており,哺乳動物でも種々の部位から幹細胞が抽出されている。海馬由来神経幹細胞は,動物実験の段階では中枢神経系のさまざまな部位に移植されている。海馬由来神経幹細胞を内耳に移植することに多少の無理はありそうであるが,幹細胞の場合,起源はどこの細胞であっても結果的にうまく生着し,当該組織に分化するという報告もある。しかし,障害を与えた網膜に神経幹細胞を移植した際に,海馬由来神経幹細胞が形態学的には網膜細胞と類似の細胞に分化したが,網膜特異の抗体には反応しなかったという事実もある。このような事実を考えると,できれば内耳由来の幹細胞を抽出,培養できれば,海馬由来神経幹細胞よりも内耳に対する移植の可能性は高まると考えられる。さらにはすべての組織の元になる胚性幹細胞の利用も有望視されている。倫理的問題が解決されれば,もっとも臨床応用が可能なものであり,聴覚系への応用も十分考えられる。一方,倫理的問題を考えれば胎児由来の各種幹細胞より,自己の間葉系幹細胞の応用が臨床応用に対する近道であるとも考えられる。
現在,各種幹細胞を内耳に投与しても,実際内耳に生着する数は非常に限られている。今後はいかにしてこの数を増やすかが問題となる。形態学的には内耳の感覚細胞が再生しても,機能的な問題はまだ未解決である。これらの点を踏まえると,内耳の再生が動物実験的に完成するにはまだ3-4年は必要と考えられ,臨床応用にはさらに数年間かは要すると考えられる。
