OSCEなんてこわくない
-医学生・研修医のための診察教室監修:松岡 健〔東京医科大学(霞ヶ浦病院)第5内科教授〕
第16回 心電図
| 原 武史 | (東京医科大学・第2内科学) |
| 山科 章 | (東京医科大学教授・第2内科学) |
| 《検査のポイント》
心電図は基本的な生理検査の1つとして診療の場で広く活用されており,とりわけ循環器疾患の診断では最初に行なうべき必須の検査である。心電図により,不整脈の診断,虚血性心疾患(狭心症,心筋梗塞)の診断,心房心室の負荷,肥大,電解質異常,薬剤の効果や副作用の判定,などがなされる。 心電図診断はその後の治療を決定する上で非常に重要であるため,正確にきれいに記録することが要求される。記録後に必ず所見を記載し,診断をつけることを習慣とすると上達する。 |
■手順
心電図検査を行なう旨を告げ,了解を得る。| (1)検査の準備 |
*機械の設定は,振幅値10mm/mV,紙送り速度25mm/秒,フィルターoffとする
| (2)体位 |
*上半身を脱いで,両手首足首が出るようにする。腕時計,ネックレスなどをはずしていただき,ベッドに仰向けになり,体のカを抜いてもらう。ストッキングを履いているときには足首が出るようにして必ず直接,電極と皮膚を接触させる
*手首,足首の内側,胸部の所定の位置にペーストを塗り,電極を付ける(写真1,2)
 写真1 手首の電極の付け方 |  写真2 足首の電極の付け方 |
| (3)心電図の記録 |
*肢誘導,胸部誘導のスイッチをonにして,心電図波形をみる(まだ記録は始めない)
*筋電図や交流雑音の除去,基線の調節を行なう
*記録を開始する
標準肢誘導(I,II,III)
単極肢誘導(aVR,aVL,aVF)
胸部誘導(V1-V6)
の順番に記録する
*各誘導5心拍以上記録し,T波とP波の間の平らな部分に1mV波形(キャリブレーション)を入れる
*電極を患者さんから取りはずし,ペーストをきれいに拭き取る
■解説
| (1)検査の準備 |
(a)アースの取り方
3Pの電源コードであれば,対応するコンセントに差し込むだけでアースが取れるが,2Pの電源コードの場合は,アース線を接続する。CCU(冠疾患集中治療室)や心臓カテーテル検査室では他に電気機器を使っており交流雑音が入りやすいため,付属のアース線を接続する。
(b)機械の設定
振幅値10mm/mV,紙送り速度25mm/秒,フィルターoffが標準であり,まずはこの設定で記録する。
●振幅値:左室肥大など波形の大きい時は振幅値5mm/mVまたは2.5mm/mVとして波形同士が重ならないように記録する。また,P波の波形やQRS波形を詳細に観察する時には振幅値を20mm/mVにすると便利である。
●紙送り速度:QRS波形を詳細に観察する時には50mm/秒と速くして波形を拡大する。10mm/秒と遅くして長時間(3分間程)記録すると短時間の記録ではとらえられない不整脈が記録紙を節約して記録できる。
●フィルター:ノイズの混入がある場合はフィルターを入れる。フィルターをかけると心電図波形に影響があるので注意する(R波高の変化,ペースメーカ信号の消失など)。
ハムフィルター …交流雑音対策
ドリフトフィルター…基線の揺れ対策
筋電図フィルター …筋電図対策
(c)自動記録機能(オート)について
心電計によっては自動記録機能(オート)が付いているが,波形を自動処理するため,QRS波高が高い場合,勝手に振幅値(キャリブレーション)が変更されて縮小されてしまう。またフィルターもかかってしまい,心筋虚血の検出のために重要なST変化がわかりにくくなってしまう。QRS波が重なる場合にも,最初は基本設定(振幅値10mm/mV,紙送り速度25mm/秒,フィルターoff)にて記録する。
| (2)体位 |
(a)検者の位置 左前胸部に電極を付けるため基本的には患者さんの左側に立ち検査を行なう(写真3)。
 写真3 患者さんの左側に立って 検査を行なう |
(b)電極の取り付け 皮膚と電極のインピーダンスを下げる目的でペーストを塗る。皮膚が汚れている時はアルコール綿で拭いた後,ペーストを塗る。電極間がペーストでつながると正確な記録ができないので,つながらないように注意する(写真4,5)。
 写真4 電極の付け方(全体像) |  写真5 電極の付け方(前胸部誘導) |
(c)頻回に心電図を記録する場合 不安定狭心症や急性心筋梗塞の患者さんで頻回に心電図をとり,その些細な変化も重要な場合において,胸部電極のずれは人為的な心電図変化を作ってしまい判定を難しくする。このような場合には,患者さんに断り油性マジックで胸部電極の位置をマーキングしたり,粘着テープ式の電極を貼らせてもらうと,電極の位置ずれがなくなり正確な記録,経過観察ができる。特に,V3誘導とV6誘導は,ずれやすいので気をつける(写真6)。
(d)右側胸部誘導,背部誘導の付けかた(写真6,7)
心筋梗塞の中でも右室梗塞や後壁梗塞を標準12誘導で見逃すことがある。右室梗塞では右側胸部誘導,後壁梗塞では背部誘導の記録が必要となる。
【右側胸部誘導】胸部誘導を正中線に対称に右前胸部に付けたもの
V3R:V3相当の右胸壁上の点
V4R:V4相当の右胸壁上の点
V5R:V5相当の右胸壁上の点
V6R:V6相当の右胸壁上の点
【背部誘導】V4-V6と同じ高さで背部に付けたもの
V7:V4と同じ高さで後腋下線との交点
V8:V4と同じ高さで左肩甲骨中線との交点
V9:V4と同じ高さで脊椎左縁との交点
右胸心の場合は胸部誘導だけでなく,四肢の誘導も左右の電極を正常と反対に付けると,心電図の評価が容易になる。
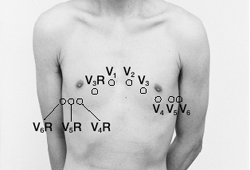 写真6 前胸部誘導(V1-V6)と右側胸部誘導(V3R-V6R)の付ける位置 | 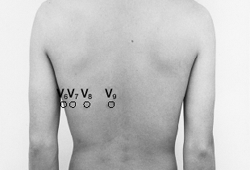 写真7 背部誘導(V7-V9)の付ける位置 |
| (3)心電図の記録 |
記録の前にノイズの混入がないか,基線は適切な位置にあるかチェックする。筋電図や交流雑音が入る時はその原因を除去する。
(a)筋電図対策
●患者さんにリラックスしてもらい全身の力を抜いてもらう。
●寒い時には部屋を暖かくする。
●四肢誘導に混入する時は腕の付け根に電極を付けてみる。
●筋電図フィルターの使用。
(b)交流雑音対策
●心電計のアースを確実に取り付ける。
●皮膚と電極,電極と誘導コードの接触不良がないか確認する。
●患者周囲の電源コードを遠ざけるか,必要のない電気機器のコードをコンセントから抜く。
●誘導コードを広げすぎない。
●ハムフィルターの使用。
(c)基線の動揺対策
●ゆっくり呼吸をしてもらう,もしくは一時呼吸を止めてもらう。
●電極や誘導リードの動きを抑える(粘着テープ式の電極に変えるなど)。
●ドリフトフィルターの使用。
胸部誘導の記録で振幅が大きい場合は記録可能範囲内に収まるように基線を調節する。波形が大きすぎる時は振幅値を5mm/mVまたは2.5mm/mVとして記録する。このときも必ず1mV波形(キャリブレーション)を入れる。
●調べておこう
□正常心電図
|
◆臨床では
胸部誘導の肋間が変わると当然その波形も変化する。一肋間上に付けるとV4からV6でR波高が減少し移行帯はやや時計回転方向に移動,一肋間下に付けるとV4からV6でR波高が増高し移行帯はやや反時計回転方向に移動する。経過観察中に肋間を間違えて記録すると,心負荷や虚血による心電図変化なのか鑑別が難しくなるので気を付けよう。また,後壁梗塞では,V7からV9の背部誘導において異常Q波やST上昇を観察できるが,高位後壁梗塞では,V7からV9の一肋間上で記録するとより強く異常を記録できることがある。 |
◆OSCEでは
OSCEの試験や臨床の場で実際の心電図の記録は誘導リードもたくさんあり,最初は戸惑うと思われる。痛い検査ではないので,何度か実物の心電計を使って友だち同士で心電図を記録して慣れよう。OSCEの試験では,心電図の付け方だけでなく,その所見を読みとることも求められることがある。試験時間に限りがあり(1分程?),順序立てて系統的に読まなければならない。付け方同様こちらも練習して慣れよう。
|
先輩からのアドバイス
◆誘導の覚え方標準
◆胸骨角は診察の要。(肋間の数えかた)
◆バッテリー駆動の心電図
◆患者さんの持ち物は
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●連載の終了と単行本発行予定
弊紙連載「OSCEなんてこわくない」は今回をもって最終回とさせていただきます。長らくご愛読いただき,ありがとうございました。なお,読者からのご要望にお応えして,本連載は,内容をより充実させ,明年2月末に単行本として発行される予定です。ご期待ください。 (「週刊医学界新聞」編集室) |
