〔連載〕医者が心をひらくとき
A Piece of My MindJAMA(米国医師会誌)傑作エッセイ集より
|
(前回2503号)
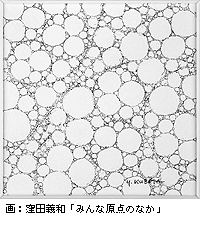 私が友人や同僚からよく受ける質問とは,「どうしたらエイズの患者の診療などということができるのか? いったい,どうやったら『そんなこと』ができるのか?」というものだ。この質問に対して私が用意している答えとは,恐ろしい病気であるにもかかわらず,患者たちはヒーローとして振る舞うからだ,というものだ。エイズは,患者たちの短い人生からこれまで何十万年という貴重な時を奪ってきたが,他の悲劇においてもそうであるように,この病気は,幾多のすばらしい人々の,人間としての品性の気高さを明らかにしてきた。HIV関連疾患のみを担当する専門医として,外来や回診で患者たちが毎日示す勇気や人間性に,私はいつも驚かされ,そのたびに,謙虚な気持ちにさせられるのだ。そして,そういった気高い行ないの多くは,私が一番期待していなかった患者によってなされ,私は,自分の人生観や人間観がいかに狭いものであるかを思い知らされるのだ。
私が友人や同僚からよく受ける質問とは,「どうしたらエイズの患者の診療などということができるのか? いったい,どうやったら『そんなこと』ができるのか?」というものだ。この質問に対して私が用意している答えとは,恐ろしい病気であるにもかかわらず,患者たちはヒーローとして振る舞うからだ,というものだ。エイズは,患者たちの短い人生からこれまで何十万年という貴重な時を奪ってきたが,他の悲劇においてもそうであるように,この病気は,幾多のすばらしい人々の,人間としての品性の気高さを明らかにしてきた。HIV関連疾患のみを担当する専門医として,外来や回診で患者たちが毎日示す勇気や人間性に,私はいつも驚かされ,そのたびに,謙虚な気持ちにさせられるのだ。そして,そういった気高い行ないの多くは,私が一番期待していなかった患者によってなされ,私は,自分の人生観や人間観がいかに狭いものであるかを思い知らされるのだ。
ステファニーが,他の患者と違う点を強いて挙げるとするならば,彼女の苦しみは他の患者よりも重いものだった,ということになるだろう。ありふれたものからまれなものまで,彼女はありとあらゆるエイズの合併症を経験していた。非定型抗酸菌の全身感染,気胸を反復しそのたびに胸部チューブを入れなければならなくなるニューモシスティス・カリニ肺炎,ヘルペスおよび真菌による口腔咽頭食道の重症感染,決して止むことのない消耗性の下痢,菌種が同定できない血液感染症など,数え上げたらきりがない。そして,当然のことながら,破滅的な病気と闘っている人々の多くに見られる不安うつ病が,これらのすべての合併症に伴ったのだった。それにもかかわらず,家族の愛と励ましを受けて,彼女は持ちこたえ,家長としての責務をも果たし続けた。診療チームの誰もがその回復力に驚いたし,彼女はもっとも楽観的な見通しを何年も越えて生き続けたのだった。
最後の入院は,下り坂だけの経過となった。重症の肺炎で呼吸不全となった後,薬剤副作用や,さまざまな合併症が次々と重なった。診療チームと家族の間とに,これがきっと最後の入院になるだろうという,暗黙の了解が成立した。
彼女の死は簡単には訪れなかった。死が訪れる前に,痙攣発作,血栓症,腫瘍,感染,肝および呼吸不全,のすべてが起こったが,2つのことだけは変わらなかった。不整脈を起こすこともなく心臓が力強く機能し続けたことと,意識は残酷なほど清明だったこと,であった。
彼女は,チューブやさまざまな器械につなげられても勇敢に耐えた。そして,大丈夫ですか,検査をしてもいいですか,新しい治療をしましょうか,と私たちが尋ねるたびに,力一杯うなずいた。ステファニーは生き続けることを望んだ。私たちのしていることが,かすかの希望しかもたらさない一方,想像しがたい苦痛と苦悩を彼女に与えているに違いないことを私たちは認識していたが,彼女の勇気,そして彼女の母親と子どもたちの勇気が,治療に対する私たちの思いを支えた。生き続けるために,彼女は,ありとあらゆる可能性に賭けようとしていた。私たちはその彼女の願いを果たすために力を尽くした。
私にとって,もっともつらかったのは,ステファニーの10歳になる息子さんの苦しみを見ることだった。彼は,時間が許す限り母親の見舞いに訪れた。最後の訪問は,彼女が亡くなる2,3日前のことだったが,私はそのときのことをこの先何年も忘れないだろう。学校からの帰り,リュックを片方の肩にかけながら,彼は母親を見つめていた。これが母親を見る最後になるということは,きっと彼にもわかっていただろう。小さな子どもを最後にさわろうとする母親の手は,壊疽のために腫脹し,変形していた。その首は,治療に反応しない髄膜炎のために硬直し,唇は,ただれ,ひび割れていた。いったい,彼は,どうやってこういったことに耐えることができるのだろう? 私は,不思議に思わざるをえなかった。しかし,彼は見事に耐えていた。母親のベッドサイドに立ち,涙をこらえながら,彼は,どんなにお母さんが好きかということを,何度も何度も母親に語り続けた。彼は,母親を抱き,キスさえもした。大きく恐ろしい器械から出るチューブが母親の鼻や口につなげられていることを思えば,決して,容易なことではなかった。
数日後,私は,再び彼に出会った。彼の母親の葬儀の席だった。ちょっと曲がっていたとはいえ,髪の毛をきちんと梳かし,新品のスーツと革靴に身を包んでいる彼の姿を見たときには,心が痛んだ。母親がいない10歳の子どもが,これほどきちんと身繕いしていることが痛々しくてならなかった。
彼は,立ち居振る舞いも完璧にこなした。ほとんど身動きをせずに,背筋をぴんと伸ばして席に座り続け,唇を堅く結び,目はまっすぐ前に向けていた。会葬の最後に,型どおりに棺を運び出す行列が始まった。中央の通路を進む棺のすぐ後に,家族が続いた。教会を出ようとする列はしばし止まったが,小休止の間に巨大な教会の中に聞こえる音は,くぐもったすすり泣きの声だけだった。突然,大理石の床の上に靴音が鳴り響き,私は,目を上げた。彼が走りよってくるのが見えた。彼は両腕を投げ出すようにして,私の首に抱きついた。強く彼を抱きしめる私の耳に,
「お母さんのことを診てくれてありがとう,ニーナ先生」
と,震えた声で言う彼の言葉が大きく響いた。
その瞬間,自分が毎日,どうやって「そんなこと」ができるのかが,私の心の中で明瞭になった。そして,何よりも,なぜ,「そんなこと」をするのかが。
