OSCEなんてこわくない
-医学生・研修医のための診察教室監修:松岡 健〔東京医科大学(霞ヶ浦病院)第5内科教授〕
第14回 縫合・抜糸
渡邊 克益(東京医科大学教授・形成外科学)| 《手技のポイント》
縫合針は円の一部を切り取った円弧状にできている。円を想定して,手首をひねり,回転させることで,彎曲した縫合針を皮膚に垂直に刺入し,引き抜くことが可能となる。糸付き針と持針器とによる器械縫合では,糸が絡まないように持針器は外側が凹凸していないものを選択しなければならない。 |
■縫合の手順
| (1)縫合開始前の準備 |
*患者さんに縫合する旨を伝える
*消毒が済み,麻酔がかかっていることを確認する
*消毒が済み,麻酔がかかっていることを確認する
| (2)縫合(単純結節縫合法) |
*持針器で針を持つ
*針を刺入する(針先は皮膚に対して垂直)
*手首を戻しながら針を進める
*持針器で針を把持して引き出す
*針を刺入する(針先は皮膚に対して垂直)
*手首を戻しながら針を進める
*持針器で針を把持して引き出す
| (3)糸結び |
■解説
| (1)縫合開始前の注意点 |
消毒が済み,麻酔がかかっていることが前提となる。
全身麻酔の場合:麻酔医に縫合開始する旨を伝える。
局所麻酔の場合:患者さんに局所の痛みがないかを確認し,痛みがあれば麻酔剤の追加などの対策をとる。患者のバイタルサインを確認し,異常があれば対策をとる。
手術中のトラブルを避けるための患者とのコミュニケーションも大切。もし手技中に疼痛や何らかの異常を感じた時は,速やかに術者に伝えてほしいこと,異常があれば適切に対処することを患者さんに説明・確認してから手技を開始する配慮が必要である。
| (2)縫合(単純結節縫合法) |
1)持針器で針を持つ。
糸と針の接続部分は損傷しやすいので,この部を避けて針を把持する。針は持針器の先端近くで針先を上に向けて持つ。
針と持針器の角度は 直角か,針先を心持ち前方に傾けた状態とする。接続部分は余して持つ。
2)刺入点の選択
創縁から針の半径よりやや短い距離をとる。
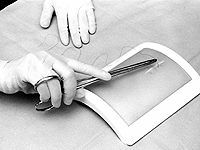 3)針の刺入
3)針の刺入
針先が皮膚に垂直となるように,前腕を内側にひねる(大きな針では 肘も外側に張り出すように持ち上げる)。
創縁を鑷子で軽く持ち上げると,その分 前腕のひねりが少なくてすむ。
4)針の送り込み:
針は創の方向に直交するように進める。ひねった手首を戻しながら針を進める。初心者は針を引き出す側に比べて,針を刺入する側の組織量が少なくなる。刺入する側の組織をたくさん取り込むように意識することで,均等に糸がかかる。
反対側にでた針先は鑷子で押さえておく。
持針器から針をはずす。
 5)針の引き出し:
5)針の引き出し:
突き出た針先の先端を避けて持針器で把持する。この時に手首を再度内側にひねる。こうすることで,針を引き抜くためのねじれが腕にできる。
手首を戻しつつ,針を回転させながら皮膚から抜く。
| (3)持針器を利用した糸結び |
1)糸の端が2cmぐらい残る程度に引き抜く。
2)適当な位置で左手で糸を把持し,針を持針器から外す。
3)左手の糸に,右手の持針器を右回転で絡める。通常は1回,外科結びにする時は2回糸を絡める。
4)糸を絡めたままで,持針器で糸の断端をつかむ。
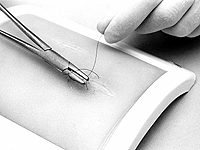
5)両手で糸を引いて結ぶ。左手を右前方に,右手は体に近く左方向に引く。

6)今度は左回転で持針器に糸を絡めて,糸の断端をつかむ。前回と同じ回転で糸を絡めると,結び目は外科医の嫌う縦結びになる。
7)前回と左右の手が逆になる方向に糸を引いて結ぶ。
8)両方の糸を持ち上げて,切る。
■抜糸の手順
| (1)抜糸の準備 |
*患者さんに抜糸する旨を伝える
*消毒が終わっていることを確認する
*消毒が終わっていることを確認する
| (2)糸の切断 |
*鑷子で糸を持ち上げる
*引き出された糸をハサミで切る
*引き出された糸をハサミで切る
| (3)糸の引き抜き |
■解説
すでに消毒してあることが前提となる。抜糸時に麻酔はしない。(1)患者さんに抜糸をする旨を伝える。
(2)鑷子で糸を軽く持ち上げて,引き出された部分の糸をハサミで切る。この時,糸を強く引くと余計な痛み与えてしまう。
縫合が小さい場合は 引き出さずにそのまま皮膚近くで糸を切る。

(3)糸は創縁の方向に引く。創縁から離れる方向に引くと,縫合創に離開するような力がかかってしまうので避ける。
OSCE-落とし穴はここだ
(1)手技のみに気を取られて,患者に対する配慮を忘れないようにします。 (2)持針器の種類
(3)縫合手技
|
(この項つづく)
