| 連載 第7回 | 再生医学・医療のフロントライン | ||
軟骨の再生
| |||
軟骨再生のストラテジー
 骨と軟骨はいずれも,「硬組織」に分類される。内蔵臓器と違って荷重を支えるほどに“硬い”ところに組織機能の重要な部分が含まれている。この硬さは,細胞が産生した細胞外マトリックスの性質に由来している。すなわち,骨ではヒドロキシアパタイトと呼ばれる大量のミネラル成分がI型コラーゲン線維に沈着(石灰化)しているので,無機質の“硬さ”を示す。
骨と軟骨はいずれも,「硬組織」に分類される。内蔵臓器と違って荷重を支えるほどに“硬い”ところに組織機能の重要な部分が含まれている。この硬さは,細胞が産生した細胞外マトリックスの性質に由来している。すなわち,骨ではヒドロキシアパタイトと呼ばれる大量のミネラル成分がI型コラーゲン線維に沈着(石灰化)しているので,無機質の“硬さ”を示す。
一方,軟骨細胞が作り出す細胞外マトリックスではII型コラーゲンによる細線維とプロテオグリカンが主成分で,通常,石灰化していない。多量の水和水を包含するプロテオグリカンが作り出す膨潤圧をコラーゲン線維の抗張力が支えるので,軟骨は独特の粘弾性(荷重がかかるとゆっくりと縮んで,荷重がとれるとゆっくりと元に戻る)を示す。また,軟骨には神経や血管が存在しない。この点が神経や血管が発達している骨との際だった違いである。
関節表面を覆う軟骨組織はわずか数mmの薄い細胞層からできているものの,その粘弾性と無神経・無血管性によって可動性を保ちながら荷重を支えることができる(図1)。血行のない組織の再生は一般的に困難で,加齢や外傷などによって軟骨が損傷を受けると容易に変形性関節症に移行する。その結果,大きな痛みを発する。そこで,自然治癒が困難な軟骨損傷に対して,再生能を補強する試みがなされている。
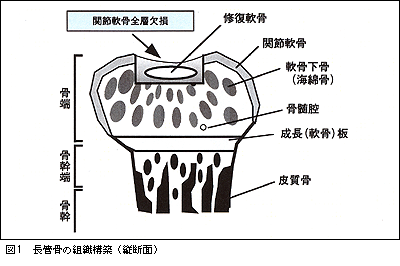
幹細胞移植による軟骨再生
骨髄由来の間葉系幹細胞が軟骨再生修復に参画できる関節軟骨全層欠損の場合では,欠損が小さければ自然に治癒することがある(図2)。近年,間葉系幹細胞や軟骨幹細胞の性格を有する細胞を用いて,その自己複製と軟骨分化がどのようなシグナルで制御されているか解析できるようになってきた。そこで,動物実験レベルでは間葉系幹細胞システムの活性化と動員を生理的なシグナル分子を使って刺激することで,軟骨再生を誘導することが考えられるようになってきた(図3A)。ただ,ホルモン様のタンパク質因子を用いることになるので,当分の間,臨床応用は困難である。
これに対して,骨髄から間葉系幹細胞を分離培養して,これを組織欠損部位に移植することで軟骨・骨の形態形成を促す方法が注目されている(図3A)。これは,患者自らの幹細胞を骨髄から比較的容易に採取できるので,免疫適合性の問題も回避できる有望な方法となろう。ただ,高齢者のみならず成人では,骨髄に含まれる幹細胞数はかなり減少するので,体外培養でどの程度に細胞を増殖させることができるかが鍵となる。一方,酵素処理によって組織から分離された軟骨細胞は,限られた範囲では体外培養によって増やすことができる。そこで,自家の培養軟骨細胞を移植して欠損部を軟骨で埋めることが行なわれている(図3B)。周囲の骨・軟骨と強固な接合が保たれるかなど,不十分な点もあるが,関節表面を軟骨様組織で素早く覆うことによるメリットは大きい。
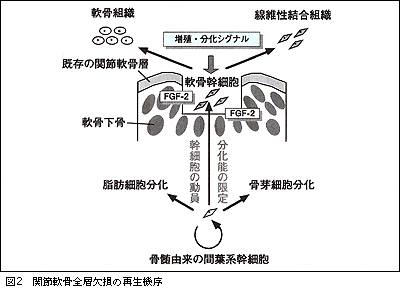
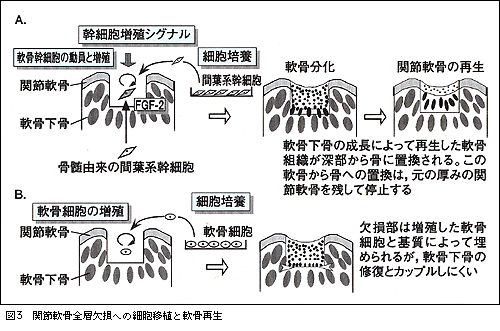
今後の方向性
いずれにしても,幹細胞移植による軟骨再生は臨床的に試みられつつある。しかし,その技術評価は10年を目処として長期にわたって検証される必要があるので,広く行なわれるまでには相応の年限を要する。今後,ES細胞から間葉系幹細胞へと分化誘導する方向の研究も急速に進むと考えられるし,幹細胞の分離・精製や増殖技術が成果をあげれば,臨床応用に一層早く近づくと考えられる。| 《第1回 心臓細胞再生の現状と展望(福田恵一)》 |
| 《第2回 皮膚の再生(朝比奈泉)》 |
| 《第3回 角膜の再生(中村隆宏,木下茂)》 |
| 《第4回 血管の再生(日比野成俊,新岡俊治)》 |
| 《第5回 末梢血管の再生(森下竜一)》 |
| 《第6回 骨の再生(大串 始)》 |
