〔インタビュー〕
子どものこころの問題をシェアする医療
臨床家が知っておきたい「子どもの精神科」
| 広沢郁子氏 (都立梅ヶ丘病院医長) 大倉勇史氏 (都立梅ヶ丘病院医員) | 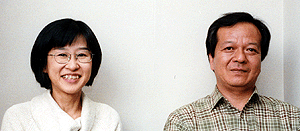 |
子どものこころの問題が社会的な注目を集める一方で,実際に子どもの精神科医療を担う専門医の数は少なく,またその育成も進んでいないのが現状である。
このたび本紙では,『臨床家が知っておきたい「子どもの精神科」-こころの問題と精神症状の理解のために』(医学書院刊)を記した都立梅ヶ丘病院のスタッフとして活躍する広沢氏と大倉氏に,子どもの精神科の現状とその臨床のあり方について,話を聞く機会を得た。
●子どもの精神科の現状
増加する子どもの患者
――最近,子どもが精神科を受診する数が年々増えているそうですね。広沢 当院では,初めて病院を訪れる患者さんの数を毎年調査しています。平成13年度(2001年)と平成4年度(1992年)とを比べると,約660名ほどだった患者数が約1500名と約2.3倍に増えています。「少子化にも関わらず,なぜ受診する子どもさんが増えているのだろうか」と,スタッフの間でもよく話題に上ります。
精神科医療に対する抵抗感が少なくなっていること,マスメディアを通して,注意欠陥・多動性障害(attention-deficit hyperactivity disorder : ADHD)や高機能自閉症などの状態,また「児童精神科」という名称が一般に浸透してきたことなどが,受診の頻度が増えている理由の一部ではないかと考えています。
受診者の傾向・紹介経路
広沢 当院にはこころや発達の問題を持っている,精神科医療の対象となるあらゆる子どもたちが受診します。ここ数年の傾向として,それまでは自閉症圏の子どもが最も多くて,つまり発達障害圏(精神遅滞,自閉症,学習障害など),神経症圏(恐怖性不安障害,強迫性障害,適応障害,身体表現性障害など),精神病圏(精神分裂症,気分障害など)という順でした。この中でも,この数年はADHDの子どもが,受診者数としては最も増加傾向にあるというのが現状ですね。大倉 このような子どもさんは,学校関係から紹介される場合が多いです。一方,小児科関係では脳波異常が見られ,また多動性があるということで,診察を依頼されるのが一般的です。
広沢 児童精神科への受診のピークは,3歳と7歳と14歳にあります。3歳のピークは自閉症の子どもたちが,また7歳のピークはADHDの子どもたちが多く,適応障害などの神経症圏のピークが14歳です。精神分裂病は20歳前後が好発年齢ですが,14歳にピークがあります。受診のピーク時というのは,問題が出てきやすい,もしくは気づかれやすい年代と言えるかもしれません。
大倉 発達の問題ですと,健診で気づかれて紹介されたり,また幼稚園や就学時点で気がつかれたり,行為障害圏では学校での問題から受診という場合が多いですね。
広沢 行為障害は家庭内に限局するものと,家庭外でも見られるもの,単独型と,社会化型といったグループがあります。家庭内に限局した場合は親御さんから,社会化されない孤立型で家庭外でも起こる場合は,家族のみならず,学校の先生や児童相談所から紹介されます。
さらに集団化され非行に近い形になると少年センターや警察が対象で,その中で精神科医療が必要と思われる方が紹介されるというように,現れる状況によって医療への紹介経路も多岐にわたります。
社会を反映する病
――精神疾患とは社会を反映する病気と言われます。広沢 診察室は,ある切り取った場面でしかありません。診察室で初めてお目にかかるということは,ある意味では最もフォーマルな場面であり,診察室の場面からだけでは,その子どもの状態や環境は,なかなかうかがい知れない部分もあります。しかし,逆からみれば,診察室は社会の小さな窓のようでもあり,その時代にその社会で起きている現象を垣間見ることができる場とも言えます。
大倉 「子どもは保護のもとにある弱い存在」とだけ言っていいのかわかりませんが,社会的な問題が最も突出しやすい年代だと思います。そういう意味で,社会の世相を反映する形で症状を出すということがあると思います。
広沢 感覚としては,子どもの精神科が社会でクローズアップされてきたというのが,フィットしますね。本当に受診者数が増えました。
しかし,本当にその疾患の実数が増えているのかどうかは,疫学的な調査をしてみないとわかりません。ある意味では同じ症状でも,それに対する保護者や学校の先生方など周囲の意識が高まってきた面があるとも考えられます。
●注目される子どものこころの問題
子どもをいつ医療につなげるか
広沢 当院では,病院内に独立した組織「子どもの精神保健相談室」を設置して,ケースワーカーと臨床心理士が相談を担当しています。そこで,医療の介入が必要かどうかを判断すべく,お話を聞いて受診につなげるという形を取る場合もあります。子どもたちを,いつ医療につなげるのがよいか,という点ですが,発達障害圏の子どもたちは早期に,その年代に沿った適切な療育や対応ができると,いろいろなことを獲得したり,周囲の理解を深めたり,問題や偏りを軽減できたりします。精神疾患圏全般としてとらえると,病院に訪れた時が適切な時期だと考えられます。
しかし,例えば不登校はあくまで現象であって疾患ではないため,「不登校だから病院に」と言うのはおかしな話です。精神的な健康度が高ければ,たまり場や自宅でぬくぬくと冬眠する中で,心のエネルギーを回復していくこともあります。それを早急に医療が介入してしまい,病気がごときに思わせてしまうとマイナスになる部分もあります。また,不登校で引きこもるうちに,だんだん眠れなくなり,「誰か家の下にきて自分のことを見張って,悪口を言っている」などと言い,情動が不安定になることがあれば,医療的な介入が必要になります。
――摂食障害やうつ病など,子どもにはないと思われていた疾患があると聞きます。
広沢 確かに摂食障害は小学校中学年ぐらいの子どもさんが,ぽつりぽつりと見られるのは事実です。また,本当に内因的なうつ病とは言いきれませんが,抑うつ状態を呈するとか活気がないということで,小学校中学年ぐらいで受診する子どももいます。その意味では低年齢化と言えますが,やはりこころや脳の領域に注目が集まったことに起因していると感じています。
大倉 子どもをそのように注目して見るか見てないかに,相当影響されていると思います。受診した人が低年齢であるというだけで,発症が低年齢化しているかどうかははわかりませんよね。これまでは周囲が気づかなかっただけとも考えられます。
病気か病気でないかが問題じゃない
広沢 また,親御さんの育児不安,子育てに対しての不安も感じられますね。大倉 親御さんたちは,「病気か病気じゃないか教えてください」と診察室に来ることが多いのですが,大事なことは,その問題の解決にあたって,医療が何を提供できるか,なのです。「病気なのか病気じゃないのか」に線を引くことが本当によいことなのかは疑問があります。しかし,「病気か病気じゃないかを言ってください」とおっしゃる場合が多く,非常に困ってしまいます。受診されるのですから,少なくとも問題があることは確かですが,病気かどうかは本質的な問題ではありません。子どもの問題に対して,病院にしろ学校にしろ,司法も含めて多くの関わりが持てると思いますが,医療が提供できるものをお子さんに合わせて対応することが大切なのです。
原因探しに偏り過ぎない
広沢 精神科医の立場だと,同じ状態像でも診断が違うこともあります。興奮でも,一過性なものもあれば,病的なものもあります。それを客観化して,彼らの状態・問題が何かを見極めることが,私たちの役目の1つです。両親は,「何がそれを引き起こしているか」と,原因探しをされてしまいがちです。あの時,学校の先生にこう言われたからとか,いじめられたとか,親御さんの中でストーリーを作ったり,過去を振り返ってご自身を責めたりされますが,これは子どもにとってプラスにはなりません。
子ども自身が自分の過去を振り返った時に,親や私たちが,彼らの言いたいことを受けとめることは大事なことです。しかし,保護者や学校の先生が原因探しをしても,精神科疾患で原因がわかっているものはほとんどないのが現状なので,実り多いものになりません。それよりは,これから先どうしていくかを具体的に組み立てていくほうがよいのですが。
神経症と不登校
――人格障害と診断される子どもが,最近増えていると聞きます。広沢 児童精神科医の立場から言うと,18歳以下の場合は極力,人格障害とは診断はしないという前提があります。ただ,マスメディアの影響とも思いますが,用語として耳にされることがあるのでしょう。少数ですが18歳以下の方たちにもいます。その後の経過を追いつつ,人格障害の診断をする場合もあります。
大倉 確かに人格障害に近い心性を持った患者さんはいますが,積極的には人格障害の診断はしません。
――神経症も同様ですか。
広沢 神経症の範囲は広いのですが,受診理由は不登校が多いですね。不登校自体は疾患ではありませんが,親からみると,学校にいけない子どもはとても心配なようです。また子ども側に焦りが生ずることもあり,不登校が受診理由で病院にきます。その中で,例えば「教室に入る」と思うだけでドキドキしたり足がすくんだりして,教室に入れないという場面恐怖や,さまざまな経験がストレスとなり,適応上の問題が生じる適応障害などがありますね。また,頭痛や腹痛などの身体症状で受診する子どもたちもいます。
他には,「強迫神経症」といって,自分でもばかげているとわかっていても,同じことが何度も頭に浮かんだり,同じことを何度もしないと気が済まないという疾患は,思春期年代の子どもの神経症としては比較的多いですね。
解離性同一性障害(多重人格障害)について
――イマジナリー・コンパニオンという概念と解離性同一性障害などの精神疾患とは違うのでしょうか。広沢 「イマジナリー・コンパニオン」(空想上の仲間)と「解離性同一性障害(多重人格障害)」との異同は,論議されている部分があります。イマジナリー・コンパニオンは,基本的には自ら,現実には存在しないことを気づいていて,自分を慰めたり,励ましたりしてくれる存在であり,成長とともにだんだん消えていくものです。
一方,解離性同一性障害は,2つ以上の独立した人格が存在します。しかし,子どもの解離性同一性障害の場合には,他の人格に気づいていて,自ら「多重人格」と言って受診する場合も多いようです。別途の独立した人格であれば,自分が多重人格者かどうかわからないのですが,どうもそのあたりの境界が曖昧です。
他の人格に対する意識がある場合は,特定不能の解離性障害というジャンルに分けます。当院を受診される子どもたちは,別人格があることがわからない場合もありますが,うっすらとわかっている子どものほうが多いようです。だからといって,詐病ではなく,本人も苦痛だったり問題行動があったりと,治療的な介入が必要な場合があります。
大倉 さらに幻聴に対して,「他の人格があるから多重人格だ」と言う精神分裂病の患者さんもいます。言葉だけでは判断できない部分があります。
また,多重人格に関しては,マスメディアで多く取り上げられた頃は,「多重人格」の表現を多く聞きましたが,最近はそういった形で訴えてくる人は少なくなっています。それでも解離症状を起こして入院という人は続いてます。
――このような子どもたちは,例えば20歳を越えて成人となったら成人の精神科を受診されるのでしょうか。小児科におけるキャリーオーバーでも問題となるように,スムーズに連携されるのでしょうか。
広沢 そうですね。児童精神科の場合は18歳までを対象とします。しかし,20歳代以降でも外来通院をしている場合もあります。発達障害に限らず,精神病圏,神経症圏の子どもでも大変だった時期をともに歩んできたことから,お付き合いが長くなる場合がありますね。特に発達障害圏の場合は,成人精神科の医療現場では担いづらい現状があるようです。
もちろん医療の必要がなくなる人や,成人期に入院治療が必要になる場合もあり,さまざまですが,決まったルートやマニュアルがないのが現状です。
●診察室の中で
広沢 具体的に治療に入ると,精神療法や薬物療法を施行しますが,発達障害では療育的な指導も行ないます。言語の力があれば言語で表出されることを受けとめながら考えていく,サポーティブな精神療法が,スタンダードだと思います。子どもの場合も当然ですが,信頼関係ができないと,治療は難しいです。子どもに現実的な提案を少しずつした場合,それに反発すること,耳を傾けてくれることなどさまざまです。こちらの対応へのアクションがあれば,またそこから考えていくという形で進んでいきますね。
大倉 本人は,苦しいことや困っていることが,まわりから理解されていないと感じていることがあります。そのあたりを的確に理解することが,最初かもしれないですね。
「こういうことなんだね」と言うと,全然違うじゃないかと否定する場合もありますが。また,苦しみ自体が,本人が感じる苦しみと,まわりが見ている苦しみの違いに焦点をあてて話をすると,話にのってくる場合もあります。それは言語化できるような子どもの場合ですが。
広沢 言語化が難しい子どもで,興奮が強い時には,ありとあらゆる手だてで鎮まるように工夫します。時には自傷行為を起こしたり,興奮がおさまらない場合もあります。誘因が不明な場合もありますが,さまざまな状況への反応であったり,SOSの表出だったりもします。言語の少ない子どもに関しては,どのような状況で起こりやすいかの把握や,そのような状況の回避のための物理的工夫もします。またSOSの場合には,こちらがそれをキャッチするように努めます。言語化が可能な子どもへは「そういう形じゃなくても,言葉でもちゃんと伝わるんだよ」ということへの理解を深めるように配慮します。
常に患者さんとは心理的に等距離にいるように心がけています,感情的に近づかれても巻き込まれずにいる。一方,ものすごい反発や非難を受けたりすると,こちらも人間ですのでグサっとくる時があります。しかし,それでも感情的にならず,冷静にそして受容的に心理的に等距離でいる。これは,若い時代にトレーニングされていることですが,未だにこのトレーニングは続いているような状況です。
子どもは育ちゆく存在
広沢 子どもとは育ちゆく存在ですから,子どもの精神科医療は,疾患だけではなく,成長について考える必要があります。それから,子どもたちを取り巻く家族や,学校,社会を包括して考えていくことが大事です。その中で,その子どもにとってどうすることがよいのかを,皆で,それぞれの専門性のもとに支えていけたらいいだろうな,と思います。大倉 私も広沢先生と同様の気持ちで日常の臨床に携っています。
もう1つは,例えば昨今問題となっている司法については,司法とは結局,法律自体が必要最小限のルールですから,それだけで子どものすべてをみられるわけではありません。それに何を付け加えることができるかという問題を考える必要があり,その差がこれから顕在化してくると思いますね。
基本的には,そのお子さんにとって何が一番いいことなのか,何をすべきなのかをきちんと考えながら,法律の適用を考えなくてはなりません。
――本日はありがとうございました。
 | 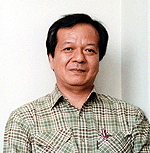 | |
| 広沢郁子氏 1985年順天堂大学医学部卒。同大精神医学教室助手を経て,1991年より現病院に勤務。1998年より現職。日本児童青年精神医学会「教育に関する委員会」委員。子どもの精神疾患全般の診療にあたっている | 大倉勇史氏 1991年東京医科歯科大学医学部卒。同大附属病院の脳波室勤務などを経て,1998年より現病院に勤務。現在,生理学的精神医学に興味がある |
