第26回国際内科学会議開催
Global Physicians Network : A Challenge for the New Century
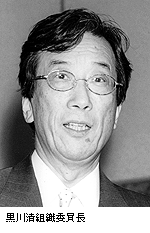 第26回国際内科学会議(International Congress of Internal Medicine:ICIM)が,黒川清組織委員長(東海大学総合医学研究所長)のもとで,さる5月26日-30日の5日間,京都市の国立京都国際会館において開催され,「Global Physicians Network:A Challenge for the New Century」のメイン・テーマのもとに世界の内科医7000余名が一堂に会した。
第26回国際内科学会議(International Congress of Internal Medicine:ICIM)が,黒川清組織委員長(東海大学総合医学研究所長)のもとで,さる5月26日-30日の5日間,京都市の国立京都国際会館において開催され,「Global Physicians Network:A Challenge for the New Century」のメイン・テーマのもとに世界の内科医7000余名が一堂に会した。
ICIMは,1948年にスイスのバーゼルで準備委員会が設立された「国際内科学会(International Society of Internal Medicine:ISIM)」が2年ごとに開催する会議で,第1回は1950年,フランスのパリにおいて開催された。わが国では,1984年に織田敏次東大名誉教授を会長とした「第17回ICIM」に続き,2度目の開催になる。また同時に今回は,日本学術会議とともに日本内科学会も主催に当たり,「日本内科学会創立100周年記念行事」の中心的企画としても位置づけられている。
日本内科学会がISIMに加入したのは1952年で,1954年の第3回ICIM以降,毎回参加。また,ISIMの運営に関しても,井形昭弘氏(前鹿児島大学学長)が理事長を務めた他,大島良雄元日本内科学会理事長,日野原重明同名誉会員らがISIMの役員として活躍してきた。特に日野原氏は「Hinohara-Sasakawa Lecture」を設立し,1990年以降この特別講演が会議の1つのハイライトになってきた。(別掲表参照)
21世紀初となる今回の会議では,(1)Global Physicians Network:A Challenge for the New Century(黒川氏),(2)Internal Medicine:A Global Challenge for the New Millennium(J. Johnsonn氏・ACP-ASIM, アメリカ)の2題のPresidential Address,「Hinohara-Sasakawa Lecuture:Patient Safety and Medical Errors Reduction;An Unviersal Challenge(J. Noble氏・ボストン大学,アメリカ)」の他,Special Session, Plenary Lecture, Special Symposia, Global Physicians Network, Lecture & Topics, Case Study/Case Discussionなどの学術プログラムが企画され,広範多岐にわたる分野で討議がなされた。

■「世界内科医ネットワークを形成し,21世紀に挑戦しよう」
周知のように,内科学は現在,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,血液内科,腎臓内科,内分泌・代謝内科,膠原病内科,神経内科などに専門分化されているが,今会議では,生命科学の進歩,EBM(Evidence-Based Medicine)とその実践,ゲノム医学,長寿社会,生命倫理,脳と心,行動と社会,組織再生医工学などの横断的テーマを主要題目として各種のプログラムが組まれた。メイン・テーマを冠した『Presidential Address』において黒川氏は,「20世紀後半の目覚しい科学の進歩によって,医科学もさまざまな面で飛躍的な進歩を獲得した。その大きな1つの潮流は,言うまでもなく“専門化・細分化”であり,内科学もその例外ではない」と前置きし,20世紀の歴史を次のように概括した。
「その一方で,20世紀の科学の進歩によって人口の爆発的な増加が起こった。特に先進国では高齢化・長寿化が顕著になり,これによって疾病構造の大きな変化がもたらされた。例えば,生活習慣病然りであり,悪性腫瘍やアルツハイマー病などの老人病然りである。
その結果,21世紀を迎えた今日,臨床医学の根幹をなす内科学に関し,“これから内科学は何をするのか?”,“内科学とは何か?”ということが大きなテーマになってこざるを得ない」
黒川氏はまた,かねてからの持論である「医療体制改革のための5つのM(=(1)Market,(2)Management,(3)Molecular biology,(4)Microchip/Media,(5)Moral)」をあらためて披露し,医学・医療界のみならず,「東西問題」「南北問題」に揺れ動き続ける世界への問いかけとした。
『Globalized Evidence』と『Localized Dicision』
さらに黒川氏は特に近年急速に普及しつつある“情報化社会”について触れ,「もう1つ重要なことは,“21世紀は情報社会”ということであり,言うまでもなく,医療を始め現今の経済・金融,政治などの世界が国際化,いわゆるグローバリゼーション化してきたことである。医療の世界においても,情報が医師という専門職だけでなく,国民の間に広く国境を越えて共有されるようになってきた」と指摘。そして,「情報化時代においては,先進国・途上国を問わず,インターネットやEメールなどを通じて,内科医はさまざまな情報を共有することができる。そして,最新の情報をもとにして,最新の知見による最良の診療,換言すると『Globalized Evidence(世界に通用する医学的根拠)』をそれぞれの国の国民と共有し,提供することが責務となる。しかし,またその一方では,これまで以上に宗教などのさまざまな文化的背景を含めた『Localized Dicision(個別事情に合わせた個々の決断)』が重要になる」と強調して『Presidental Address』を締めくくった。
| 表「Hinohara-Sasakawa Lecture」
・1990(Stockholm); J. D. Rowley, USA : Molecular biology in leukemia ・1992(Lima)(政情不安により中止) ・1994(Budapest); Karl Oeberg, Sweden : Multiple endocrine neoplasia type I(MENI)from gene to clinic ・1996(Manila); Francis A. Waldvogel, Switzerland : Microorganisms and the sepsis syndrome-a unifying clinical concept ・1998(Lima); Kiyoshi Kurokawa, Japan : Hypertension kidney and human civilization ・2000(Cancun); D Alarcon-Segovia, Mexico : Medical grand rounds before Cortes |

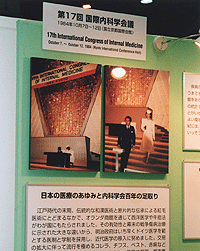
|
●Special Session:Outcomes Research/Health Service Research
|
