“Nurses Di@logue”
初の糖尿病看護国際シンポジウムが開催される
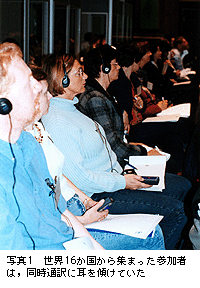 さる5月2-4日の3日間,北欧・デンマークの首都コペンハーゲンにおいて,“Nurses Di@logue”と題する,世界で初めての試みである,「糖尿病看護国際シンポジウム」が,Novo Nordisk社により開催された。
さる5月2-4日の3日間,北欧・デンマークの首都コペンハーゲンにおいて,“Nurses Di@logue”と題する,世界で初めての試みである,「糖尿病看護国際シンポジウム」が,Novo Nordisk社により開催された。
現在,糖尿病患者は全世界で1億5000万人,WHO推計によれば2025年には3億人にのぼるであろうと言われている。彼らをケアするにあたって,看護職者の肩にかかってくる責任と,同時にその可能性がいかに大きいものであるか。そして看護職者はどのように糖尿病管理に貢献していけるのか。それを追究すべく,本シンポジウムが企画された。
ヨーロッパ諸国のほか,イスラエル,アメリカ,そしてアジアからは唯一の参加となった日本を加えた世界16か国より,総勢300余名(うち日本人25名)の看護職者が一堂に会し,これらのテーマについて活発な意見交換,そして日々の体験の共有が図られた(写真1)。
看護職者に必要な医療経済的知識
シンポジウムは,柱となる本会議,および対話式セッションにより構成された。まず本会議においては,「糖尿病管理――その克服すべき障壁」をテーマとし,「DAWN(Diabetes Attitudes,Wishes and Needs)研究」に関し,糖尿病を専門とする医師,看護師,心理学者ら4名が登壇し,報告・分析する形で進められた。「DAWN研究」とは,2000年に世界13か国,総計9300名の糖尿病患者および医療従事者を対象に,電話・対面聴取により行なわれた,稀にみる大規模な心理・社会的調査である。
その結果として,「糖尿病患者の31%は,医師に自分の症状を十分に説明できていないと感じている」,「医療従事者の半数以上が,自分は糖尿病患者の心理的な欲求を把握し,かつ評価することができていないと感じている」,「看護職者の30%以上は,糖尿病患者が医師とのコミュニケーションに負担を感じていると気がついている」――DAWN研究の報告・分析は,不全感を持つ糖尿病患者,そしてその不全感に応えられないと感じている医療職者のもつれた関係性を浮き彫りにした。各演者とも共通し,看護職者の役割として「患者の言葉に耳を傾ける」ことを強調した。
これら一連の報告後には,パネルディスカッションの場が設けられた。その場では,フロアよりアメリカ在住の看護師が,「患者さんと対話をする時間がほしい。話をすることに医療的な価値が認められていない。どうしたらサラリーを確保することと,限られた時間で話を深めるということを両立できるのか」と発言し,会場から一斉に大きな拍手が沸き起こった。
看護職者は,日々患者の心理・社会的状況や,看護職者自身に求められるケアについても理解し,学んでいる。では次にそれをどう実現していくのか――保険制度や患者とのコミュニケーション方法等,置かれた状況は,当然各国で異なる。しかし,今必要とされるケアを患者に届けていくためには,どの国に働く看護職者にも,医療経済的視点によりコスト分析ができる知識と,具体的な政治的バックアップを獲得することが急務であるとの認識が,このパネルからなされた。
自分の腹部にインスリン注射の針を
本会議に続く「行動変容理論を実践する」と題したセッションでは,すべての参加者の手元にスイッチボタンが配付された。演者の質問に参加者が答えると,即座にその集計結果がスクリーンに映し出され,それに対する演者のコメントがなされる,という「対話式セッション」である。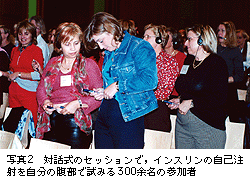 演者の1人,Torsten Lauritzen氏(Aarhus大教授)は,インスリン療法を行なう患者の自己管理を考えるための第一歩として,「今まで自分でインスリン注射器の針を刺したことがありますか?」と,会場の参加者に問いかけた。参加者はその問いに応え,手元のスイッチボタンを操作。集計され,スクリーンに明示されたのは,「No」の24.67%という数字だった。それを受けて氏は,「では今から皆さんで一緒に,自己注射をしてみましょう」と発言。サンプルとして渡されていると,多くの人々が解釈していたであろう手元のインスリン注射器を,その場で一斉に刺すという氏の思いがけない提案に,会場のあちらこちらから驚きと笑いの入り混じった声があがった。結果,「インスリン製剤の入っていない空の注射器を,自分で自分の腹部に刺す」という行為に失敗した人は,15.63%。「この数値をどう評価することができるでしょうか」と述べた氏の巧みな進行に,会場が大いに沸いた(写真2)。
演者の1人,Torsten Lauritzen氏(Aarhus大教授)は,インスリン療法を行なう患者の自己管理を考えるための第一歩として,「今まで自分でインスリン注射器の針を刺したことがありますか?」と,会場の参加者に問いかけた。参加者はその問いに応え,手元のスイッチボタンを操作。集計され,スクリーンに明示されたのは,「No」の24.67%という数字だった。それを受けて氏は,「では今から皆さんで一緒に,自己注射をしてみましょう」と発言。サンプルとして渡されていると,多くの人々が解釈していたであろう手元のインスリン注射器を,その場で一斉に刺すという氏の思いがけない提案に,会場のあちらこちらから驚きと笑いの入り混じった声があがった。結果,「インスリン製剤の入っていない空の注射器を,自分で自分の腹部に刺す」という行為に失敗した人は,15.63%。「この数値をどう評価することができるでしょうか」と述べた氏の巧みな進行に,会場が大いに沸いた(写真2)。
参加者は糖尿病分野を代表する大使
本シンポジウムには,“Di@logue”という名にふさわしく,物理的な距離および言葉の壁を乗り越えるためのさまざまな試みがみられた。本会議はインターネットによりライブ中継され,パネルディスカッションには遠くアメリカの看護職者からメールでの参加があった。また,会場においても,前述のような対話式の議事進行がとられ,参加者に一体感が共有された。座長を務めたAnne-Marie Felton氏(欧州糖尿病看護連盟会長)は参加者を,「看護職者のみならず,医療職をはじめ,すべて糖尿病に関係する人々と分野を代表している大使である」と形容した。本シンポジウムの意義は,ここに表現されたと言えよう。
なお,DAWN研究については
URL=http://www.dawnstudy.com/
そして本会議の全容は“nurses di@logue on line”と名づけられ,
URL=http://www.novoconference.com/
で公開されている。
