救命処置のスタンダードを学び教える
「医学生・研修医によるLife Support WS」開催
さる3月29-31日の3日間,東京医科歯科大学にて,「医学生・研修医によるLife Supportワークショップ」が開催され,北は北海道,南は鹿児島まで全国各地から多数の医学生・研修医が参集した。
ACLS勉強会が発展
 本ワークショップ(以下,WS)は,現在,飯塚病院研修医の大野博司さんが2000年夏に当時在学していた千葉大でACLS(Advanced Cardiac Life Support)勉強会を開催したことに端を発している。その後,その勉強会には関東圏の他大医学生も参加するようになり,昨年3月には,それまでにACLSを学んだ学生により,全国から学生を集めての「心肺蘇生を学びたい医学生・研修医のためのワークショップ」が開催された。今回のWSは,その第2回目にあたるが,外傷の初期対応もプログラムに含めた他,参加者が各大学で,同種の勉強を広めることができるように,学習や勉強会運営のノウハウが詰まったCD-ROMを作成するなど,大幅に中身を充実させた。
本ワークショップ(以下,WS)は,現在,飯塚病院研修医の大野博司さんが2000年夏に当時在学していた千葉大でACLS(Advanced Cardiac Life Support)勉強会を開催したことに端を発している。その後,その勉強会には関東圏の他大医学生も参加するようになり,昨年3月には,それまでにACLSを学んだ学生により,全国から学生を集めての「心肺蘇生を学びたい医学生・研修医のためのワークショップ」が開催された。今回のWSは,その第2回目にあたるが,外傷の初期対応もプログラムに含めた他,参加者が各大学で,同種の勉強を広めることができるように,学習や勉強会運営のノウハウが詰まったCD-ROMを作成するなど,大幅に中身を充実させた。
日本全国から参加者
本WSの運営スタッフ40人,参加者30人(学生28人,研修医2人)の他,見学者は30名以上であった。「十分な学習ができるように参加者の定員は30名としたが,60名以上の応募があり,学年や参加理由などを考慮の上,参加者を絞らざる得なかった」と運営スタッフの中心となった桑原宏哉さん(東医歯大卒)は話す。
参加者に話を聞くと,「救命処置は医師として,不可欠のスキルであるにもかかわらず,大学では十分な教育が受けられない。救命処置の基本を身につける上で,貴重な機会だと思った」と口を揃える。
運営スタッフ側の気合いの入り方も相当なもので,ある学生は「学生同士の勉強会は『なあなあ』になるのが怖い。そうならないように運営スタッフは厳しいトレーニングを積んできた」と胸を張っていた。
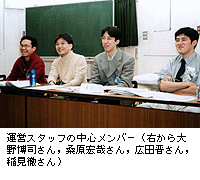 | 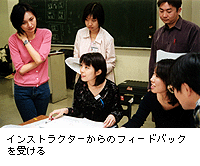 |
情報発信の起点に
3日間のプログラムは,初日にACLS講義,試問,実技が繰り返され,2日目午前にはACLSのMega Code(実技試験,シナリオに基づいたシミュレーション),午後は,外傷初期対応講義,試問,実技,夜は懇親会,3日目の午前中に,外傷初期対応のMega Codeが行なわれるというハードなもの。しかし,参加者はモチベーションが高く,「確かについていくのは大変だが,のんびりやると怠けるので,これくらいテンポが速いほうがいい」と必死に取り組んでいた。開催を終えて,桑原さんは「きついスケジュールだが,うまくいった。細かいことにはこだわらず,ACLSと外傷初期対応の大まかな流れをつかんでいただく,という最低限の目標は果せたのではないか」と満足げな笑顔をみせていた。
「参加された皆さんには,ぜひ各地でこのような勉強を広めてほしい。『SHARE』,『情報発信』というのが今回のWSの重要なコンセプトなのです」と強調する桑原さんは,今後の学習機運の盛り上がりに,大きな期待を寄せている。
「目の前に人が倒れていて,何もできない医師でよいのか?」
『ACLSマニュアル』(医学書院刊)など,エビデンスに基づいたACLSのスタンダードを示すテキストなどの出版もあり,救急処置トレーニングへの医学生・研修医の関心は,ここ数年で飛躍的に高まっている。本紙では,今後も学生主体による同種の活動に注目していきたい(下記に運営スタッフ,参加者のコメントを掲載)。
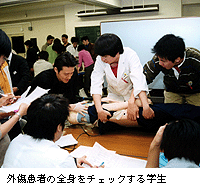 |  |
●外の空気にあたり,謙虚さ持とう
大野博司さん(飯塚病院研修医・WSスタッフ)に聞く―――昨年は医学生,今年は研修医としての本WS開催ですが,何か感じるものは?
 大野 臨床研修に出て実感するのは,自分だけの技術だけでは何も動かないということです。実際に医療を動かしているのは,チームであり,そのチームがある一定の考え方や技術を共有していないとよい医療はできません。
大野 臨床研修に出て実感するのは,自分だけの技術だけでは何も動かないということです。実際に医療を動かしているのは,チームであり,そのチームがある一定の考え方や技術を共有していないとよい医療はできません。
だから,自分だけが勉強して知識や技術を得ても,そこで満足していてはいけないと思うのです。例えば,今回のWSでACLSや外傷初期対応を学んだら,それをきっかけにして,それを先輩や後輩,救急救命士,看護婦の方たちとも共有することができないか,ということを考えることが必要ではないか,と感じています。
医療をよくするために何が必要か
―――学生同士,研修医同士で学び合うことのメリットとは?大野 いろいろな医師を見ていると,時として経験は進歩を阻害すると感じることがあります。自分たちのやり方に固執し,他に耳を貸さないわけです。すると,そこにはどうしても進歩がないし,一つの組織なり,地域なりですらスタンダードを確立することが難しくなります。むしろ,経験の乏しい学生のうちに,医療とは教え学び合い共有するものだという正しい一歩を踏み出すのはよいことだと思います。
―――日本の医療をよくするためには,何が必要だと感じますか?
大野 1つの大学や医局の中だけにいると,どうしてもその組織の中だけで蓄積された経験や考え方を盲信してしまうことがあります。外部の人間と交流し,自分たちの日々の実践を謙虚さをもって眺め,常にスタンダードをめざす姿勢が大切ではないかと思います。自分が所属している研修病院には,そのようなオープンな雰囲気があり,日々その大切さを感じています。
●学生によるACLS勉強会問合せ先《産業医大ACLS勉強会》土日を利用して月に1度開催。学外からも各回3名受講可能。 連絡先:岩澤聡子(産業医大6年) E-mail:s-bird@nyc.odn.ne.jp 《千葉大ACLS勉強会》
《東医歯大ACLS勉強会》
|
●あっという間,しかし充実した日々
遠藤悟史(千葉大学医学部5年・WSスタッフ)目立つ部分にとらわれず患者さんの全身を検索する
 僕がACLSという言葉を知ってから,5か月がたちました。本当にあっという間で,しかし充実した日々だったと思います。
僕がACLSという言葉を知ってから,5か月がたちました。本当にあっという間で,しかし充実した日々だったと思います。
ACLSは心肺蘇生のガイドラインの1つなので絶対的というものではありません。しかし世界水準と考えられており,これを学ぶことで心配蘇生において何をすべきかということやチーム医療の重要性などを理解することができたと思います。
さらにワークショップのもう1つの柱である外傷初期対応については今回が初の試みであったため,大野さんがまとめられたテキストをもとにスタッフが実際に体を動かし,議論することで,作り上げられました。目立つ部分にとらわれずに,患者さんの全身を検索するのだという概念は,非常に納得のいくものだと思います。
また,僕自身は,まだ病院実習に出ていないので,議論を重ねる中でさまざまな先輩から実際の現場についてのお話が聞けたことが本当に幸運でした。
いずれの内容も講義,口答試問,実習の三段階で構成されていたので,参加者の方も理解しやすかったのではないかと思います。それは納得することと実際に体を動かせることはやはり別物だからです。わかっているのに体が動かないという経験は誰しもあると思います。しかし実際の現場ではそれではいけないのだということを,スタッフである自分も痛切に感じることができました。
新しい出会いのすばらしさ
今回のワークショップを通じて感じたことは,新しい出会いのすばらしさです。違う大学の学生同士で将来のことを語ったり,酒の席で個人的なことを話したりすることはとても刺激的なものでした。参加者,スタッフを越えてそのような経験ができたことは何にも代えがたいと思っています。僕は今回のワークショップでの出会いで少し成長できたのではないかと思っています。そして,僕と出会ったことがほんの少しでも誰かの役に立つのなら,こんなに嬉しいことはありません。またいつか皆様にお会いできる日を楽しみにしています。そして,まだ見ぬ友人たちとの新しい出会いを待ち望みつつ,千葉大に戻ってからも,今回のワークショップで得たものを広めていきたいと思います。
●広めようLife Supportの輪
片岡明久(高知医科大学6年・WS参加者) A・C・L・S? この言葉を知ったのはちょうど1年前に「週刊医学界新聞」に紹介された,このワークショップ(以下WS)の記事からだった。大学でBLS(Basic Life Support)は習ったのだが,
A・C・L・S? この言葉を知ったのはちょうど1年前に「週刊医学界新聞」に紹介された,このワークショップ(以下WS)の記事からだった。大学でBLS(Basic Life Support)は習ったのだが,
「実際に心肺停止の患者さんを目の前にして,私は世界標準の心肺蘇生ができるのだろうか」
当時記事を読んで正直に思った感想だ。
そしてメーリング・リスト「college-med」で,今年もこのWSがあることを知り,待ち遠しい気持ちで参加した。
感動の3日間
WSではACLS・外傷救命初期対応を3日という短期間で行なった。学ぶことが非常に多く,決して楽な内容ではなかったが,・目からウロコの講義
・賞賛の嵐の口頭試問
・皆で助けあった実技
・盛大なるMega Code
というただ受身で学ぶのではなく,学んだことをその場でアウトプットし,誉められ,体を動かして身につけるカリキュラム構成で,効率よく確実に,そして楽しく心肺蘇生アルゴリズムが学べた。
また,さまざまな大学の学生が混ざり合い,学生同士で教え教わるという新鮮さあふれる環境での勉強は,
「どうして同じ学生でここまでレベルが違うのだろう」 と思ったこともあったが,それがよい刺激になり,やる気が倍増し,本当に実りあるものだった。
さらに2日目,3日目のMega-Codeでは自分がリーダーの時,困惑してしまう場面に遭遇したのだが,チームメイトに助けられ,医療におけるチームプレイの大切さを身をもって体験した。
初日の朝にはガチガチに緊張していたのにその日の夕方には楽しくて楽しくて胸を躍らせながら,そして真剣に学んでいる自分の姿にふと気づいた。
そしてSHAREへ
このWSで一番印象に残ったことは,何よりもSHAREすることの大切さである。 大野先生のお言葉にもあったが,ここで学んできたことを自分だけで留めてしまって は自己満足で終わってしまう。SHAREして広めていけば,さらに多くの患者さんに還元できるであろう。これからが本当の意味でのLife Supportの勉強の始まりだと思っている。皆さん,ぜひ一緒にACLSを学び,SHAREし広めていきましょう。



