第74回日本胃癌学会が開催される
「胃癌をワイドに攻める」をテーマに
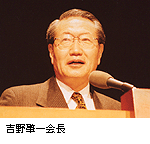 第74回日本胃癌学会が,さる2月7-9日,吉野肇一会長(慶大看護医療学部長)のもと,東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催された。
第74回日本胃癌学会が,さる2月7-9日,吉野肇一会長(慶大看護医療学部長)のもと,東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催された。
この学会では,会長講演や特別企画「国際対談『ガイドラインに思う』」,「化学療法著効長期生存例に学ぶ」の2題,およびシンポジウム「胃癌を分子生物学的に攻めたこれまでの成果と将来展望」,「胃炎,消化性潰瘍の研究は,胃癌手術にどの程度応用されるのか?」の2題に加えて,パネルディスカッションでは胃癌治療における経口フッ化ピリミジンまたは抗癌剤感受性試験の意義をテーマに,さらにビデオシンポジウムや一般演題などが企画され,最新のトピックスをめぐって議論がなされた。
■胃癌における分子生物学的治療の展望
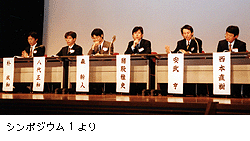 シンポジウム1「胃癌を分子生物学的に攻めたこれまでの成果と将来展望」(司会=阪市大 平川弘聖氏,金沢大 高橋豊氏)では,「これまで分子生物学における新しい知見が多数出されたが,なぜ臨床に応用されないのかを,改めて見つめ直したい」との,平川氏の言葉を発端に,各領域の成果が公表された。
シンポジウム1「胃癌を分子生物学的に攻めたこれまでの成果と将来展望」(司会=阪市大 平川弘聖氏,金沢大 高橋豊氏)では,「これまで分子生物学における新しい知見が多数出されたが,なぜ臨床に応用されないのかを,改めて見つめ直したい」との,平川氏の言葉を発端に,各領域の成果が公表された。
まず最初に西本直樹氏(広島大原爆研)が,胃癌における腹膜転移と肝転移の危険因子と予後について臨床病理学因子と分子生物学的因子をともに用いて多変量解析を施行。原発性胃癌切除165例に,c-erb-2,c-met,k-sam,PCNA,p53,p21,p27,PDECGF,VEGF(vascular endothelial growth factor),E-カドヘリン,βカテニン,MMP-2,MMP-9の13の因子を検討したところ,k-sam+c-metが腹膜再発予測因子で,またMMP-9が肝再発予測因子であり,k-sam+e-metが深達度,リンパ節転移の有無,間質について独立した予後因子であることを明らかにした。
次いで安武亨氏(長崎大)は,フローサイトメトリー(FCM),FISH(fluorescence in site hybridization),CGH(comparative genomic hybridization)を用いて,胃癌との関連を検討。FCMを用いた検討ではDNA aneuploidy症例の予後不良やリンパ節転移が多く認められた。またFISHでは7番と17番染色体増加例にリンパ節を多く認めたことを示した。特に,氏は現在,BTAKやZNF217など老化を抑制する因子を有する20番染色体に注目し,本領域の新たな可能性についても示唆した。
胃癌における分子標的療法の可能性
乳癌におけるHER2蛋白に対する分子標的治療が効果をあげているが,猪股雅史氏(大分医大)は,このHER2と進行胃癌との関連について報告。進行胃癌76症例を対象に,HER2蛋白の発現を抗HER2抗体による免疫組織化学法で判定したところ,21%に高分化型胃癌と有意な関連が認められ,また高分化型胃癌の肝再発例の約40%がHER2蛋白陽性であったことを明らかにした。氏は,「ハーセプチン療法は,高分化型胃癌の進行再発例に対する分子標的療法として期待できる」と結論づけた。続いて,森幹人氏(千葉大)が,胃癌の発生・伸展に関与する遺伝子群の抽出・グループ化の可能性の検討を目的に,胃癌解析用のcDNAマイクロアレイを作製。これにより,胃癌細胞株すべてに発現の高い遺伝子11個,低い遺伝子28個の抽出,リンパ節転移株と肝転移株とを2群に分ける遺伝子群を計32個を抽出でき,臨床検体を用いたクラスター解析では,リンパ節転移陽性群と陰性群の2つに分けることが可能であったことを報告した。
八代正和氏(阪市大)は,著明な線維芽細胞の増生を伴った増殖伸展を特徴とする4型スキルス胃癌に注目し,この癌の増殖に癌細胞周囲の宿主線維芽細胞から産生される因子が関与していたことから,線維芽細胞を抑制するTarnilastを投与。これにより4型スキルス胃癌増殖の抑制が認められ,この癌特有の間質相互作用を阻害し,治療効果を示したと報告した。
最後に朴成和氏(国立がんセンター東病院)は,化学療法中の256例を対象に,感受性関連因子VEGF,p53,bcl-2,GST-p(Gluthatione S transferase),TS(Thymidylate syntahse),DPD(Dihydropyrimidine Dehydro‐genase)の発現を免疫組織学的に検討。個々の感受性因子は,腫瘍縮小効果に関与するが,予後因子ではなく,またVEGF,p53,bcl-2,TS,GST-pなど腫瘍縮小効果に対するfavorable phenotypeの数による奏効率,生存期間の予測と,VEGFの発現による治療法選択の可能性を示した。
また,特別発言として登壇した,磨伊正義氏(金沢大がん研)は「これまでの癌の総論的な問題に対して分子生物学は各論であり,今までの方法では太刀打ちできない」としながらも,分子を標的とした創薬や血管新生等を応用した新しい治療法の成果を考えると,分子生物学は21世紀の癌治療に大きく貢献するだろう,と結んだ。
■胃癌治療ガイドラインを考察
昨年,同学会では,本邦初のがんの治療ガイドラインである「胃癌治療ガイドライン」(以下,ガイドライン)を発表して話題となったが,特別企画1では,日米欧における胃癌治療ガイドラインをめぐって世界の第一人者が登壇した。日本におけるガイドライン設立の立役者となった中島聰總氏(癌研化学療法センター)を司会に,Murray Brennan氏(Memorial Sloan Kettering Cancer Center,アメリカ)と,Engenio Santoro氏(Regina Elena Cancer Institute,イタリア)と,日本から高橋俊雄氏(都立駒込病院)と北島政樹氏(慶大)が議論に加わり,コンセプトから今後の方向性までが話し合われた。ガイドラインの評価を検討
一方,吉野会長による会長講演では,「胃癌治療ガイドラインに思う」と題して,設立の背景から,改訂などを見据えた今後の展望が語られた。氏は「ガイドライン」の基本方針として,「治療の技術的問題に立ち入らないこと」をあげ,これについては,(1)病気に応じた過不足のない治療の提示,(2)治療効果の尺度はEBMによる,(3)(2)は生存期間とするが,症状の寛解,腫瘍の縮小,QOLの改善も評価する,(4)日常診療上,有用な治療法の他に,研究的に行なわれている有望な治療法も示す,(5)成績,文献を資料として収録,の5点を提示。
また氏は,治療の標準化時代におけるインフォームド・コンセントのあり方として,「胃癌治療法の選択にあたっては,医師,患者とも本ガイドラインを常に参照することが望ましい。しかし,ガイドラインの適応とは異なる治療法を選択する場合には,医師はなぜその治療法を選択する必要があるのかを平明に説明し,患者の理解を得る必要がある。すなわち,説明と同意書に署名を得ることを治療の前提にすべきであり,ガイドラインに基づく治療を選択する場合も同様の手続きを行なうべきである」と,指摘した。
また,Sheneyfeldらによる1985-97年に発行された279のガイドラインを25個の基準で評価・検討した研究を参考に,氏も同じ基準でガイドラインを評価したところ,「欧米のそれらとほぼ同レベルにあり,合格点と言える」との評価を下した。
今後の課題として,日本の研究成果を英文化して,「Gastric Cancer」などの専門有力誌に発信することが,日本の重大な義務であること,また本邦独自の治療ガイドライン作成指針および評価方法の検討が必要などと示唆した。
