MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


呼吸器感染症のベーシックな知識が自然に身につく
ガイドラインをふまえた成人市中肺炎診療の実際
河野 茂 編集
《書 評》杉山幸比古(自治医大教授・呼吸器内科)
複雑化・難解化してきた感染症
 もはや感染症は重大な脅威ではない,という流れが以前はあったが,現状はまったく異なり,現在では感染症は人類にとってきわめて重要な課題であり,耐性菌の問題などを含めむしろ,さらに複雑化・難解化したと言っても過言ではない。呼吸器の日常診療においても,きわめてありふれた疾患として肺炎は存在し,われわれ臨床家は日々これに直面している。肺炎の特徴は,原因微生物がきわめて多岐にわたり,宿主の状況も多彩であることから,様々なパターンを取り得るということにある。また,時に致命的ともなるきわめて重大な疾患と言える。こういった現状を踏まえ,2000年3月に日本呼吸器学会より市中肺炎のガイドラインが刊行されたわけである。
もはや感染症は重大な脅威ではない,という流れが以前はあったが,現状はまったく異なり,現在では感染症は人類にとってきわめて重要な課題であり,耐性菌の問題などを含めむしろ,さらに複雑化・難解化したと言っても過言ではない。呼吸器の日常診療においても,きわめてありふれた疾患として肺炎は存在し,われわれ臨床家は日々これに直面している。肺炎の特徴は,原因微生物がきわめて多岐にわたり,宿主の状況も多彩であることから,様々なパターンを取り得るということにある。また,時に致命的ともなるきわめて重大な疾患と言える。こういった現状を踏まえ,2000年3月に日本呼吸器学会より市中肺炎のガイドラインが刊行されたわけである。
本書は,このガイドライン策定に中心的役割を果たされた,長崎大学第2内科の河野茂教授が,呼吸器感染症のメッカである,同教室の一門を結集されて,編まれたものである。
市中肺炎診療をきめ細かに解説
本書では,市中肺炎をきわめて多角的にとりあげ,X線像から始まり,診断・治療に至るまで,きめ細かに解説され,ガイドラインの理解をさらに進める内容となっている。特に診断としての喀痰グラム染色の重要性には力が入れられており,美しいカラー図版が読者の参考となろう。様々な原因微生物の中でも,特徴あるレジオネラ,マイコプラズマ,クラミジア,カリニについては個別に詳しく述べられており,さらにきわめて重要である肺炎球菌をはじめとする細菌類についても,個々に詳述されている。また,今日では,様々な基礎疾患を抱えた人たちが,市中で暮らしており,そういった方々の肺炎にも対処が必要となるが,それに対しては,基礎疾患別の治療が個々に言及されており,大変有用である。特に肺炎の場合,治療が大問題であるが,エンピリックにはじまり,起因微生物が明らかな場合も個別に,きわめて実践的に述べられているのが本書の際立った特徴である。実際に重症度別に,ベストな抗菌薬が商品名で用量・用法とともに明示されており,この部分は即,日常診療に役立つ。呼吸器感染症に直面する可能性のある方々すべてに有用の書と考えるが,特に若い世代には通読していただくことにより,市中肺炎のみならず,呼吸器感染症全般へのベーシックな知識が自然に身につくものと考えられ,ぜひ一読をお勧めしたい。
B5・頁240 定価(本体4,600円+税)医学書院


病院経営に有用な原価計算をプロの会計士が解説
病院原価計算ハンドブック新日本監査法人医療福祉部 編集
《書 評》渡辺明良(聖路加国際病院人事課長)
随所に示されるノウハウ
 この『病院原価計算ハンドブック』は,日本を代表する監査法人のプロの会計士たちが,その知見と実務をもとに,病院経営に必要な原価計算について執筆した貴重な1冊である。私も,病院における原価計算に関する検討を行なう場面で,筆者の方々とたびたびご一緒させていただき,毎回そこから多くの示唆を得ているが,本書にはそれらのノウハウが随所に示されている。病院経営に携わる人々にとっては文字通りのハンドブックとして,また病院の原価計算を学習・研究する学生にはよき参考書として,多くの医療関係者にお勧めしたい。
この『病院原価計算ハンドブック』は,日本を代表する監査法人のプロの会計士たちが,その知見と実務をもとに,病院経営に必要な原価計算について執筆した貴重な1冊である。私も,病院における原価計算に関する検討を行なう場面で,筆者の方々とたびたびご一緒させていただき,毎回そこから多くの示唆を得ているが,本書にはそれらのノウハウが随所に示されている。病院経営に携わる人々にとっては文字通りのハンドブックとして,また病院の原価計算を学習・研究する学生にはよき参考書として,多くの医療関係者にお勧めしたい。
本書は全体が2部構成となっており,第1章では,病院原価計算の基礎知識について体系的な整理が行なわれている。特に各項目ごとに目的・キーワード・着眼点といったポイントと,筆者たちの持つ豊富な会計関連資料がNOTEとして示されており,理解の助けとなっている。また,会計学の学術書では,とかく難解な用語や記述となりがちな理論についても,病院の事例に当てはめながら,わかりやすく解説しているのが特徴である。
また,人事管理や在庫管理,情報公開など,組織運営と原価計算のつながりについても解説されている。このことは,原価計算が単なる経営指標を作成するためだけでなく,原価計算を通じて病院経営のあり方を改善していく手段となることを示しており,実践の場面で参考になる内容となっている。
さらに,投資意思決定のための原価計算に関して,これが病院の経営戦略立案と実行に有用なツールであることを示すとともに,その手法についてもわかりやすく解説されている。
一方,原価計算は内部管理的側面が強いため,その目的や手法は病院ごとに異なる場合があり,そのことが各病院で原価計算を実施する上での壁となることがあるが,第2章では,筆者たちの豊富な実務経験をもとに,医療法人や大学病院,自治体病院など,各病院のケースに応じた原価計算のあり方や,ベンチマークの手法など,原価計算を利用した経営管理手法に関する応用編としての事例が示されており,読者のニーズに対応した解説が得られる内容となっている。
必要性増す病院原価計算
病院経営環境が厳しさを増す中,病院原価計算に対する必要性も高まっているが,病院原価計算はその実務を支える理論の浸透が,一般企業におけるそれと比べていまだ十分とは言えないことから,原価計算が病院経営のツールとしてさらなる発展をするためには,実務だけではなく,理論体系の整備と確立が不可欠であると思われる。そのためには,今後いろいろな視点から病院原価計算に対する研究や実践が行なわれることが望ましい。このような意味から考えると,実務者の視点でまとめた昨年の拙書『実践病院原価計算』(医学書院)に続き,今回の本書『病院原価計算ハンドブック』が出版されたことは,会計士の視点からの病院原価計算という点において,時代の要請に合った1冊であるといって過言ではないだろう。
A5・頁192 定価(本体3,000円+税)医学書院


際立つ教科書,実践の書としての価値
脳外傷リハビリテーションマニュアル神奈川リハビリテーション病院
脳外傷マニュアル編集委員会(代表:大橋正洋) 著
《書 評》安藤徳彦(横市大教授・リハビリテーション科)
非常に有用な使い勝手のよい本
全体は7章だが,構成は4つの部分に分類できる。第1は脳外傷概論であり,第2は事例紹介,第3は脳外傷治療解説であり,最後に国際的に広く使用されている評価方法と用語集が紹介・解説されている。この構成は,初めての人には戸惑いを感じさせるかもしれない。しかし読み返してみると,脳外傷を知る教科書としても,座右に置いてマニュアルとして使用するためにも,また医師以外の多数職種の人にとっても非常に有用な,また使い勝手のよい本であることが容易に理解される。
項目の中で,概論では,脳外傷の定義,受傷原因,年齢構成,障害内容と米国における多彩なリハビリテーションプログラムが概説されている。
事例紹介は,受傷後早期に対処した症例から社会復帰支援が中心的課題であった症例まで,よく見られる典型的な障害を中心に,個別に症例を紹介する形で障害内容とアプローチが解説されている。記載は問題志向型医療記録(POMR)の形式を踏んで,各症例ごとに課題(問題点),主観的所見,客観的所見,リハビリテーションプログラム(プランニング),経過,結果,考察の順で解説されているので,具体的で非常にわかりやすい。
事例(1)は急性期によく発生する異所性骨化の例,(2)はボディイメージ(身体認知)の歪みに対する理学療法,(3)は筋緊張亢進で随意性を発揮できない症例に対する作業療法,(4)は看護婦を中心とするチームアプローチの紹介事例,(5)はコミュニケーション障害に対する言語療法の紹介,(6)は臨床心理を中心とする復学支援の症例,(7)はケースワーカーを中心とする在宅生活実現の支援症例,(8)は行動障害に対する支援,(9)は記憶障害例に対する就労支援,(10)更生施設の利用例,(11)一般就労実現例である。
脳外傷治療解説は,発生頻度,診断,発生機序,受傷直後の治療,慢性期の精神症状と薬物治療,この時期の安全確保,合併症とその治療,高齢者,小児特性と支援内容,就労支援,社会保障制度,施設利用,権利擁護に及ぶ。
次の章では,脳外傷の障害像の中核をなすのは認知機能障害と行動障害であるが,これがQ&Aの形で解説されている。検査法,神経心理学的検査法,高次脳機能障害,認知機能障害の解説とアプローチ,行動障害の解説と対処法,家族支援が詳しく記述されている。さらに付録として脳外傷の代表的な評価方法,用語集が収められている。
集大成された数多くの経験
本書は,日本で脳外傷のリハビリテーションに関して最も経験の深い医療機関の1つである神奈川リハビリテーション病院で,大橋正洋氏を中心とする治療チームが分担執筆している。単に教科書的な知識で書かれた記載ではなく,数多くの経験に裏打ちされた体験を集大成した書物であることが,教科書としても実践の書としてもこの本の価値を際立つものにしている。B5・頁184 定価(本体4,500円+税)医学書院


より深く良質の地域医療を求める心がけを凝縮
〈総合診療ブックス〉高齢者の外来診療で失敗しないための21の戒め
宮崎 康,佐藤元美 編集
《書 評》今井正信(全国国民健康保険診療施設協議会長)
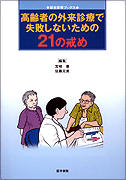 この書は,まさに総合診療書にふさわしい内容である。われわれの地域,特に高齢者の多い僻地や離島での診療に携わった者にとって,こういう「総合された専門書」とも言えるものは,割合少ないものである。特に,高齢患者の病態を身近に体験している者にとって,しばしば本書に記載された症例とまったく同じ不思議な経験をして戸惑う事態がある。いかに良質な医療を提供しようと心がけながらでも,失敗とは言えないような失敗を繰り返して,さらに深いところにある真実まで到達した時の安心感と喜びは,地域医療でのみ感じられるものではないかと思ったりもする。
この書は,まさに総合診療書にふさわしい内容である。われわれの地域,特に高齢者の多い僻地や離島での診療に携わった者にとって,こういう「総合された専門書」とも言えるものは,割合少ないものである。特に,高齢患者の病態を身近に体験している者にとって,しばしば本書に記載された症例とまったく同じ不思議な経験をして戸惑う事態がある。いかに良質な医療を提供しようと心がけながらでも,失敗とは言えないような失敗を繰り返して,さらに深いところにある真実まで到達した時の安心感と喜びは,地域医療でのみ感じられるものではないかと思ったりもする。
高齢者の病態を正しく把握・消化して後輩にアドバイス
本書には,まさにより深く良質の医療を求める諸氏が,地域で一生懸命診ている患者の新しく出現する病状の変化を見逃さないで,正しくとらえ直し,自分の中で消化して後輩に届けるという,見事な内容であり,日常身近に置いて読み直しながら診療に役立て得る書と言える。その上,地域医療に最も必要な臨床現場でのコミュニケーション改善までをも含む在宅での取り組みなどは,実際に地域内で住民と一緒に保健・医療・福祉を考えている総合診療の専門医およびそのスタッフでないと発想し得ないものである。これこそ,21世紀の医師にとって最も臨床研修しなければならないことであると確信している。この書の中にある理念こそ,最も大切な地域医療の真髄だと思える。高齢者患者には,本書の症例にみるような,多彩ではあるが十分な観察と最近の発達した機器,手法により治療できる数多くの大切な症例がまだまだあると考えられる。さらに,良質の総合診療書を書いていただきたいと祈念し,心ある編者などに今後を期待して書評とする。
A5・頁208 定価(本体4,000円+税)医学書院


家庭にも1冊常備して置きたいガイドブック
介護保険時代の医療福祉総合ガイドブック荒川義子,住居広士 監修/日本医療ソーシャルワーク研究会 編集
《書 評》武内昶篤(聖ヨハネ会総合病院桜町病院事務長)
 書籍の読み方,見方には人各々のスタイルやクセがある。私の場合は,序文を読み,次に目次を見る。パラパラとめくってあとがきがあればそれを読む。
書籍の読み方,見方には人各々のスタイルやクセがある。私の場合は,序文を読み,次に目次を見る。パラパラとめくってあとがきがあればそれを読む。
従来とは趣を異にするガイドブック
今回ご紹介する『介護保険時代の医療福祉総合ガイドブック』も手にしてパラパラと頁をめくった。その段階で今までに手にしたガイドブックやハンドブックと趣が異なっていた。それは,挿絵とイラストが豊富に使われていることである。その意図は知る由もないが,このような類のものには少々もったいないと思った。特に挿絵は,純文学や詩集などに使うほうが何倍もひき立つのではないかと思ったほどである。1枚の絵に短かい文章なり,詩をあしらったらそれで楽しいものになりそうだ。ガイドブックの類は,見た目よりもその内容に主眼が置かれ,とかく味気ないものになりがちであるが,ゆったりとした雰囲気をかもし出している。よく見るとイラストは前回(1997年発行『医療ソーシャルワーカーが案内する医療・福祉ガイドブック』)と同じタッチであるが,しかしワンパターンではない筆使いが見られる。挿絵もイラストもその担当者が,この案内書の発行に限りなく心を寄せていることがわかる。その意味でもこのガイドブックが,単に医療ソーシャルワーカーが仕事を進めるための情報提供誌というものの域を超えた思いをうかがい知ることができる。
サービス利用者の理解と納得に結実する情報
しかし,主題はあくまでも内容である。この種のガイドブック,ハンドブックの類は,医療福祉分野に限らず,公私の出版機関から大小さまざまなものが出ている。何十回と版を重ねているものもある。そこへ「この1冊」という意気込みで参入したのである。かなり自信を持っての出版であろう。と思いきやそうでもなさそうである。どちらかと言えば,恐る恐るの思いがうかがえる。序文から引用してみよう「勇気を持って,本書をお届けします」スタートのこの1行がすべてを示している。「今日の制度は,明日には偽りとなり,化石になる」という認識の上に立って「知らないでいることの危険,措置から契約への移行,選択して自己決定する時代への転換すなわち自己責任の時代だからこそ権利擁護も視野に入れなければならない」,しかしそのための情報提供がどこまで十分に行なわれているか。それがサービス提供者としての情報提供にとどまることなく,サービス利用者の理解と納得に結実する情報をいかに整理するかに心を砕いて検討を加えたことも,この手引書の特徴と言ってもよいようだ。「医療福祉の専門職集団と利用者集団との共同作業から生まれた」と言う謙虚さが「賢い利用者になってください」との思いとともにうかがうことができる好書である。その他については,すでに述べた通りで特筆することはないが,活用されている資料が豊富であり,見やすくわかりやすいのもうれしい限りである。文中ところどころにそれとなく散りばめられている「ワンポイント式のコラム」も味わいがある。ただこうした手法は最近の流行のようで,いろいろなところで取り入れているために,もう少し工夫があってもよかったかな,と思わないわけではない。
いずれにせよ執筆者の一覧をみるとその数の多さではなく,医療ソーシャルワーカーと言われる人々の活躍の場の広さに驚かされる。医療ソーシャルワーカーだから医療機関という時代は終ったようである。それだけに数年の経験で一通りのことは把握できた時代も過去のことになってしまった。本書は,各地方自治体発行のガイドブックとともに必携の書と言えよう。できればこれからの時代,各家庭に1冊常備をお勧めしたい。
A4・頁280 定価(本体3,200円+税)医学書院


効率的な病態スクリーニングのための検査を追求
異常値の出るメカニズム 第4版河合 忠,屋形 稔,伊藤喜久 編集
《書 評》今井宣子(阪大附属病院・臨床検査部)
恩師が勧めた座右の1冊
15年ほど前のことである。検査技師学校時代の同窓会があった。その時,たまたま帰りが恩師と一緒になった。恩師はちょうど大学をリタイアされ,関連病院に異動したばかりであった。電車の中で恩師は1冊の本をカバンから取り出して,こう言った。「今これで勉強してんねん」。それは,『異常値の出るメカニズム』というタイトルの本だった。恩師は,リタイア前は臨床検査技師学校の教務主任であった。同時に内分泌専門の内科医でもあった。 ご存じのように大学病院の医師は,一般的に言って非常に専門性が高い。市中の一般病院に赴任し,広く浅くなんでも診なければならないようになり,初めて自分が臨床検査についてほとんど何もわかっていなかったことに気づいたのだ,と言う。そこでいろいろ検査に関する書物を本屋で探したところ,この本が一番自分の知りたいことが書いてあったのですぐに購入し,病院への通勤の往復に電車の中で読んで勉強しているのだと笑いながらおっしゃった。そして私にも買って読むようにと勧めてくださった。これが私と本書との出会いである。爾来,本書は私の座右の1冊となった。
その初版から数えて16年目,このたび第4版が刊行された。この16年の間の臨床検査業界の急激な変貌,そして自分自身の技師生活を重ね合わせてみると感慨はまた一入である。
さて,本書執筆の基本方針は明確で,初版の頃から一貫して“病態スクリーニングのための基本的な検査をいかに効率的に利用するか”にある。
すなわち,“必要最小限の臨床検査を実施して,それらの検査結果を十分に診療に反映させること”であり,“簡単で迅速に検査結果が得られて,幅広い病態をふるい分けるスクリーニング検査の結果から最大限の医学情報を探り出し”,それによって“同じ質の医学情報を提供する検査を無用に重複させることなく,臨床検査の効率的利用が可能”とすることにある(“ ”は序文より引用)。
序論の「検査値を正しく判断するために」からキーワードを拾い上げていくと,「診療における臨床検査の役割」,「生態情報の特性-ホメオスターシスと揺らぎ」,「生体変化はファジーなもの」,「適切な計測技術が必要である」,「計測値は絶対ではない」,「基準値の正しい考え方・使い方」,「正常値から基準値へ」,「基準値の意味-広義と狭義がある」,「個人基準値と集団基準値の使い分け」,「境界値の意味と対策」,さらには「EBM(Evidence-Based Medicine);根拠に基づく医療」,「EBLM(Evidence-Based Laboratory Medicine);根拠に基づく臨床検査医学」へと本書の特徴が明快に示されている。
わかりやすい独自のイラスト
本書の最も大きな特徴は,難解な内容が非常にわかりやすく書かれていることの一点に尽きよう。それを支えているのは,随所にちりばめられている河合先生の手によるオリジナルなイラストである。本文を読まなくても,これだけでも十分に理解できると言っても過言ではない。臨床の第一線で活躍されている医師・臨床検査技師はもとより,研修医,学生,その他の医療従事者にぜひとも一読していただきたい1冊である。
B5・頁416 定価(本体5,800円+税)医学書院
