対談
臨床日記からみる戦後病人史
『私の精神分裂病論』が提起したもの
 |
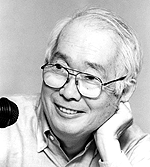 |
| 浜田 晋氏 浜田クリニック院長 |
川上 武氏 医療法人健和会顧問 |
『私の精神分裂病論』を研究対象とした理由-3つのカテゴリー
川上 私ども「医療史研究会」は,現在「戦後日本病人史」というテーマを共同執筆していますが,その仕事の中で精神障害者は近代,戦前とはまったく異なる様相を呈していることがわかりました。まず,「現代日本病人史」よりは「戦後日本病人史」のほうがはるかに難しい。例えば,精神障害者に近い存在である「重症心身障害児」は,戦前にはまったくと言ってよいほどいませんでした。間引きが行なわれている世界では,そういうことは起こらなかったわけです。
それから高齢化社会になると,深沢七郎が小説に書いた戦前の「楢山節考」のような発想がない世界になって,新たに「寝たきり老人」や「ボケ老人」という問題が出てきます。さらには日本の産業構造の変化に伴って,「社会病」と言われる労災・公害・職業病,医療過誤というような問題の性格も,また,「一般病」と言われる癌や腎不全というような疾病も戦前と異なってきています。現代日本病人史の場合は,精神障害者という概念を1つのものとして考えますが,そのような作業の中でわれわれは,精神障害者を3つのカテゴリーに分けて考えざるを得なくなりました。つまり,「精神分裂病」,「うつ病」,それからいわゆる「トラウマと心の病」の3つです。
その中でも最も難しいことは,精神分裂病患者への技術進歩の影響です。そういうものが社会や家族,また人権意識の問題という観点からどのように扱われたかが明確にならないのです。
戦前史は呉秀三の『精神病者私宅監置ノ實況』(内務省衛生局,1918)があるのですっきりするのですが,戦後史になりますと,わけがわからなくなってしまうのです。医療史的にいきますと精神病院は増え,抗精神薬は開発される。それから……。
浜田 精神病の軽症化の傾向があります。
川上 そうですね。そういう問題が出てきますと,精神病,特に精神分裂病患者の地域における状況に関して,われわれは深い理解がなく,また,そういうことに関する資料が少ないこともわかりました。
そういう時に,ちょうど浜田先生がお書きになった『私の精神分裂病論』(医学書院刊)に出会いまして,この本を戦後の精神医療史の中心として取り上げたいと思ったわけです。
浜田 大変嬉しいのですが,何となく面映い感じで,いたたまれない心境でいます。
「論になっていない」という批評について
浜田 はじめから私には,この本を若い精神科の先生方や,地域で活動しているいろいろな方々に,広く読んでほしいという気持ちがありました。特に第 III 部の日記は,医療人や福祉関係の人のみならず,日本という国のありように関心を持っておられる一般の方にも読んでもらってもよいとさえ思っています。たまたま,私が昭和45年から47年までやってきたことを記した日記が残っておりましたので,編集者の勧めもあって,日記の中から精神分裂病者の部分だけを編集し,精神医療がいかに歪んでしまっているか,「精神病者の人権」がいかになおざりにされているか,という批判を込めて書いたつもりです。
案の定,精神科医の方にご講評をいただきますと,高く評価してくれる方と,まったく認めない方に,きれいに2つに分かれました。後者の中には,「“分裂病論”になっていない」という批判があります。
つまり,彼らの頭の中には「精神病理学」という書斎で作られた分裂病の見方,あるいは考え方という論理があって,こういう「街の中で分裂病者がどう生活しているか,という記録だけでは論ではない」という考えがあるのでしょう。「論になっていない」という批判とともに,「昔の話ではないか。今とは違っている」という批判も強くありました。
私としては,そういう反応が大変興味深かったのですが,先日川上先生が「これは,論になっているところが面白い」とおっしゃられたのには驚きました。そういうことからも,本日は川上先生がおっしゃる「論」と,一般的な精神科医の考えている「論」との違いをお聞きしたいと思います。
「東大闘争」と『私の精神分裂病論』
川上 そのためにも,この本の構成に触れたいと思います。全 III 部の中の第 I 部が,松沢病院の経験です。先生は当時から,「グループ活動」や,あまりにも有名になった「球遊び」などを実践され,「精神病因論」に関してはすでに全国的な影響力をお持ちになり,臺弘先生や平尾武久先生によって理論化されて,一定の地位を占めていました。
その後,臺先生が群馬大学から東大教授で戻られる時に,浜田先生を講師に迎えるという異例の人事が行なわれ,第 II 部の「東大闘争前後のこと」になるわけです。
ここで浜田さんが丸山眞男と高橋和巳を取り上げていらっしゃるのは,私には衝撃的なことでした。丸山眞男と言いますと,日本の思想界では神様にも等しい方です。一方,高橋和巳は割合に早く亡くなりましたが,彼は最期に『エコノミスト』に,全共闘が内ゲバを始めたことに対する激しい批判の文章を書いています。
この日記が書かれた時代は,日本の戦後史としては重要な時期です。つまり,昭和45年には「よど号事件」が起きました。また先生とは別な立場で,宇井純氏が東大で公害の自主講座を始めており,両者には共通したものがあります。そしてその翌年は,田中角栄が総理大臣になって「日本列島改造」が始まる年です。ですから,この本には当時の日本のバブルが始まる前の地域医療のことが書いてあります。
それから,浜田先生は東京のほとんどすべての地域を歩いていますが,これは非常に珍しいことです。ふつう,医師は病院にいれば病棟にいる。外来診療所でも自分の地域だけで,これだけ広範囲の患者さんを診られるチャンスはあまりありません。
しかも,大変な激動期です。その後の社会の動きを見ると,当時はまだ崩れてはいないけれども,本質的な社会構造が崩れる途中だったわけです。
浜田 私の中では,いまでも東大闘争は非常に大きな存在としてあります。
社会の中での精神科医の役割はどのようなものであったか,あるいは東京大学というものはどういうものなのかと,学生が真摯に問うたわけです。その問いかけが心に強く響いて,東大という大病院を出ようという気持ちが起きたきっかけになったと思います。
川上 そうですね。浜田先生は東大闘争がなければ,「精神分裂病者にとって,医者とは何か」ということを,ここまで深くは考えなかったのではないかと思います。おそらく,松沢病院時代のオーソドックスな精神科医の道を,そのまま歩んで行かれたのではないですか。
浜田 私もそう思います。よく「地域医療」と言われますが,病院が持っている技術や,論理をそのまま地域に持ち込んで,広めながら実践していこうとするのが一般的ですね。私の中に,病院医療自体を根本から,地域の側から見直してみよう,という気持ちが強くあったことは事実です。
川上 そうですね。それにしてもよく歩いたものだと感じます。
浜田 私自身も,今でもよくわかりませんが,何かやりきれなさというか,「いても立ってもいられない」というような気持ちがあったと思います。
東大闘争の挫折感がバネになったわけですが,非常に不安であったし,気持ちは揺れていました。いわば,精神科医のアイデンティティ・クライシスというものが背景にあったと思います。
「論」になっている2つの理由
川上 そうでしょうね。この本の「後書」に,最初は「子どもの時に見た精神障害者から回顧的に入っていこうと考えた」という趣旨のことが書いてありますが,もしあの道をとったら面白い読み物にはなっても,「分裂病論」にならなかっただろうと思います。ところで,先ほどの話に戻りますが,私が「論」だと思った点は2つありました。
第1には,精神分裂病患者の家族,地域,セックス,地域の目,経済生活といったものに対して,価値観を投影しないでストレートに書いていることです。
大学や大病院の中にいる人が「精神病論」を考える時は,おそらく昆虫標本や植物標本を集めるように,系統樹を作ることから始めると思います。しかし,「病人史」的に考えると,「病院がどのような状況だったのか」,「どのような技術進歩で変化したのか」,「経済生活や社会生活はどう変わったか」というように考えるわけです。
逆に言いますと,精神分裂病論はここから出発しなければならないでしょう。そのためでもあるのでしょうが,この中には精神病院の悪い実例もかなりありますね。
浜田 本当はもっと書きたかったのですが,かなり抑えて書いています。
川上 そうですか。それから,「論」になっている第2点としては,第 I 部に書かれている精神科医としての浜田先生と,日記の中での浜田先生の質が違うのではないかと思う。それくらい,先生は精神病者に対して絶えず同じ次元で見ています。
しかしながら,そんな中で浜田先生らしいと思ったことは,分裂病の患者さん対しては実にやさしくて親切で,否定しないでゆっくり聞いていきますが,心気症やノイローゼの患者さんが来ると,ビシャッと突き放しています。そういう性格が若い時からあったのだなと感じました。
浜田 お名前を出すのも僭越ですが,あの呉秀三先生もそうだったらしいですね。神経症の患者が来ると,横を向いてまったく話を聞かなかったそうです。
どういう資質なのかは私にもよくわかりませんが,精神科医は分裂病の好きな先生と,ノイローゼの好きな先生に二分されるようです。昔は分裂病の好きな先生が多かったのですが,最近の診療所の中には,分裂病の患者さんが来ると断る人もいるようです。
川上 私は,精神科医が病人史を知らなさすぎるのではないかと思います。
分裂病は治しにくいのですが,うつ病は抗うつ剤が比較的よく効きます。「心の病」と言うのも,フロイトやユングの手法でアプローチすれば時間を稼げるでしょう。不安になることも少ない。しかし,分裂病の患者さんはいつ自傷他害になるかわかりませんし,症状もきわめて多様に表われます。
変わらない「病者」に対する目-私の「精神分裂病論」
川上 ところで,時代とともに地域も変わりますし,家族も変わります。また,性の問題の取り上げ方も変わります。しかし,経済的にも,社会保障の面でもずっとよくなったけれども,変わらないものもあります。それは何かと言えば,精神分裂病者に対する,社会や体制の側の目です。これは,呉秀三の時代とさほど変わっていませんね。
浜田 そうですね。まったく同感です。
川上 そういう気がします。分裂病の患者さんは非常に多彩です。この本の中にも先生が,予後的なものを考えていますが,そういうところがよいところですね。
浜田 なるほど。長い目で見ていかなければいけないということと,1人ひとりはそれぞれ違うのだという「多様性」と言うのでしょうか。ひと言でいえば,分裂病者の多様な生き方を日記という形を借りて書いた,そういう事実を今の時点でまとめてみた,ということなのです。
単なる論であってはいけない,いわゆる「反論としての論」,「精神分裂病論批判」というように私は今思っているのですが,それでよろしいでしょうか。
川上 この本の中に出てくる方で,先生と対照的なのは小坂英世さんでしょう。
彼は「小坂精神分裂病理論を作りたい,これを立てるまでは死ねぬ」と言います。彼の言っていることは,実は新興宗教のカリスマ的なものに過ぎません。
しかし,浜田先生の日記は,もっと大きな理論を生み出す土壌になっています。つまり,「浜田日記」にしなかったところがよいと思いますね。
『忘れられた日本人』と発表しなかった『日記』
 川上 話は少し飛びますが,呉秀三の『精神病者私宅監置ノ實況』が面白いのは,彼に人権意識があり,彼は分裂病患者に非常に愛情があったからだと思います。ただ彼は東大教授,しかも大正7年頃の東大教授ですから,「こういう方針で調べて来い」と助手を全国に派遣して調査してできあがったものです。
川上 話は少し飛びますが,呉秀三の『精神病者私宅監置ノ實況』が面白いのは,彼に人権意識があり,彼は分裂病患者に非常に愛情があったからだと思います。ただ彼は東大教授,しかも大正7年頃の東大教授ですから,「こういう方針で調べて来い」と助手を全国に派遣して調査してできあがったものです。
これは民俗学の柳田國男の方法と同じです。有名な『遠野物語』もそうですが,彼は自分では行かずに,現地の郷土史家や弟子に聞き取りをやらせて,それを取って仕事をまとめました。それに対して宮本常一は,すべて歩いて調査したのです。そういう作業のもとで,『忘れられた日本人』という名著が書かれました。
あの『忘れられた日本人』の中の最後の「土佐源氏」は,先生が今回発表しなかった日記の部分と似ているのではないかと私は密かに思っています。
浜田 なるほど。
川上 しかし,あの「土佐源氏」は創作なのです。それを最近,佐野眞一さんが『旅する巨人』(文藝春秋)という本に書いています。これはすばらしい本です。
そのような関心から,私は先生の日記を読みましたが,とにかく文章があまりにも上手すぎます。作家になれるくらいの文体をお持ちになっています。
浜田 いやいや,とんでもない。
川上 例えば,こんな一節があります。
「分裂病者として生きるために,この人は生まれて来ているのだな」
こういうところは泣かせますね。あそこまで精神分裂病患者に対するのめり込み,と言うか思いやりがあれば,やはり患者さんを多面的に見ますよね。そういうところに非常に感心しました。
『私の精神分裂論』に対する「私の幻想論」
川上 ところで,先生が診られた患者さんは,東京の中でもどちらかというと貧困層の方ですね。浜田 いや,貧民層(下町)と三多摩地区(田舎)と中間層(山の手)の3地区に分けられています。1日で東京の端から端まで動いたりしました。
川上 分裂病患者は貧困層だけでなく,豊かな階層にもいます。そういうところは,きちんとしておかなければいけないと思います。先生のこの本の中に,例えば血族(親族)相姦という問題についても,貧困で閉鎖された家族を見ているから,「血族結婚的なことがどうして多いのだろう」というコメントを入れていますね。あれは,やはり底辺に追い詰められた階層を見ている中で出た結論で,普遍化できるかどうかという問題になります。
むしろ,現在はそれがあらゆる階層に及んでいます。そんな点が少し気になりました。しかし,面白い本です。
浜田 (笑)いや,やはり学問というものに対する私なりの幻想が残っていて,つい一般化したくなるのですね。個別性の中にこそ真実がある………。
しかし,日記を書いていた当時は自分自身が揺れていた時代で,大げさなことを言えば,「もう,死んでもいい」というようなところに追い詰められていました。そういう状況にいて1人の精神科医が社会の中へ飛び出し,途方に暮れて七転八倒して,精神科医という白衣を捨てたわけです。
そして,「患者にとって精神科医とはいったい何なのか?」「社会は精神科医にどんな役割を欲しているのか?」「1人の患者をどこまで守れるのか?」と問い続けた。私自身のなまの記録です。そういう記録もあってもいいのかなと思って,「それじゃ,これでいくか」と最終的に決断したのです。
実は,分裂病をまとめようという気持ちになった時には,この日記のことはまったく考えていませんでした。「どないしようかな」と唸っていると,たまたま20何冊かの日記がひょっと目につきました。まったくの偶然から出た産物です。「こういうものがあったのだ」と読み直しだしたのです。そうしたら結構今より力があるなと感じて,次第に自分なりにこれをまとめるという方法もあるのかなという気持ちになっていったのです。
締め切りの時間もかなり迫っていたし,私の寿命も迫っているので,「今やるしかないか!」という感じで取り掛かったのです。その時,たまたまちょっとしたうつ状態にあったので,余計にしんどかったのですが,それだからこそ,あれを読み直して「ああ,こういう手もあるか」と思ったのかもしれません。
「日記」の中の“医師と患者”
川上 先生は「分裂病」をまとめようと思って,全体の構想は立てたわけで,25年間の浜田クリニックの統計から予後を考えていきます。これは臨床疫学的な方法ですね。それで一定の答えが出ると思うけれども,松沢病院の時よりはもう少し実践的な答えが出ると思います。こんなことを言うと失礼ですが,なかなか日記を超せないだろうと思います。
浜田 (笑)そう思いますね。
川上 私は昔から予後学に興味を持っておりまして,『臨床医の予後学』(医歯薬出版)という本も作り,若い頃から患者さんを長いスパンで見ることの重要性を考えていました。先生も25年のスパンで見ようとするけれども,定量化してくると人間はそこで捨象化されてしまいますね。
浜田 そうですね。対象化されますし,私の気持ちが入りませんね。日記には私の気持ちがもろに入っていますし,同じ地平に立っているということで,私と患者さんとの距離が,どちらがどちらかわからなくなってきます。1人の人間と1人の人間という患者さんとなまの出会いのできる状況が日記には出ます。
ところが,診療所に座って患者さんを診ている時は,私は医師であり,相手は患者さんです。そして,患者さんは対象化され,統計化されてまとめられます。どうしてもそういう方向に向かいますが,これとはかなり違った次元の仕事になるでしょう。
川上 違うでしょうね。日記ですと,例えば「社会的入院」についてわりと肯定的なところがありますね。現代は老人病でも社会的入院はすべて害悪かのように言われています。しかし,アメリカではケネディの時代に精神病者を施設からすべて出したら,ホームレスになってしまいました。
それに対して浜田さんは,「精神病院に何十年もいる患者さんは,そこで生活を終わることがいいのかな」という,非常に温かい目で見ています。これは医療史や医療理論を研究する者にとっては,非常に変わった視点なのです。
その辺も,日本の精神病院の持つ特質性を,単に全面否定をしているわけではないですね。そういうところも,「ああ,なるほど」という気がしました。
浜田 患者さんは行き場がありませんからね。一方で,急性患者には拘束して病院に運ぶ。分裂病者が興奮しますと押さえつける。そして,病院の裏口からリフトで上げて,電気をかけて大量に薬を使い,3か月たって陽性症状がとれたら,そのまま病院から追い出すというやり方です。慢性病に対する医療(福祉)の継続性がありません。
川上 この本には薬づけや回転ドア現象の実例,また社会的入院も入っています。それから,「保護室」という名前の座敷牢よりもっと悪い「集団的な座敷牢」があることもきちん書いてあります。
しかし,だからこそ逆に言えば,『縛らない看護』(医学書院)を実践されている吉岡充さんの上川病院のように,「縛らない」ことが注目される時代なのです。
ただ,現実には縛らなければならない患者さんがかなりいるはずです。そこをどのように理論化していくか。1つの切り口だけでは無理ではないでしょうか。それから,ボケ老人の問題も1つの切り口だけでは解決できません。相手に即した,もっと多角的なアプローチが必要になってきます。そういうことをこの本は教えてくれますね。
そこが,私が「論になっている」というところです。
「精神科ケアマネジメント」と「多様な暮らしに寄り添う」こと
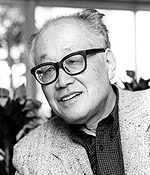 浜田 話題が飛びますが,私の日記と対極にある新しい動きとして,「精神科ケアマネジメント」という制度が平成14年から開始されます。いわゆる「ケアマネジャー」が患者さんの家に行って,彼らがどういう生活をしているか,つまり,「きちんと食べているか」「食べ方はどうか」「お風呂に入っているか」「掃除はされているか」「人と話しができるか」など,介護保険法と同じような項目をいくつか挙げて,5段階で点数化し,コンピュータで処理します。
浜田 話題が飛びますが,私の日記と対極にある新しい動きとして,「精神科ケアマネジメント」という制度が平成14年から開始されます。いわゆる「ケアマネジャー」が患者さんの家に行って,彼らがどういう生活をしているか,つまり,「きちんと食べているか」「食べ方はどうか」「お風呂に入っているか」「掃除はされているか」「人と話しができるか」など,介護保険法と同じような項目をいくつか挙げて,5段階で点数化し,コンピュータで処理します。
今までどのような医療を行なってきたのかということを一切抜きにして,医師がほとんど関わらない形でケア会議というものを作り,患者さんの生活をレベルアップしようとしています。「この患者さんはこういう点が問題だから,こういうふうにしよう」というような制度が現在進行中です。
医療と福祉が分断され,それを国が制度化しようとしています。
川上 それは介護保険法ですか。
浜田 いえ,老人に関してすでに始まっています。身体障害者と知的障害者と精神障害者の3つをひっくるめて「ケアマネジメント」という制度が進行中なのです。
川上 それに関連して,先生は小坂英世さんに対応して岡上和雄さんを非常に高く評価しています。今はともかく,初期の岡上和雄は中間施設を川崎で作っていた。また保安処分に反対した。先生が精神障害者のケアマネジメントが始まると言われますが,同時に保安的なものも出されてきていますね。
浜田 そうですか。
川上 新聞に出ていました。これは精神科医だけでなく全国民の問題ですが,精神科医が立ち上がる気配はまったくないですね。この間,新聞に出ていた要綱では,実態は保安処分的なものです。
浜田 これは,われわれ地域で活動している医師にはまったく隠しされています。一応,厚生労働省と法務省の保安処分新設の合同検討会に,何人かの精神科医が入っているのですが,彼ら他の精神科医にその情報をまったく流さないですね。去年の秋頃,どこかからか漏れてきて,それからわれわれが慌ててどう対応すべきかを考えているところです。しかし,精神科医自身に危機感意識がありません。特に,若い精神科医がだめです。社会的文脈の中で捉える視点が乏しいですね。
「多様な暮らしに寄り添う」と言うと,少しいやらしくなりますが,私の日記は「多様な精神分裂病者の暮らしを,その現場で見守っていく」というスタンスで書かれているのですが,現在の日本の社会はそれとまったく逆の方向へ歩みつつあります。
つまり,点数やコンピュータで評価していくこと,これは介護保険と同じです。介護保険が痴呆というものに対してまったく無力であるのと同じように,精神障害者に対してもおそらく何の役にも立たないだろうと思います。かえって彼らを傷つける危険性を持っています。
川上 浜田先生が書かれたこの本をどう読んでいくか,特に日記の部分をどう読んでいくかということは重要です。高度成長とバブル崩壊が終わった今,先生が診た患者像と今とがどう変わってきたか。そこに焦点を置かなければいけないと思います。
日本人の「日記」と「記録性」
浜田 今回,「日記」という方法をとったのですが,後で私が分裂病を中心に編集し直したものですから,純粋な日記,つまり日記そのものではありません。これを書いた頃から,少し日記にのめり込みまして,いろいろ集めてみました。外国でも『アミエルの日記』『ジイドの日記』『ルナールの日記』などがありますが,きわめて内省的で,自分自身をとことん見つめていく方向性のものが多いようです。
その点,日本だけの現象かもしれませんが,日本では「記録性」という側面がかなりあります。例えば,清沢洌の『暗黒日記-戦争日記:1942年12月~1945年5月』(橋川文三編,評論社,1995),高見順の『闘病日記』(上・下巻,中村真一郎編,岩波同時代ライブラリー,1990),『終戦日記』(文春文庫,1992),伊藤整の『太平洋戦争日記』(全3冊,新潮社)などです。
この種のものは記録として,あるいは時代そのものの息遣いのようなものがよく出ていて非常に面白い。
もう1つは,その人の本質というようなものが出てくるものです。例えば,正岡子規の『仰臥漫録』や『病牀六尺』です。とにかくこの人は,「食うこと」「排泄すること」「眠ること」「来客があったこと」「死」の5点を延々と克明に綴ってあります。それがまた実にユニークで,面白いのです。
それと中江兆民の『一年有半』でも,天下国家を論じたその後に,「女房と八百屋で大根を何本と何を買って帰った」というようなことが書いてあって,意外性というか,非常に人間的な息吹きを感じるのです。
私の今回の本とほとんど同時に,フェレンツィという人がフロイトについて書いた日記『臨床日記』(みすず書房)という本が発行されました。ご存知のように,フロイトはブロイヤーと一緒に仕事を始めたわけですが,その本の中に,ある日フロイトが漏らした言葉として「ヒステリー患者は嘘をつく。嘘をつくから自分は失望した」と言い,以後,フロイドは二度と患者を愛さなかったという一文があるのです。
あれだけ患者にのめり込んでいったフロイドが「二度と患者なんか愛するものか」という怒りに満ちた感情をあらわにした。日記という形だからこそ,それが生きてくるのだろうと思います。
日記というものが医療史の中でどの程度の評価を得ていたのか,私はつぶさにはわかりかねますが,精神科医の書いた日記というのはわりとつまらないですね。
「医療史」の中の「日記」
浜田 川上先生,医療史の中でも日記という形は他にあるのでしょうか。川上 例えば,石川啄木の日記と梶井基次郎の介護日記と比較しますと,やはり階層性が露骨に出ています。
石川啄木の場合,東大の青山内科に入院しても,牛乳を飲むのと解熱剤を飲むぐらいです。自宅に帰ってから開業医に往診を頼むと,代診が来る。解熱剤もケチるので売薬に頼らざる得ない。そういうことが書いてあります。
梶井基次郎になると,母親が来て温泉でじつに丁重な介護をしてくれる,ということもわかります。
それから,先生は無意識だったと思いますが,日記を書く時にはある目的が自然に働きます。それは,政治家の場合が多く,例えば西園寺公望や木戸幸一の日記がありますが,木戸日記の場合は非常に自己防衛的側面が強いです。今の政治家でも日記をつけている人はいると思いますが,そういう人は日記をつけることによって明日の道を探し当てるわけです。要するに,自分のところにいろいろと言ってくるけれども,それをつけていれば,「あいつはこの前,こう言っていたけれどもどうだ」ということになります。
先生の場合も,知らない間に,「分裂病とは何なのだろう」というテーマが頭の底にあって,それを日記に書いている。そういう点では「患者さんの日記」というよりも「政治家の日記」に近いと思います。
浜田 なるほど。医者の書いた臨床日記は多いですか。
川上 いろいろありますが,医者の書いた日記は総じて面白くないですね。やはり,山田風太郎の日記『戦中派不戦日記』(講談社)が一番面白いですね。
そういう意味では,この本で分裂病論が確立されたというふうに,直線的に理解すべきものではないのではないでしょうが,分裂病を論じる時の大きな材料,土壌を提供したと私は理解しています。それが,「論」への道です。
浜田 過分なお褒めのお言葉をどうもありがとうございます。また本日は,長時間大変有益なお話をお聞かせいただきましてありがとうございました。
(おわり)

