対談
慢性肝炎診療の現状と問題点
『慢性肝炎診療マニュアル』発刊によせて
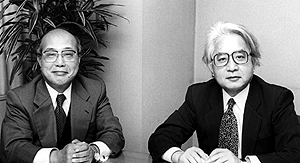 | ||
| 沖田 極氏 山口大学教授・医学部先端分子医科学 消化器病態内科学/日本肝臓学会理事長 | 小俣政男氏 東京大学教授・消化器内科学 日本肝臓学会企画広報委員会委員長 | |
『慢性肝炎診療マニュアル』について
沖田 今回,日本肝臓学会が監修した『慢性肝炎診療マニュアル』が出版されました。本日は,この本を実質的に企画・進行なさった企画広報委員会委員長である小俣先生に,まず最初に,この本を企画した意図をお伺いしたいのですが。
小俣 学会活動を通して強く感じますことは,学会は専門家の間だけの議論に終始せず,持っている知識,ことに蔓延している疾病については,一般医の方にも広めていく必然性があると思います。
これまでも日本肝臓学会として『肝がん白書』や『肝がん撲滅のために』を出版し,大きな反響がありました。今回は沖田理事長のご要請もあって,『慢性肝炎診療マニュアル』を出版したわけです。
C型肝炎をめぐる最近の動向-「有識者会議」について
沖田 広く一般医にも読んでいただきたい意図があるとのお話ですが,最近,特にC型肝炎については国民の関心も高まり,厚生労働省も「肝炎対策に関する有識者会議」を作って対策を考えました(資料参照)。これについてはどのようにお考えですか。小俣 まず第1点は,C型肝炎による肝疾患,特に肝癌の患者さんが急増しているという現状があります。またその一方では,C型肝炎に感染されている方が何人いるのかはあくまでも推定の域で,過去の感染は正確にはわかっておりません。そのような点からも,昨今の動きは啓蒙的な側面が多くありますが,それなしにはわが国のC型肝炎対策は成り立たないと思いますし,その一環として「有識者会議」は重要な側面を検討されていると認識しています。
しかし,C型肝炎対策はきわめて多様性に富んでいます。従ってわれわれの義務は,現に疾病に病んでいる患者さんをいかに救い,ひいてはわが国の国民の健康福祉が増進できればと,すべての肝臓専門医は感じていると思います。
沖田 ご指摘のように,わが国のC型肝炎の患者数の実態は把握されていませんので,対策の立て方も大変難しいです。もちろん強制はできませんが,40歳以上の方に関してはHCV(C型肝炎ウイルス)抗体を測れば概数はわかると思います。その点について,例えば今回の「非加熱血液製剤を受けた方を調べましょう」というのは,あまりにもわれわれの考えとかけ離れている点もあるような気がします。
小俣 非加熱製剤の問題は小さなフラクションの話だと思います。それを前向きに再スタートとして捉えるべきでしょう。基本的には新たな感染はほとんどないわけですから,過去の感染の原因を探求する問題と,現に立てなければいけない対策とを切り離して考えるべきで,後者に関してわれわれの責務は大だと思います。
エビデンスに基づいた対応を
沖田 過日,厚生労働省が昭和47-62年の間に非加熱製剤を使った病院名を発表しました。それらの病院で医療行為をされた人たち,ひいては国民全体がある意味で疑心暗鬼になってしまいます。つまり,具体的な実数がわからないままにそういうことが行なわれているわけですから,先生がおっしゃったように,啓蒙活動は大事でしょうが,同時にやはりエビデンスに基づいて対応しないといけない。そういう点からも,実態とかけ離れた形で動いているのではないかと危惧します。小俣 HCVの検査が可能になる以前の輸血にはすべて感染のチャンスがあったわけです。私が千葉大学にいた当時の昭和62年度の厚生省の班会議でも,キャリアは1.4%くらいと推定していました。当時はウイルスが発見されていないために,年間10万-20万というレベルで感染があったわけで,それが10年間累積しますとかなりの数になります。
沖田 危険性を煽るのではなく,具体的な実勢で議論することが重要でしょうね。
小俣 あるデータによると,40-50歳以上の方の2割ぐらいが肝機能障害に引っかかるそうです。特に最近は脂肪肝が多いですが,脂肪肝が多いから肝臓病が多いというのは間違いで,次の段階としてHCV抗体とHBs抗原を調べてほしいと思います。おそらく日本国民の95%以上の方は両方持っていませんから,HBs抗原とHCV抗体を調べると,脂肪肝もしくは単なる過度の飲酒との違いがわかります。倫理的な配慮も必要ですが,そこをまずやっていただきたいと思います。
慢性肝炎の診断上の問題点
沖田 次に,慢性肝炎の診断上の問題点に関してお伺いしたいと思います。一般医の方が,例えば「慢性肝炎」,あるいは「肝硬変に近い」という診断をどこまでできるかが最大の問題です。このへんについて,今回のマニュアルは具体的に記述されていると思いますがいかがでしょうか。小俣 ウイルスが発見される以前は,慢性肝炎は血液検査だけではわからないので,肝生検を最終的診断としていました。私自身も数十年,肝生検を行なってきましたが,きわめてまれですが,生検は事故があり,何よりも患者さんの負担が大きいわけです。それに,1度肝生検をしても5年もたてばまた変化します。患者さんの顔を見るたびに,何とか肝臓の中を見ることができないものかといつも思っていました。
小俣 ところがある時,10年間にわたるデータの時系列が出るようなコンピュータができ,それを使うとGOTやGPTなど一般的に使われている,いわゆる肝機能検査ではなく血小板が右肩下がりにきれいに落ちてくるのがわかりました。しかも,肝生検でしかわからない軽微な線維化,例えばF1やF2の微妙な動きが捉えられることに気づきました(表1参照)。
一方超音波検査で,時に正常肝でも肝硬変という診断が返ってきます。ところが,血小板はF1,F2でも微妙に下がってきます。例えば,同じ患者さんで5年前に23万であった方が,17万-15万になる。一方,年に2-3回,超音波検査をしていつも所見は同じでしたから,「もしかしたら,血小板数を測ることは,来院のたびに肝生検をすることと同じではないか」と。
10年前から血小板の話を強調しているのですが,「肝硬変になれば血小板が減る,ということは教科書に書いてあるではないか」と言われるのですが,肝生検を見続けた者にとって知りたかったのは,「F1,F2,F3」という軽微な変化です。しかし一方,軽微とは言っても30年間の生涯推定発癌率は,15%未満(F1)から90%(F3)と,きわめて大きく異なります。
また,日本のHCV陽性者の70-80%は,この「F1,F2,F3」群に属すると考えられます。富士登山に喩えれば,肝臓を検査して「悪い」と言われても,本当は富士山の裾野に留まっているにすぎず,一生何ともない人もたくさんいるわけです。65歳で血小板が18万でしたらF1です。年率推定発癌率は0.5%ですから,いままで1合しか飲んでいなかったお酒も,もう少しなら飲んでもよいかもしれない。医療現場のそういう体験がC型肝炎対策に織り込まれることが必要だと思います。
| (表1)慢性肝炎の組織学的ステージング | ||||||||||
| ||||||||||
患者さんの知識と医師の意識
沖田 肝臓の病気ではないかと思って来院される人達は,かなりの量の知識を持っています。問題はこれを患者さんの知識としてではなく,医師の知識として持っているかどうか,どこまで浸透しているかが最大の問題だと思います。小俣 最近の患者さんはよく勉強されています。GOTやGPTのデータを持ってきたり,「最近,こういう話を聞いたのですが,どうでしょう」と訊いてきます。今回のマニュアルは,医学的なことはもちろんのことですが,それとともに,一般医の方にとって簡便な方法も紹介しています。
沖田 血小板の下降に関しては,B型・C型の両方を同じと考えてもよいのでしょうか。
小俣 発癌した時点の血小板数を700-800例調べると,C型肝炎から肝癌に移行する場合は,14万で区切ると85%は囲い込めます。つまり,15%ぐらいの方は14万以上で発癌しています。ただ,B型はそれが少し異なり,10万単位で括っても4割を逃してしまいます。
それは発癌のプロセスが異なるからで,血小板の数が肝の線維化や硬変化を表すとするならば,やはりB型肝炎から移行する肝癌では,平地に波瀾(線維化がなくても発生する)が起こっているということがあります。ことに若年の方には多いと思います。ですから,正常肝に近い人からも発癌するB型肝炎は,外来の診療に慎重を要します。
沖田 そうですね。現状としては,B型とC型とその慢性肝炎の診療で若干の差異があることは認識していただきたいですね。
「点」として捉えるか,「線」として捉えるか
沖田 慢性肝炎を「点」と捉えるか,あるいは「線」と捉えるかという問題は重要だと思います。トランスアミナーゼが少し高いから直ちに慢性肝炎と診断するのでなく,慢性肝炎を肝硬変・肝癌という流れの中で捉えれば,患者さんがその線の上のどこにおられるかが理解できるでしょう。小俣 先ほどの例に戻りますと,私はよく患者さんに富士登山のモデルを書きます。先ほどのF分類で,「癌」が頂上の5段目とすると,肝硬変はF4,F1-3は慢性肝炎になります。
そこで,あなたはどこにいるかということがきわめて重要で,いわば「点」なわけですが,この1段を登るスピードが10年かかるということを,われわれは厚生労働省から支援を受けた共同研究で初めて明らかにしました(Shiratori Y, et al. Ann Intern Med 132:517-524, 2000.図1参照)。
つまり,毎年0.1段ずつ登ることになります。これが先生の言われた「線」かもしれません。F4でしたら,年率推定発癌率は7%ですから10年間で70%になります。一方,F1でしたら,われわれの成績ですと約0.5%未満ですから,F5の癌までは数十年かかることになります。そういう位置づけをしないで,GOTやGPTだけに注目していたのが肝臓病の診療の現場だったと思います。
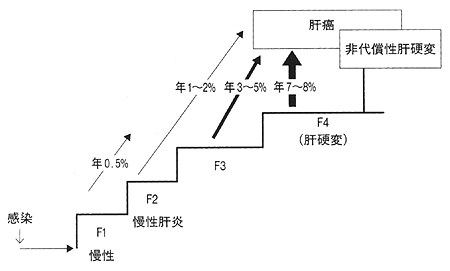 図1:C型慢性肝炎の自然史(病期の進展と発癌) |
| (『慢性肝炎診療マニュアル』〔医学書院刊〕より) |
肝癌に対する治療戦略
沖田 線で捉えなければいけないということも,小俣先生のご説明で十分おわかりいただけたと思いますが,その線上を走るスピードを落とすことで,つまり先ほどの富士山の例で言えば,逆に頂上から下へ降ろしていくことが可能になります。小俣 1つはウイルスを駆除してしまうことです。それにはIFN(インターフェロン)治療がありますが,「C型慢性肝炎の自然史」がきわめて明確になっている現在,これまでは先ほどのような位置づけなしで,むしろ闇雲に行なわれてきた一面もあったと思います。
例えば,30年後に癌になる可能性のある人にとっては,ウイルスを駆除することは確かに大事かもしれません。しかし,30年後の医療は相当変わっていますから,ウイルス駆除療法の必然性,すなわち発癌リスク算定をしなくてはいけないし,またそれが可能になりました。ステージングやF分類,あるいは血小板の数によって,「10年推定発癌率」や「生涯推定発癌率」を考慮して,適応の有無を決定することが第一ですね。
第2段階はウイルス量とgenotypeによって,ウイルスを駆除できるかどうかをインフォームすることです。そして,駆除できる確率が高いので,治療の要ありとなると,起こり得る副作用をすべて告知すべきです。例えば,「45歳でF3」の方であれば,残りの人生は30年で,年3%の発癌率ですから,90%の生涯推定発癌率を考えれば,ぜひとも治療を行なうべきでしょう。逆に「65歳でF1」の方には,たとえどのように小さくとも副作用を味あわせてはいけません。そのへんのご理解が少し足りないと私は思います。
沖田 IFN療法の話が出ましたが,一般の医師の方々にご理解いただけるかという問題があります。そのためにわれわれがどう努力すればよいかということになりますが,具体的にお聞かせいただけますか。
小俣 ウイルスの量やgenotypeに関しては皆さんがご存知です。しかし,IFN療法にしても行なう必要がない人もいるわけです。また,行なっても仕方がない方もいます。そのような生涯にわたって肝癌死に至る可能性がきわめて少ない方に対する認識,例えば先ほど申し上げた「C型慢性肝炎の自然史」から算定できる発癌率に関する情報を十分にお知らせしていない,また前述の会議でもまったく触れられていないことは大問題で,逆にわれわれが周知させる責任を負っています。それが今回のマニュアル作成の大きな動機だと思います。
C型慢性肝炎に対する治療戦略
沖田 そう思います。一般医の方はIFNのメリットもよくわかっておられるし,いまご指摘なさったgenotypeやウイルス量にしてもよくご存知ですが,理解していることと,治療することがまた別になっていますね。小俣 その前段階の,治療の必然性があるかどうかという視点に対するご理解が欠落していると私は思います。大袈裟に言えば,繰り返しになりますが,C型肝炎の自然史に対する理解が十分でない。B型肝炎と異なり,C型肝炎はほとんど線維化の延長線上にある一本道で,その予後(発癌への道)が読めます。
沖田 もう1つの考え方として,肝庇護療法のようなものでトランスアミナーゼだけを下げていればよいのではないか。むしろそのほうが副作用もないし,コンプライアンスもよいのではないかという意見がありますがいかがでしょうか。
小俣 現実的な対応としては,やはりウイルスが駆除できる方は限られています。
治療の必然性があるけれども,ウイルスが駆除できない方には,各種の肝庇護薬によってトランスアミナーゼを下げ,発癌率も下がるという成績が出ています。近い将来を考えた場合,また,過去のIFN治療で,ウイルスが駆除された患者さんの劇的な効果を見た者にとっては,やはり駆除という道を探さない限りは,当座の踊り場的な対策だと思います。
抗ウイルス療法の今後の展開
沖田 C型肝炎に対する治療がウイルスの駆除ということになりますと,現在われわれは抗ウイルス剤としてIFNしか持っておりません。今後抗ウイルス療法を展開していくべきかということに関して,ご意見を伺えますか。小俣 昨今の議論がエイズとのアナロジーで語られているという意見が一部にあるようですが,外国で行なわれていたのに日本で行なわれていない対策というものがC型肝炎で何かあるかとしたら,外国ですでにスタンダードになっている治療が日本ではできないことです。これこそ,C型肝炎の最大の問題だと私は思います。
ご存じのように,本邦で10年前から始まったIFN治療は世界に先駆けました。世界的な見地からみても,日本発の相当な量の情報を世界の研究者にもたらしました。例えば,IFNを投与すると,線維化の寛解率が年0.28であるという報告があります(前掲:Shiratori Y, et al.図2参照)。
このような日本発の情報を,逆に外国の先生方が利用して対策を講じているという事態が生じています。外国では週に1回の投与で済むPeg‐IFNとリバビリンはスタンダードになりつつありますが,依然として日本ではIFNの単独療法が行なわれています。いわば「4合目から5合目」,つまり間もなく癌になろうとしている方が最も多い長寿国日本ではできないのです。
エイズとのアナロジーを探すのであれば,こういう状況こそ,当時非加熱製剤をストップしなかった状況に近いのではないでしょうか。マグニチュードは違いますが,あえて言うならそう思います。
沖田 その通りだと思います。エイズにしても,問題になった時に厚生労働省は,法の枠を超えて輸入して使用したこともあるわけですね。C型肝炎に関しても欧米でリバビリンのようなものが出ているわけで,これだけ多くの患者さんがいるのですから,早く使えるような状況を作らなければいけないと思うのですが,いかがですか。
小俣 新GCPも施行され,行政当局もだいぶ前向きになっておりますから,できるだけ早く最善の抗ウイルス計画を日本で認可する方向に向かえばよいと思います。
私はPeg-IFNとリバビリンがスタンダードになると思います(追加注:Peg‐IFNとリバビリンの併用療法が日本で難治と言われた1型高ウイルス群で,実に46%の駆除率であるというデータが,米国・アトランタで行なわれたDDWで発表された。昨年秋のダラスのAASLでも同様の発表があり,本邦で唯一紹介されているIFN単独療法の7-10%と比して明らかな差がある)。さらに,この併用療法は「1b」以外の方の駆除率も非常に高く,9割ぐらいです。先日の会議でも,「癌にならないウイルスだけを駆除しているのではないか」という議論にはがく然としましたね。
先生と同様,私も癌患者さんを日々診察していますが,患者さんは不幸にして日々亡くなられます。そういう患者さんのウイルスが高率に駆除できると外国で既に報告されているのに,日本では行なうことができないのは非常にナンセンスです。
沖田 そうですね。肝臓病に関する情報を日本から世界に向けて発信したいのですが,外国から入ってきた情報を追っかけているような状況になってます。
小俣 抗ウイルス剤療法に関しては,国や薬剤メーカーの力によるところが大きいです。その機会を与えられず,そのツールもなしに世界と戦えと言われても無理です。その機会を与えてもらえれば,患者さんに対してどう使うべきかということに関してわれわれは知恵を絞ります。それが許されてない現状に対して,われわれが辛いと言うより,患者さん自身が大変辛いことになります。ウイルスが駆除できるかもしれない患者さんが相当数いるのに認可されていないという現状は,非加熱製剤をストップしなかった状況にある意味では似ていると思います。
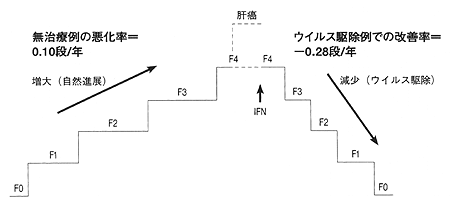 図2:C型慢性肝炎の線維化進展率とウイルス駆除による改善 |
| (『慢性肝炎診療マニュアル』〔医学書院刊〕より) |
21世紀の肝臓病学――――
グローバル・スタンダードの中で考える
沖田 その問題については,日本肝臓学会としても声を大にして呼びかけ,なおかつ行動に移さなければいけないと思います。この点は,企画広報委員長の小俣先生のアイデアや行動力が期待されていますが,今後どのように取り組んでいくか,具体的なお考えをお聞かせくださいますか。
小俣 IFNに関する抗ウイルス療法の国際性の欠如に関しては,第1に併用療法がスタンダードになっているのに,日本では単剤療法が行なわれていること,第2にIFNが国際的に比較しても非常に高価であること,第3に治療期間が半年と限られていることが挙げられます。かつて長期に行なったほうがよいというデータを日本から出しましたが,半年というのは日本だけです。それから,第4は「肝硬変には施行するな」と言っていることです。間もなく癌になる人に施行するなと言っているわけで,肝硬変に対する無理解の証でもあります。
非代償性肝硬変でお腹に水が溜まった方は無理ですが,慢性肝炎の地続きである初期肝硬変(代償性)の方に治療ができないことは大問題だと思います。外国ではすでにそちらに焦点を絞っています。
昨年9月,米国は国を挙げて「HALT-C Stage(C型を止めろ)」という研究を開始し,私は参考人としてNIHに呼ばれて,2時間ほど話をしました。彼らは何としてもF4の患者を癌になることからまぬがれさせたい(HALT-C)という研究を7年掛かりで開始したわけです。まだC型肝炎の発生率がわが国の4分の1の米国でさえも本腰を上げている一方,わが国では超高危険群であるF4は治療対象から外れています。
F1やF2の人が癌になるのは30年後ですから,そういう場合とは医療のレベルはまったく異なってきます。しかし,グローバルスタンダードという観点から考えても,今挙げた4点はぜひとも早急に是正しなければならないし,企画広報委員としても声を大にしたいと思います。
われわれが現場で何をしているかというと,世界に類をみないほど綿密に癌の早期発見に努めているわけです。逆に言うと,早期癌の診断に関する日本の医療のレベルは非常に高いと思います。世界に冠たる診断能力を持ってますし,癌の治療法も日本独自のものがあります。先ほどの比喩に戻れば,富士山の頂上にいる人に対するマネージメントは,日本は非常に優れていると私は思います。優れた抗ウイルス療法という武器さえ与えてくれればと,日々切歯扼腕しております。
沖田 最終段階である肝細胞癌に至る過程は,ほとんどが慢性のウイルス性肝炎を原点として進展するのであれば,やはり慢性肝炎の段階で,いわゆる「富士山の頂上」に行かないように,われわれ肝臓専門医はその先陣を切って努力すべきでしょう。
本日はお忙しいところを,どうもありがとうございました。
小俣 こちらこそ,ありがとうございます。
| (表2)主なウイルス性肝炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (「肝炎対策に関する有識者会議報告書」より) |
| (資料)「肝炎対策に関する有識者会議」報告書概要
I.肝炎対策の検討〈略〉
|
