〔連載〕How to make
クリニカル・エビデンス
-その仮説をいかに証明するか?-
浦島充佳(東京慈恵会医科大学 薬物治療学研究室)〔第8回〕高木兼寛「脚気病栄養説」(8)
米ソ核軍縮交渉
「Walk in the Woods」とは,米ソ核軍縮の交渉過程から生まれた言葉です。最初,米ソ軍縮会議派遣団は交渉の過程で暗礁に乗り上げていました。そこでアメリカ代表と旧ソビエト代表は会議センターを離れ,一息入れるため,そばの森の中を一緒に散歩しました。歩きながら,彼らはお互いの考え,興味,目的,人生観について腹を割って話し合い,人間対人間として相互理解を深めました。
そして,会議センターに帰ってくる頃には,森の中を歩く前,まったく道筋の見出せなかった軍縮問題も,一気に解決に向かったのでした。
多角的交渉術(multi-dimensional negotiation)
このような交渉術を「multi-dimensional negotiation」と言いますが,ここで言う「dimension」は会議に参加した各人が持つ性格,立場,考え,意思,現実問題などを指します。当然,参加者によってdimensionは異なるはずです。そして,このdimensionから見た問題解決は,「uni-dimensional」, 「two-dimensional」,「multi-dimensional」の3つに分けて考えると理解しやすいと思います。
まずuni-dimensionalは,他人のdimensionを無視した交渉者の自己満足を指します。
つまり,「私はこれがしたいからこれを行なう。他人がどうなろうと構わない」という理屈です。「高蛋白食なんて金のかかる食事は,絶対困るんだよ。交渉の余地はないね」という考えはuni-dimensionalに相当します。
Two-dimensionalとは,「われわれと奴ら」という見方をします。
自分たちは何を達成するかを知っており,相手は打ち負かすべき敵,あるいは障害でしかありません。結局,勝つか負けるか,食うか食われるかでしかないのです。Two-dimensionalの考え方の人は,「海軍の連中に負けるわけにはいかない。栄養が病気の原因だなんて聞いたことがない。結局のところ,病気は細菌によって発生するのだ。これから脚気病細菌説を唱えて徹底交戦する。これはドイツ医学とイギリス医学の対戦でもあるのだ。脚気病栄養説を医学界から葬ってやる」という言い方をするでしょう。このような状況では,交渉が前進するはずもありません。
一方,multi-dimensionalな問題解決は,「お互いの協力が成功の鍵を握る」ということを皆が心の底で知っている点で大きく異なります。
このような場合,交渉を成功させる上でバランス感覚を育てることが大切となります。交渉過程で時に,two-dimensionalとなることがあるかもしれません。しかしながら,交渉の流れが変わっても,常にmulti-dimensional approachの利点を見失ってはいけません。
それでは,具体的にどうやったらmulti-dimensional approachを皆の心に根づかせることができるのでしょうか?
そこで,「Walk in the Woods」が威力を発揮します。
「Walk in the Woods」のステップ
「Walk in the Woods」の「Walk」は,multi-dimensionalでの問題解決と自己発見の道のりは一歩一歩進むところからきています。大概,大きな問題を討議する際,テーブルに着席するメンバーは各々の思い,考え,要求,願望を胸に秘めて臨みます。このようなメンバーの意思を統一することは難しいものです。「Walk in the Woods」の特徴は,通常の討論を回り道する点にあります。この交渉術は核軍縮の時に威力を発揮するだけではなく,夫婦間の問題でも,看護婦―医師間の問題でも使うことができます。
次回は下の図を具体的に解説していきたいと思います。
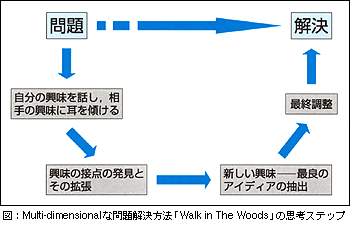
(この項つづく)
