《新シリーズ》
この先生に会いたい!!
《なぜ箕輪先生に会いたいのか?》
ACLS(Advanced Cardiac Life Support;2次救命処置)について勉強会を行なう時に,さまざまな救急医療の教科書や雑誌を調べました。そしてそれらの中に何度となく箕輪先生の名前を見つけました。そこで,あらためて自分自身が今まで読んできた医学書を探してみたら,箕輪先生による『医療現場のコミュニケーション』や『救急総合診療Basic20』(共に医学書院)などの著作や『ミシガン診察診断マニュアル』,『ケースブック問診と身体所見でここまでわかる!』(共にMEDSi)などのHistory taking/Physical examinationを重視した翻訳書を見出したのです。
ある時は患者さん中心の姿勢を強調するジェネラリストとして,またある時は患者さんのエマージェンシーに的確に対応していく救急医としての活躍がとても印象的であり,惹かれるものがありました。
卒業を控え,まもなく医療現場に出ようといういま,ぜひ箕輪先生にお会いして,先生ご自身の「医療への思い」を直接聞いてみたいと思いました。
(大野博司)

大野 箕輪先生は学生時代をどのように過ごし,卒業後の進路をどのように考えていたのですか?
箕輪 僕は東京都出身の自治医大生でしたから,医学部へ入学した時から,いずれ離島に行くということが決まっていました。実は,理学部に進もうかとも迷ったのですが,「人の役に立ち,それが実感できる仕事をしたい」と思い,自治医大に進みました。「へき地だったら間違いなくそれができるだろう」と。もちろん,へき地がどのようなところかはまったく知らずに,一種のロマンだけでしたが。
何でもできる医者になりたい
箕輪 医学生になってからは,どんな医師になるべきか考え,自分の目標になるようなロールモデルを探してみたりもしました。「幸運なことに」と言うべきか,やがて,僕は明確なロールモデルに出会うことになります。それが佐久総合病院の若月俊一,国保沢内病院の増田進,ゆきぐに大和綜合病院の黒岩卓夫,権平達二郎の4先生でした。自分で「ここぞ」と思うところの先生には会いに行って,休みにはそこにへばりついていましたね(笑)。彼らは1つの場所で,住民とともに「地域」を作り上げていった。それまでなかった医療のあり方を創造していった。すごいですよ。いつしか「へき地で何でもできる医者になること」が僕の目標になっていました。「何でも診る,決して断わらない医者になるにはどうしたらよいか?」医師として成長していく中で,僕はずっとこのことを問い続けてきた気がします。
大野 「総合診療医」,「ジェネラリスト」でありたいという考えが,箕輪先生の医師としての基盤にあるのですね。つまり,「なんでも屋さん」というような……。
箕輪 何かでくくろうとしたらね。
大野 救急医療もその活躍の場の1つだということですね。
箕輪 そうですね。日本の中で自らをジェネラリストと位置づけて,十全に力を発揮しようと思ったら,へき地で仕事をするのがいちばんいいですね。ましてや,自分の生まれ故郷であれば最高です。地元の名士であり,近所に住んでいるのは,小学校の同級生や小さい頃から知っている近所のおじさん,おばさんたちですから。
95年に米国デンバーの田舎へ行ったんです。Family Practice Residency Courseの中に「Rural Track」というものがあり,レジデントとしてへき地で過ごすのです。そこには指導にあたる家庭医が4人いてグループ・プラクティスをやっていました。そこに1-3年目の研修医がそれぞれ1人ずつ計3名が訓練を受けていました。彼らの話を聞いたら,みんな「俺はここで研修を受けたい」と手をあげて来ているのです。そして「将来,故郷の小さな村に家族と戻りたい」と言っていました。だから,そこで役立つ知識を,10床足らずのそのコースで勉強しにきたというんですね。生まれた所と働く所を完全に一致させて考えていて,人間が成熟しているなあと思いました。
日本でも,自治医大が類似のコースをもっていて,岐阜県の揖斐郡北西部地域医療センターと連携しています。また,室蘭の日鋼記念病院北海道家庭医療学センターでファミリー・プラクティスを地域の現場で教えるということがすでに始まっていますが,私の場合は,そのようなへき地の事情も何も知らないで,たまたま19歳で人生を選択したという感じがします。その後,三宅島で合わせて6年間,医者をしました。楽しかったし,たくさんのことを学びましたよ。いま,僕はへき地にはいませんが,そこで学んだことは生きているし,同じ「地域医療」をしているんだということを強く感じています。
地域を知らないと医療はできない
大野 いまもジェネラリストとして「地域医療」をやっていると。箕輪 そうです。ジェネラリストと言う時,いつもその身の置き所が問題になる。日本の場合には,1人診療所や200床規模までの病院の内科系ポジション,そして,救急,大病院の総合診療部くらいでしょうか? 僕はたまたま救急医療をやっているけれども,「地域救急医療」と「総合診療」でないと,絶対にいい救急医療はできません。僕はへき地でやってきて,全体としてのコミュニティ=地域を知らないと医療はできないことを学びました。地域で考えて,その中で救命救急センターの位置を決め,高度専門病院の持っている力を発揮する。来た患者さんに,1次も,2次も,3次もありません。みんな診ればよいのです。全部診て,病院の中で解決するために,病院の力を全部使えばよいのです。
大野 千葉市内では,1次,2次,3次が全部分担されていて,どこに送ればよいかという話があって……。
箕輪 それを医師でない救急隊に判断させるのは無理です。医師でも現場での問診と身体所見だけで判断することは難しい。私たちだって十分な問診と身体診察を行ない,その上に,病院のすべてを使って検査をして,はじめて診断の結果を出すわけですから。
医師もできない仕事をしてもらうには,救急隊に教育を徹底的に施す必要があります。それが無理ならば,やはり医師が現場へ出て行くことです。それを船橋は「ドクターカー」という形でやってきたのです。
僕はいま,病院の中にいるけれども,地域医療の中からみて,この病院をどう使うかを考えるんです。船橋の医師会の先生方もそう考えておられる。自分がやるべきことは,患者さんが来た時にこの病院の持っている力をどう発揮していくかを考えること,そして(患者さんと病院の)パイプになろうということです。船橋の持つ歴史の上に,蓄積してきた自分の力を使っているつもりです。もっともここに来たのは,まったく偶然のことで,金弘先生(船橋市立医療センター救命救急センター長)が,「ここにはジェネラリストが必要だ」という断を下して人を探された時に,声がかかっただけのことです。不思議な縁を感じています。
Bystander CPRとearly ACLS
大野 秋田市ではBystander CPRの実施率が非常に高く,船橋市ではドクターカーが機動的な活動を行なっている。この2つの市が,日本の中ではずば抜けて心肺停止状態からの蘇生率が高いという話を聞いています。箕輪 救急医療の概念を整理するならば,chain of survival(救命の輪)の中で,まずearly access,早く連絡をすること,次ぎにCPR(心肺蘇生)を始め,さらに薬を使って蘇生をし,病院に運ぶ。この輪が全部つながらないと救命はできないということになります。
その中で,まずBystander,つまり近くにいた人が人工呼吸をする。これは最初のいちばん大事なことで,秋田ではそれをやっている。船橋でも,中学校や高校,地域での教育の成果により,最近はだいぶBystander CPRの実施率が上がってきました。この1-2年では,3-4割の人が蘇生したという結果が出ています。人口55万人のうちの15万人にCPRを教えようという運動を,この15年やってきたのですが,それが功を奏しているのです。
もう1つはearly ACLS,薬を使った治療です。除細動も含めて,early ACLSを始めること。これは船橋では明らかに進んでいます。ドクターカーで,医師が現場で血管確保をして薬を使い出すわけです。通常,救急隊は除細動器しか持っていませんが,船橋では現場で薬剤を使用できるのです。僕らのデータでは,除細動だけだと約1割,あとの9割は除細動以外に薬剤を使ってはじめて心臓が動き,社会復帰している。だから,Bystanderはもちろん大事ですが,early ACLSで,早い段階で現場に医師と薬剤が到着して治療することも大事なことです。これは車の両輪で,片輪だけでは絶対によい成績はあがりません。
「究極のICUは地域だ」
大野 かつて秋田大で稲葉英夫先生(現金沢大教授)が行なわれたように,医学生がハイリスクの退院患者さんの家族にCPRを教えてはどうかと,千葉大でも検討しています。箕輪 それはよいですね。私たちの施設では,ハイリスクの患者さんの入院中に,その家族に救急救命士が教えています。「あなたのご主人(奥さん)はまた具合が悪くなって,また救急車のお世話になる可能性がありますから,今のうちに勉強しましょう」と言って,自分の夫や妻が救急車で運ばれていった時のことを思い出せるうちに指導するのです。そうすると,モチベーションが高いから,あっという間に身につきます。この2年間でたった1例だけですが,旦那さんが再び心停止になった時に,指導を受けていた奥さんがBystanderになり社会復帰できたことがあります。
大野 病院や救急車の中ではなくて,町の中を,あるいは家庭自体を1次の救急施設にしていくという考え方が大切ですよね。
箕輪 その通りです。AHA(米国心臓協会)による2000年ガイドラインに出てくる言葉の中に,「究極のICUというのは地域だ」というものがあります。これはどういうことかというと,地域のあらゆるところでCPRがなされて,除細動器が置かれたら,それが究極のICUだというんですね。アイゼンバーグという人の言葉だそうで,30年前に言ったらしいです。すごいと思いませんか。その想像力! 日本の医師が,病院からものを見ているのとは違い,すでに30年も前からコミュニティの中でものを見るという発想があった。やはり,米国のお医者さんのほうが上だね(笑)。これは,そのまま社会の成熟度の違いですよ。「救急は,地域のものだ」なんて当たり前のことなんですね。
大野 どちらかというと,日本では疾患とか病態生理とか,そっちのほうに向かっていく傾向があるのに対して,欧米では,目の前の患者さんにいかに役立てるかという意識が……。
箕輪 目の前の患者さんに役立つためにはどういうことが必要か,そのためには病院に何を用意するべきか,そして個々の病院に力の限界があるとしたら,地域全体で何をしなければいけないかという発想は,論理的ですよね。欧米ではそれが自然に行なわれている。一方,船橋の場合には,地域の医師会の人たちが,特別な医療をというよりも,船橋の医療をよくするにはどうしたらよいかを考えてやってきたことが,これもきわめて論理的だったわけで,それがよい結果に結びついていると言えます。
患者さんから出発する救急総合診療
大野 学生仲間とACLSの勉強会をしたり,箕輪先生の編集された本(『救急総合診療Basic20問』)に出会わなければ,救急医療というと,エマージェンシーに対応するというよりも,むしろ侵襲学だったり,病態生理学だったり,学問としての「救急医学」で終わってしまい,目の前の患者さんにどういうふうに対するか,アプローチの方法などを学ばないまま医師になってしまったと思います。箕輪 大学というところは制限された,特殊なところですからね。僕たちが学生のころもそうでしたよ。自分たちの手元にないものは,わざわざ佐久病院やゆきぐに大和綜合病院まで休みのたびに教えを請いに行ったわけです。大学の中だけでは決して学べないことはありますから,学生さんには積極的に学外で学ぶことを期待します。
あとは自分の興味です。侵襲学が好きな人には,「やるな」と言ってもやるでしょう?それと同じです。逆に,侵襲学が嫌いな人に「別の救急がありますよ」と言ったら,こっちをやるでしょう。しかし,教育する場面としてどちらが多いかというと,明らかに日本では専門分化して,ディジーズ・オリエンテッドのものをやっている。それでは,コミュニティからのものの見方とか,ペイシェント・オリエンテッドの仕事は見えない。それは教えられていませんから。でも,それではいけません。
僕はいつも言うのですが,救急車で来る患者を「おもしろい」と思えばいいんですよ。「どうしてこの人は救急車で来ちゃうの?」と。「こんなに軽いのに,どうして救急車で来ちゃったのか?」と。そこに興味を感じればいいのです。「この人は,腰が痛いだけなのに,どうして救急車で来てしまったのか」とか,頭痛とか,なんでもない人が,「家族の事情で来ちゃった」なんていうことがあるわけでしょう?こんなにおもしろい話はないじゃないですか。どうして家族がそういう判断を下したのか。この人の何が家族に「おかしい」と思わせたのかとかね。それをおもしろいと思える人間は,大丈夫です。それを「つまらん」「きわめて不愉快である」という人には,(救急には)来ないでほしいですね。そういう人は,救急医療をやらないほうがいい。「どうして来たのか」,すべてはそこから始まるわけですからね。
救急車で来た患者との出会いを楽しいと思い,その患者さんの問題を自分で見つけようとすることのおもしろさ,これがもっと教えられるとよいのですが。ジェネラルなものの見方というのは人間を見る時の見方だから,臓器学とは違います。
地域を変える
大野 話は変わりますが,僕が入っているメーリングリストで,ある救急救命士の方が,患者さんにとって,救命士と医師との連携関係はどういうものがあるべき姿なのかということを以前,話題にされました。その方は,ある病院では取り合ってくれないし,CPRもやらずに,ただ患者さんが死ぬのを待っているだけというような医師を見たこともあって,そのもどかしさを訴えておられました。一生懸命市民に向かってCPRを教えてきたのに……と。箕輪 その救急救命士の人は一生懸命で,熱意とやる気のある人なんだね。その人たちがそういう医者の姿をみると,いやになるだろうと思います。しかし,逆に医者にも「もうその段階ではない」という場面も実際にあるから,「いつでもその場ではこうすればいい」ということではないと思うのです。
お互いに幻想はないほうがいいです。救命士も,医者が万能だと思ったりしないほうが……,まあ,思ってはいないだろうけれども。少なくとも,すべての医者が同じように有能で,同じようにできると考えるのは,お互いにとってよくないね。どこの施設でもそうだと思うけれども,働いている人に完璧は求められないのと一緒です。それは,医療のチームプレイの場でも同じでしょう。搬送先の病院の先生が,自分の期待したとおりの医者であることなんて,きわめてめずらしいし,逆に医者の側が考えているとおりの救命士であることも少ないですよ。しかし,それを前提にした上で,チームプレイをしなくてはいけないということです。1人ではできないのだから。
例えば,へき地ではリソースが少ないんですね。医者も看護婦も少ない中でやり繰りしなければいけないのでつらいです。私の経験では,吐血患者が出た時に輸血用の血液が日赤から来ないのですから,自分たちで血液を用意するしかないのです。あらかじめ血液型を聞いておいた村役場の若い野球部員たちを夜中に呼んで,同時にその家族に声をかけて,従兄弟や親類で同じ血液型の若い人を探してもらう。輸血センターもない体制で,検査技師もいない中で,しかし輸血をしなければいけない状況でどうするか。自分たちで作るしかないんですね。
この限られたリソースの中でやるという点では,実はどこにいても同じだと思うのです。自分たちの持つものを使ってどうしたらいいかを考える。それは救命士も同じだと思う。
自分たちが運んでいく先の病院,あるいは自分たちの地域にある病院の先生たちについて,その水準が貧困だと思い,「なんとかしたいがどうしたらいいか」と思ったのだとしたら,それを解決するために考えられることは何でもやってみてほしいですね。地域の中のキーパーソンになる医者を見つけて引っ張っていってもらうのもよし,あるいはそれが駄目なら市民の側から訴えを起こしてもらうのもいい。
例えば佐久の若月先生の場合は,医者の情熱に地域も応え,農協も応え,行政も応えてくれて,そうやって町が盛り上がっていった。逆に沢内村は,深沢村長という偉い人がいて,「うちには医大のローテーションの医者はいらない,地域のことを知らないような医者は来ないでいい。自分で医者を探してくる」と言って,自分たちの好みに合った医者を村長が探してきたのです。これも1つの優れた見識でしょう。「地域のために,俺が市長になったらあの医者は辞めさせてやる」というようなね。そういう人が出てくるようにならないと,地域は変わりません。ちょっと過激な意見ですが(笑)。
大野 市民と,救急救命士と,医師の三者が会って情報交換ができる場があればよいと思うのですが。
箕輪 そう。船橋市でも,毎月,ドクターカーの医師会の先生と救命救急センターの先生,そして救命士が集まっています。でも,そういう場があっても,その場を引っ張る人がいなければ駄目です。「俺はやる!」という人ですね。
船橋には情熱に燃える医師会の先生方や金先生がいた。秋田にも,立派な先生がいて,消防の中にも熱心な人がいて,そういう人たちがいたからできたことです。
大野 市民のレベルでも,救急救命士のレベルでも,医師のレベルでも,自分のやるべき仕事というか,役割を果たした結果として……。
箕輪 パートナーシップができた。千葉市のように人口100万という規模になると,なかなか身動きが取りにくいけれども,船橋のように55万の人口のところでこれができるのだから,数十万の都市でもできるし,数千人のへき地ならもっとやれる。
DNR(Do Not Resuscitate)
大野 もう1つおききしたいことがあります。日本でのDNR(Do Not Resuscitate),何かで倒れて運ばれてきても「(治療を)されたくない」と思った場合の現実というのはどうなのでしょう。箕輪 日本でDNRを実施するには,まだ法的な限界があります。アメリカでは,Advanced Directive(=生前意思)については法律になっていて,書かなければいけませんが,それは必ず守られます。僕がデンバーに行った時にお世話になったお年よりは,それをどう書こうかと悩んでましたね。数枚つづりになっている書類の提出期限が決まっていて,例えば「ICUに入った時はどうする」とか,「意識がなくて運ばれた時にはどうする」とか,「臓器の提供についてはどうか」と,全部あるんです。だから,きっと市民は悩んで決めるものなんですね。そうやって悩んで決めた,その意思表示がわかるような仕組みができている。そういう法的整備が進んだり,あるいは法律化しないまでもそういう方向にだんだん成熟してきた時に,DNRについての医療機関の対応ははっきりしてくると思います。
DNRについてはいろいろな研究があって,病気を持っている本人のかなり親しい人,例えば主治医や家族に尋ねた場合と,本人の意思とがどれくらい一致するかというと,きわめて一致率は低いそうです。だから,本人以外の人たちが理解していると思ってDNRをやっても,実際にはそれは本人の望んだAdvance Directiveというかたちにならない。言わば,家族と周囲の人たちのDNRですね。もちろん,そこには周囲の人たちにとっての意味があるのだけれども,本人の意思を確認した上でのDNRは非常に少ないと思います。これはおそらく問題になるよね。僕は,問題だと思いますよ。
大野 救急の場で,「これは家族のため,身内のためのDNRではないか」と疑問を持ちながらやってるところも,少なからずあるのでしょうか。
箕輪 いちばん身近だった人が意思決定をしてくれていると信じてはいるけれども,それが,本人の意思だったかというのは確認できずにやっているところはあるかもしれません。これは未解決の大きな問題です。
大野 生前に,死など不吉な話をするのをあまり好まないような姿勢が,日本人の死生観としてあるような気がします。
箕輪 それはまだ勉強不足でよくわかりません。死生観,日本人の死についての考え方や,死の迎え方というのは西欧とは違うとは思いますが,これはまだ仮説の域を出ないのではないでしょうか。結論するには情報が乏しいと思います。しかし,大切な疑問です。そういう疑問から始まって解決する努力をしていかないといけないと思います。
大野 いろいろと貴重なお話をありがとうございました。
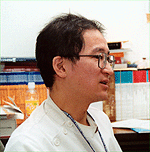 | 箕輪良行氏
1979年自治医大卒。79-81年都立豊島病院でローテイト研修。81年日本医大救命救急センター。82-85年三宅島阿古診療所。85-88年都立墨東病院救命救急センター。88年-現在自治医大(91年より大宮医療センター講師)。92-95年三宅島中央診療所長。98年-現在船橋市立医療センター救命救急センター部長。主な著書に『医者は患者の味方です』(潮出版),『医療現場のコミュニケーション』(共著,医学書院),『救急総合診療Basic 20問』(共編,医学書院)。 |
| 大野博司さん
26歳。「自分自身を活かし,本当に社会に還元できることは何か?」で悩み,早大理工学部を中退。千葉大医学部へ入学。長期休暇には,体の不自由な子どもたちのキャンプに学生ボランティアとして参加している。昨年,青木重憲氏(茅ヶ崎徳洲会総合病院)の主催するACLSコースに参加し感銘を受け,医学生が卒前に身につけるべき必須の技能として,心肺蘇生・ACLSを捉え,学生主体のACLS勉強会を開催している。今後,千葉大だけでなく,他の医科大学でも開催する予定。e-mail:QWI03166@nifty.ne.jp |  |
