連載
「WHOがん疼痛救済プログラム」とともに歩み続けて
武田文和
(埼玉県健康づくり事業団総合健診監・埼玉医科大学客員教授・前埼玉県立がんセンター総長)
〔第22回〕患者とのコミュニケーション(2)
がん患者に真実を伝える-その2
ほとんどの患者は真実に気づいていた
埼玉県立がんセンターで,患者に真実を伝えること「truth-telling」の検討が進んでいた1989年,第27回日本癌治療学会総会(メインテーマ:癌治療とQOL,10月25-27日,名古屋市)の特別企画シンポジウム「癌看護に求めるもの」の演者に,渡辺孝子副看護部長(現:国際医療福祉大教授)が指名され,患者自身による病名認知率を中心とした調査結果を報告した。当時の埼玉県立がんセンターは,300床の病床から年間400名のがん患者が死亡退院していた。そこでの3か月間における100名についての調査報告であったが,病名を伝えられていたがん患者は33%にすぎず,伝えられていないがん患者の3分の2以上が主治医の伝えた病名を「嘘」と見抜いていた。この調査結果は院内に大きなインパクトを与えた。またこの結果は,偽りの診断名と気づかれないために費やすエネルギーを,真実を伝えることと,伝えた患者の支援に費やすことのほうが合理的と,職員皆の考え方の方向性を決めることとなったのである。
真実を伝えられた患者の反応
このような考え方が患者に真実を伝える実践を推進させ,10年を経た時には,自分の病名や病状を知らないがん患者は皆無に等しくなった。1989年には33%にすぎなかったものが,1993年には真実を伝えられた患者が76%,1995年には92%,1997年は98%となり,病状説明も非常に充実した。同じ地域の,他の病院では29%という数値であり,この差は短期間で大きくなったが,患者からの苦情は寄せられなかった(図参照)。しかし,一方の医師については,毎年数人以上がこの問題を検討していない病院や大学から赴任して来るために,院内で議論を継続させる必要性はあった。真実を伝えられたがん患者は,一旦は心に衝撃を受けて落ち込むが,多くの患者は間もなく回復した。いずれの患者支援にも,職員がチームワークを発揮した。こうした支援に未熟な医師が患者本人に真実を伝えたという場合には,同僚医師や看護職が患者の観察とケアを強化して対応した。
看護職の観察によれば,真実が伝えられてから3-4週たっても精神状態が良好でない患者は10%程度であった。このような患者の場合には,精神科医もケアに参加した。そうすることで患者の精神状態は平常に戻り,あるいは初診時よりも改善し,前向きの姿勢がみられるようになる。また,病棟内の雰囲気が明るくなり,病室からは笑い声が聞かれるようになった。心身両面の苦しさのコントロールの成果とコミュニケーションの壁がなくなったことによると受け止めている。こうなるまでの経緯の中から,その検討内容を事例を通して紹介したい。
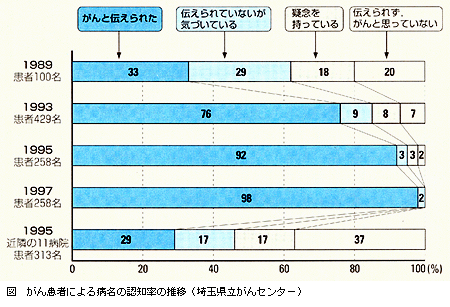
診断名を隠されたA氏
事例 A氏,63歳,男性,病名:胃がん。1990年,名門小学校の校長を定年退職した。3年後,A氏に強い頸部痛が起こった。近隣の医療機関での診察の結果,胃の進行がんを発見,がんは頸椎に転移しており四肢麻痺が始まっていた。がん専門病院を受診するよう勧められ,当時の常として本人に病名を説明しないまま,当がんセンターが紹介され来院。検査と処置が急いで進められ,痛みにはモルヒネが使われたが,十分な効果をあげずに数日が過ぎた。
温厚な教育者であったA氏は無口だったが,しばしば医師と看護職に怒りをあらわにした。このため奥さんと主治医,病棟婦長の話し合いが持たれたが,奥さんには「本人が発病以来なにも説明されずにいることが精神的動揺の原因と考えている」と伝えた。奥さんは,「世間の慣習にしたがっていて大切なことに気づきませんでした。主人には私が説明します」と答えた。
医療側は支援を約束し,奥さんは1人でベッドサイドに向かった。説明を受けたA氏は,「それならすべてに納得がいく」と奥さんの説明を受け入れた。その直後から,A氏は無口ではなくなり,主治医や受持看護婦と率直に会話し,十分な医療情報を得ることもできるようになった。四肢麻痺のため,ベッドに寝たままとなっていたA氏の残された時間は短かったが,毎日を平穏に過ごした。
その当時の日本では,がん患者本人に病名や病状を説明することなく医療行為が進められていた。しかし現実には,A氏のように悪い知らせ(bad news)であっても誠実さを持って真実が伝えられると,患者は悪い知らせを受け入れ,家族や医療者に支えられながら新しい状況に適応していくのである。伝えていないがために疑心暗鬼となった患者の精神的反応に苦慮した医師が,伝えたらもっと大変なことになると考えるのは誤りである。伝えた経験と伝えなかった経験の双方を持つ医師は「伝えるべきだ」と言う。しかし,伝えた経験がない医師は「伝えるべきではない」と感じているようである。
