印象記
第7回アルツハイマー病と関連疾患会議
遠山育夫(滋賀医科大学分子神経科学研究センター・教授)はじめに
「第7回アルツハイマー病と関連疾患会議」は,2000年7月9-13日の日程で,アルツハイマー世界会議2000(World Alzheimer Congress 2000)の一部に組み込まれる形で,アメリカ合衆国ワシントンDCで行なわれた。アルツハイマー世界会議2000は,アルツハイマー病に対する社会的関心が盛り上がる中,国際,米国,カナダの3つのアルツハイマー病協会が中心となって開催したもので,7月9-13日の研究主体の会議(「第7回アルツハイマー病と関連疾患会議」に相当)と,7月14-18日の介護・看護に関する会議からなり,さらにその前後にいくつかのシンポジウムやワークショップが行なわれた。私はそのうち,7月7-8日に開催された「アルツハイマー病の脳内炎症反応に関するシンポジウム(Neuroinflammation in Alzheimer's disease)」と,「第7回アルツハイマー病と関連疾患会議」に参加させていただいた。この1年,アルツハイマー病研究の進歩は著しく,最新の情報を集めようと毎日約3000名の参加者が詰めかけ,会場はどこも満員であった。またCNNテレビをはじめとするメディアも会場を取材し,会議の内容がテレビや新聞でも連日取りあげられるなど,アルツハイマー病に対する社会的関心の高さが窺われた。
会議では,毎日8時30分から10時まで,大会議場で3名の講師が特別講演を行ない,アルツハイマー病研究の最新の話題を解説した。5日間で計15名の講師による特別講演は,いずれも素晴らしいもので,すべてを聞くことにより,アルツハイマー病研究の全体像が見えるように構成されていた。特別講演に引き続き10時30分から12時30分まで,6つの会場に分かれてシンポジウムが行なわれた。午後は,最終日を除き一般演題が発表された。一般演題は,12時30分から14時45分まで展示会場でのポスターセッション,午後3時から5時まで6つの会場で口演発表が行なわれ,充実したプログラムが組まれていた。各種シンポジウムや口演が6つの会場に分かれて同時に行なわれ,すべてを聴くことは困難で,聴きたい演題を選択するのに困るほどであった。そこで,私が特に興味を持った発表を中心に,会議の成果を報告したい。
アルツハイマー病の脳内炎症反応とワクチン療法
まず,本会議に先立って開催された「アルツハイマー病の脳内炎症反応に関するシンポジウム」では,2日間にわたり,私を含め22名の招待講演者がワークショップ形式で発表を行なった。このシンポジウムは,世界各国の約30名の研究者で構成されるNeuroinflammation Working Groupが中心となって開催したものである。シンポジウムと同時に,研究成果を「Neurobiology of Aging」誌(Vol. 21, No.3, 2000)にも発表し意見を募るという,シンポジウムならびに誌上討論という2重の討論形式をとった。各講師の発表には,それぞれ10分ほどの討論時間が設けられた。発表が終わると質問者がマイクの前に並ぶ光景は日本の学会ではあまり見られず,いささか緊張した。このシンポジウムで最も注目されたのは,アルツハイマー病のワクチン療法を「Nature」誌に発表したSchenk博士(エラン製薬)の講演であった。ヒトのアミロイド前駆体蛋白(APP)遺伝子を過剰発現させたトランスジェニックマウスでは,加齢とともに脳内に多くのβアミロイドの沈着を認めることが知られている。Schenk博士は,このマウスの皮下にヒトのβアミロイドを注射して免疫を活性化させると,脳内のβアミロイドの沈着が著明に減少することを報告した。齢数によっては,トランスジェニックマウスの脳内のβアミロイド沈着が消失するほどの効果で,いまだかつてこれほどの効果がある治療法はなく,強いインパクトを与えた。その一方で,ドイツのHampel教授(ルードウッヒ・マキシミリアン大)は,COX2抑制剤を含めたアルツハイマー病の抗炎症剤療法が,今のところ思ったほどの成果をあげていないことを報告した。
こうしたことからSchenk博士は,アルツハイマー病で起こっている炎症反応はむやみに抑制すべきでなく,むしろ活性化させるべきだと主張した。アルツハイマー病の神経炎症の専門家の中には,抗炎症剤療法がアルツハイマー病に効果があると考えている人も多く,Schenk博士に対し多くの質問がなされ,会場の聴衆を巻き込んだ激しい議論が展開された。おそらく,脳内免疫炎症反応は,諸刃のやいばとして,病態に関与しているのであろう。この点に関し,Neuroinflammation Working Groupの代表者の1人Rogers博士(サンヘルス研究所長)は,本会議の特別講演で,「アルツハイマー病の脳内免疫炎症反応は,あくまで2次反応と考えるべきである。アルツハイマー病の根本治療が開発されれば,抗炎症剤療法はやがて消えていく運命にあるだろう。しかし,根本治療が確立されるまでは,いきすぎた炎症を抑える抗炎症剤療法は一定の評価を与えられるべきである」と総括し,会場から大きな拍手を浴びていたのが印象的であった。
アルツハイマー病の分子遺伝学
アルツハイマー病の原因究明については,今回も分子遺伝学的研究成果に注目が集まった。家族性アルツハイマー病の原因遺伝子としてAPP遺伝子に次いで,プレセニリン1および2遺伝子が同定され数年が経過した。本会議の関心事としては,家族性アルツハイマー病の原因遺伝子から孤発性アルツハイマー病の疾患関連遺伝子に移ったと言ってよい。すでに20種類以上の疾患関連候補遺伝子が報告されている。Tanzi博士(ハーバード大)は招聘講演の中で,アポリポ蛋白ε4遺伝子に加えてα2マクログロブリン遺伝子の重要性を強調した。しかし,引き続いて行なわれた分子遺伝学のセッションでは対立する報告がなされ,Tanzi博士らのグループとの間で激しい議論が展開された。全体的には,アポリポ蛋白ε4遺伝子はアルツハイマー病の疾患関連遺伝子として認知されたが,それ以外の遺伝子については,いまだ論争の中にあるという印象を受けた。
プレセニリンとβアミロイド
現在のところアルツハイマー病における最も初期の脳内変化は,βアミロイドが脳に蓄積することと考えられている。βアミロイドは,APPがβ-セクレターゼとγ-セクレターゼというプロテアーゼで順番に切断されて生じる。昨年,BACE,BACE2という2種類のβ-セクレターゼがクローニングされたが,γ-セクレターゼについてはいまだ不明である。興味あることに,家族性アルツハイマー病の原因遺伝子であるプレセニリンをノックアウトしたマウスから調整した初代培養ニューロンでは,γ-セクレターゼ活性が消失することが知られている。したがって,γ-セクレターゼ活性にプレセニリンが重要な関与をしていることが予想された。昨年,Selkoe博士(ハーバード大)らのグループが,プレセニリン1の6番目と7番目の膜貫通領域にある2つのアスパラギン酸(Asp)残基(Asp257, Asp385)のいずれかをアラニンに置換するとγ-セクレターゼ活性が抑制されることを報告し,プレセニリンがγ-セクレターゼそのものである可能性を示した。この報告以来,プレセニリンがγ-セクレターゼそのものか,あるいはγ-セクレターゼ活性に必要なコファクターなのかが盛んに議論されてきた。
本会議ではプレセニリンがγ-セクレターゼそのものであるとのデータが,複数のグループから報告された。中でも,メルク研究所のGardell博士らは,γ-セクレターゼ活性を強力に阻害する物質を使って,γ-セクレターゼの活性部位を光親和性標識したところ,標識されたタンパクは,プレセニリンのN端フラグメントおよびC端フラグメントであることを明らかにした。
これらフラグメントは,未知のプレセニリナーゼによって,6番目と7番目の膜貫通領域の間で切断される。興味あることに,切断前のプレセニリンタンパクは標識されないことから,プレセニリンは,断片化されてはじめてγ-セクレターゼ活性を持つと結論づけた。彼らのデータは,プレセニリンがγ-カットを行なうことを初めて直接的に証明したものとして強いインパクトを与えた。ちなみに,このデータは学会直前に「Nature」誌に掲載された。
一方,日本の西道博士(理化学研)らは,βアミロイドの分解機構に焦点を当てた研究発表を行なった。アイソトープラベルしたβアミロイドをラットの脳に打ち込み,その分解過程を詳細に分析し,主な切断部位を明らかにするとともに,分解を担う酵素がneutral endopeptidaseであることを示した。βアミロイドの産生・分泌機構に関する演題が多数を占める中で,分解経路に焦点を当てた西道博士らの研究は,独創的かつ重要であると思われた。
タウタンパク
前回の本学会では,Frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17(FTDP-17)におけるタウ遺伝子変異が注目を浴びた。今回の学会では,タウ遺伝子のエクソン12と13の領域の変異がピック小体様の神経原線維変化を生じさせることが報告された。FTDP-17以外のピック病,進行性核上麻痺(PSP),Corticobasal degeneration(CBD)などのタウオパチーと呼ばれる疾患群も,すべてタウ遺伝子の機能障害として捉えることが可能になってきたという印象を受けた。タウタンパクに関する最大のトピックスは,タウの変異遺伝子を導入したマウスの脳に,神経原線維変化が生じるか否かという問題である。ここ1-2年多くの施設がこの命題に挑戦してきた。今回ついに,Hutton博士(ジャクソンビル・メイヨクリニック)らがAPPとP310Lの変異タウ遺伝子のダブルトランスジェニックマウスで,日本の高島博士(理化学研)らがV337Mの変異タウ遺伝子を導入したトランスジェニックマウスで,それぞれ神経原線維変化を作ることができたと報告した。これにより,タウ遺伝子変異により神経原線維変化が生じることが動物モデルで確認されたとともに,神経原線維変化研究のよいモデル動物が完成したことになる。両演題は,最終日に設定されたホットトピックスに選ばれた。ちなみに,Hutton博士らのデータは「Nature Genetics」誌に受理されたと会場でうかがった。
アルツハイマー病の新しい治療戦略
上述のSchenk博士らによるアルツハイマー病のワクチン療法は社会的関心も高く,会場に各種メディアが取材に来ていた。CNNテレビをはじめとするテレビ局もこの学会についてニュースを流すとともにアルツハイマー病のワクチン療法についての特集を組んだ局もあった。新聞にもアルツハイマー病のワクチン療法が大きく取りあげられていた。Schenk博士が特別講演で述べたところによると,すでに米国と英国でアルツハイマー病患者に対するワクチン療法の第1相試験が行なわれたという。米国では,24名のアルツハイマー病患者に投与した結果,問題となるような副作用は見られなかったと発表した。Schenk博士らは自信を深めており,2001年には第2相試験を開始したいと述べていた。一方,「アルツハイマー病のメカニズムと治療へのアプローチ」というシンポジウムでは,γ-セクレターゼの阻害剤を用いたアルツハイマー病の第1相試験が進行中であることが報告された。
これまでなかったアルツハイマー病の病態に直結した治療法の開発が,ようやく実を結びつつあるという印象を受けた。同時に,基礎研究から臨床応用へのスピードの速さに驚きを感じた。γ-セクレターゼは,βアミロイドの産生に関わるとともに,細胞間の相互作用を担うNotchシグナル伝達にも重要な役割を果たしている。Notchシグナル伝達への影響による副作用など,速い臨床展開にいささか危惧も抱いた。
これら新しい治療薬を含め,現在有効とされているアリセプト(エーザイ)などの抗コリンエステラーゼ治療薬は,できるだけ早期に用いるのがよいと考えられている。そこで,アルツハイマー病の早期診断の試みもいくつか報告された。特別講演では,Petersen博士(メイヨクリニック)が「Mild Cognitive Impairment(MCI)」という概念を発表し,詳細に解説した。
MCIとは,「正常老化の範囲を超える記憶障害があるものの,その他の認知機能障害は見られず,社会生活も正常に保たれているグループ」と定義され,Petersen博士はこうした症例を医学的に積極的に捉えることを提唱した。なぜなら,正常老化からアルツハイマー病への移行時期にある患者もこのMCIグループに属しているはずなので,そうした患者をピックアップできればアルツハイマー病もごく早期から治療が可能となる,と考えられるからである。
メイヨクリニックでは,すでに1000例以上の症例をMCIとしてフォローしているとのことである。いまだ剖検例は少ないが,9例の剖検例の脳病理診断が報告された。4例がアルツハイマー病,4例がBraak病,1例が神経原線維変化のみを示す痴呆例(NFT-only dementia)であったという。本邦では稀と考えられているBraak病の頻度が高かったことはやや驚きであるが,MCIの約半数例は,ごく早期のアルツハイマー病であろうと結論づけられた。
おわりに
第7回アルツハイマー病と関連疾患会議は,3000名以上の研究者が参加し,1300題以上の研究成果が発表された。1つの疾患を冠する会議としては異例の規模であると思われる。一般メディアの関心もきわめて高く,アルツハイマー病克服にかける人々の期待と熱意の高まりを肌で感じた1週間であった。発表内容も全体的に大変すぐれており,「Nature」およびその姉妹誌に掲載あるいは掲載予定の演題がならび,アルツハイマー病に関する最新の情報を得ることができた。最後に,今回私に学会に参加する機会を与えてくださった金原一郎記念医学医療振興財団の方々に心からお礼を申し上げる。
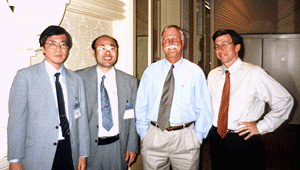 アルツハイマー病の脳内炎症反応に関するシンポジウム会場にて(左から秋山治彦博士〔都精神研〕,筆者,Rogers博士,Schenk博士) |
