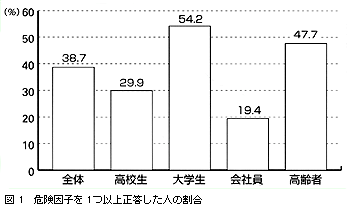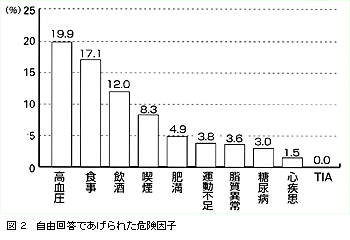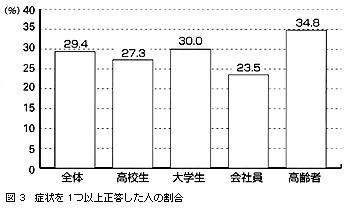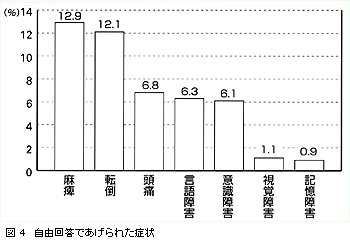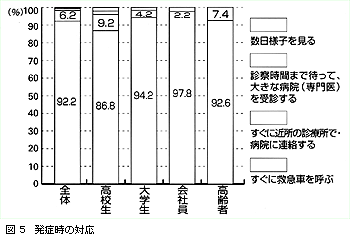【調査報告】脳卒中における一般市民の意識調査
脳卒中の危険因子や症状は一般市民にほとんど知られていない!
中山博文(日本脳卒中協会事務局長) 日本脳卒中協会は,脳卒中の予防方法や発症時の適切な対応方法を普及するという観点から調査研究を行なっており,その1つに「一般市民の脳卒中に関する知識」調査がある。予防には危険因子の知識が不可欠であり,発症後迅速な受診を実現するには,症状の知識を持ち緊急対応する必要がある。この報告は,脳卒中の危険因子,症状,救急対応の必要性に関する知識について,一般市民における普及度を調査した結果を述べるものである。
なお,1998年から大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻の辻本朋美氏,三浦早苗氏,大野ゆう子教授の協力のもと,同上の調査研究を進め,その結果を本年4月27-28日に開催された第25回日本脳卒中学会総会(会長=杏林大 齋藤勇氏,東京・京王プラザホテル)で発表した。本紙では,その概要を紹介する。
不足している脳卒中の知識
調査時期は,1998-99年。対象者は,高齢者(155名,平均年齢68.9歳),会社員(98名,平均年齢46.5歳),大学生(120名,平均年齢21.1歳),高校生(154名,平均年齢15.2歳)の合計527名。アンケート用紙(別表参考資料参照)を配布し,脳卒中の危険因子および脳卒中の症状を記述式で5つ,発症時の対応方法については選択式での回答を求めた。調査の結果,脳卒中の危険因子について,1つ以上正答できた人の割合は全体で38.7%と少なく,集団別に見ると,会社員では19.4%と最も低く,大学生では54.2%と最も高率であった(図1)。個々の危険因子に関して,高血圧,塩辛い食事については約2割が危険因子としてあげている。それに対し,飲酒,喫煙は約1割,運動不足,肥満,脂質異常,心疾患,糖尿病,TIA(一過性脳虚血発作)については5%以下ときわめて低率であった(図2)。
また,脳卒中の症状について1つ以上正答できた人の割合は,全体で29.4%と危険因子よりもさらに低く,集団別に見ると,やはり会社員が23.5%と最も低く,高齢者では34.8%と最も高率であった(図3)。個々の症状に関しては,約1割の人が運動・感覚麻痺と転倒を症状としてあげていたが,他の症状については1割未満であった(図4)。
発症時の対応方法については,「すぐに救急車を呼ぶ」「すぐに近所の診療所・病院に連絡する」という救急対応の選択肢を選んだ人の割合は全体で98%。いずれの集団においても95%を超えていた(図5)。
以上の結果から,ほとんどの一般市民は,発症時における救急対応の必要性を認識しているものの,危険因子,症状についての知識が不足していることが明らかになった。
生活習慣病の知識に疎い日本人
この結果を1995年に米国で行なわれた同様の調査(電話聞き取り調査)1)と比較すると,危険因子を1つ以上正答した人の割合は本調査では39%だったのに対し,米国では68%。症状については,本調査では29%であるのに対し,米国では57%と,いずれも米国の約半数であった。この結果から,日本では米国と比較して,一般市民の脳卒中の知識,特に危険因子と症状の知識が不足していることが懸念された。では,わが国の脳卒中予防の現状はどうであろうか。残念ながら危険因子となる喫煙や飲酒などの生活習慣,そして高血圧や糖尿病などの疾病の治療状況にはまだまだ改善の余地がある。
1999年に発表された,厚生省の脳卒中対策に関する検討会(座長=国立循環器病センター総長 山口武典氏)の中間報告2)によると,わが国の喫煙率は男性5割,女性1割と高く,男性の飲酒者の半数は過度の飲酒者(日本酒換算2合/日以上)である。
一方,高血圧に関しては男性で5人に1人,女性では7人に1人が高血圧であり,男女ともに70歳以上では30%以上が高血圧(平成9年国民栄養調査)であるにもかかわらず,男性の高血圧者の中における未治療者の割合は,40歳代で7割以上,50歳代では5割以上,60歳代で4割以上,70歳以上が約4割と各年代で高率である(循環器疾患基礎調査)。
また糖尿病に関しては,有病者数は690万人(1997年糖尿病実態調査)であるのに対し,医療機関にかかっている総患者数は218万人(1996年患者調査)であり,約7割が未治療の状態にある。
これらの状況の改善の第一歩が危険因子に関する知識の普及であることは言うまでもない。
今必要とされる知識とは
次に,脳卒中急性期医療という観点から症状の知識について考えてみたい。1990年代にストロークユニット(stroke unit;脳卒中における専門的知識を持ち,脳卒中患者のケアを行なう専門家の学術的チーム。なおストロークユニットでは,多職種からなるスタッフがチームの脳卒中管理指針に従い,患者の包括的評価を行ない,協調的に治療を実施している)3)における急性期治療が脳卒中後の生命予後および機能予後の改善に有効なことが確立され,欧州を中心にストロークユニットの導入が進められていること。加えて,将来的に超急性期(発症3時間以内)脳卒中に対する新たな治療方法(血栓溶解療法,神経保護療法)がわが国に導入される可能性があることから,発症後可及的速やかに脳卒中患者を専門医のいる医療機関に集める必要がある。これを実現するためには,一般市民が脳卒中の症状についての知識を持ち,発症時に脳卒中の可能性を疑い,緊急対応することが必要である。その第一歩となるのが,症状についての知識の普及である。このように,危険因子と症状の知識はそれぞれ異なる観点から普及の必要性が高く,日本脳卒中協会はその実現をめざして,脳卒中市民シンポジウムの開催,学会との市民公開講座の共催,電話相談,パンフレットの提供,インターネットホームページ開設(下記)等の活動を行なっている。この実現には,日本脳卒中協会等の団体による市民教育のみならず,学校教育,地域保健活動,市民検診,かかりつけ医による健康管理,職場検診等,多角的アプローチが必要であり4),本稿がその一助となることを願っている。
・日本脳卒中協会ホームページ
http://patos.one.ne.jp/public/jsa/
- 1)
- Pancioli AM, Broderick J, Kothari R, et al: Public perception of stroke warning signs and knowledge of potential risk factors, JAMA 279, 1288-1292, 1998
- 2)
- 厚生省保健医療局生活習慣病対策室:脳卒中対策に関する検討会中間報告書,1999年9月
- 3)
- 中山博文:ストロークケアユニットのあり方,週刊医学界新聞,No.2308, 1998
- 4)
- 中山博文:National Stroke Strategyの観点から見た課題,脳卒中,21, 483-485, 1999
| 参考資料 脳卒中に関するアンケート調査質問項目(抜粋) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||