【解説】「身体拘束ゼロ作戦」の意義
抑制をはずすことは寝たきりにさせないこと
身体拘束ゼロをめざす協議会の発足
本年5月に,丹羽雄哉前厚生大臣は,縛らない看護・介護を前面に打ち立てた「身体拘束ゼロ作戦」の推進を表明。同6月9日に,厚生省内に「身体拘束ゼロ作戦推進協議会」を発足させた。「抑制廃止」をめぐっては,1999年3月31日付で,厚生省令「介護保険施設等における身体拘束の禁止規定」が通達されている(7月31日付,2398号に関連記事を既報)。身体拘束ゼロ作戦の推進
「身体拘束ゼロ作戦推進協議会」は,本年4月施行の介護保険法で身体拘束が原則禁止され,その上での質の高い介護サービス実現が望まれることから,「身体拘束を現場から廃止する努力と関係者の支援が重要」などを趣旨として発足した。また同協議会は,「身体拘束ゼロ作戦」を推進すべく,国および各都道府県に「推進協議会」の設置。身体拘束に向けて幅広い意見や情報交換を行なうこと」を具体的な取り組みと定め,本年度中に一部自治体にモデル協議会を設置し,来年度には全県に設置することを提示している。さらに,各都道府県の推進協議会には,具体的な助言を行なう身体拘束相談窓口や,助言指導を行なう介護相談員(介護サービス利用者のための相談等に応じるボランティア)の養成を行なうこと,「身体拘束ゼロマニュアル」の作成と普及,介護・福祉機器の開発と普及に加え,「身体拘束ゼロ推進シンポジウム」の開催なども計画している(図参照)。
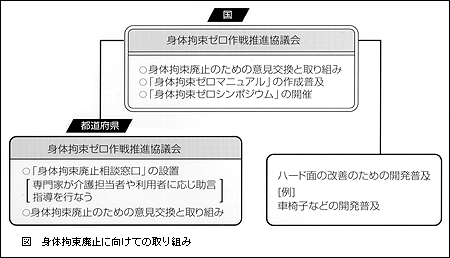
高齢者医療にとっての大英断
介護保険に「身体拘束禁止」の一項が入った背景には,1998年10月に福岡市で開催された「第6回介護療養型医療施設全国研究会」で発表された「抑制廃止福岡宣言」(表1参照)も関与していると言えるだろう。その宣言作成にかかわり,1986年から抑制廃止を実施している上川病院(東京都八王子市)の吉岡充理事長は,「福岡宣言を発表してからは,急速に拘束を禁止しようとする施設が増えてきました」と語る。また厚生省が示した「身体拘束ゼロ作戦」については,「これからの高齢者医療にとっての大英断であり,寝たきりゼロ作戦につながるもの」と位置づけ,「なにが抑制なのかを定義づけることも大切」と16のチェック項目を示す(表2参照)。身体拘束ゼロ作戦は寝たきりゼロ作戦の実践編
「寝たきりゼロ作戦」が世に出て10年がたったが,まだ「寝たきり」の状況は多くの施設,在宅でもみられている。吉岡理事長も,「身体拘束ゼロ作戦は寝たきりゼロ作戦の実践編となるものであり,より普及していくだろう」と予測する。抑制をやめることは,その人を起こすことにつながる。「抑制をはずすことは寝たきりにさせないこと」と現場の担当者や一般市民は気づき始めた。そのことが,一層身体拘束禁止に拍車を駆けている。「身体拘束ゼロ作戦」のこれからの方向性について吉岡理事長は,「この法律が熟知されるようになれば,現在の85%は抑制がなくなるでしょう。問題は残った15%ですが,5-10年後にはほとんどの施設で抑制がなくなると考えています」と語る。また,「不必要な抑制をしている施設が圧倒的に多いが,抑制をはずすことで患者は落ち着きをみせ,問題行動も減少する。さらに,患者や家族の満足につながり,スタッフの満足度もあがる」と指摘する声もある。そのためには,施設でのサービス提供者と受ける側が本当によい,というコンセンサスが得られることが重要であり,スタッフの意識改革とマンパワーも課題となるだろう。
| 表1 抑制廃止福岡宣言 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 表2 抑制チェック項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
