ツーソンの空は晴れて
アリゾナ大学医学部サーバー心臓センターにて
高階經和(社団法人臨床心臓病学教育研究会会長・アリゾナ大学医学部客員教授)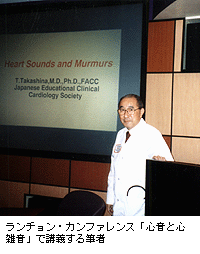 今回,私は3月8日から3月11日まで,友人のエーヴィ(G. A. Ewy)教授に客員教授として招かれ,再びアリゾナ州ツーソン市(Tucson)にあるアリゾナ大学医学部サーバー心臓センターを訪れる機会を得たので,その訪問記を記してみようと思う。
今回,私は3月8日から3月11日まで,友人のエーヴィ(G. A. Ewy)教授に客員教授として招かれ,再びアリゾナ州ツーソン市(Tucson)にあるアリゾナ大学医学部サーバー心臓センターを訪れる機会を得たので,その訪問記を記してみようと思う。
前夜遅くにツーソンに着いたために,時差の影響が身体に多少残っている。翌9日朝7時に,エーヴィ教授がホテルまで迎えに来られた。雲ひとつなく晴れ上がった青空のもと,いまだにツーソンの朝の空気は冷たく肌寒い。
「ケイ,よく眠れたかい?」(ケイとはアメリカでの私のニックネームである)
「ぐっすり眠ったよ。今日は気分爽快だ」
と1日の会話が始ったが,車の窓を通して電信柱のような巨大なサボテンがグリーンベルトに一定の間隔で植えられているのが目に入る。街全体に巨大なサボテンが植えられているのは,全米でもおそらく砂漠の街ツーソンだけであろう。50年間に2センチしか成長しない「サワロ・サボテン」という。そして1本の枝が幹から生えるのに15年はかかると聞くにおよんで,「一体,このサボテンは何年かかって,ここまで大きくなったのだろう?」という疑問が湧いてくる。きっと気の遠くなるような歳月がかかったのだろう。
『新しい心臓病患者シミュレータ=“K”』
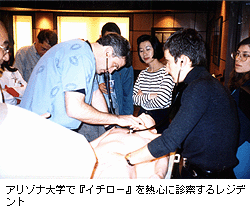 午前7時30分からマッフィンやクロワッサンとコーヒーだけの朝食を取りながら,エーヴィ教授が「ドクター高階は日本だけではなく,国際的にもよく知られた臨床心臓病学の専門家ですが,今朝は特に皆さんのために『新しい心臓病患者シミュレータ“K”』(日本名は『イチロー』)を使って,学生に心臓病患者の診かたの指導方法を教えるためにアリゾナ大学にお招きしました」と丁重に私を8人のレジデントに紹介してくれた。
午前7時30分からマッフィンやクロワッサンとコーヒーだけの朝食を取りながら,エーヴィ教授が「ドクター高階は日本だけではなく,国際的にもよく知られた臨床心臓病学の専門家ですが,今朝は特に皆さんのために『新しい心臓病患者シミュレータ“K”』(日本名は『イチロー』)を使って,学生に心臓病患者の診かたの指導方法を教えるためにアリゾナ大学にお招きしました」と丁重に私を8人のレジデントに紹介してくれた。
私は彼らに,「このシミュレータを今までに見たことがありますか」と聞いてみたが,誰も見たことがなく,最初のうちは彼らもやや緊張気味であった。まずスイッチの入れ方から始まり,コンピュータの画面に表示される各疾患の身体所見(頸静脈波,頸動脈波,心尖拍動や心音・心雑音)をファンクション・キーとカーソルを使って,マネキンにどう再現するかをデモンストレーションし,その後各レジデントに自分で操作できるまで実習をしてもらった。
エーヴィ教授も一緒になって学生たちに各疾患の身体所見の特徴や,特に聴診所見を把握させることの重要性を強調してくれたが,彼らはすでにマイアミ大学のゴードン(M. S. Gordon)教授らが開発した心臓病患者シミュレータ『ハーヴェイ』での研修は経験ずみであった。しかし,『イチロー』では自分の聴診器を使って,各疾患の心音や心雑音の変化や特徴を聴くことができたことと,不整脈とともに心尖拍動や全身動脈波などの身体所見が同時に変わることに,かなりの興奮を覚えたようであった。
「ドクター高階,この音はほとんど実際の患者のものと変わりませんが,どのようにして入力されたのですか?」
「これらの心音・心雑音はすべて実際の患者から記録したもので,胸毛のある人などではかなりバックグランド・ノイズが入るのでクリーニングソフトで消しました」
「道理でリアルなんですね」
「ハーヴェイの音は誇張しているように思いますが」
「それはすべての心音や心雑音が,心音シミュレータで合成されたからでしょう」
「このシミュレータの開発にはどれくらいの期間がかかったのですか?」
「私と東京工業大学の清水優史教授と京都科学の片山英伸氏との共同研究で,約7年がかりで開発に成功しました」
「それで,この“K”はいつ頃アリゾナ大学に入ったのですか?」
「3年前だったと思います」
などと次々に質問が私に飛んでくる。
そこでエーヴィ先生が,「今度のバージョンは一番よくできているね」とのコメントを付け加えてくれた。
そして,「オーケー。それでは,ここで皆さんの耳のテストをしてみましょう」と言って,コンピュータの画面の向きを変え,『イチロー』を使って各心疾患を順番に出し,身体所見と聴診の同時診察法について解説を交えながら実習を行なったが,ほとんどのレジデントが学生への教え方のコツを会得したようであった。
循環器専門ナース・スペシャリスト
翌3月10日は,午前8時にエーヴィ教授の秘書が車で迎えにきてくれた。8時半から看護大学の教育研修プログラムの責任者である女性のモーア教授(K. Moore)にお目にかかることができたので,私は「われわれは近い将来,循環器専門ナース・スペシャリストのコースを作り,そのコースを修了した者をアメリカに留学させたいと考えています」と希望を述べた。
モーア教授からも「ドクター高階のお考えには大賛成です。日本を始め,もっと多くの国のナースの方々に来ていただいて,アメリカの医療の現状などを見ていただき,参考になることはどしどし吸収して欲しいと思います。ただ,ナースの仕事は患者やその家族,そしてドクターとの密接な連係がなければ成り立ちませんから,そのためにはぜひとも英語力を身につけてからいらしていただきたいと思います」とのコメントをいただいた。
当然のことと言えばそれまでだが,ドクターの場合もナースの場合も,語学が留学への大きな壁になっていることは明白な事実である。アメリカに行けば何とかなる,という安易な考え方は許されないことをここに改めて記しておきたい。英語で自由に患者や家族,そしてドクターとの会話ができなければ,1年半,700時間にわたる「ナース・プラクティショナー」の第1段階の実習を修了することができないからである。
CCUでの回診
約1時間の話の後,私は4階にあるCCUでエーヴィ教授と合流し,数名のレジデントと一緒に回診を始めた。すでにご存知の方もおられると思うが,アメリカの医療現場における病歴,診察所見や各検査,そして治療方針の各項目に関して,レジデントが診察して記載した内容のすべてにわたってその病棟の責任者である教授や,シニア・ドクターが正しいと判断すれば,サインをしていく。それがなければ,もし将来,医療訴訟に巻き込まれた場合は必ず医師は不利な立場に立たされるのである。私は回診の間に昨今のわが国における医療事故の多発も,この方法によって防げるかも知れないと思った。
回診の途中で,ある部屋に入った時である。エーヴィ教授が私を患者に「このドクターは日本から来られた教授です」と紹介された途端に,「始めまして,どうぞよろしく」と日本語で挨拶した老人がいた。エーヴィ教授もびっくりした様子で,「あなたはどうして日本語がそのように上手に話せるのですか?」と尋ねた。すると今度はその老人から,「私はノース・ウエスト航空の仕事で14年間,東京に勤務していました」という英語の答えが返ってくると,すかさず「道理で。それでは高階教授に,日本語で診察をお願いしようかな」というエーヴィ教授のジョークが飛び出した。
ランチョン・カンファレンスにて
 CCUでの3時間の回診も終わり,続いて私はランチョン・カンファレンスのため4階にある会議室に向かった。学生やレジデントたちが集まってくると,エーヴィ教授が次のように私を紹介してくれた。
CCUでの3時間の回診も終わり,続いて私はランチョン・カンファレンスのため4階にある会議室に向かった。学生やレジデントたちが集まってくると,エーヴィ教授が次のように私を紹介してくれた。
「今日のゲスト・スピーカーは,プロフェサー高階です。高階教授は臨床心臓病学教育研究会の会長であり,日本を初め国際的にも非常に著名な臨床心臓病学の権威であります。来週,アナハイム市でアメリカ心臓病学会の学術年次総会が開催されます。この学会には世界中から有名が心臓病の専門家が出席されますが,今回,プロフェッサー高階がこの学会に来られることを伺っていましたので,その2-3日前にアリゾナ大学で臨床心臓病学のベッドサイドにおける診察法の中の『心音と心雑音』についてお話いただきたいとお願いしました。今日はそのノウハウを伺えるものと思います。ケイ,よろしく」
私は,「エーヴィ先生,どうもご丁寧なご紹介をありがとうございました。再びツーソンに来られて嬉しく思い,またエーヴィ先生にお招きいただいたことを大変名誉に思う次第です。今日は『心音と心雑音』についてお話するわけですが,臨床における診察の第一歩は完全な病歴と身体所見の把握にほかなりません。これは世界中のどこでも共通のことです。しかし,ハイテク技術を駆使した診断機器の進歩のお陰で,あまりにも多くの臨床家がその技術に頼り過ぎ,ベッドサイドにおける診察手技の重要性を忘れがちです。これは日本においては特にその傾向が見られます。今日は診察手技の中でも,特に聴診について話したいと思います」と挨拶した。
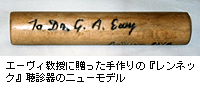 そして,「もう少しで忘れるところでした。実は,私がロサンゼルス空港の待合室でエーヴィ先生待っている時,大変高齢な紳士が私のところに来まして,『あなたはツーソンに行きますか?』と聞きました。彼はどう見ても200歳くらいでした。私が,『ええ,行きますが』と答えると,『エーヴィ先生に会う機会がありますか?』と聞いてきました。『ええ,しかし,どうしてそれをご存知なのですか?』と聞くと,『いやー,エーヴィ先生は大変な聴診器の蒐集家なんですよ。これは私が作った最新のモデルです。どうかエーヴィ先生にお渡しください』と言うのです。『ところで,あなたのお名前は何とおっしゃるのですか』と再び聞くと,『レンネック(Laennec)です』と言ったのです」と切り出して,私が2か月かかって作り上げた木製の聴診器を鞄から取り出してエーヴィ教授に手渡した。すると,「これは素晴らしい!」とエーヴィ先生は大喜び。学生やレジデントたちは大爆笑であった。
そして,「もう少しで忘れるところでした。実は,私がロサンゼルス空港の待合室でエーヴィ先生待っている時,大変高齢な紳士が私のところに来まして,『あなたはツーソンに行きますか?』と聞きました。彼はどう見ても200歳くらいでした。私が,『ええ,行きますが』と答えると,『エーヴィ先生に会う機会がありますか?』と聞いてきました。『ええ,しかし,どうしてそれをご存知なのですか?』と聞くと,『いやー,エーヴィ先生は大変な聴診器の蒐集家なんですよ。これは私が作った最新のモデルです。どうかエーヴィ先生にお渡しください』と言うのです。『ところで,あなたのお名前は何とおっしゃるのですか』と再び聞くと,『レンネック(Laennec)です』と言ったのです」と切り出して,私が2か月かかって作り上げた木製の聴診器を鞄から取り出してエーヴィ教授に手渡した。すると,「これは素晴らしい!」とエーヴィ先生は大喜び。学生やレジデントたちは大爆笑であった。
続いてエーヴィ教授は,「レンネックが生きていた1800年代の初め頃には,直接聴診法しかなく,特に女性の患者の場合は胸にハンカチーフをおいて聴診をしなければならなかったのです。その後,ふとしたヒントから初めて木製の聴診器で聴診を始めた方が,レンエックです」と解説をしたが,これは私が次に用意したスライドの内容と同じだったのである。そこで「いまエーヴィ先生が言われたことが全部このスライドに書いてあります」と言った途端に再び大笑い。
Without Auscultation, No One Can Master Cardiology.
これで私もすっかり気分が楽になり,聴診器の選び方に始まり,心音と心雑音の聴き方から,鑑別方法などを40枚のスライドにまとめて約1時間にわたって講義した。日本語のスライドも交え,「皆さんは日本語も読めるでしょうから」と,イラストの表題だけが日本語のものも用意した。絶えず笑いと微笑みが学生たちの顔に浮かんだ。そして,エーヴィ先生も独自のコメントを示しながら,時には私のQ&A形式の講義の質問に対する正解と思われる解答に対して,手を上げて答えてもらった。そして最後のスライドで,『聴診なしには心臓病学をマスターする者はない。幸運を祈る』(Without Auscultation, No One Can Master Cardiology. Good Luck!) という私の作った格言が出た途端に,会場全体から笑いと大きな拍手が沸き起こった。その後エーヴィ教授が丁重なお礼の言葉を述べられた。多くの学生を初め,チーフ・レジデントのドクターがわざわざ私に握手を求め「素晴らしい講義をありがとうございました」と礼を述べてくれた。
「人工地球」と「ソノラ砂漠博物館」
翌日にはレンタカーを借り,抜けるように青い空のもと,ツーソンの北側にあるカタリナ山(Catalina Mountain)の向こう側にある有名な「人工地球」(Biosphere)を訪れた。コロンビア大学が進めるこのプロジェクトは,将来,人間が火星に住むようになった時に,どのような人工環境が必要かを調査する壮大な巨大科学の殿堂であった。テキサスの石油会社の大富豪がスポンサーとなり,コロンビア大学が技術面の協力をしているという。日本と比べようもないアメリカの開発魂の一面を見た思いであった。その後,車を西に約200キロ走らせて「ソノラ砂漠博物館」を訪れた。車窓を眺めると全山巨大なサボテンの林が続く。博物館ではアリゾナでしか見られないめずらしいガラガラ蛇や爬虫類をはじめ,数々の砂漠に住む動物たちや鳥類を目にすることができた。翌日は,ロサンゼルス郊外のアナハイム市で開催された第49回アメリカ心臓病学会に出席するためにツーソンを後にしたが,その前夜,ホテルの前から見上げた夜空一杯に煌(きら)めく数々の星の神秘的な美しさは決して忘れることはできない。
日本に帰って数日後,エーヴィ先生から「ケイ,今回のあなたの講義は本当に素晴らしかった。学生やレジデントたちに大いにうけました。本当にありがとう」というEメールが届いたのである。
