第6回日本看護診断学会学術大会開催
看護診断・介入・成果の連携が明確に
 第6回日本看護診断学会学術大会が,さる6月17-18日の両日,筒井裕子大会長(滋賀医大)のもと,滋賀県大津市の滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールにて,「高齢社会でHUBとしてはたらく看護診断」をメインテーマに開催された。
第6回日本看護診断学会学術大会が,さる6月17-18日の両日,筒井裕子大会長(滋賀医大)のもと,滋賀県大津市の滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールにて,「高齢社会でHUBとしてはたらく看護診断」をメインテーマに開催された。
同大会では,会長講演「高齢者における看護診断とその方向性」(筒井氏)をはじめ,教育講演が「クリティカルパスに看護診断は必要」との前提で行なわれた「看護診断とクリティカルパス」(阪大 江川隆子氏)など2題の他,シンポジウム I「看護専門領域における看護診断」(司会=日赤看護大 黒田裕子氏,愛媛県立医療短大 中西純子氏),II「高齢者ケアにおける看護診断」(司会=山梨県立看護大 大島弓子氏,阪市大看護短大 黒江ゆり子氏)や「看護診断用語検討委員会報告」(黒田裕子氏)が企画された。また,10題の一般演題が行なわれた他,ワークショップ「正しく行なう看護診断」や,事例セッションにも多くの参加者が参集。今後の学術大会が,参加型へと変革するだろうことを予感させた。
なお,海外からの演者には,『看護成果分類(NOC)-看護ケアを評価するための指標,測定尺度』(藤村龍子・江本愛子監訳,医学書院)の著者として,またNOC(看護成果分類)の研究者として知られる,メリディーン・マース氏(米・アイオワ大教授)を招聘し,専門領域であるNOCや高齢者看護と看護診断を結びつける講演が,2日間にわたって行なわれた。
看護専門領域での看護診断
クリティカルパスに看護診断は必要
 「看護診断とクリティカルパス」を教育講演した江川氏は,「クリティカルパスを活用するために,看護職は看護過程や看護診断を十分に理解していることが必要。さらに,このツールを活用し,他の専門家と交渉ができ,必要に応じて変更のできる『ナースケアマネジャー』の育成がこれからは脚光を浴びる」と述べるとともに,21世紀に持っていくものとして,上記の他に「看護診断とNOC/NIC(看護介入分類),看護データベースと看護診断,NOC/NICのデータセット,看護診断が含まれたクリティカルパス」をあげた。
「看護診断とクリティカルパス」を教育講演した江川氏は,「クリティカルパスを活用するために,看護職は看護過程や看護診断を十分に理解していることが必要。さらに,このツールを活用し,他の専門家と交渉ができ,必要に応じて変更のできる『ナースケアマネジャー』の育成がこれからは脚光を浴びる」と述べるとともに,21世紀に持っていくものとして,上記の他に「看護診断とNOC/NIC(看護介入分類),看護データベースと看護診断,NOC/NICのデータセット,看護診断が含まれたクリティカルパス」をあげた。
また,シンポジウム I「看護専門領域における看護診断」では,4領域から演者が登壇し意見を述べた。精神領域からは神郡博氏(福井県立大)が,「共通してどの領域の看護診断にも情報の的確な把握とアセスメントが必要」とした上で,「特に精神科においては,患者から話してもらえる技術や情報の収集がしやすい普段の観察が大事」と指摘。菊地敦子氏(慶大病院)は助産領域から,今後の課題として「助産領域におけるウェルネス型看護診断を開発すること。その診断を助産婦としての責任の範囲でアセスメントし,看護ケアが実践できる診断としての妥当性を評価し体系化すること」をあげた。野村美千江氏(愛媛県立医療短大)は,在宅看護の視点から発言。オハマ訪問看護システムを用いた在宅看護実践での看護診断の活用と課題に触れるとともに,環境,生理的,心理社会,介護,健康に関連した行動の5つの領域からの介入計画を報告した。成人(急性期)の領域からは,「看護診断による看護計画」のコンピュータ化を全病棟で実施した徳島大病院の上田孝子氏が報告。NIC/NOC導入の経緯や目的について概説するとともに,「NIC/NOCを参考として66の看護診断ラベルと看護介入,アウトカムをリンクさせコンピュータ化した結果,アウトカムの達成感が数値で客観的に表示できた」などと述べた。また,今後の課題として,「66以上の看護診断ラベルとNIC/NOCのリンク。NIC/NOC導入後の看護成果の検証」をあげた。
2部に分けて招聘講演
NOCの長所と問題点を指摘
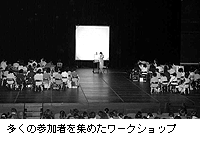 マース氏による初日の招聘講演は「看護診断・介入・成果の歴史と展望」と題して行なわれた。氏は,「情報技術社会にあって,看護はコンピュータによる情報システムに乗り遅れている。看護介入の有効性を分析する上でも,データ構築は重要。看護システムとデータベースに標準化された看護専門用語を組みこむことが急務である」との立場から,主に,標準化された看護診断やNICと同様,重要視されなければならないNOCについて解説した。
マース氏による初日の招聘講演は「看護診断・介入・成果の歴史と展望」と題して行なわれた。氏は,「情報技術社会にあって,看護はコンピュータによる情報システムに乗り遅れている。看護介入の有効性を分析する上でも,データ構築は重要。看護システムとデータベースに標準化された看護専門用語を組みこむことが急務である」との立場から,主に,標準化された看護診断やNICと同様,重要視されなければならないNOCについて解説した。
NOCの長所に関して氏は,(1)包括性,(2)研究に基礎を置く,(3)帰納的で演繹的なアプローチ,(4)臨床実践に根拠を置く,(5)明確で臨床的に有用な用語,(6)情報を最新化する,(7)他の専門職によっても使用可能をあげた。一方,問題点として(1)成果測定の時期,(2)臨床システムにおける実用性と妥当性,(3)すべての看護現象に対して1つの系統分類法,(4)標準用語の他の開発者との協力と共有を指摘。その上で,「国家政策に影響を与える上でも,エビデンスによる看護情報のデータ化は必要」と述べた。
日米の看護における類似点と相違点
2日目に行なわれた「高齢者と看護診断」では,前半を日米間の看護の類似点と相違点の分析にあてた。類似点としては,歴史的に両国とも医学モデルによるヘルスケアシステムであり,病院から拡大したコミュニティケアであったことを示した。また,看護職の役割が病院から地域に移ってきたが,家族による在宅ケアが難しい時代となった。その要因としては女性の役割強化,出生率および拡大家族の減少を共通点にあげた。一方で,看護教育の多様化や大学教育はアメリカに比し日本はゆっくりであるものの発展しているとした。また相違点に関しては,日本の高齢者の約2%が施設入所者だが,アメリカの高齢者人口は2100万人でナーシングホームの入所者はその5%。入院期間も日本の50日に対し8日であることをあげ,「日本における入院患者の45%が65歳以上の高齢者であることに,病院看護職は気づいていないかもしれない」と指摘した。
さらにケアの質の分析に関しては,「アメリカではMDS(Minimum Data Set)などの使用義務があるが,日本ではMDSが注目され始めたところ」と分析。
氏はその上で,標準化された看護用語は知識の向上,自立と責任の促進,コミュニケーションの改善,ケアの質の評価などを発展させるとし,看護診断の重要性を説いた。また,長期療養ケア(LTC)領域に用いられる看護診断として,(1)セルフケア不足,(2)動性の障害,(3)思考過程の変調,(4)皮膚統合性の障害,(5)排泄の変調,(6)栄養の変調,(7)身体可動性の障害などを指摘。
その後マース氏は,会場の参加者に,1)個人事例検討,2)組織レベルでの事例検討,3)政策レベルでの事例検討を提示し,それぞれに看護診断を行ない,目標,介入法を考えさせるという試みをゲーム形式で行なった。
なお,次回の第7回日本看護診断学会学術大会は,江本愛子大会長(三育学院短大)のもと,明年6月21-22日の両日,横浜市のパシフィコ横浜で開催される。
