《短期集中連載》全7回
ボストンに見る米国の医学,看護学,
ならびに医療事情の激しい動き(3)
日野原重明(聖路加看護大学名誉学長)
MGH(マサチューセッツ総合病院)にて〔続〕
(第2394号より続く)12月27日(月)・第3日目午後
スプライマリ・ケアの父ストックル教授との再会
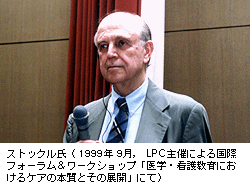 ハーバード大学公衆衛生大学院をこの日の午前中に訪れた後,堀越夫人は私をMGH(マサチューセッツ総合病院)の玄関まで車で送ってくださった。前回私がここを訪れたのは,ちょうど2年前である。
ハーバード大学公衆衛生大学院をこの日の午前中に訪れた後,堀越夫人は私をMGH(マサチューセッツ総合病院)の玄関まで車で送ってくださった。前回私がここを訪れたのは,ちょうど2年前である。
馴染みのある古く狭い玄関を入ると,誰の案内もなく,外来棟の5階にあるプライマリ・ケア部門のストックル(John D.Stoeckle)内科教授のオフィスを訪れた。
ストックル教授は1948年にハーバード大学医学部を卒業し,今年77歳である。彼は71歳までは現役の内科教授であり,31年間の教官時代にプライマリ・ケア医学の生みの親のような働きを果たされ,6年前に名誉教授となられたが,引き続きプライマリ・ケア外来で,医学生やレジデントを指導しながら,自分の患者の診察を続けてこられた。また,厚生省から送られた日本からの留学生にも,親身になって世話をしてこられたのである。
彼によって教育されたゴロール(Goroll)助教授,およびその他の若手の各科のプライマリ・ケア専門医によって「Primary care Medicine」というB5判856頁のテキスト(1981年,J.B.Lippincott Co.)が出版されたが,この本はストックル教授に捧げられている。ストックル先生は,いまだに診察時に検眼鏡も使っておられる様子である。
また先生は,患者と医師関係(Doctor-Patient Relationship,略してDPR)に非常に興味を持ち,これに関する著述も多い。彼が後輩のビリング(J.A. Billings)助教授と共著で「Clinical encounter」(臨床的出会い)と題したA5判352頁の本の第2版を1999年に出版されている。この本は本年秋には,私と京大の福井次矢教授の監訳で医学書院から『臨床面接技法-患者との出会いの技(アート)』というタイトルで出版される予定である。
アートとしての医術を身をもって具現する
私が理事長をしている(財)ライフ・プランニング・センター(以下:LPC)主催の東京でのフォーラムに,私は1996年の9月と1999年の9月の2回にわたって,ストックル先生を講師に招待した。このフォーラムでは,医師と患者とのコミュニケーションに関するテーマが取り上げられ,患者と医師との対面の仕方,椅子の置き方やコミュニケーションの技術などについての説明があった。ストックル教授は訪問ナースとチームを組んで,外来に来られない患者の在宅ケアの指導をし,ナースの患者訪問には医学生も同伴させていると述べられた。身をもって単なるサイエンスでなく,アートとしての医術の実践のモデル(姿)を自らの外来診察の中で具現し,医学生やレジデントにその行動(performance)をもって示しておられるのであった。
ハーバード大学医学部には,「New Pathway」と呼ばれる,10年余り前から始めたカナダのマクマスター大学方式の教育がある。これはテューターの世話による小グループによる体験学習方法(テュートリアル)によって臨床医学を学生に教える,という教育方法として有名だが(東京女子医科大学をはじめ,日本の医学校でも近年ぼつぼつ始まりかけている),その他にストックル教授などのように,教師が医学生によいモデルを示す中で一緒に学ぶという体験学習の教育方法が,よい臨床医を育てるために非常に貢献していると思う。それが日本には大変欠けていることが大きな問題であることを痛感した。
ビリング助教授と在宅ホスピス
ビリング助教授は,ハーバード大学医学部を1972年に卒業し,カルフォルニア大学サンフランシスコ校で卒後の研修を受け,1975年にMGHに内科のフェローとして帰って来られた。そして1980年からはホスピス活動に入り,1992年9月には,ボストン・トリニティ・ホスピスの在宅ホスピス事業の医療部長をしておられた時,LPC主催の「第18回医療と教育に関する国際セミナー:QOLと医療・看護におけるQOL」に彼を日本に招聘した。またその翌年の7月には,ホスピス研究ツアーのグループを私が連れてボストンを訪れた時に彼の在宅ホスピス・ケアの本部を見学し,近くに住む癌患者を彼が往診する風景を一行が見学させてもらったのであった。ビリング先生は,1998年度からはMGH内での緩和ケアサービス部門の長として癌末期患者のターミナルケアを指導するために,ハーバード大学の助教授となられた。そして,MGHのすぐ近くにあるMGH付属の健康科学大学院の看護学のコーレス(Coreless)教授とともに,MGHで医学生やレジデントに講義や臨床指導をされておられると言う。彼は今,1998年に創刊された「Journal of Palliative Medicine」の副編集長でもある。
ビリング先生が1992年に来日された時には,「在宅ホスピスとは何か?:Dr.Billingsを囲んで」とのタイトルで,医学界新聞主催の座談会が企画され,先生と私と,それからビリング先生の著書『進行癌患者のマネージメント』を翻訳された帝京大の星野恵津夫講師とが加わったが,その記事は,医学界新聞の2060号(1993年9月20日号)に掲載されている(下欄参照)。
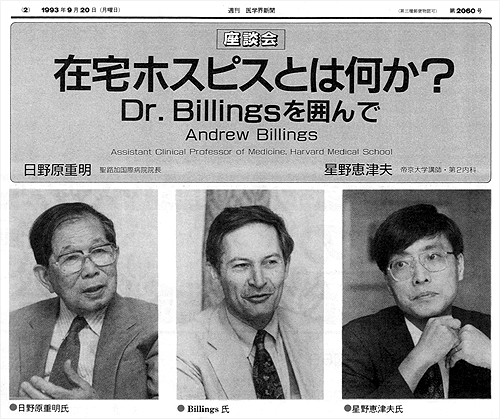
米国のホスピス活動
一般に米国でホスピス活動というのは,その大部分が在宅ホスピスケアで,訪問ナースがこの主な責任を持ち,医師は必要時に,ナースの要請で往診をし,死の判定をする。時にはその判定をナースに任せることがある。モルヒネの投与量もナースが事実上処方し,その責任は医師が持つという状況である。米国では病院の中に緩和ケア病棟を持つことは,英国やカナダ,オーストラリアほどには多くなく,むしろ各病棟に散在している癌患者を,ホスピス専門の医師とナースがアドバイザーとしてコンサルテーションを行ない,担当医に症状コントロールや精神的ケアの指導をする場合が多い。MGH内に入院している末期癌患者で緩和ケアの指導をビリング先生とナースのコーレス氏が担当している患者さんの数は平均10-12名で,この他在宅ホスピスケアを受けている患者は100名内外だとのことである。
米国にはコネティカット州のニューヘブンに,45名の末期癌患者を収容する独立型ホスピスがあるが,これは例外で,たとえ独立型でも非常に小規模のホスピスが国内にはごく少数しかなく,在宅ホスピスケアが主流となっている。
バリー準教授とMedical Decision-Making
ストックル先生とビリング先生との会食中に,バリー(M.J.Barry)準教授が遅れて加わった。彼は1979年にコネティカット州立大学医学部を卒業し,1983年からハーバード大学の内科の研究フェローとなり,1996年から準教授となり,翌年からMGHの総合臨床部の主任となった医学部卒業後20年の若手である。彼に履歴書(C.V.)を欲しいと言うと,オフィスに帰りすぐにその1通を私に持ってきた。
最近,アメリカ人のC.V.には,生年月日がないことが目立っている。ごく最近までは女性のC.V.には生年月日は書かれず,大学卒業年度から履歴が書かれていたが,今では男性も生年月日は略されているのが普通である。
米国の研究者や教育者はいつでも自分のC.V.が渡せるように準備しており,新しい任務に就くとか,研究論文を書いたり,委員会の委員長に就くと,その履歴を即刻コンピュータにインプットするので,誰もが最新のC.V.がすぐ出せるようにしている。これは,1つには米国では自分の売り込みについて心がけている,という厳しい競争社会の中で働いているからである。
一般にGeneral Medicineを専門とする人の多くは,臨床疫学やEBM(Evidence-Based Medicine:証拠に基づく医学)をも専攻しているが,彼は1996-1997年にはSociety for Medical Decision-Makingの会長を務めている。
この領域は臨床疫学の中でも臨床家に特に求められる内容のものである。これは,ある患者を治療する際に,まず内科的に観察するのか,または化学療法をすぐ始めるのか,外科的処置をするのか,あるいは少し観察し,様子を見てから手術するのかなどという臨床判断を,何の根拠に基づいて行なうのかを検討し,患者の生存の安全性を指標として科学的根拠に基づいた選択をする方法の研究で,これは臨床疫学の中の重要な部門とされている。
問われる“出版社の先見性”
この臨床判断の決定に関してのテキストとして,最も早く書かれたものは1980年にワインスタイン(M.C.Weinstein)とファインバーグ(H.V.Fineberg)によって出版された「Clinical Decision Analysis」というタイトルの本である。私はこの学問をできるだけ早く日本に紹介すべきだと考え,その日本語の翻訳書を出版するために,京大の福井次矢教授と方々の医学出版社と交渉した。しかし,これは出版してもまだまだ売れない本だという出版社の見通しのために,翻訳版を引き受ける出版社がなく,12年もの時間が過ぎて,ようやく1992年に『臨床決断分析-医療における医師決定理論』というタイトルでこの本を医歯薬出版社から出版することができた。
一般に欧米に新しい医学の動向が現れても,出版社の先見性がないと,普及は遅れ,そのために医学や看護学の領域において日本の後進性が見られることになる。たとえ発行部数は少なくても,そのような将来発達が約束される本はもっと早く出版してほしいものである。
看護の領域でも,看護過程や看護診断,フォーカス・チャーティングに関して,米国の看護学の開拓者によるさまざまな本が出版されているが,英語版が出た後,遅いものは10年も日本語への翻訳が遅れるものがあり,米国でその学説の振り子が反対に向かう頃に翻訳され,日本がせっかくそれに追いついた頃には,米国ではもはや流行しないというようなことがよくある。
今やEBM,またはEBN(Evidence-Based Nursing)は,医学や看護学の教育には絶対に必須と考えられるようになったが,この内容も,臨床疫学の中に総括されていた時には流行せず,むき出しの表現名としてEBM,またはEBNとなったら,遅まきながらこれが日本に急速に伸びてきたのである。
バリー先生はGeneral Medicine専攻で臨床判断に関する研究の他に,前立腺癌や泌尿器系疾患を扱った研究,また前立腺疾患とQOLに関する論文やエイズに関する論文が多いが,その他にも医療の経済性に関する論文もある。さらに先生は,どうすれば患者や家族へのヘルス・サービスがよくなるか,という問題と取り組む研究グループの主任にもなっていると話された。
Partners GroupとCare Group
昼食後も1時間半にわたってこの3人と話をしたが,その後ストックル先生の案内でMGHの病棟をひと回りした。MGHは4年前から,ブリガムウィメンズ病院と経営上Partners Health Care Systemという組織を形成し,両病院の間でそれぞれの病院に特に優れたサービスを提供できる部門に,患者をお互いに紹介し合ったり,また物品購入なども共同して行ない,HMOによる医療費の切り崩しに対しても両病院が一体となって交渉してきた。このPartners Groupは,ベス・イスラエル病院とディーコネス病院の合併体としてのCare Groupとは嶮しく相競ってきた間柄である。Care Groupで両病院の融合が期待通りにいかなかったのに対して,Partners Groupのほうが円滑にいっているという話を聞いた。
しかし,MGHの病院棟を回っている間に,各科の病棟の現場で聞くと,両病院の協定を始めた頃はブリガムウィメンズ病院の産婦人科部は非常に名声があるため,産科のケースや婦人科の大きい手術を要する患者は,最初はブリガムウィメンズ病院に委ねることにしたので,MGHのほうは産科の病棟のベッド数を非常に少なくしてしまった。そのうちに,それはMGHにとって不便なことだという理由から,MGHの産婦人科医師が一旦減少させた産婦人科の病床を増やす方向に図っているとの話を聞いた。
互いに歴史のある古い病院が合併または協定するということは,やってみるとなかなか難しいことを米国の,特にボストンの病院経営者は感じている様子である。
1999年度の全米の最優秀総合病院評価の結果が,U.S.News & World Report誌上で発表されたが,ハーバード大学の教育病院としての民間病院のMGHと,この病院と経営を協定しているブリガムウィメンズ病院は,ともに最高の10位までのランキングに入っている。
ちなみに,第1位はジョンズ・ホプキンス病院(ボルチモア市),第2位はメイヨ・クリニック(ミネソタ州ロチェスター市),第3位がボストンのMGHである。上にあげたブリガムウィメンズ病院は第9位にある。過去にあったような輝かしい病院のリーダーシップが公認されるには,BID(ベス・イスラエル・ディーコネス)メディカルセンターは今後,イーストとウエストキャンパスとが完全に融合する努力が必要だと私は思った。
次の予約の時間が来たので,私にはタクシーが呼ばれ,3時15分にはMGHを去って,約5分離れた距離にあるMGHと関連を持つMGH Institute of Health Professionというナースやコメディカルの大学院大学に向かった。
| ||||||||||||||||
