癌治療の新たな戦略
Tumor Dormancy Therapyとは何か
インタビュー 高橋 豊氏(金沢大学がん研究所)に聞く腫瘍縮小なき延命
―――お忙しい中をどうもありがとうございます。早速ですが,本日は現在ホットな話題になっておりますTumor Dormancy Therapyについて,提唱者のお1人である先生にお伺いしたいと思います。まず概要についてご説明いただけますか。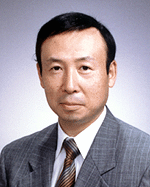 高橋 Tumor Dormancyというのは,ひと言で言えば,腫瘍が長期間増殖せずに,休止・静止している状態をさします。
高橋 Tumor Dormancyというのは,ひと言で言えば,腫瘍が長期間増殖せずに,休止・静止している状態をさします。
従来の癌の治療目的は,あくまでも「治癒」ということにありましたが,それが困難な癌が多いことがわかってきた結果,それに代わる最終目的として「生存期間の延長」ということが考えられるようになりました。そして生存期間については,例えば薬物療法に関すると,「縮小なくして延命なし」という言葉が金科玉条のごとくに言われてきました。つまり,縮小しなければ生存期間は得られないということですが,最近状況が変わってきました。
その契機は,フォークマン(Folkman)が中心となって開発した血管新生抑制剤ですが,これはその特性上縮小させることは難しい薬剤です。ところが,長期間その増殖を抑制するということで,以前は免疫学的な意味合いに使われていたTumor Dormancyという言葉がさかんに使われるようになりました。
翻って考えてみますと,これは血管新生抑制剤だけでなく,薬剤治療に関しても同じことが言えるわけです。われわれは以前から通常の抗癌剤において,「縮小はなくても延命はある」と報告してきました。
つまり,化学療法の効果判定で言えばNC(no change:不変),いわゆる再燃抑制期間の延長が生存期間の延長に寄与することを証明したわけで,われわれはそれを「腫瘍縮小なき延命(survival without tumor shrinkage)」という題で報告してきました。そこで両者を組み合わせまして,われわれは縮小ではなく,増殖を抑制することによって延命を得る「Tumor Dormancy Therapy」という治療法が必要ではないか,それこそが生存期間の延長につながるのではないかと考えて提唱したわけです。
―――この考え方を提唱するにいたるまでの先生のパーソナル・ヒストリーをお聞かせいただけますか。
高橋 私がこういう仕事を始めたのは偶然や流行りだったからではありません。医師になった時から,癌の発育速度,癌の自然経過に興味を持っていました。当時は「癌の時間学」と呼ばれていましたが,癌が発生してから転移して患者さんが亡くなるまでの時間的経過をみていくことで,自動的に「速度」という概念が出てきます。速度というのは癌の種類によっても,またその発育場所によっても違うように,いろいろな要素を含んでいます。
そういった意味からも,腫瘍は大きくならなければ患者さんを死に至らしめないのですから,増殖を抑制することが患者さんの自然経過をストップさせ,それが生存期間につながるということは当然な話です。ところが,薬物療法の効果判定にはなぜかそういった概念がありません。それほど小さくならないのに,とにかく「小さくしなければいけない」ということにしか目が向けられず,なかなか研究が思うように進みませんでした。
ところが,現在はまさにさまざまな分子標的治療が出現してきました。その中でも特に,私は血管新生についてアメリカで研究しましたが,この血管新生抑制剤が最も進んでいます。このような薬は,縮小する力は弱く,Tumor Dormancy Therapyでいくしか道はないことは,すでに臨床試験で実証されています。
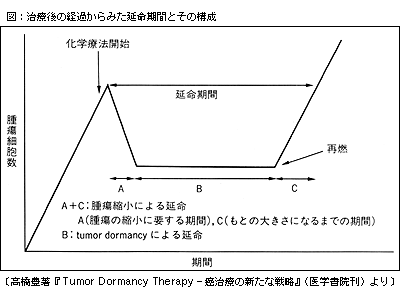
なぜ注目されているのか
―――なぜこの時期に注目を浴びるようになったとお考えでしょうか。高橋 それは大変重要なポイントです。これまで癌に対して各種の化学療法が施行されてきました。ご存知のように癌に対する化学療法の効果を分類しますと,肺小細胞癌,睾丸腫瘍など効果が期待される癌,頭頸部癌,膀胱癌,子宮癌,乳癌など少し期待される癌,食道癌,肺非小細胞癌,胃癌,大腸癌,腎癌などのようにほとんど期待されない癌に分けられます。
胃癌や大腸癌などの消化器癌は多少の縮小,いわゆる奏功率は得られても,生存期間の延長はなかなか得られないのが現状です。その理由は,縮小率がそれほど大きくないからです。しかし私はここで,癌に対する化学療法による延命が,「縮小による延命」と「増殖を抑制する(dormant)ことによる延命」の2つがあることに気づき,しかも消化器癌では後者のほうが長いことを示すことを理論的にも実証できました。ですから,消化器癌のように縮小が得られにくい癌には,縮小にこだわってきたこれまでの療法ではなく,dormantを延長させることによって生存期間を得る治療のほうが効率的ではないかと考えたわけです。
―――欧米では「the more the better」,一方わが国では「the lesser the better, the longer the better」という考え方がありました。化学療法や術後補助療法の問題も含めて,そういう従来の考え方と,この考えがどのように結びついたのでしょう。
高橋 血管新生抑制剤に関しては,欧米ではMMP(matrix metalloproteinase)阻害剤を中心に,臨床試験が行なわれています。さらに最近では乳癌の増殖を司る遺伝子c-erbB-2の抗体であるherceptinが大変よいという報告がなされています。
「よい」という意味は,縮小を助けるのではなくて,併用する薬剤の効果を長続きさせる,つまり増殖を抑制するという戦略で使われているわけで,まさにTumor Dormancy Therapyという考え方が実践されてきたわけです。そして,Tumor Dormancy を最もよく表現できるのが,「TTP(time to progression:増殖抑制時間)」という指標です。最近では純然たる化学療法のスタディでも,このTTPを第1,もしくは第2エンド・ポイントとして問うことが多くなり,TTPを重視することが生存期間の延長につながることに気づき始めたようです。
化学療法の流れの中で
―――化学療法の大きな流れの中での位置づけはいかがでしょうか。高橋 消化器癌に関しては,日本では低用量CDDPと5FUの併用が盛んに行なわれています。これは,BCM(biochemical modulation:生化学的効果修飾)の観点からなされてきた治療法ですが,見方を変えると低用量の化学療法,つまり副作用のない,そして長期間継続できる治療法です。
私どももそういう療法をめざして,カンプトテシン(CPT-11)という,どちらかというと縮小をめざす抗癌剤を低用量投与することを考案して,検討したところ大変よい成績が得られました。具体的には週に1度投与していたものを,20-30%減量して週に3回に分割する治療法です。
同じような話がタキソールという抗癌剤であります。これは,欧米を中心に乳癌で行なわれた「weekly taxans」というスタディで,これは同じように,3週間に1度投与していたものを,毎週1回投与するという治療法で,副作用もなく,効果も増強したと報告されています。
これまでの化学療法は,副作用という障壁のために十分な量が投与できず,結果的に効かなかったケースもかなりあったのではないでしょうか。そういった意味で,副作用を軽減しながら少しずつ投与することで,投与期間や総投与量が増加し,その結果本来の効果を引き出すことができたということを感じているわけです。こうした低用量の化学療法では,腫瘍がゆっくり縮小するという特徴があります。この理由として,癌を殺しているのではなく,アポトーシスを誘導したり,増殖を中止させているのだと推測しております。しかし,その「ゆっくり小さくなる」ということ自体が生存期間の延長につながっていることを明らかにすることを強調したいと思います。
dormant chemotherapyという概念
―――先生はTumor Dormancyをめざした化学療法を,“dormant chemotherapy”として提唱しているとお聞きしましたが。高橋 化学療法には,従来intensive chemotherapyとpalliative chemotherapyという2つの大きな概念があります。そして,この2つと異なるTumor Dormancy をめざす化学療法を“dormant chemotherapy”として,第3の化学療法として考えていく必要性があると思われます。この3つの化学療法の相違を整理してまとめると(表)のようになります。
まずintensiveおよびdormantは積極的な化学療法であり,あくまでも癌と闘う治療です。両者の違いは,前者が主に縮小により生存期間の延長をめざすのに対して,後者は主にTTPの延長によって生存期間の延長をめざすことにあります。
いずれにしても,dormant chemotherapyという概念の創出によって,これまでintensiveとpalliativeしかなかったために,極端に言えばintensiveな化学療法ができないと言われていた症例に対して,生存期間を延長させることができる化学療法が存在することを証明できたわけです。つまり,癌の種類,患者の状態,使用する薬剤の3大因子から,これらの3極のどの化学療法を選択すべきかを検討していけば,より効率的で副作用の少ない治療が可能になることが期待されます。
―――最近は分子生物学的なアプローチから,「発生・発育・浸潤・転移」という癌の基礎研究が非常に盛んになりましたが,このことも要因の1つに考えられますか。
高橋 そうですね。癌細胞はただ単に増殖や転移を繰り返すのではなく,そこには癌細胞自身,もしくは周囲の間質細胞などから産生される数多くの物質や細胞内に存在する数多くの分子が複雑に絡み合っています。その一部でも寸断できれば,癌の増殖や転移に支障をきたすことができます。
つまり分子標的治療というのは,腫瘍そのものを殺すのでなく,戦争に譬えると敵の輸送手段を遮断したり,制御システムを混乱させたりして,敵の勢力を弱体化させるものと言えます。これによって直接癌細胞を攻撃することなく,癌細胞の増殖を抑え,転移を阻止するわけです。
| 表:Intensive, Dormant, Palliative Chemotherapyの相違 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| (QOL:quality of life. TTP:time to progression〔増殖抑制時間〕) | (前掲書より) | ||||||||||||||||||||
| 資料:Tumor dormancyを得るための治療法とその主なもの | (前掲書より要約) | |
| ||
「縮小なくして延命なし」の限界
―――患者さんにとって,副作用がなく,しかも奏効する,つまり増殖を抑制するのであれば,臨床家の先生方にとっても大きな意義があると思いますね。高橋 最初にマスコミが中心となって,「化学療法は効かない」という話がありましたが,これこそまさに「縮小なくして延命なし」という考えに基づいて言われたことだと思います。
―――「縮小」ということにのみ力点が置かれて評価されたということですね。
高橋 ええ。十分な延命につながるような大きな縮小は稀にしかありませんから,「化学療法は必要ない」という評価は確かに当たっていますが。しかし,それは先ほどから申し上げているように,「dormantな期間」に気がついていないところが問題だったわけです。先ほど話に出た補助化学療法は微小癌,微小転移がターゲットになります。微小転移というのは,なんら宿主に影響を与えません。これこそdormantの治療が期待できるものです。つまり,微小癌を長期にdormantな状態にもっていけばほとんど何の影響もなく,結果的に癌の再発を予防して,その人の寿命をまっとうできるわけです。実際に,縮小が見られない経口の抗癌剤でも,adjuvantすると効くというデータがあります。
皆さんが「縮小なくして延命なし」という言葉を信じ過ぎるものですから,adjuvantとして,縮小がないのに化学療法や免疫療法を使う意義に疑問を持っていると思いますが,これをdormantで考えると簡単に答えが出ます。つまり,dormantな状態を維持することによって,延命を得たと考えると非常にわかりやすいでしょう。また微小癌ならば,そうした療法でかなり抑えていける可能性が強いものと思 われます。とにかく,「縮小なくして延命なし」という言葉は,大きな弊害を生んでいます。例えば現在使われている抗癌剤の投与量が,はたして本当に必然性があるかどうかは問題があります。つまり,最適投与量はもっと低い可能性が十分あります。
われわれは実際にそれを,前述したCPT-11で実証できたと考えています。先ほどの続きをお話ししますと,従来の方法に比較して投与量は3-4倍は可能で,それに伴って効果も良くなっていますし,もちろん副作用も激減しています。
より豊かな今後の展望をめざして
―――先生は最近,『Tumor Dormancy Therapy-癌治療の新たな戦略』を出版されましたが,どのような狙いがあったのでしょうか。高橋 まず最初に,Tumor Dormancy Therapyとはどういうことかを皆さんに知っていただくことです。そして縮小がなくても延命はできるということを,認識していただきたいことが2番目です。
そして3番目は,最も重要なことですが,治療法の検討です。私1人の力ではとても実現できることではありません。これまで縮小がないばかりに見捨てられてしまったものの中にも,再検討することによって,まだまだ多くの治療法を発見できると思いますので,皆さんにぜひ研究していただきたいということです。
要するに,現段階では癌の完全治癒は難しいですから,新たな治療法を研究し続けなくてはいけないということです。糖尿病や高血圧の治療では,1つの薬剤で比較的長期間現状維持が可能ですが,癌では耐性があって長期間継続しません。これが実現して初めて患者さんに,「癌を眠らせて,共存していきましょう」と自信を持って言えるのではないかと思います。そのために,多くのdormancyが得られるような治療法を,われわれが用意しておかなければいけません。
―――何か別の薬剤で期待できるものはありますか。
高橋 私の考えでは,いま最も簡単に使えそうな薬は,アメリカでよく使われているchemoprevention(癌の化学予防),つまり癌の発生を抑制する薬です。
しかし,これも実は癌の発生を抑制するのではなく,発生した癌をdormantにするという薬だとも考えられまして,即座に微小転移のdormantにも役立つ可能性が十分あると思います。私はそのうちの1つのα-difluoromethylornithine(DFMO)で,実験的に転移を抑制できることを証明することに成功しております。このDFMOは,すでにアメリカでは大腸癌,皮膚癌,膀胱癌などの予防が,安全性とともに報告されていまして,chemopreventionとして期待されている薬剤の1つです。
真の意味における患者本位の医療:癌との共存をめざして
―――薬剤感受性の個人差に応じたオーダーメイド医療,テーラーメイド医療という治療法が最近盛んに言われていますが,Tumor Dormancy Therapyも同様の治療法と考えてよろしいのでしょうか。高橋 まさにその通りです。患者さんの状態や腫瘍の程度に応じて“さじかげん”でうまく腫瘍をコントロールしていく治療ですから,このTumor Dormancy Therapyはまさに患者さんのため,患者本位の治療だと思っています。
―――先生はご著書の中で,「癌との共存」ということを強調なさっていますが。
高橋 多少繰り返しになるかもしれませんが,先ほどから申し上げているように,腫瘍の縮小が完全治癒につながると考えたことが,いわゆる「ボタンの掛け違い」になったのではないかと考えています。一部の腫瘍を除いて,ほとんどの症例では,「縮小」は50%を少し越える程度で,しかも一時的なものです。少なくとも完全治癒にはつながりません。つまり,糖尿病や高血圧症と同様に,癌もまた完全治癒は難しいのです。
もともと糖尿病や高血圧症では治癒をめざすのではなく,悪化させないで現状維持をめざすことが多いわけで,癌の治療も同様だと思います。現状維持,つまりtumor dormancy,換言すれば「癌との共存」をめざすことこそ,本質的な治療ではないかと考えています。
これまでお話ししましたように,近年,血管新生抑制剤,増殖因子やそのレセプター拮抗剤,低用量化学療法などの研究が次々と進み,臨床で用いられる薬剤や治療法が開発されつつある状況の中で,改めて癌との共存を捉えなおす現状があることと,そのための癌治療におけるパラダイムの転換が必要になってきたことを強調したいと思います。
私が言うところの「共存」とは,患者さんが癌と闘うわけではなく,妥協して癌と和解することですが,その代わりに長期にわたる忍耐が必要とされます。われわれ医師は,これまで以上に患者さんと信頼関係を築き上げ,長期にわたって患者さんの忍耐をサポートし続けることが重要であると思います。
―――本日は長時間にわたりまして,どうもありがとうございました。
