[連載] 質的研究入門 第10回
保健医療の現場における観察法(2)
“Qualitative Research in Health Care”第3章より
著:NICHOLAS MAYS, CATHERINE POPE (c)BMJ Publishing Group 1996
大滝純司(北大医学部附属病院総合診療部):監訳,
瀬畠克之(北大医学研究科):訳
藤崎和彦(奈良医大衛生学):用語翻訳指導
観察に関するいくつかのルール
サンプリング
何らかの記録や分析を行なう前に,まず観察すべき対象を選ばなければならない。他の質的調査と同様に,統計を基本としたサンプリングが行なわれることはほとんどなく,むしろ,目的に合わせてサンプリングを行ない,ある特徴を持った集団や状況を十分に吟味して選び出すことが多い(詳細は第2章,2378号,2380号を参照)。
このようなサンプリングの目的は,対象人口集団の全体を代表する標本を抽出するためではない。観察対象に見られる一般的なカテゴリーについて,その1つひとつを個々の標本が代表するように抽出することが目標になる。最も極端な場合では,たった1つのケースから,多くの状況を説明できるような特徴やカテゴリーを描き出すことも可能である。
1960年代に行なわれたGoffmanによる精神病院の観察は“全制的施設(total institution;施設に収容されている被収容者が,社会から隔離された上に,同じ権威のもとで,同じプランに従って生活全般にわたって全面的に管理されているような施設を指す)”という重要な概念を生み出した。この研究によって,精神病院も刑務所や修道院などと同様に“全制的施設”の1つであることが示された。
記録
質的研究方法としての観察には,人の言葉や行動を観察しそれを記録することが含まれる。すべてのことを記録することは不可能なため,この過程は必然的に選択的にならざるを得ず,しかも,観察する道具であり記録する手段でもある調査者に大きく依存している。それゆえに,フィールドノートという調査中の出来事を同時にあるいは直後に書きとどめる古典的手法を用いるにしても,録音やビデオを使うにしても,観察内容を系統立てて記録し,分析することが重要である。
結核療養所の患者という特殊な立場からRothは,そこでの出来事をあるがままに記録することができた。しかし,このような状況はそう簡単にできるものではなく,身分を隠して潜入するという方法をとろうが,参加者に近い形での観察を行なおうが,多くの場合調査者は,記録のために記憶術を身につけたり,密かに“書きとどめる”ために何度もトイレに駆け込んだりしなければならない状況に置かれる。
系統的にデータを記録することは,ビデオカメラを持って撮って歩く旅行者やフェンス越しにのぞき見をするうっとおしいお隣さんのような観察とは違う。ビデオやテープレコーダーを用いても“すべてを収集する”ことはできない。しかし,調査者は,出会った状況に対して自分がどのように感じ,どう対応したのかも含めて,そこで起こったことをできる限りありのままに記録するように努めなければならない。この種の調査が持つ主観的な視点は,実験研究に求められる客観的な立場とは対極にあるが,実際に質的な観察のデータを解析する際には,これが重要になるのである。
調査者は,通常フィールド日記や研究経過の記録に,種々の出来事やそれに対する調査者自身の反応,あるいはその間における調査者自身の考えの変化などを詳細に記述する。これをもとにして試験的な仮説を立てたり,あるいは事象を分類する枠組みを作り込んでいくことが多い。分類や仮説を検討する中では,それらに当てはまらなかったり,否定するような事例について詳細に記述しておくことが大切である。そのような事例から,きわめて多くのことが明らかになる場合がしばしばあるからだ。試験的な分類をして,それに当てはまらない事例を探すのは,観察調査で用いられる重要な分析手法の1つである。
分析
観察調査の間に集められたフィールドノートは,詳細で叙述的な記録だが,それゆえに厄介でもある。記述しただけでは説明したことにはならないからだ。
調査者がしなければならないのは,データを選り分け,その意味を解き明かして,観察した状況や出来事や相互作用に意味づけをすることである。このような分析過程は,データを収集している時期に始まることが多く,その点で,データの収集が完全に終わってから分析を始める量的研究の進め方とはまったく異なっている(図参照)。
データを系統的に記録するのと同じように,分析もまた系統的に行なう。「分析的帰納法(analytic induction)」や「継続的比較(constant comparison)」も含めて,さまざまな方法が観察データの扱い方として提唱されている。理論上のこまごましたことを除けば,これらはすべて内容分析(content analysis)の変法であり,テープから起こした資料やフィールドノートと照らし合わせながらカテゴリーを作りあげ,仮説を検証し,作り直す作業である。先にも述べたBloorによる耳鼻科外来での観察研究でも,このような分析過程が詳細に記述されている(表)。
量的研究と同様に質的研究でも,データから得られた証拠を呈示した上で結論を導き出すことが重要である。具体的には,特徴的な事例を呈示し,事象について詳しく記載し,字句をそのまま引用することがこれにあたる。観察から導き出した解釈が妥当かどうかについては,その研究についてどれほど信憑性のある系統的な記述をするかにかかっており,観察研究の記述が小説と異なるのは,その公正さが十分に保たれているという点なのである。
Hughesは,「観察研究は,そのフィールドにおける文化やしきたりを十分に伝え得るものでなければならず,それを学んだ別の研究者が,そのフィールドの中に溶け込むことができるほどのものでなくてはならない」と述べている。こうしたことはたやすいことではないが,それゆえに観察調査では個々の研究者に多大な努力が求められるのである。
本章では他の方法では到達できない領域にたどり着くために,観察法がどのように利用できるかを示した。観察法が他の調査方法と比べて系統的ではないとか,いいかげんだとか,役に立たないと決めつけずに,よい研究をしていただきたい。この方法は,保健医療分野の研究者の道具箱に入れておくだけの価値があるのである。
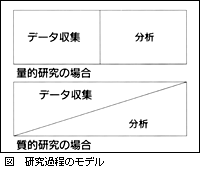
| 表 分析 | |
|
