座談会
21世紀の耳鼻咽喉科を展望する
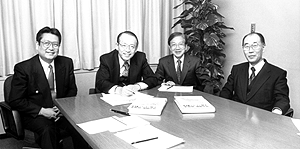 | |||
| 森山 寛 (東京慈恵会 医科大学教授) | 小松崎篤 (東京医科歯科大学 名誉教授 ・日本耳鼻咽喉科学会 理事長) | 本庄 巌 (司会/ 京都大学名誉教授) | 犬山征夫 (北海道大学教授) |
基本に立ち返る必要がある時代に
21世紀へ引き継ぐキーワード
本庄 このたび,『耳鼻咽喉・頭頸部手術アトラス(下巻)』が,昨(1999)年5月刊行の上巻に引き続き,医学書院から発行されました。これを機会に,21世紀の耳鼻咽喉科がどうなるかという将来展望につきまして,編集に当たりました先生方から,夢を含めてお話しいただこうと思います。まず最初に,日本耳鼻咽喉科学会の理事長でもある小松崎先生から総括的な話をいただけますか。小松崎 キーワードをあげますと,まずは感覚器,そして,それに関係するコミュニケーション,リハビリテーション(以下,リハビリ),頭頸部外科などが,20世紀から引き続き重要になると思っています。
まず感覚器については「21世紀は脳の時代」,「感覚器の時代」と言われていますが,耳鼻咽喉科に関係する感覚器というのは非常に多い。聴力,めまいといったものから,味覚,嗅覚などもあります。コミュニケーションについては,聴力と大きく関係する「聞こえ」,あるいは発声があります。さらに,それらの末梢神経系だけではなく,コミュニケーションにおける大脳のプロセスというものも,これからの耳鼻咽喉科には重要となると思います。
リハビリについては,従来の耳鼻咽喉科のQOLということを考えますと,必ずしも十分に対応していなかったと思います。難聴,めまい,発声,嚥下等のリハビリについては,まさに耳鼻咽喉科が対応しなければいけない分野だと思います。それから,宇宙医学と身体のバランス,自律神経なども新しい分野としてあげられます。
一方では,画像や分子生物学を利用し,かつQOLを考慮に入れた治療がますます重要になるだろうと思っています。
本庄 各論につきましては,後ほどそれぞれご専門の立場からお話いただくことにして,次に,本書下巻作成の中心となりました犬山先生からお話しいただけますか。
犬山 耳鼻咽喉科の手術にはいろいろな方法がありますが,いわゆる切除手術に関しては,以前とはかなり変わってきました。一方では拡大された面もあり,今までは手の届かなかった境界領域での手術ですと,上方では頭蓋底手術,下方では上縦隔の郭清術が入りました。それと同時に,頸部の郭清術なども昔のようにラディカルにではなく,なるべく神経や筋肉を温存する方向に変わってきているのも特徴と言えます。
それから話はちょっと違いますが,ガマ腫の手術を例にとりますと,あれは袋を取ろうとしてもなかなかうまくいかずに再発を繰り返すということがあったのですが,舌下腺を取ることによって完璧に治せるようになりました。大きな進歩の1つです。
本庄 森山先生,手術に関して「ミニマム・インベーシブル・サージャリー」といった観点から何かございますか。
森山 昔から,ミニマム・インベーシブルがいい,ということはわかっていたのでしょうが,今のように医療機器は発達していませんでした。それが大きな要因でしょうが,今日では,医療機器の進歩と社会のニーズがみごとに合致したと言えます。むしろそのスピードに,われわれ医師が引きずられているというところも少しあるように感じます。つまり,われわれがそれを十分に使いこなしているかと言うと,一部の人を除くとその発達に追いついていけてはいない。臨床の中で十分に使いこなされていないのではないかと思うのです。そして,「それを使えば,簡単に安全にできる」と考えてしまうことから,本来の手術の基本を忘れかけている部分がなきにしもあらずなのではないでしょうか。その意味では,「基本に立ち返る」という点からも,このアトラス書の発行は有意義だと思います。
機器の進歩と裏腹にある危険性
小松崎 上巻の時もそうでしたが,この下巻を企画する段階で各執筆者にお願いしましたのは,手術の術式を具体的に示すことは当然ですが,手術に関連したインフォームドコンセントについてもお考えいただいて,場合によっては1つの手術について何人かの先生が担当するという方法をとりました。また,手術ごとにその手術を進行する際に気をつけなければいけない点についても触れていただいています。日本ではこれまで,このような視点から書かれたアトラスはなかったと思いますので,「これは役に立つ」とのご意見もいただき,関わったわれわれは自負しております。森山 例えば,今は鼻でも頭頸部でもそうですが,解剖を知らなくてもナビゲーションでポイントアウトして,そこを削るということが可能です。そのために,基本的な解剖や手術のアプローチの知識がおろそかになりがちです。私が先ほど「医療機器に引きずられる傾向にある」というのは,そういう意味です。もう1度基本に立ち返る必要があることをしっかり強調しなければいけないと思います。
小松崎 内視鏡が出てきた時もそうでした。従来は見えにくかったところが非常によく見えるようになり,気軽に手術ができるようになった。そのため,昔は解剖について非常に厳しくやっていたのが,軽んじられる傾向が出てきて,問題も起きてきた。そういった危険性も伴うということが裏腹にあるわけで,これはすべての分野に言えることだとは思います。
犬山 再建外科手術の進歩も本当に著しいものがあると言えます。再建術の歴史をさかのぼりますと,紀元前700年頃のインドで初めて行なわれています。その後宗教上の理由などから途絶えた時期もありましたが,日本では1975年頃から有茎皮弁による再建がさかんになってきました。以後,有茎筋皮弁での再建,現在は遊離皮弁,あるいは遊離空腸といった臓器からの移植も可能にというように発展し,機能面からも整容的な面からも大きく貢献しています。
これらの手術では,耳鼻咽喉科単独でできる手術も多いのですが,特に境界領域や遊離空腸などの場合は,こちら側が消化管を扱うのに慣れていないということもあり,最初は他科との共同で手術するのがよいと思います。
見えなかったものが見える時代に
視覚でとらえられる脳機能
 本庄 話題を少し進めまして,診断技術,あるいは検査法の進歩について,現在の取り組みと将来像についてお話しいただきたいと思います。
本庄 話題を少し進めまして,診断技術,あるいは検査法の進歩について,現在の取り組みと将来像についてお話しいただきたいと思います。
小松崎 21世紀になってもどんどん進むのは画像診断であり,もう1つは遺伝子診断だと思いますね。
森山 今のCT画像は,耳小骨まできれいに見えるようになりました。さらに画像診断の技術は進むでしょう。それからファイバーが非常に細くなりました。そのため,目の中に入るものや,鼓膜を通して中耳腔だけではなく内耳の蝸牛の中に入るようなものも,もうすぐ可能になると思います。ダイレクトに見られるということから,診断だけが1人歩きするという懸念はありますが,直接視覚としてとらえられるというのは非常に大きなことだと思います。
犬山 例えば,副咽頭間隙は,昔のエックス線ではとても見ることができませんでしたが,CTやMRIの出現によって実に簡単に診断できるようになりました。
本庄 エコーは,現在どの程度まで進んでいるのでしょうか。
森山 最近ではエコーも非常に鮮明になり,色を変えて出すこともできるようになっていますね。また,食道ファイバーのエコーで,食道がんの浸潤の広さもわかりますので,頭頸部腫瘍には有用です。それに,CTですと放射線のこともありますが,エコーは非侵襲性なのでもっと開発が進むのではないでしょうか。
犬山 甲状腺や耳下腺も,エコー下の穿刺吸引細胞診ですと簡単ですね。
小松崎 耳鼻咽喉科における感覚器や神経に関しては,単に末梢だけではなくて,末梢から入った情報が中枢神経でどうプロセッシングされていくかが大切になります。
本庄 中枢神経,大脳での働きですが,従来は,発声機構であるアウトプットと,インプットを受け持つ聴覚の部分の検証は,ヒトではなかなかできませんでした。動物でも,大脳皮質にいく手前でどうしても止まっていました。ところが,脳機能画像が使えるようになりますと,ほとんど侵襲なくわれわれが言語をどのように処理しているのか,あるいは喋る時にどこを働かせているのかが,はっきり視覚でとらえられるようになりました。これはとても大きな進歩です。耳鼻咽喉科の大切な分野として,コミュニケーションの中枢のレベルからの研究がもっともっと進歩してほしいと思いますし,人工内耳という具体的な医療からスタートしますので,これからは車の両輪のように,臨床と研究とがともに進歩していくだろうと思います。
情報入力は低年齢から
 小松崎 聴覚における大脳の役割についてずっと研究しておられて,非常にインパクトを与えられたことというのがいくつかあるのではないかと思うのですが。
小松崎 聴覚における大脳の役割についてずっと研究しておられて,非常にインパクトを与えられたことというのがいくつかあるのではないかと思うのですが。
本庄 一番インパクトがあったのは,脳の可塑性の臨界期,年齢制限があるとわかったことでしたね。これにはまいりました。つまり,もうわれわれの脳には新しい情報はあまり書き込めない(笑)。逆に言いますと,幼児期にきちっとした情報を入れてやらないと,あとでいくら入れ直そうとしてもロックされてしまって入り込めないということです。これは,経験的にはわかっていたことなのですが,耳鼻咽喉科以外の領域の人たちにもぜひ知っていただきたいことです。極端に言いますと,子どものしつけは2-3歳ぐらいまでにきちんとしないと,取り返しがつかないということです。
森山 音楽でも,バイオリンをやるのだとしたら低年齢から始めないとだめだと言われていますね。
本庄 語学についても,まさにそういうことが言えると思います。
本庄 聴覚に関してですが,人工内耳では,生まれつきの難聴児の場合,10歳をすぎると成績がよくないということから,やはりはっきりとした年齢制限があります。今は小型の人工内耳が開発されて,日本でも承認されました。以前は,けっこう大きかったために,やはり2歳児では埋込みが無理だったと思います。
小松崎 学会でも,以前は18歳以上という年齢制限がありましたね。それは,ある程度リスキーではないスタート地点を求めたためでした。外国では早くから低年齢化されましたが,日本では今年度の耳鼻咽喉科学会で2歳児からとなります。
感覚器では,そうとう低年齢の時期から基本的な情報を入れるということを始めることが大事です。絶対音感も50歳すぎたら無理ですよね(笑)。
適切な補聴器を選ぶために
本庄 それに関連しまして,高齢者の補聴器も大きな問題です。補聴器が,今のところ必ずしも十分な機能を果たしていないのではと危惧するのですが。小松崎 補聴器の重要性は,従来「音を大きくする」ことでした。よく眼鏡と比較されますが,眼鏡の場合は聴覚でいう伝音難聴と同じで,ボリュームさえ上げればよいわけです。補聴器の適用になるのは,むしろ伝音難聴よりも感音難聴の補聴器,神経がやられているのをどうするかということですので,増幅器のゲインを上げることも症例によっては役立ちますが,それ以外に,もう少し非連続的な,革命的な進歩も期待されます。
本庄 同感です。今は,デジタル補聴器ですとか,ノンリニアの補聴器が開発され,少しずつ言語聴取能力はあがっています。しかし,飛躍的なところにはいっていない。一方,人工内耳のほうはどんどん伸びていまして,どちらを選ぶかがこれから問題になってくると思います。ただ,補聴器というのは,今は一般に耳鼻咽喉科医以外のところでも販売やフィッティングがされていますが,これについては将来的にはどう考えていけばよいでしょうか。
小松崎 これは非常に大きな問題です。補聴器を正確に適用できる耳鼻咽喉科医の養成が必要だと思います。補聴器が眼鏡屋さんで簡単に買えるというのではなく,補聴器の販売ネットワークの中には常にトレーニングを受けた専門医がいる,というようにしていかないといけないでしょうね。
よく言われますのは,孫が初月給でおじいちゃんに補聴器を買ってあげたけれど,おじいちゃんは満足しない。「どうも安物を買ってくれたんじゃないか」というわけです(笑)。結局,十分に使えない。それというのも,適切な補聴器が選べないからだと思いますね。
森山 補聴器も,老人になってからつけると,まさしく「買っては棄て」を繰り返すことが多い。これはやはり,脳のアダプテーションが老人の場合には悪いということでしょう。ですから,補聴器が眼鏡ほど受け入れられないのは,補聴器の音をどうも頭のほうで処理しきれないということがありますが,そのあたりも含めて啓蒙が必要ですね。1台の補聴器で,最初から最後まで満足している人はきわめて少ないです。
小松崎 補聴器の利点や欠点が,一般的に理解されず,時には過大評価されていることもありますね。
森山 補聴器の使い方について,リハビリという言葉があたるかどうかわかりませんが,ケアや補聴器の限度についての具体的な指導は必要ですね。
小松崎 補聴器には限界がある,ということを説明してから売るという形にしなければいけませんね。
森山 東京では,区によってですが補聴器が必要な高度難聴の場合,補聴器を買う際に補助金が出る,というところもあります。そういったことも含めて,ネットワークづくりが大事だと思います。
本庄 もう1つの柱であります,めまいについての展望をお聞かせください。
小松崎 めまいに関係するのは,もちろん内耳だけではないのですが,機能検査や画像が大事になります。しかし,画像から「めまい」と診断のつくパーセンテージは決して多くないと思いますので,問診,機能検査が重要です。
身体のバランスに関する前庭系というのは,3つの半規管と2種類の耳石からなっていますが,現時点で機能検査として有用なのは,外側半規管の検査だと思います。あとの2つの半規管である上半規管,後半規管の機能検査はなかなか難しい。さらに2種類の耳石の機能検査も十分ではありません。したがって,この5つのうち4種類はいまだ十分に検査方法が確立していないと言うことになり,この検査方法の確立が21世紀への宿題だと思います。
他科との協調が大事になる時代に
本庄 続けてリハビリについてもお話しいただけますか。小松崎 難聴のリハビリ,聴能訓練もさらに進歩することが期待されます。聴覚系のリハビリと前庭系のリハビリを比較してみますと,前庭系のリハビリのほうがある意味で楽なんですね。どうしてかと言いますと,聴覚系というのは代償作用がありませんが,前庭系,身体のバランスには代償作用があります。したがって,トレーニング効果が聴覚系よりもずっと上がるからです。それが,宇宙飛行士の訓練などに使われています。ただし,どういうかっこうでリハビリをするのが最もよいのかとなると,さまざまな方法があって必ずしも一定していません。
例えば,両側性の前庭機能が廃絶した場合のリハビリをどう行なえばよいのかとなると,結構難しいですね。幸いにして,両側性の前庭機能が高度に低下しているというのは,それほど多くはありません。もう1つ。例えば,身体の小脳性運動失調のリハビリについては,身体のバランスシステムということで,将来,耳鼻咽喉科の関与というのも必要になってくるでしょう。つまり,身体のバランスに関係する中枢神経系のリハビリに対しても,耳鼻咽喉科が関与するということが重要となるでしょう。
発声と嚥下のリハビリテーション
本庄 その他のリハビリではいかがですか。嚥下や発声というものがありますが。 犬山 発声で対象になるのは,喉頭全摘後の発声訓練ですが,これも非常に歴史が古いのです。声の質としてよいのは食道発声で,器具等も要りませんので最も便利ですが,喉頭全摘を経て創が落ち着いた時点では,特に高年齢の方には人工喉頭が習得しやすいと思います。ただ,今までの人工喉頭というのはモノトーンで,ロボットが喋っているような感じになってしまうものでした。現在では,それまでの欠点を工学的に改良し,抑揚をつけるレベルでの人工喉頭も発売されるようになってきています。
犬山 発声で対象になるのは,喉頭全摘後の発声訓練ですが,これも非常に歴史が古いのです。声の質としてよいのは食道発声で,器具等も要りませんので最も便利ですが,喉頭全摘を経て創が落ち着いた時点では,特に高年齢の方には人工喉頭が習得しやすいと思います。ただ,今までの人工喉頭というのはモノトーンで,ロボットが喋っているような感じになってしまうものでした。現在では,それまでの欠点を工学的に改良し,抑揚をつけるレベルでの人工喉頭も発売されるようになってきています。
その他に,昔からのタピアの笛とか,シャント・オペレーションという方法が使われています。これらはアトラス(本書)にも触れられていますが,なるべく喉頭全摘をしないような治療を開発することが今後の最大の課題でしょう。
森山 嚥下は,中枢性の問題が一番ですね。私どもの関連のリハビリ病院では,神経内科が協力して実施していますので,かなりの効果があります。ただ,嚥下障害の手術にはいくつかの問題があります。診断の精度,手術の適応,いつ手術をするのかなどです。また,その後の訓練指導は耳鼻咽喉科医がしなければいけませんね。
本庄 確かに中枢性も多いのですが,末梢にちょっと手を入れるとリハビリによい効果をもたらすことも多いですね。
森山 輪状咽頭筋を切るですとか,食道を広げるだけで効果は現れますね。ちょっとむせるだけで,患者さんは怖い。それが余計にストレスとなって,どんどん悪くなるのですが,1度食道を通って飲めると自信を持ち,以後は飲めるようになることがあります。嚥下障害については,そういった補助的な手術も意外と大事ですね。
小松崎 難聴やめまいにしても,また嚥下,発声にしても,やはり末梢器官とそれに関係する中枢機構との関連で,その両方に対しての見識を持つ必要があると思います。中枢機構がどうなっているのか,そいうことも21世紀の耳鼻咽喉科が包括しなければいけない大きな問題ですね。脳神経12対の中で,視神経以外にはだいたい耳鼻咽喉科が関係していますから,その中枢機構がどうなっているのかを常に考えながら対応していくことが重要となります。
本庄 痙攣性発声障害というのは,教科書的にいいますと中枢に問題があると言われており,神経内科がそれを扱うことが圧倒的に多かった。しかし末梢の喉頭で,例えば甲状軟骨形成術をやると,それが不思議に治ります。だからやはり,レセプターの部分をちょっといじってやると悪循環が取れることがあるようですので,末梢だけとか中枢だけとかいうように偏らないほうがいいですね。
森山 発声や嚥下は,いろいろなものが複雑にからみあっているデリケートな機能です。人間が生きていく上での根元である食事とコミュニケーションでの発声は,人間が最も大事にしているものです。それがちょっとつまずいただけで,かなり慌てるんですよね。それでよけいに悪くなってしまう。その時に,少しだけ援助をするとよい展開をするということが実際にあります。
睡眠時無呼吸症候群の場合ですと,閉塞性の睡眠時無呼吸ですから,中咽頭あたりに主病変があります。ただ,現在は内科,精神科,耳鼻咽喉科に加えて歯科でも診ていますが,治療の主体は,ある程度手術で補い,その後を保存的にどうしていくかを考えることが,私はよいと思います。
と言いますのは,これからの人間は固いものを食べなくなる。つまり,歯を使わなくなるから当然下顎が後退する。そうすると,中にある舌などの器官は後ろに落ち込む,さらに国民病として体重は増えていくというように,さまざまな問題が起こってきます。この閉塞性の睡眠時無呼吸というのは,増えることはあっても減少はしません。その意味で,やはり耳鼻咽喉科的な処置,治療を大事にしながら,そこに保存的Nasal CPAPをからませるとか,精神科的なアプローチをするという方向が必要です。したがって,他科との協調が非常に大事になっていくと思います。
花粉症治療の新しい方向性
本庄 最後に,アレルギーについてはいかがでしょう。 森山 鼻に関するアレルギーは,ここ10年くらいでかなり病態の変化が出てきています。アレルギー性鼻炎も増えていて,ダニやホコリ以外に,スギ花粉症が出てきました。また,スギ以外のものも今後は抗原になりつつあります。ヒノキもこれから増えるとみられ,4千万人いるとされますスギ花粉症のかなりの人がヒノキ花粉症に移るのではないかと言われています。
森山 鼻に関するアレルギーは,ここ10年くらいでかなり病態の変化が出てきています。アレルギー性鼻炎も増えていて,ダニやホコリ以外に,スギ花粉症が出てきました。また,スギ以外のものも今後は抗原になりつつあります。ヒノキもこれから増えるとみられ,4千万人いるとされますスギ花粉症のかなりの人がヒノキ花粉症に移るのではないかと言われています。
副鼻腔炎のほうも,いわゆる化膿性だったものが1960年あたりからアレルギーが合併するようになってきました。今,非常に多いのはぜんそく合併の副鼻腔炎,あるいは好酸球が非常に浸潤している例です。そういう病態の変化というのが,20世紀終わりから21世紀にかけて目立ってきました。そうすると,当然治療も手術だけではなく,それに合わせたものにしなければいけないということで,その対応が早急に迫られています。5年,10年のスパンで病態変化が急激になってきています。それに対する良薬もまだ開発されていません。
本庄 それは個体,環境のどちらの要因によるものでしょう。
森山 私は,個体のほうが大きいのではないかと思います。確かに,大気汚染の問題や環境ホルモンといった環境の問題もあると思いますが,やはり子どもの時からの食生活の変化,抗原曝露の期間,いろいろな色素剤の入った食事の摂取,動物タンパクの摂取など,抗原にさらされやすいということから,このような病態変化になってきたのだと思います。アメリカが,ちょうど20年くらい前からそうなっていますが,日本はいま急激にアメリカの状態に似てきていますね。花粉症に関しては,現在急速減感作などが試行されていますが,将来的にかなり有望なのはペプチド療法で,いずれDNAワクチンでのコントロールも可能になると思います。
本庄 ペプチド療法とは,どのようなものなのですか。
森山 抗原(タンパク)のうちT-sellに反応するアミノ酸を生合成して,エキスとして使うことにより,アナフィラキシーの発生をきわめて低く抑えることができることになります。したがって,大量にかつ急速な免疫療法が可能となります。これがペプチド療法ですが,いずれにしましても,日本の医療費に占めるアレルギー疾患の比率はとても高いということで,科学技術庁や厚生省,そして文部省も含めて躍起になって減少させようとしているようです。
本庄 これまでの耳鼻咽喉科を俯瞰し,さらに次世紀への展望というものが語られたと思います。耳鼻咽喉科は,とかくこれまで「手術をしても完全には治らない病気」というイメージが強くありました。これは,われわれも含めて責任があると思います。また,蓄膿症,慢性中耳炎,扁桃炎といった「化膿性疾患」という旧態依然としたイメージがまだあるように思います。
しかし,現在の耳鼻咽喉科はそれから離れたところを飛びつつあるということが,今日語られたと思います。そのあたりのことが他科のみなさんにもわかっていただければ,この座談会の意味があったと思います。このたびの出版となった『耳鼻咽喉・頭頸部手術アトラス(上・下巻)』を活用していただき,患者さんのためのよい手術を期待したいと思います。本日はどうもありがとうございました。


