米国における「クリニカルパス」の導入・活用状況
-米国での訪問調査を実施して
池田俊也(慶大医療政策・管理学教室)
はじめに
近年,わが国でもクリニカルパスを通じた業務改善に関心が集まっている。この度,米国東海岸の著名な病院を訪問し,クリニカルパスの導入・活用状況について見学する機会を得たので,その概要を報告する。実質的な調査期間は本年3月20-24日の1週間。訪問先は,ボルチモアのジョンズポプキンス大学病院,フィラデルフィアのペンシルバニア大学病院,ボストンのブリガム&ウイメンズ病院ならびにマサチューセッツ総合病院の順であった。ジョンズポプキンス大学病院
ジョンズポプキンス大学病院では,外科部門におけるクリニカルパス担当者のDawson氏らと面談した。同病院では1990年より約40種類のクリニカルパスを開発したものの,実際に運用しているものは少ないと言う。外科部門において,特に成果があがったものとしては複雑な胆道系の手術を対象としたクリニカルパスがあり,平均在院日数は13.3日から10.1日に減少した。また,クリニカルパス作成に当たっては,複数の医師間で意見の相違があった場合,実際にアウトカムを調査し,両者に差が見られなかった場合には両方ともクリニカルパス上に反映させると言う。実際のクリニカルパスを閲覧したところ,「Dr.○○以外」という記載もあり,あくまでもエビデンス重視,アウトカム重視でクリニカルパスを作成している姿勢がうかがわれた。
ペンシルバニア大学病院
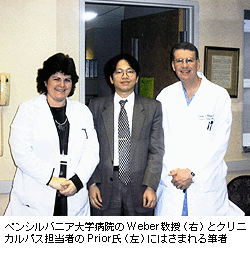 ペンシルバニア大学病院では,まず大学病院全体におけるクリニカルパス担当者であるCorey氏と面談を行なった。
ペンシルバニア大学病院では,まず大学病院全体におけるクリニカルパス担当者であるCorey氏と面談を行なった。
氏は,クリニカルパス導入のポイントとして,(1)作成・導入時における医師の関与,(2)関連職種すべてがチームを組む,(3)患者を巻き込む(患者用資料の作成や患者満足度調査の実施等),(4)バリアンスの収集と解析,(5)管理部門による支援,などをあげていた。運用中のクリニカルパスは,表1に示す計34種類であるが,肺炎等の内科系クリニカルパスについては院内で十分に受け入れられておらず,ルーチンに使用されてはいないとのことであった。また,当面はクリニカルパスの数を増やす予定もないと言う。
次に,同病院の1999年度質大会において最優秀賞(Quality Award)を受賞した「頭頸部癌のクリニカルパス」に関して,耳鼻咽喉科頭頸部外科のWeber教授ならびに当該クリニカルパス担当者であるPrior氏と面談した(写真)。
頭頸部癌のクリニカルパスは,耳鼻咽喉科頭頸部外科における唯一のものであり,医師5名,看護婦5名,薬剤師1名,理学療法士4名,言語療法士2名がチームを組んで1995年に導入した。頭頸部癌を対象に選んだ理由は,(1)14日後の再入院率が17%と高率であること,(2)平均在院日数が16.4日と長いこと,(3)1症例あたりのコストが105,410USドルと耳鼻咽喉科頭頸部外科の中で最高であること,(4)抗生剤投与など重要な部分で不統一があること,(5)患者満足度調査において改善の余地が認められたこと,(6)ケアコーディネーションの必要性が高いこと,などであった。クリニカルパスの導入前・後を比較すると,在院日数は8.0日と大幅に減少した一方で,郵送調査による患者満足度は有意に上昇した。再入院率,合併症発生率,院内死亡率といったアウトカムは不変であった。
なお,同病院ではバリアンスデータの収集に際しマークシートを用いていた。すなわち,すべての項目をもれなく収集することをめざすのではなく,重要な項目を絞り込み,解析の簡便性と迅速性を重視していた。
例えば,頭頸部癌のクリニカルパスでは,表2に示す通り,手術日に理学療法士が診察したか,術後1日目に人工呼吸器が外されたか,術後2日目に疼痛が中等度以下か,といった22の項目のみをバリアンス収集項目としていた。なお従来は,バリアンスの要因として,システム要因,医療提供側の要因,患者側の要因を区別して収集していたが,すべての場合において区別することは必ずしも容易ではない。そのために,空欄が増えてしまうことから,要因についてはマークシートで捕捉することはせず,別途カルテなどから収集する方式に変えたそうである。
なお,同大学ではコンピュータによるオーダーエントリーシステムを導入しており,病棟の各所にオーダー用の端末が配置されていた。クリニカルパスに関するオーダーも端末から行なうことが可能となったことから,従来のオーダーシートと一体化したクリニカルパスではなく,裏表1枚の簡便なクリニカルパスに移行予定とのことであった。
ハーバード大学関連病院
ハーバード大学の関連病院であるブリガム&ウイメンズ病院とマサチューセッツ総合病院は,1994年に合併しているが,クリニカルパスの取り組み状況は異なっていた。ブリガム&ウイメンズ病院質改善部門のMcDonough氏によれば,8種類のクリニカルパスを運用中であるが,質改善部門の人員が不足しているため,現状では十分なバリアンス解析が行なわれていないとのことであった。現在はクリニカルパスの電子化を進めており,バリアンス解析がより容易になる見込みとのことであった。一方,マサチューセッツ総合病院質改善部門のMort医師らの話では,66種類ものクリニカルパスが作成されており,こちらも紙ベースからコンピュータに移行中とのことであった。パイロット版としてコンピュータ上で肺炎のクリニカルパスを閲覧したが,オーダーエントリー項目がテンプレート化されており,最小限の情報が整理され紙ベースよりもはるかに見やすかった。また,より詳細な情報を必要とする場合には,web(ホームページ)の画面で図表や関連文献が閲覧できるようになっており,電子化のメリットが最大限に生かされていた(図)。
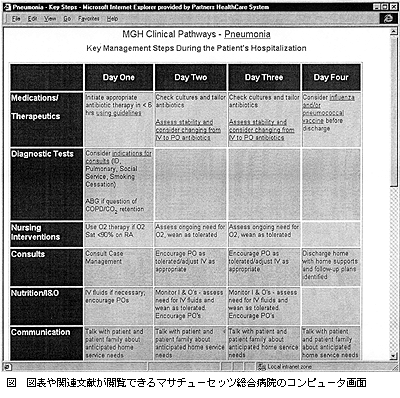
わが国への示唆
今回の訪問調査を通じ,各施設における成功事例の共通項を整理することにより,クリニカルパスを通じた質改善を成功に導くための条件のいくつかが明らかになった。例えば,(1)医師を中心として多職種間のコーディネーションを基本とした開発を行なうこと,(2)コスト削減よりも医療の質の改善を主眼とした取り組みを行なうこと,(3)アウトカムの測定を行ない,当事者に定期的にフィードバックすること,(4)バリアンス解析の項目を絞りマークシートや電子カルテ等を利用して効率的に解析を行なうこと,などである。これらの事柄は,わが国においても取り組むべき課題といえるのではないだろうか。今回の訪問調査は,厚生科学研究「医療技術評価推進事業」(主任研究者=東医歯大 阿部俊子氏)の一部として実施した。また,訪問先のアレンジに際しては,池上直己氏(慶大医療政策・管理学教室教授),柳田洋一郎氏(東京マタニティクリニック院長),橋本英樹氏(帝京大),ジョンズポプキンスの中川秀樹氏をはじめとする多くの方々のご協力を得た。ここに深謝する。
| 表1 ペンシルバニア大学病院で使用中のクリニカルパス | |
|
| 表2 頭頸部癌のクリニカルパスにおけるバリアンス収集項目 | ||
|
