「エビデンス」とは何か-科学史から見たEBM
広井良典(千葉大助教授・総合政策学科)臨床疫学としてのEBM
はじめに
EBM(Evidence-based Medicine:根拠に基づく医学)という言葉あるいは概念が,医学・医療における中心的なキーワードとなりつつある。また,これに関する論文・特集記事や新雑誌の創刊などが,同様の発想に立つ「根拠に基づく医療(Evidence-based Healthcare)」や「根拠に基づく看護(Evidence-based Nursing)」を含めて,大量に現れるようになっている。改めて確認するまでもなく,EBMの基本的な発想の1つは,これまで医師ないし医療従事者の“勘と経験”に依存してきた要素の大きい医療の世界を,確固とした科学的・客観的基盤に根ざしたものとし,それを通じて医療サービスの質を高めていこう,というものである。こうした理念は,ともすれば医師の主観的な「裁量」にすべてが(しばしば権威主義的なかたちで)ゆだねられ,医療が一種の「ブラックボックス」とでも言えるような閉鎖的な性格を強く持ってきたわが国の医療のこれまでを考えると,とりわけ重要な意味を持つものであり,筆者自身,こうしたEBMの発想や実践は,今後の医療現場や臨床研究において着実に浸透していくべきものと考えている。
しかしながら,新しい概念が登場してきた場合にしばしば起こることであるが,最近の議論を見ていると,EBMという概念ないし考え方について誤解があるのではないか,と思われるような紹介や説明の仕方も一部に見られるようになっている。そこで本稿では,特に科学史的な視点をベースとしながら,EBMという概念の基本にある考え方やその背景について簡潔に述べてみることとしたい。
EBMという言葉の魅力
EBMの本質ともいえることでありながら,しばしば忘れられがちである基本的な点が,EBMとはすなわち「臨床疫学」のことである,という点である。臨床疫学(clinical epidemiology)とは,文字通り公衆衛生分野における「疫学」の考え方を医療の「臨床」に応用しようという理念のもとに,1970-80年代前後を中心に発達した学問分野である。カナダのマクマスター大学のDavid Sackettらが中心となり開発されたこの臨床疫学という分野は,後に述べるような医療をめぐる時代のニーズにもかなうものであり,一定の着実な進展を見せてはいたものの,そのネーミングに難があったのか――例えば,「疫学」という(公衆衛生畑の)言葉ないし発想に抵抗を感じる臨床医は多い――,大きく普及するには至らなかった。ところが90年代に入って,同大学のGuyattがこれに「EBM」という新しい名称を与えたことを契機として,一気に広く受け入れられるところとなり,冒頭述べたような今日における隆盛となったのである。
こうした事情について,日本におけるEBMの第一人者である京都大学の福井次矢氏も,「その内容は決して目新しいものではなく,すでに1980年前後より一般内科領域での診療・研究の屋台骨と考えられていた臨床疫学そのものであったが,EBMという言葉の魅力のためか,急速に人口に膾炙することとなった」(西村昭男編:医療科学;医療の新しいパラダイム-Evidence-based Medicine,医療文化社,1999)と述べている。
疫学の発想と近代医学-「現象」か「実体」か
西欧近代科学のパラダイム
このように,EBMとは他でもなく「臨床疫学」ということなのであるが,ではそもそもその場合の疫学とは何であろうか。ここでは,疫学についての教科書的な説明ではなく,本稿での文脈にそくする限りでの重要な点について述べてみたい。おそらく,一般の日本人が初めて「疫学」という言葉に触れたのは,世界的に見ても最大の公害被害の1つと言える,昭和30年代における水俣病の発生とその解明に関してではなかったかと思われる。
熊本県水俣市の工場付近で奇病とも言える異変が発生した。当初はネコが死に,ねずみが増えるといった環境異変にとどまっていたが,それがやがて人に現れる。しかしその異変の実体や,ましてやその「原因物質と病気の発生メカニズムの解明」などはすぐにはわからない。
しかし,明らかに異変が起こっていることは確かであり,ともかく早急な対応が必要である。ここで大きな役割を果たしたのが,そうした「実体」的な因果関係を追及するのではなく,まずは「現象」相互の相関関係を(統計的な手法を通じて)明らかにしようとする「疫学」研究であった。
すなわちこういうことである。今,私たちが医学の本流として扱っている「近代医学」は,病気というものについて次のように考える。それは,「1つの病気には基本的に特定の原因物質が存在しており,それが物理・化学的な因果関係の結果として特定の病気を引き起こす。その発現のメカニズムを解明するのが医学(研究)の目標であり,またそれによってこそ治療も可能となる」という考え方である。
これは,「バイオメディカル・モデル」と呼んでもよい考え方であり,歴史的に見ると,19世紀に「特定病因論」というかたちで確立したものである。それが,20世紀初めにかけてまず感染症の予防,後に治療に絶大とも言える成果をもたらし(抗生物質の開発など),世紀半ば以降は分子生物学と合流して現在の遺伝子研究等へと展開してきた,医学の“メインストリーム”をなすと言ってよい考え方である。その基本にあるのは,病気の原因と発生機序を「ミクロ」的な(要素的な)「実体」とその因果関係に求める発想,と言ってよい。まさに「西欧近代科学」のパラダイムである。
EBMの本質
ところが,こうした発想やアプローチは必ずしも万能とは言えない面を持っている。その第1は,上に記した水俣病の例に見られるように,直ちにそうした「実体的な原因物質と病気の発生メカニズム」が解明されない場合の対応,というケースである。そうした場合に,“実体的なエビデンスがない”ことを理由に,明らかに「現象面での異変」が起こっているのに対して迅速な対応をとらないとすれば,それはまったくの本末転倒というものであろう(実際に,わが国における水俣病への対応はそのような道をたどり,多くの悲惨な結果を生んだ)。現象面での観察から出発する「疫学」が重要になるのは,こうした場面においてである。もちろん,「現象面での相関関係」は多分に見かけ上のものにとどまる場合もあり(例えばある地域において,病気Aの発生頻度と,ある食物Bの消費量が多いという事実があったとしても,「食物Bが病気Aの原因だ」と直ちに結論づけられるものではない),拙速は慎まれるべきである。そして,だからこそ,そうした現象面での,つまり「臨床的なデータ」をしっかりと積み重ねて統計的に整理し,できる限り客観的な判断と対応を行なおうとするところに疫学が,そしてその臨床への応用としての「臨床疫学」つまりEBMが生まれたのである。
したがって,EBMがいうところの「エビデンス」とは,(しばしば誤解されるように)決して(生物学的な)ミクロの原因物質や因果関係といった意味ではなく,医療者が目の前にする患者の訴え・ニーズとそれへの対応そのものが,1つひとつの「エビデンス」なのである。やや象徴的に言えば,「実体」からではなく個々の「現象」(患者の訴えや状況)から出発するというのが,「臨床疫学」としてのEBMの本質的な発想である。
それは,例えばがんの治療過程において,特定の検査値の動きや局所的な生理学反応のみに注目するのではなく,心理面を含めた患者の訴えやQOLそのものを重視するという方向と重なるのである。
EBMの意義
さて,先に述べた「バイオメディカル・モデル」が万能とは言えない第2の場面は,いわゆる生活習慣病への対応である。改めて確認するまでもなく,生活習慣病ないし特性疾患の場合,単一の原因物質(遺伝子など)や直線的な因果関係が存在することはむしろ稀であり,無数の環境要因と,ストレスなど心理面の要因などがきわめて複雑に絡み合った帰結として病気というものが生まれる。だとすれば,バイオメディカル・モデルが想定するような「特定の原因物質の解明とその除去」としての病気の治療というシナリオがすべての特性疾患の場合に果たして万能か,という疑問を持ったとしても,それはあながち不合理なことではない。そこで,むしろそうした実体的な因果関係を初めから想定するのではなく,むしろ個々の患者の訴えやその置かれた状況の把握,実施した臨床対応,予後のフォローアップ等々から出発し,しかもそれらをしっかりとした記録ないし統計的なデータベースとして蓄積していき,それを踏まえて最適な診療を追及する,という対応が独自の重要性を持ってくる。
EBMの意義は他でもなくこうした点に存在するのである。
近代科学・医学の展望とEBM
不可欠な「複雑系」コンセプトの理解
以上述べてきたことを踏まえ,さらに広い視点でEBMと今後の医学の展望をまとめると図のようになる。上記のように,病気の「実体」的な把握という発想に立ち,その因果的な発生メカニズムを追求してきたのが近代医学(バイオメディカル・モデル)であった(図のA)。一方,個々の「現象」から出発し,その統計的な把握という手法をベースにして病気への対応を行なってきたのが疫学や公衆衛生の分野である(図のD)。図に示されているように,これまでこの両者はまったくの“対極”にあり,あまり接点がなかった。しかし,先に述べたような背景(生活習慣病への対応など)から,バイオメディカル・モデルのほうも,原因物質と直線的な因果関係という理解では不十分となり,病気や医学についての新しいパラダイム(理解の枠組み)が求められてくる。とりわけ「複雑系」というコンセプト(注:近年の物理学,数学などの分野で唱えられるようになった概念で,さまざまな自然現象を単線的な因果関係としてではなく,無数の要因が複雑に絡み合うものとして把握しようとする考え方)に象徴されるような,「心理面や環境要因などが無数に関わり合う結果としての病気」という理解が不可欠になるのである(図のAからCへのシフト)。そして,ここまで来ると,つまり対象の間の非因果的な関係まで視野に入れるようになると,これまでの前提であった「実体-現象」という区分自体が維持困難になる。こうして,病気への現象面からのアプローチという疫学的な発想との接点が生まれ,そこに「臨床疫学=EBM」の舞台が開かれるのである。
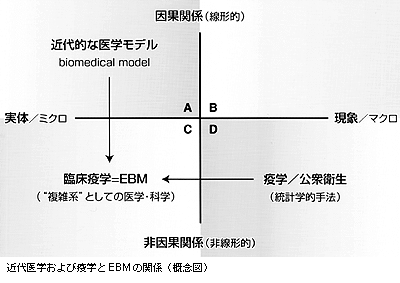
看護に求められるEBMの理解と実践
本稿で述べてきたように,EBMという概念ないし考え方の中には,近代医学・科学の基本的な枠組みそのものを超えるさまざまな要素が含まれている。看護に即して言えば,それは患者の個々の訴え,ニーズや状況というものに一義的な関心を向けてきた「看護」という営みに,新しい固有の意義と独自性を与えるものである。それは同時に,狭い意味の「医療モデル」をより広大な視野から相対化できるような場所へ看護を解き放っていくための,1つの武器となり得るものとも言える。看護職は,患者のニーズそのものから出発する,というスタンスにもっと自信を持ってよいし,それがEBMあるいはEBNという方法論と結びつく時,看護学という領域は,近代科学を超えた新しい科学の姿を切り開いていくフロンティアとなる,と言っても過言ではない。深い認識に裏づけられた,EBMについての理解とその実践が求められているのではないだろうか。
