MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


自分で学ぶ授業に最適な医学生理学教科書
ガイトン臨床生理学 早川弘一 監訳《書 評》菅 弘之(岡山大教授・生理学)
生理学教科書の世界的ベストセラー
 本書の原書はTextbook of Medical Physiology(9th Edition)で,著者はGuyton AC & Hall JEである。アーサー・ガイトン教授が本書の第1版を1956年に出版して以来,半世紀弱が経った。私も1960年代前半に医学生だった折,この第2版を愛用した思い出がある。米国留学先の佐川喜一教授(故人)がガイトン教授の弟子であった関係で,ガイトン教授と何度もお会いする機会を得た。ガイトン教授はハーバード医学校卒で,脳外科医をめざしておられたが,ジョンス・ホプキンス医学校でレジデント中にポリオに罹られて,出身地ミシシッピー州に帰り生理学者に転向された。生理学授業は学生による理解度を最高にするように工夫され,手足が不自由のため口述したものを秘書がタイプし,学生の意見を採り入れて推敲を重ね,第1版が完成したとのことである。その後,世界各国語に翻訳されて,生理学教科書の世界的ベストセラーとなった。
本書の原書はTextbook of Medical Physiology(9th Edition)で,著者はGuyton AC & Hall JEである。アーサー・ガイトン教授が本書の第1版を1956年に出版して以来,半世紀弱が経った。私も1960年代前半に医学生だった折,この第2版を愛用した思い出がある。米国留学先の佐川喜一教授(故人)がガイトン教授の弟子であった関係で,ガイトン教授と何度もお会いする機会を得た。ガイトン教授はハーバード医学校卒で,脳外科医をめざしておられたが,ジョンス・ホプキンス医学校でレジデント中にポリオに罹られて,出身地ミシシッピー州に帰り生理学者に転向された。生理学授業は学生による理解度を最高にするように工夫され,手足が不自由のため口述したものを秘書がタイプし,学生の意見を採り入れて推敲を重ね,第1版が完成したとのことである。その後,世界各国語に翻訳されて,生理学教科書の世界的ベストセラーとなった。
著者の序文にもあるように,臓器,系レベルで発展してきた生理機能学が,過去20年くらいの間に分子,細胞レベルにまで掘り下げて理解できるようになり,膨大な知識量となった。しかし医学においてはまとまった単位としての生体の諸機能を理解するためには,個々の要素機能に関する知識の寄せ集めではなく,それらが有機的に結合された自然の状態で統合的に理解される必要がある。それに応えるべく,ガイトン教授が教科書としても内容の統合に留意された点で,本書はユニークであり続けてきた。現在の内外の生理学教科書の多くは編者がいて,その下に多くの執筆者が各論を書く方式なので,本書ほどの統合された内容には達していない。
このようなバイブル的な生理学教科書が,循環器病学者として著名な早川弘一教授(日医大学長)の監訳のもとに「臨床生理学」と銘打って翻訳出版されたことは,日本の医学教育にとってきわめて喜ばしいことである。分担翻訳者は日医大の臨床家グループ87名である。さらに教授クラス13名が責任編集者として,4名の生理学教授,名誉教授が編集協力者として加わっている。このような布陣をもって,総頁1100余頁の翻訳本が完成した。
初めて生理学を学ぶ学生に
具体的に内容を見ると,いくつかのユニークな点に気づく。まず図が簡潔で,わかりやすい。これらの中には旧版から見覚えのある図も多い。それらは長年の風雪に耐えて淘汰されない概念が凝集している図である。序文にも書かれているように,批判があれば改良を加える方針で改訂版が出版されてきているので,古くからある図には不死身の概念が宿っていると言えよう。次にユニークな点は,記述が簡潔なことである。これは,定着している考え方を学生にわかりやすく書くという原則に沿っているからである。したがってそれぞれの分野の専門から見ると物足りない部分もある。しかし生理学を初めて学ぶ学生が最低限の知識を学習する教科書,あるいはその後の生理学復習用の教科書としては,本書の簡潔性,統合性はきわめて有効である。昨今の医学知識が膨大となり,生理学の授業時間が減少する反面,生理学から臨床医学への橋渡しとしての病態生理学が重視され,「授かる授業」から「自分で学ぶ授業」への意識改革が要求される時代には,本書は最適な医学生理学和文教科書,参考書と考えてもよいと思う。
B5変・頁1156 定価(本体20,000円+税) 医学書院


ヘリコバクター・ピロリを理解するための1冊
ヘリコバクター・ピロリ フォーラム病態と治療の最前線 藤岡利生,榊 信廣 編集
《書 評》中村孝司(帝京大市原病院教授・内科学)
若年研究者たちの5年間の結晶
 竹本忠良教授による本書の「序として」によれば,本書は,1995年から毎年2回開催され,今年で10回になる「ヘリコバクター・ピロリフォーラム」という,若年研究者による研究会の5年間の結晶がまとめられたものであるという。中高年のいわゆる斯界の権威者をまったく含まない,若年研究者だけで作りあげた,活力のあふれる論文が多数ならんでいる。
竹本忠良教授による本書の「序として」によれば,本書は,1995年から毎年2回開催され,今年で10回になる「ヘリコバクター・ピロリフォーラム」という,若年研究者による研究会の5年間の結晶がまとめられたものであるという。中高年のいわゆる斯界の権威者をまったく含まない,若年研究者だけで作りあげた,活力のあふれる論文が多数ならんでいる。
単に自分のデータのみをあげて結論を主張する原著形式の論文でなく,これまでの多くの成果を十分咀嚼して総説として書かれているので,H.pyloriをとりまく諸問題の現況を理解するのに大いに役立つであろう。
では内容をみてみよう。全体は大きく3部に分かれており,1冊約200頁のうち,第1部病態では約70頁がさかれ,H.pyloriとその病態に関与すると考えられている種々の要因(接着因子,サイトトキシン,サイトカイン,NO,アポトーシス,白血球,リンパ球,菌株の多様性,宿主因子,酸分泌の10項目)がまとめられている。H.pyloriの基礎的な分野であり,最近では若手研究者が多数この分野に精力的にとりくんでおり,立ち遅れたわが国のH.pylori研究も,世界のレベルに到達してきたことを示す領域である。まだ未解決の問題が山積しており,やりがいのある分野である。
第2部は実験動物による感染実験や発癌を取り扱った部分であり,4篇で約30頁がこれにあてられている。H.pyloriによる発癌はきわめて大きな問題であり,動物実験によるわが国での成果は世界を抜いており,論文からも生きいきとした活力が伝わってくる。特に読みごたえのあるところであろう。
除菌治療を始める人たちの参考書に
第3部は治療篇であり,本書の半分がこれにふりむけられている。12篇の論文から成っており,H.pylori除菌治療の基本から,除菌の対象,具体的な除菌の方法とその評価がくわしく述べられており,H.pylori除菌治療が保険医療として認められようとしている現在,これから除菌治療を始める人たちの参考書として実地に役立つ部分である。このように,この1冊でH.pyloriに関する現在の知識のレベルが十分理解できる手ごろな読みやすい書であると考える。
B5・頁208 定価(本体4,700円+税) 医学書院


臨床の場で必要されるコミュニケーションのすべて
医療現場のコミュニケーション箕輪良行,佐藤純一 著
《書 評》高久史麿(自治医大学長)
コミュニケーションに必要な技術の習得
今回箕輪良行,佐藤純一両氏の執筆による『医療現場のコミュニケーション』と題した単行本が医学書院から出版されることになった。医師という職業の基本に,患者やその患者の家族との対応がある。また現在の病院の診療はチーム医療の形で行なわれ,医師にはそのチームの中心となることが期待されている。したがって医師と患者やその家族との間,ならびに医療関係者の間で良好なコミュニケーションが行なわれなければ十分な医療を行なうことはできないし,医師にはその必要性を十分に理解するだけでなく,コミュニケーションに必要な技術を習得しておくことが求められる。一方,現在のわが国の医学現場を見てみると,以前に比べてプライマリ・ケア教育の一環としてコミュニケーション教育の重要性が認識されるようになったとはいえ,本書に一部紹介されているようなアメリカの医学校におけるコミュニケーション教育に比べて,まだまだ不十分と言わざるを得ない。また現在のように,インターネットに熱中し,コンピュータの前から離れない医学生が多くなると,コミュニケーションの下手な若い医師が今後増えるのではないかと憂慮される。このような時期にこの本が出版されることは誠に意味あるものと考える。
本書の著書である箕輪良行,佐藤純一の両氏はいずれも私が現在勤務している自治医大の卒業生で,卒業後は離島での医療に従事している。また現在も医療の最先端にあって患者の診療にあたっている。したがって,この本に書かれているさまざまなケースの紹介や,各ケースに関するコメントには,著者たちの今までの経験が滲み出ている。
医療の「アート」の部分
医療は,サイエンスとアートから成り立っている。最近よく言われるevidence-based medicineや治療のガイドラインなどは,医療の中のサイエンスの部分と言えよう。一方,本書で取り上げているコミュニケーションは,アートの部分と言える。サイエンスの部分については,いろいろな情報手段を使って最新のニュースを入手することができるが,アートの部分については,各医師の性格,人生観,経験の積み重ねなど,さまざまな要因によってその評価が左右されることが多い。しかしアートに関しても,サイエンスと同様にさまざまな情報を得ることによってその内容を向上させることが可能である。本書がその手法の1つとして多くの医師たちに読まれることを期待している。最後に,随所に挿入されている「ちょっと一言」(下段)に著者たちの似顔絵が描かれているが,実物はもっとよいはずであることを付け加えたい。
A5・頁212 定価(本体2,500円+税) 医学書院
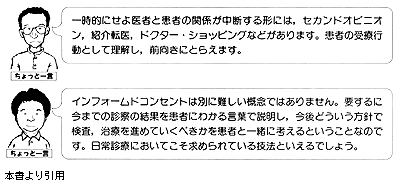


PTおよび学生ための臨床場面での実用的な手引書
四肢麻痺と対麻痺第2版 Ida Bromley 著/荻原新八郎 訳
《書 評》高橋正明(昭和大医療短大教授・理学療法学科)
患者主体の視点が明確に
 アイダ・ブロムリ著の『四肢麻痺と対麻痺』第5版が翻訳され,医学書院から出版された。訳者は初版(原著第3版)と同じく荻原新八郎先生である。内容は脊髄損傷に関係する生理学,急性期の理学療法からリハビリテーションまで網羅され,初版と基本的な流れは同じであるが,新たに,上肢の機能的電気刺激,姿勢と座席適合,C1,2レベルの超上位損傷者の治療,および脊髄損傷者の老化による諸問題が取り上げられた。また章立てや項目立てにより吟味し工夫した様子がうかがえる。例えば「自己介護」の項目が「個人的自立」へ,「マット上動作」が「基本的実用動作」へと変更されているように,患者主体の視点が明確に打ち出されているのである。そして何よりも嬉しいのは,初版に比べ1つひとつの説明がとてもていねいになされていることである。
アイダ・ブロムリ著の『四肢麻痺と対麻痺』第5版が翻訳され,医学書院から出版された。訳者は初版(原著第3版)と同じく荻原新八郎先生である。内容は脊髄損傷に関係する生理学,急性期の理学療法からリハビリテーションまで網羅され,初版と基本的な流れは同じであるが,新たに,上肢の機能的電気刺激,姿勢と座席適合,C1,2レベルの超上位損傷者の治療,および脊髄損傷者の老化による諸問題が取り上げられた。また章立てや項目立てにより吟味し工夫した様子がうかがえる。例えば「自己介護」の項目が「個人的自立」へ,「マット上動作」が「基本的実用動作」へと変更されているように,患者主体の視点が明確に打ち出されているのである。そして何よりも嬉しいのは,初版に比べ1つひとつの説明がとてもていねいになされていることである。
ずっと以前であるが,英国人の書くものは内容が実にプラクティカルであるという印象を持った。プラクティカルといえばすぐに米国人を思い出すが,彼らのように常に理屈がついて回るのと違い,英国人は,実用的で役に立つ知識をけれんみなく読者に提供してくれる。そのためか,なるほどと思うことよりもハッとさせられることのほうが実に多い。本書の初版を読んだ時も同様に感じた。しかも著者が原著第1版の序で述べているように,理学療法士および学生のために臨床場面での手引き書を作るという明確な意図を持って書かれた実用書である。教わることが多かった。
なるほどと思うより,ハッとさせられることが多い1冊
しかしながら初版はけれんみがなさ過ぎた。表紙は色が地味でタイトルの文字が小さい。中は段組を組んでおらず白い部分がやたらと目につく。ほとんどの説明図が手書きの絵である。そしてさらには説明が淡泊で,とにかく今様に一言で表現すれば体裁がダサイのである。それが第2版では見事に変身した。まず,表紙が別物と思えるほどのアピール力を持った。初版と第2版を並べて学生に取らせると間違いなく第2版を選ぶ。中は2段組となり,専門書らしく読みやすい。写真による物品の提示が増えた。手書きによる説明図は以前と同じであるが,体裁が良くなると主張したいところが容易に表現できる手書きのよさが逆に引き立つ。読んでいて,とにかくハッとさせられることの多い1冊である。B5・頁246 定価(本体4,800円+税) 医学書院
