ドクターヘリは救急医療を変えるか
医師が同乗して救急患者を治療しながら病院への搬送を行なう「ドクターヘリ」。日本でも,その実用化へ向けて,検討が進みつつある。昨年10月より始まった厚生省のドクターヘリ試行事業では,東海大附属病院と川崎医大附属病院に同省が民間会社から借り入れたヘリコプターを常駐させ,実際に「空の救命活動」を行ないながら,実用化へ向けての可能性を探っている。
本紙では,ドクターヘリの本格的運用を開始した東海大等の取材を通して,見えてきたドクターヘリ導入の意義と課題,そして今後の可能性について報告する。

置き去りにされてきたヘリの活用
欧米の先進国では,救命活動におけるヘリの活用はすでに日常的に行なわれている。しかし,わが国では,十数年前からその必要性が医療関係者などにより指摘されてきたにもかかわらず,ヘリの活用は進んでこなかった。特に,5年前の阪神大震災ではヘリが十分に救命活動に活かされず,批判を浴びている。ヘリの活用が遅れてきた背景には,いわゆる「縦割り行政」の弊害の他,細分化されているために広域的な対応ができない防災システムの弱点を指摘する声もある。
戦後,わが国は防災の行政区画を市町村を基本に細かく区分してきたため,広域的に活動する防災組織を持たなかった。そのため,ヘリを活用した広域的な搬送システムの検討は,島嶼部や離島などを除けば,置き去りにされてきた感がある。
都道府県や一部の市は,いわゆる「消防・防災ヘリ」を保有し,その数は,現在全国に67機を数えるまでになったが,年間の出動回数はわずか760回(98年)に過ぎず,十分に活用されていないのが現状だ。
これらのヘリは防災一般に多目的に用いられ,救急医療に特化している例は少ない。そのため,救急医療用の特別な装備を有さず,突然の対応も難しい。また,必ずしも医師や看護婦が同乗するわけではなく,現場や搬送中の処置にも限界がある。
始動したドクターヘリ事業
 ヘリを活用した救命活動が立ち遅れてきた中,昨年10月より始まったドクターヘリ試行事業は画期的だ。東海大と川崎医大に配置されたドクターヘリは救急医療の専用機であり,昼間は常に出動できるように待機している。そして出動要請があり次第,医師などの医療スタッフとともに出動し,患者を収容,医療機関へと搬送を行なう。防災システムではなく,救急医療システム上に位置づけられ,医療機関に配置されるというところに,その大きな特徴がある。
ヘリを活用した救命活動が立ち遅れてきた中,昨年10月より始まったドクターヘリ試行事業は画期的だ。東海大と川崎医大に配置されたドクターヘリは救急医療の専用機であり,昼間は常に出動できるように待機している。そして出動要請があり次第,医師などの医療スタッフとともに出動し,患者を収容,医療機関へと搬送を行なう。防災システムではなく,救急医療システム上に位置づけられ,医療機関に配置されるというところに,その大きな特徴がある。
ドクターヘリに期待されるもの
「明らかに(ヘリのような)広域的な搬送システムが有効なケースがある」ドクターヘリ事業の責任者を務める猪口貞樹氏(東海大救命救急センター次長:インタビュー)はこう指摘する。
東海大のドクターヘリが主な守備範囲としている神奈川県西部には,医療資源へのアクセスに地域格差がある。人口密度が低いために医療資源が乏しい地域,山岳地帯などの地理的事情の他,慢性的な交通渋滞の存在により搬送に時間のかかる地域,などがある。そのような地域から重症患者をいかに迅速に3次救急医療施設へ搬送するかが大きな課題となっていた。
東海大救命救急センターにおける昨年度の救急症例の中には,重篤な症例でありながら搬送に30分以上を要したものが年間約300例。搬送中に心肺停止したケースも11例あった。ドクターヘリの導入によって搬送時間の短縮や治療成績の向上が期待されている。
今回の試行的事業では,(1)ドクターヘリの導入による急患の予後改善状況の評価,(2)費用対効果の評価,の2点が大きな目的として掲げられているが,少なくとも,このうち(1)については有効性が実証されるだろうと猪口氏はみる。
ヘリ到着と同時に治療開始
「救急医療は『1分1秒の争い』。ヘリの活用により,医師が診るまでの時間が,30分から7分に短縮されれば,治療の成績は大きく向上する」ドクターヘリ・チームのリーダーの1人である中川儀英氏(東海大救命救急センター)は,ヘリ活用のメリットをこう話す。
時速約250キロで飛行するヘリは,神奈川県西部全域へ7分前後で到着する。そして,ヘリ到着と同時に診断・治療を開始できる。到着した医師らは,患者を搬送すると同時に,診断・治療を開始し,ヘリの中から搬送先の医療機関へ指示を出す。ヘリが医療機関へ到着するころには地上のスタッフが必要な検査・治療の準備を整え,待機している。これにより確定診断までの所要時間を格段に短縮されることになる。
「ヘリは乗ってしまえばとにかく早い。だが,それだけに,患者をヘリに乗せるまでの時間の短縮が重要になる」
中川氏はこう強調し,むしろ搬送時間短縮のポイントは,ヘリに患者を乗せるまでのプロセスにあると考えている。
航空法規則改正で活用に弾み
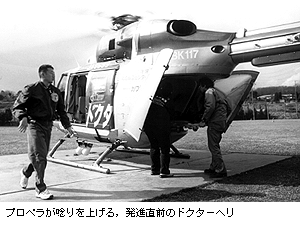 「いかに早く離陸するか」これがまず課題となったが,東海大では訓練を重ね,出動要請を受けてからヘリが離陸するまでの所要時間を,最短で4分,平均的には6分程度まで縮めてきている。離陸までの動作はきわめて迅速だ。
「いかに早く離陸するか」これがまず課題となったが,東海大では訓練を重ね,出動要請を受けてからヘリが離陸するまでの所要時間を,最短で4分,平均的には6分程度まで縮めてきている。離陸までの動作はきわめて迅速だ。
ところが,時間短縮への最大の障害として立ちはだかっていたのは,離発着場の確保だった。民間のドクターヘリは,航空法の規定により,学校の校庭や公園などあらかじめ許可を受けた場所でしか離着陸できず,その許可を得るために時間のロスが生じたり,離着陸場が最終的に確保できず,引き返すケースすらあったのだ。
このような弊害を解消するため,さる2月1日,運輸省はようやく航空法施行規則の改正を行ない,ドクターヘリは着陸スペースなどの条件さえ整えば全国どこにでも離着陸できるようになった。これにより,今後は一層の時間短縮,より機動的な活動が可能になるものと期待されている。
もう1つのポイントは現場救急隊とのランデブー(待ち合わせ)だ。現在のところ,高速道路などの災害発生地点に直接ドクターヘリが降りることはない。多くの場合,災害現場や患者が発生した場所に近い,学校の校庭などの臨時離発着場に降りることになる。したがって,そこまでは現地の救急隊が救急車で患者を搬送している。この救急隊とのランデブーがうまくいかないと,時間のロスが生まれ患者の治療に影響が出かねない。
そのため,東海大でも本事業が開始された昨年10月以降,各地域の救急隊と協力して,頻繁にシミュレーションを行なってきた。中川氏は「慣れの問題なので,経験が蓄積されれば解決する」と救急隊との連携に自信を見せると同時に,「シミュレーションを通してヘリの有効性や使い方を,現場の救急隊の方に知ってもらいたい」とその活用の広がりに期待している。
救命の地域格差なくしたい
ヘリで駆けつけた症例には「軽くてよかったと思うものは非常に少ない」といわれる。その多くは重篤な症例であり,ヘリで搬送しなかったら,予後が変わった例もあったのではないかと考えられている。「同じ重傷度でも救命救急センターへの搬送時間が短い地域なら助かるが,搬送時間が長い地域では助からない。こんな『地域格差』があってよいのだろうか。ドクターヘリの活用によってこの『救命の地域格差』はなくせる。ドクターヘリは21世紀に向けて,いまさらながら,導入されるべき搬送手段だ」中川氏の言葉に力がこもる。
厚生省では,東海大,川崎医大での実績を踏まえ,ドクターヘリの全国展開を進める考えだ。
