MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


臨床の場に心拍変動を取り入れるための入門・解説書
心拍変動の臨床応用生理的意義,病態評価,予後予測 林博史 編集
《書 評》杉下靖郎(筑波記念病院名誉院長)
心拍変動の考え方から臨床まで
 近年,心拍変動の概念およびその実際の検査が,循環器の臨床に取り入れられ,さかんに用いられるようになってきた。しかし,その生理的意義やその応用のあり方について十分に理解されているとは限らないように思われる場合が見られる。本書は,ゆらぎ,生体リズムという広い立場から,そのような意義,応用も含めて,詳しく述べられている。
近年,心拍変動の概念およびその実際の検査が,循環器の臨床に取り入れられ,さかんに用いられるようになってきた。しかし,その生理的意義やその応用のあり方について十分に理解されているとは限らないように思われる場合が見られる。本書は,ゆらぎ,生体リズムという広い立場から,そのような意義,応用も含めて,詳しく述べられている。
内容は,Introduction,心拍変動の意義と測定・解析法,が述べられた後,虚血性心疾患,不整脈,突然死,心不全,高血圧症,心疾患以外の各種疾患,各種薬物,と心拍変動について各章で述べられている。第1章Introductionでは,心拍変動とは何か? から始まって,心拍変動について全体的に解説されている。第2章では,その検査法について詳しく書かれている。第3章以下では,各疾患などについて臨床的な立場から書かれている。各章の中には,細かな項目に分けて述べられているので,実際の臨床の場で十分参考にすることができる。
広く内科疾患についても触れた内容
執筆者は,いずれもわが国のその道のベテランである。全体として,本書のタイトルにあるように,「心拍変動の臨床応用-生理的意義,病態評価,予後予測」について明確に述べられている。どの章も大変わかりやすく書かれており,初心者にとっても興味を持って読み進められるようになっている。図が豊富であり,また各所にSide Memoの囲み記事があってトピックスが簡潔に解説されているのもおもしろい。その一方で文献が大変多く,細かなデータが引用されているのは学問的でよい。また,治療との関連について触れられているのもよい。本書は,循環器疾患のみならず,広く内科疾患について書かれているのもよいことである。以上のように,本書は,心拍変動の考え方,その臨床応用のあり方,生理的意義,病態評価,予後予測,の面から,大変わかりやすく書かれた入門・解説書であるとともに,その文献の豊富な点から専門家にも役立つものである。また,循環器専門家のみならず,内科一般の医師にも薦められる。
B5・頁172 定価(本体6,600円+税) 医学書院


日常診療でかかりつけ医が不安に思う問題点に応える
〈総合診療ブックス〉妊婦・更年期患者が一般外来に来たとき
20の診療ナビゲーション 青木誠,松原茂樹 編集
《書 評》英 裕雄(医療法人社団曙光会理事長)
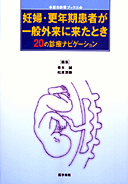 筆者は,東京都内で都市型の在宅医療に従事する立場から,本書の持つ特異な点を紹介したいと思います。
筆者は,東京都内で都市型の在宅医療に従事する立場から,本書の持つ特異な点を紹介したいと思います。
在宅医療では虚弱高齢者や末期癌患者が主な対象となりますので,妊婦や更年期の女性を在宅医療の対象としてみることはあまり多くはありません。さらに恥ずかしい話ですが,多忙のためあまり本を読む時間がとれない日常を送っていますので,編集部からこの本の書評を,との依頼があった時,遠慮させていただくつもりでした。しかし実際にこの本を手に取ってみて,驚くほど楽しく読むことができました。
現在のわが国では在宅医療のみを行なう医師はほとんどおりません。医師の多くはかかりつけ医として外来や入院患者を扱いながら,在宅医療を行なっています。このかかりつけ医の診療業務の中で,特に外来で妊産婦や更年期の女性を見る機会は少なくないはずです。本書は妊婦と更年期患者が一般外来に来たときの対応のポイントを,2部に分けて解説しています。決して大著の体裁をとっていないのですが,患者との具体的な対話法も含めた,診察や検査のしかた,妊産婦や更年期婦人への投薬例などの実例をあげながら,きわめて実際的かつ平易に解説しており,日常診療でかかりつけ医が不安に思う問題点に十分答える良書であります。
外来診療の合い間に
本来,かかりつけ医とは患者の生活全般を踏まえた,全人的医学構築をめざすものであり,個人個人の生理的変化(加齢現象も含めて)に応じた適切な医療提供を行なわなければなりません。したがって,かかりつけ医にとって妊婦や更年期患者の生理を踏まえた診療は,欠かすことができないのです。本書は主訴と症状ごとによる診療アプローチ方法を示しており,外来診療の途中に目を通すこともできるような構成ともなっています。したがってあらかじめすべてを読みこなす必要はなく,外来診療の合間に必要に応じてこの本を手に取ることで,十分実地診療に役立つものと考えます。このような診療の手引き書(ちなみに本書のサブタイトルは,「診療ナビゲーション」です)が,実際の診療の現場で果たす役割は決して小さなものではありません。この本が多くのかかりつけ医の手に取られ,外来の診察室に置かれ,活用されることを期待しています。
A5・頁208 定価(本体3,700円+税) 医学書院


「肝臓を通して患者を診る楽しさ」が伝わる診療マニュアル
これからの肝疾患診療マニュアル柴田実,関山和彦 編集
《書 評》山田春木(社会保険中央病院・内科部長)
見過ごされがちなポイントも
 本書を読むと,「肝臓を通して患者を診ること」の楽しさが伝わってくる。例えば,4つに分かれたパートの最初,「問診と身体所見」の項。舌の所見から,あるいは爪の所見からさまざまな肝臓の病態が見えてくる。あるいは第2のパートの「検査およびIVR」の項。ルーチン検査から思いもかけぬ肝臓の病態が浮かび上がる。通常の内科医の読みでは見過ごされがちなポイントがよくまとめられている。
本書を読むと,「肝臓を通して患者を診ること」の楽しさが伝わってくる。例えば,4つに分かれたパートの最初,「問診と身体所見」の項。舌の所見から,あるいは爪の所見からさまざまな肝臓の病態が見えてくる。あるいは第2のパートの「検査およびIVR」の項。ルーチン検査から思いもかけぬ肝臓の病態が浮かび上がる。通常の内科医の読みでは見過ごされがちなポイントがよくまとめられている。
本書のタイトルを見て,単なる肝臓の病気の診断,治療の要点を列記した小冊子にすぎないと思われた方がいたら,間違いであろう。仮にあなたが内科をローテート中の研修医,あるいは一般内科開業医として,1年間に診療する機会のある肝疾患患者は何人,何%くらいだろう? もし本書がそれら肝疾患患者のためだけの解説書ならば,定価4,500円と白衣ポケットの新書1冊分のスペースは高価なものにつくに違いない。
ふだん臨床の現場で,患者を肝臓という窓を通して診ている中堅の医師たちが著者の主体であるからこそ,このようなひと味違ったマニュアルができたのであろう。合計52個ある「メモ」を読むと,彼らが日常診療の延長で,本書をいかに楽しんで書いたかが伝わってくる。それは,本文のあちらこちらにもエッセンスとして散りばめられている。もしこのようなスタイルの心臓や肺疾患マニュアルが出るならば,わたしは喜んで購入したいと思う。心臓や肺疾患自体は年間10例も診ていないが,これらの臓器を通して内科疾患を見る目を知ることは,自分のプラスとなると考えるからである。
本書の第3のパート,「肝疾患各論」は,現在,基盤のみならず臨床において日進月歩の様変わりを見せているこの分野の要点が,そつなくまとめられている。ただし,難を言えばもう少し実践に役立つ記述がほしい。例えば腹水の管理では,肝硬変患者の尿中Na+濃度が80mEq/lと10mEq/lでは作戦が異なるし,17mEqで尿Na+を割れば摂取食塩grに換算できるといったような。他のパートに比べると,読んでよかったと思わせる面白味に乏しい。
若手臨床研究家の読者を意識
最後のパート「新しい臨床医学のテクノロジー」は,このマニュアルをたいへんユニークな物たらしめている。肝臓を志した若手臨床研究家の読者を意識して書かれた意欲的な筆使いが感じられる。わたしのような中堅が読んでもおもしろい。この項の担当者の1人は,長年「メディカルトリビューン」等に統計学や医学英語の解説を書いており著作も多く,これらの分野と医学とを結びつける領域でも活躍中の第一人者の1人である。ふだんこの著者の文章はやや難解とわたしは感じているが,本書のそれはたいへんわかりやすい。わたしは,気に入った小説を取り出して,気に入った箇所を何回も読む癖があるが,本書は白衣のポケットに入れておいて,何回も取り出したいマニュアルである。
B6変・頁344 定価(本体4,500円+税) 医学書院


内視鏡外科に携わるすべての医療関係者に必携の用語集
内視鏡外科用語集日本内視鏡外科学会用語委員会 編集
《書 評》守屋秀繁(千葉大教授・整形外科学)
ユニークな編集
 最近の内視鏡外科手術の普及ぶりには目を見張るものがある。従来と同じ手術を内視鏡下に行なうというだけでなく,これまでの術式とまったく異なった発想で手術が行なわれることもある。内視鏡手術のためには独特の器具を必要とするが,その使用する器具の開発が急速に進み,開発者が独自の用語をそれぞれに用いたために混乱が生じた。また短い期間に多くの外来語を取り入れたために正確な日本語訳がなく,統一性に欠ける用語が使用されてきた。この問題に日本内視鏡外科学会で早くから取り組みを始め,学会の専門部会である教育委員会で用語を統一すべく用語集を作成することとなった。しかし,内視鏡外科学会にはこれまでの臓器別のそれぞれの専門学会が存在し,その調整が必要であった。そこで特別に用語委員会を発足させ(1996年),各専門科との調整を行ない,その用語集の発刊に至った。
最近の内視鏡外科手術の普及ぶりには目を見張るものがある。従来と同じ手術を内視鏡下に行なうというだけでなく,これまでの術式とまったく異なった発想で手術が行なわれることもある。内視鏡手術のためには独特の器具を必要とするが,その使用する器具の開発が急速に進み,開発者が独自の用語をそれぞれに用いたために混乱が生じた。また短い期間に多くの外来語を取り入れたために正確な日本語訳がなく,統一性に欠ける用語が使用されてきた。この問題に日本内視鏡外科学会で早くから取り組みを始め,学会の専門部会である教育委員会で用語を統一すべく用語集を作成することとなった。しかし,内視鏡外科学会にはこれまでの臓器別のそれぞれの専門学会が存在し,その調整が必要であった。そこで特別に用語委員会を発足させ(1996年),各専門科との調整を行ない,その用語集の発刊に至った。
内視鏡外科手術が次第に市民権を得,今後もさらに発展するためには,詳細かつ正確な意見交換がなされなくてはならない。用語集は内視鏡外科に必要な器具の名称,内視鏡外科特有の手術手技を統合,規定し,診断や治療手技においては臓器別各専門科ごとに整理している。用語は大きく5章に分けて収載されている。内視鏡外科に関する手術手技用語,手術器具用語,手術所見記載に必要な用語,手術診断に関する用語,内視鏡外科手術に必要な解剖用語と大きく章で区切り,それらを個別に表示している。また,これまでの他学会などで作成された用語集とは異なり,左頁に和英対比の用語を記載し,右頁にはポイントとなる用語の意味,意義,類語について詳述してある。ユニークな編集であるが,利用する者にとってはありがたい。
論文執筆のバイブル的存在
今後内視鏡外科をさらに発展させるためには,国内外での学会発表はもちろん,論文執筆に際してこの用語集はバイブル的存在になるものと考えられる。新しい手技が開発されれば,またさらに新しい用語が必要になるであろうし,早い時期での改訂が必要であろう。しかし,現時点でのスタンダードを示したことによって,今後のより効率的な発展を助けるものと考えられる。今日,内視鏡外科を専門として行なっている医師のみならず看護婦(士),研究者など内視鏡外科に携わるすべての医療関係者,器具の開発に関わるメーカーの方々にも統一した用語での意見交換がなされるべきであり,内視鏡外科に携わるすべての関係者に必要な用語集である。また今後,内視鏡外科をめざす若い研修医には必携の用語集とも考えられ,ぜひ机上にそろえたい本である。B6・頁248 定価(本体3,500円+税) 医学書院
