MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


日常的な疾患を心拍変動を通して解釈
心拍変動の臨床応用生理的意義,病態評価,予後予測 林博史 編集
《書 評》熊谷浩一郎(福岡大・内科学)
生体機能におけるリズム,ゆらぎ
 序文にも述べられているが,生体機能には,リズム,ゆらぎが普遍的に存在し,逆に心拍などにまったくリズムあるいはゆらぎがないことこそ,病的意義があることがわかってきた。生体リズムは,自律神経系,内分泌系をはじめ,あらゆる生体機能にみられ,近年心拍変動という簡便な指標を用いて,非観血的に評価されるようになってきた。本書は日常身近な疾患の病態生理を心拍変動を通して解釈しようとする編集者らの強い思いの託された啓蒙と解説の書である。
序文にも述べられているが,生体機能には,リズム,ゆらぎが普遍的に存在し,逆に心拍などにまったくリズムあるいはゆらぎがないことこそ,病的意義があることがわかってきた。生体リズムは,自律神経系,内分泌系をはじめ,あらゆる生体機能にみられ,近年心拍変動という簡便な指標を用いて,非観血的に評価されるようになってきた。本書は日常身近な疾患の病態生理を心拍変動を通して解釈しようとする編集者らの強い思いの託された啓蒙と解説の書である。
心拍変動の臨床的有用性
本書は図表が多く,各所にSide Memoとして要点や,最近のトピックスの説明があるなど,特に構成においては配慮されていて,きわめて理解しやすい。本書は8章からなるが,まず第Ⅰ章のIntroductionは,いわば本書全体の要約でもあり,続く各論に対する総論ともなっている。第Ⅱ章には心拍変動の意義とその測定機器や解析法が解説されている。第Ⅲ章からⅥ章にかけては,各種の循環器疾患として,虚血性心疾患,不整脈,突然死,心不全,高血圧といった身近な疾患すべてを網羅しながら,それぞれについて,心拍変動の意義,病態の評価,予後の予測に対する有用性について述べられている。第Ⅶ章では心疾患以外の内分泌,代謝系,脳神経系,精神科系,呼吸器系などの病態における心拍変動の意義について記述されている。第Ⅷ章では循環器系薬剤を中心に,薬物と心拍変動との関わりが述べられている。今日,心拍変動に関する研究が発展し,循環器病学のみならずあらゆる臨床医学の領域において,その生理学的,病態学的アプローチ,さらには新しい治療戦略への応用に有用であることがわかりつつある。特に心拍変動が急性心筋梗塞後の死亡率に対して信頼性の高い独立した予測因子であることが報告されて以来,その臨床的有用性が高まった。さらに,測定機器の進歩に伴い,心拍変動は,生理的,病理的状態の解明,予後予測に対して,有用な指標になりうると考えられている。
このように,臨床医学における心拍変動に関する研究と臨床応用の現状を概観する本書の意義はきわめて大きい。広く読まれ,また活用されることで,疾患の病態に新しい理解が加わり,診断と治療についての諸家の夢がさらに大きく飛躍していくことを心から願っている。
B5・頁172 定価(本体6,600円+税) 医学書院


EBMによる治療をめざす精神科医に格好の教科書
米国精神医学会治療ガイドライン パニック障害日本精神神経学会 監訳/上島国利 責任訳者
《書 評》竹内龍雄(帝京大市原病院教授・精神神経科学)
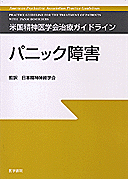 本書は米国精神医学会(APA)のパニック障害治療ガイドラインの,日本精神神経学会による公式翻訳本である。APAではこの種のガイドラインを,すでにいくつかの主要な精神疾患ついて作成し発表しているが,日本精神神経学会でも日本における治療ガイドラインの作成をめざして,その参考とするために,これらを順次翻訳出版の予定であるという。本書は,精神分裂病などともに,その口火を切って出版されたものである。
本書は米国精神医学会(APA)のパニック障害治療ガイドラインの,日本精神神経学会による公式翻訳本である。APAではこの種のガイドラインを,すでにいくつかの主要な精神疾患ついて作成し発表しているが,日本精神神経学会でも日本における治療ガイドラインの作成をめざして,その参考とするために,これらを順次翻訳出版の予定であるという。本書は,精神分裂病などともに,その口火を切って出版されたものである。
最新かつ十分吟味された情報に基づく治療指針
本書の大きな特徴は,診断分類(とそのもととなる疾患概念)が当然のことながらDSM-IVに基づいていることと,MEDLINE等からの文献検索により,evidenceの明らかな情報のみを採用し,それに基づいて記述がなされていることである(残念ながら,わが国の研究者による論文は,引用文献の中に含まれてはいない)。米国での治療を想定したものなので,一部の薬物などにわが国の現状にそぐわないものが含まれていることはやむを得ない。しかし最新の研究成果をふまえ,かつ十分吟味された情報に基づいて作成されたこの治療指針は,わが国でも近い将来,必ず必要とされるであろうEBM(evidence based medicine)による治療をめざす精神科医にとって,格好の教科書であり,その意味でも必読の書の1つといえよう。読者は質の高いreviewを読みながら,実践のヒントを得るように感じるのではないかと思われる。内容は,はじめに全体の要約が示され,次いで診断,自然経過,疫学などについて簡単な紹介があり,治療についての本論に入る。治療では「心理社会的治療」と「薬理学的介入」が主要部分を占め,それぞれ認知行動療法や,SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬),三還系抗うつ薬,ベンゾジアゼピン,MAOI(モノアミン酸化酵素阻害薬)などによる薬物療法について詳しく述べられている。SSRIはわが国でもつい最近発売され,今後何種類か導入が予定されており,そのパニック障害への適応を知る上でよい参考になるであろう。わが国ではベンゾジアゼピンが用いられることが多いが,これについては速効性の利点とともに,依存性や中止しにくさの問題が強調されている。筆者は治療初期に単独あるいは併用で用い,漸次抗うつ薬へ移行させていく方法を用いるが,併用については簡単に触れられているだけで,末尾の「研究の方向」の中に今後の研究課題としてあげられている。
認知行動療法は,専門に行なっているところはわが国ではほとんどないが,部分的に(例えば段階的な現実暴露など)応用することは日常診療においても十分可能であり有効であると思われる。このことについても「研究の方向」の中で,認知行動療法に含まれる複数の技法は,パックとしてすべてが必要かどうかはまだはっきりしないとして,やはり今後の研究課題とされている。EBMはまだわからないところ,議論のあるところは,それはそれとしてはっきり示す点に特徴があり,その点でこの「研究の方向」の章は,われわれの臨床実感とも一致し,興味深い。
そのほか「精神医学的管理」,「治療計画の策定」の項目では,個々の治療法を適用する前に臨床家として心得ておくべき一般的事項について述べられている。治療者患者関係や患者の機能障害への配慮,治療法の選択の問題など,当然のこととは言え重要な内容が盛り込まれており,学ぶべき点が多いと思われる。
翻訳はパニック障害に造詣の深い昭和大学の上島国利教授のもとになされており,正確で安心して読める仕上がりで,大変ありがたい。氏の訳者のことばの結びに,「われわれ臨床医がこれら(研究の発展と治療の進歩)に寄与することができるよう研鑚したいものである」とあるが,これからの時代,わが国の精神科医(精神神経学会員)も,臨床実践を国際的に通用するevidenceにまで高めていく努力が必要とされていることを指摘されたもので,耳の痛い言葉である。
B6・頁130 定価(本体2,400円+税) 医学書院


病因・病態,治療の理解に基づくMRI画像診断
脳脊髄のMRI 山口昂一,宮坂和男 編著《書 評》前原忠行(順大教授・放射線科)
このたび,『脳脊髄のMRI』が上梓された。編著者は,山形大学放射線科の山口昂一教授と北海道大学放射線科の宮坂和男教授で,奇しくもお2人は私が最も尊敬する神経放射線分野での先輩と,同じ神経放射線診断学を志す親友の1人であることから,喜んで書評をお引受けすることとなった。
序文によると,本書の企画案が示されたのは1995年秋であったが,当時,国内の医学書出版は西高東低型で北日本の著者によるものは少なく,これを打破すべく北日本地区の仲間に協力を呼びかけて,受けて立つことにしたとある。約3年を経過して発刊の運びとなったわけであるが,分担執筆者は,山形大学,新潟大学,秋田大学,鳥取大学,東北大学,岩手医科大学,北海道大学関連の17名で,多くは北日本のメンバーで構成されている。
画像診断の書物では画像が多くて文章が少なめのものが好まれる傾向があるが,これに頼ると診断は“絵合わせ”になりやすい欠点があり,本書は病因や病態,さらに治療のあり方までの理解に基づいた画像診断をめざしたと記されているが,まさに当初の目標通りの特色ある教科書に仕上がっている。また,読者の理解や体系的な知識の整理のための利便性を考慮して,“鑑別診断名”“病因分類の要点”“所見のまとめ”などを取りまとめた表(BOX)を多用し,読みやすく構成されているのも大きな特徴である。
中枢神経系の疾患に携わる人に
全体で592頁からなり,具体的な撮像法を解説したChapter 1に続き,「Part 1.脳」(395頁)と「Part 2.脊髄」(155頁)から構成されているが,得てして軽視されがちな脊椎・脊髄領域にも十分な紙面がさかれている。各Partの最初のChapterは正常MRI解剖に割り当てられており,限られたスペースの中でかなりレベルの高い解説が加えられている。また,各Partでは最新の疾患分類に基づき,ほぼすべての疾患が網羅されているが,頻度や重要性によって記載頁数に重みづけがされており,さらに“無症候性の深部白質病変”や“MRIで注目されたその他の病態”などMRI独自の項目が設定されている点も目新しい。記載内容のレベルからは,神経放射線診断を専門とする人々を主たる読者の対象としているものと思われるが,脳神経外科・神経内科・精神科あるいは小児科や耳鼻科などで,日常的に中枢神経系疾患の画像診断に携わる方々に,心からお薦めできる1冊である。
B5・頁592 定価(本体18,000円+税) MEDSI


日常的にEBMを実践するための最適なガイドブック
EBM実践ガイド 福井次矢 編集《書 評》黒川 清(東海大医学部長)
「EBM」とは一体に何か
 「EBM」という言葉がやたらとはやっている。これについての皆さんの反応は「日本には今までエビデンスはなかったのか?」,「われわれだってエビデンスに基づいて診療している」「実際に日本ではエビデンスになるような大規模な臨床試験がなかなかできない」「最終的に1人ひとりの患者さんの判断はわれわれ臨床医がやっていることで,統計的な成績が1人ひとりの患者にあうという判断はEBMと言われても」とかいろいろであろう。「EBM」がなぜはやってきたのか?福井次矢先生編集の『EBM実践ガイド』の序と第1章「EBMの歴史的背景と意義」に説明されている。いわゆる「EBM」というものの背景には以前は「Clinical Epidemiology」という言葉があった。これを日本語に訳すと「臨床疫学」となるが,その「疫学」という言葉の持つ意味から,なかなか広く普及しなかったというのが1つの理由になっていると思われる。
「EBM」という言葉がやたらとはやっている。これについての皆さんの反応は「日本には今までエビデンスはなかったのか?」,「われわれだってエビデンスに基づいて診療している」「実際に日本ではエビデンスになるような大規模な臨床試験がなかなかできない」「最終的に1人ひとりの患者さんの判断はわれわれ臨床医がやっていることで,統計的な成績が1人ひとりの患者にあうという判断はEBMと言われても」とかいろいろであろう。「EBM」がなぜはやってきたのか?福井次矢先生編集の『EBM実践ガイド』の序と第1章「EBMの歴史的背景と意義」に説明されている。いわゆる「EBM」というものの背景には以前は「Clinical Epidemiology」という言葉があった。これを日本語に訳すと「臨床疫学」となるが,その「疫学」という言葉の持つ意味から,なかなか広く普及しなかったというのが1つの理由になっていると思われる。
一方で,学問分野や診療行為を検証する背景は,特にアメリカでの統計学,あるいは数量的に医師の診療のディシジョンメーキングのプロセスを検証することが,1970年台から盛んになってきていた。このようなアプローチはいかにもアメリカ的で,医師の「勘」に基づいた診療がどのような定量的背景にあるのかが検証されてきた。アングロサクソンアメリカンの開かれた,しかも他流試合を盛んにやるという,プロとしての医師を社会に提供するという姿勢が強い歴史的・文化的背景があるところでは,このようにプロとしての医師の力量を高めていこうという動きがある。日本ではこのような動きはほとんどない。むしろ各大学の卒業生を医局に囲ってお互いに他流試合をしない「村社会」を形成した歴史的な背景があり,その診療行為,あるいは治療指針の科学的な検討と検証は,日本ではきわめて地盤が弱いし,またプロとしての医師側にもそのような意識もモチベーションもなかったところに問題があったことは認めざるを得ない。
医師の診療行為に対する普遍性と妥当性を検討
ところで「EBM」が導入されたのはいわゆる「マネージドケア」といわれる医療費の削減という深慮遠謀があると考える人もいる。確かにアメリカではマネージドケアが導入されたために,国費を使った大規模臨床研究(「アウトカム研究」など)などがかなり行なわれ,その成績が臨床行動の指針になってきていることは否定できない。例えばLancetとかNew England Journal of Medicine(NEJM)のように欧米のいわゆる一流のClinical Medicineのジャーナルに,特に1980年代の後半からはこのような研究成績が多く見られ,医療行政,医療政策のみならず,いかに科学的に普遍的な診療行為を行なうかという意識が強く感じられる。このような医療費コスト問題が日本にも押し寄せてきたのは,何も医療政策として医療のコストを削減しようということだけではない。その背景には従来の講座制の閉ざされた医師の診療行為に対して,その普遍性と妥当性を検討しようという社会的ニーズがあったということの他に,いわゆる「EBM」と言われるデータベースにインターネットという新しい媒体を介して瞬時に世界中どこでもアクセスできる技術の進歩があったからである。したがって「私の経験では」とか「われわれの医局の経験では」などという,きわめて限られた経験しかない人たちがいろいろと言いながら,情報を一方的に把握していたような従来の医師と患者の関係は変化せざるを得なくなってきた。つまり医師ばかりでなく,患者を含めたすべての国民がインターネットで「EBM」といわれるデータに簡単にアクセスできるという,情報へのアクセスの隔たりがなくなってきたという技術の進歩があるわけである。
「EBMは実践である」
医学の権威や新しいものが好きな人たちが「EBM」と口をそろえて言っているが,福井先生の書かれている本書はその点できわめて優れている。つまり私がいつも言っているように,「EBM」というのはこのようなデータを使って診療をするということではなく,教える側も教えられる側も,そして診療する側も診療を受ける側も,このようなデータに常にアクセスできるので,どのような理由でその診療,検査をするのかなどを常により大きな場で問われるということである。したがって,「EBM」はそのような概念あるいは議論ではなく,あくまでも実践であり,教える側も教えられる側もこれを実践しなければ「EBM」といくら口で言っても何の役にも立たない。「EBM」を日常的に実行するということが大事なのである。本書の第3章に書いてあるように「EBMの実際」,また「いろいろな文献をいかに読みこなすか」ということも,日本では実際にはそのような文献を科学的に評価する訓練を受けている人がきわめて少ない。最近では,ありがたいことにどのようなデータがどの程度の確実性を持って「EBM」の情報源としての価値があるのかということも評価・検討してあるわけで,その点で本書の表3-2に見られるように「EBMに有用なインターネット上の情報源」というものがアメリカだけでなく,世界的に確立されているということを,日本のわれわれも十分に認識するべきである。したがって情報が瞬時に行き渡る世界の中で,先進国として,そして日本のプロとしての医師集団が日常の診療にどのように「EBM」を実践するかということが,世界からはもちろん,日本国民からも注目されていると言えよう。先日の第25回日本医学会総会でも,これからの医学教育や診療について私も話す機会があった。ハーバード大学Massachusetts General Hospitalの先生とも話をしたが,実際にこのような「EBM」の情報に患者さんや家族が十分にアクセスしていて,この病院に来る患者さんの半数以上がそのようなデータを主治医に提示して相談するという。しかも病院の中にはインターネットを通じた文献検索,病気についての「EBM」へのアクセスの仕方,そのまた解釈などについても,患者さんを助けながら,患者の立場に立ってこれを支援するサービスも確立されているという。日本の大学病院も含めてこのようなことが行なわれたらどうなるだろうかということを仮定すると,本書の内容を日常の実践にいかに使いこなすかということの重要さが理解できるのではないだろうか。福井先生の編集による『EBM実践ガイド』は大変にわかりやすく,「実践EBM」あるいは「EBMは実践である」ということを実際の手順として示しており,待ちに待った本の1つであろうと言える。皆さんがこれを大いに活用して,日常的に「EBM」を口だけでなく,実践するようになってほしいものである。
A5・頁172 定価(本体2,800円+税) 医学書院


更年期女性の健康で自立した生活のために
臨床医のための女性ホルモン補充療法マニュアル閉経前後のCareとcure 第2版 青野敏博 編集
《書 評》相良洋子(都老人医療センター)
クローズアップされる更年期医療
 従来の産婦人科医療は,生殖・内分泌,周産期,腫瘍の3本の柱から成っており,更年期・老年期が問題にされることはほとんどなかったといってよい。しかし寿命の延長と人口の高齢化という避けがたい変化の中で,「更年期を過ぎても健康で自立した生活を送りたい」という女性たちの願いが切実なものとなる一方で,折しも欧米から導入されたホルモン補充療法が更年期以降の健康維持に優れた効果を発揮することが明らかになり,今やこの領域は婦人科医療の4本目の柱として大きくクローズアップされるに至っている。
従来の産婦人科医療は,生殖・内分泌,周産期,腫瘍の3本の柱から成っており,更年期・老年期が問題にされることはほとんどなかったといってよい。しかし寿命の延長と人口の高齢化という避けがたい変化の中で,「更年期を過ぎても健康で自立した生活を送りたい」という女性たちの願いが切実なものとなる一方で,折しも欧米から導入されたホルモン補充療法が更年期以降の健康維持に優れた効果を発揮することが明らかになり,今やこの領域は婦人科医療の4本目の柱として大きくクローズアップされるに至っている。
この度,改訂第2版として刊行された青野敏博教授の編による『臨床医のための女性ホルモン補充療法マニュアル』は,ホルモン補充療法を中心に据えながら,関連する5つの問題――自律神経症状,精神症状と痴呆,泌尿生殖器症状,骨粗鬆症,心血管疾患――についての知識が要領よくまとめられており,きわめて実践的な書といえる。本書が共同執筆によるものでありながら,優れて系統だった構成と内容を持っていることは,青野教授がこの領域に関して深い造詣を持っておられることに加え,臨床の現場にいる医師の指針となるよう確固たる信念をもって本書を編集されたことがうかがわれる。
ホルモン補充療法の実際
本書は,更年期の症状,症状別治療効果,治療上の注意点の3つの部分から構成され,それぞれ,疾患の成り立ちを理解するための基礎的事項,ホルモン補充療法の実際と各疾患に対する効果(と限界),ホルモン補充療法を行なう場合の留意事項が余すところなく記述されている。特に治療上の注意点の部分では,悪性腫瘍をはじめとする合併症を持つ症例に対するホルモン補充療法の適応,ホルモン補充療法を行なう場合に必要なインフォームドコンセントとカウンセリングの技術,ホルモン補充療法と悪性腫瘍に関する最近の理解といった内容が盛り込まれ,患者の立場に立ったきめ細かい対応が実践できるよう配慮されている。さらに本書は,〔私の処方〕〔私のケア〕〔他科からのアドバイス〕といったコラム欄も充実しており,ホルモン補充療法の微妙な匙加減や,境界領域に関する知識が,さりげなく書き添えられている。本書は,内容の充実度に加えて,読みやすさ,わかりやすさ,使いやすさの3拍子を兼ね備えており,すでにホルモン補充療法を実践されている方々にとって,診療内容の確認と応用,さらに更年期医療の将来を展望するために有用な書であることは言うまでもないが,これからホルモン補充療法を取り入れようと考えておられるすべての方々(婦人科医に限らず)にも,ぜひお勧めしたい1冊である。
A5・頁236 定価(本体4,200円+税) 医学書院
