鼎談
21世紀の外科学
新時代の外科医に求められるものとは
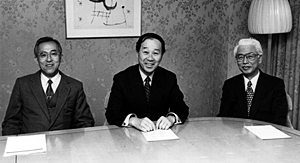 | ||
| 杉町圭蔵
(九州大学医学部長) |
武藤徹一郎
(司会・癌研究会附属病院副院長) |
小川道雄
(熊本大学教授) |
これからの外科学の展開
外科学の「産業革命」
武藤 21世紀まであとわずかとなりました。外科学はすでに著しい進歩を果たしており,21世紀に入ったからといって激変するとは思えませんが,年々の進歩を考えると将来どうなるか非常に興味深いわけです。そこで,21世紀の外科学の目標となるものはどんなものであるか,そのようなところからお話を始めていきたいと思います。杉町 21世紀というのは20世紀からの連続ですから,確かにそこで何かが変わるということはないでしょう。しかし,既に工学関係,例えば,マルチメディアの進歩などが,外科学,あるいは外科手術学の中に応用されつつあり,外科の手術そのものが変わってきています。
21世紀の初頭においても,医用工学の発展,その臨床応用の影響を受け続けることになるでしょう。そして,それは患者さんに優しい手術の方向に向くのではないかと感じています。
小川 既に20世紀の初頭には,ほとんどの手術術式が確立され,施行されています。しかし,それは安全なものではなく,また,1人の巨匠なり名匠なりが行ない,他の者にはできないというものでした。そのような時代から,全身麻酔が安全にできるようになり,輸液,輸血,感染対策などの技術が発達し,また,外科を支える基礎科学が進歩して,いわば外科学の「産業革命」が起こった。皆が急に名人になったわけではないのですが,ある一定の高い治療水準が確保できるようになったのです。
このような新たな革命が起こったのが,20世紀という時代だと思います。そして,大きな産業革命が起こったあとに,モディフィケーションが起こっていく。周辺科学の進歩により,より新しい安全で確実な方法ができる。21世紀とは,そういう時代ではないかと思ってます。
武藤 昔は教授が1人で手術をしていました。徒弟の若い頃にはただのお手伝いだけ。そして,外の病院に長として出る時にいくつか手術をさせてもらい,ほとんどそれだけが執刀した経験でした。患者さん側から考えたら,大変なことが行なわれていたんですね(笑)。
現在では,若いうちから手術のトレーニングができるようなシステムが作られていますが,小川先生がご指摘の「産業革命」ということと合わせて,より多くの人がよい治療を受けられるようになったことが,今世紀における最も大きな変化だと思います。
杉町 今後は,コンピュータ・グラフィックの技術を用い,血管系や各器官,神経など,患者さんの状態を画像などで再現し,診療チームで治療方針を立てたり,術者が手術のシミュレーションを術前に行なうなどの臨床現場の変化が期待されています。このようなシミュレーションの実現は,学生,研修医の教育にも大きな役割を果たすでしょう。
小川 より安全性も確保されますね。
武藤 診断なども昔はいわば「名人」(教授)が診てはじめて診断できて,それ以外の人はできないという時代がずっと続いたわけですが……。
杉町 昔は教授がすべてでした。診断も手術もすべて教授が行ない,若い人にはトレーニングの機会もなかった。そのため,教授の技術と若い人のそれではかなり差があったのですが,これからの時代には,その差がなくなっていくでしょうね。
小川 それが産業革命です。均質な製品ができてくるという……。
武藤 外科学の産業革命。近代の最大の特色は,マスメディアの普及,大量生産社会のもとで,誰でもどこででもいろいろなものが使えるということです。それが外科学の場にも来たということですね。
「縮小手術」時代の外科学
武藤 さて,今後の外科手術の方向性について考えていきたいと思います。日本ではこの20-30年の間に拡大手術があらゆる臓器で行なわれてきました。そして,いま反動期に至ったとでもいいましょうか,拡大手術で得られたデータを基にして今度は縮小手術を指向する方向へ振れています。この傾向はいかがなものでしょうか。手術ではやはり悪性腫瘍を扱うことが多いですから,特に悪性腫瘍の治療についてお話しいただければと思います。杉町 悪性腫瘍はこれからも増加すると思います。高齢者ほど悪性腫瘍の発症率は高まるので,高齢化の進展とともに外科医のニーズは高くなってくるだろうと思います。ただ,その場合,どの悪性腫瘍にも画一的な手術をするというのではなくて,その進行の程度を勘案し,患者さんにもっとも適した手術を提供していかなければならないということです。拡大手術はもちろん必要ですし,その安全性を高めるような研究に取り組んでいかなければなりません。また,拡大手術が必要でない患者さんに拡大手術を施行することのないように,患者さんに多くの選択肢を提供していくことも必要だと思います。
武藤 その判定の際に新しいテクノロジーが使われるわけですね。
杉町 そうです。今日,細部に至るまでかなり正確な診断が可能になってきました。例えば,胃癌や食道癌,大腸癌でも粘膜内癌がわかるようになったり,粘膜層まで進行しているかどうか,粘膜層までいっていたらリンパ転移があるとかないとか,大きさが何ミリだとか,そういうミリ単位で癌の進展がわかるようになってきました。すると,その進展の度合いによって必要な範囲だけ手術をすればよいということになってくるわけです。拡大手術を否定するものではありません。ただ,侵襲の小さい治療で済む患者さんには,それをしてさしあげればよいわけです。
小川 かつて,陣内傳之助先生(故人)の唱えられましたスーパーラジカル(超拡大)という時代――日本が急速な経済成長を遂げた時代でもあります――がありました。その超拡大手術によって癌の進展の程度がわかってきたり,また多くの早期癌が発見されるようになったという成果を基に,今日では急速に縮小手術の方向に振れています。もちろん,症例によっては拡大手術をしなければなりませんが,全体の傾向としては縮小の方向へ行くのは疑いありません。
それから,分子生物学の進歩も見逃せません。最近10数年の間に,分子生物学の成果が外科領域にも応用されるようになりました。
例えば,多段階発癌というような機構が明らかになり,癌予備軍がたくさんあるということがわかってきました。あるいはB型肝炎から起こった肝細胞癌では,肝炎ウイルスのインテグレーションサイトが違うことから,再発ではなく,多中心性発生もかなりあること,一方,C型肝炎では,p53遺伝子の変異の場所が違うことからやはり多中心性発生があるということ,さらに血中のDNAあるいはRNAを見ることによって癌細胞の動きもわかってきた。このように分子生物学の成果によって,癌の進展の範囲がより明確にわかるようになると,あるところでは拡大手術はあきらめて縮小にいき,QOLを維持しようという傾向が強まると思います。
また,拡大手術で大きく生体を破壊すると,生体は損傷を修復しなければならないということで,シグナルが出ます。そのシグナルを癌細胞が受け取って癌細胞自体も増殖することになるわけです。そういうことも考えながら私たちは手術を行なわなければなりません。やはり,侵襲の度合いをできるだけ小さくする方向へ向かっていくことになるでしょう。
新しい時代の外科医
求められる幅広い知識
 武藤 そのような外科学の流れの中で,求められてくる新しい外科医像とはどのようなものになるでしょうか。
武藤 そのような外科学の流れの中で,求められてくる新しい外科医像とはどのようなものになるでしょうか。
杉町 内科・外科の壁が徐々に取り払われて,外科医が内科的なことも考えるようになりました。また,内科医も外科の分野に入ってきている傾向があります。今後もこの傾向は強まるのではないでしょうか。
小川 熊本大学の外科でも,例えば内視鏡,あるいはインターベンショナルラジオロジー,化学療法など,できるだけ内科と外科の壁を取り払おうとしています。これからの外科医は,内科的な知識を十分持ち,「内科の治療をやったらこのような効果が期待できる,それに対して外科的治療であればこの程度の効果が得られるだろう」というようなサジェスチョンができる,あるいは「これは外科へ紹介いただいたけれども,内科的治療のほうがいいのではないか」と内科へお返しできる,そういう内科の知識まで併せ持つ外科医にならなければならないと考えています。そうなると大変すぎて入局員が余計に減るという説もあるのですけれど(笑)。しかし,そのような使命感や意欲を持った,皆から尊敬されるような外科医を育てていかなければならないと思っています。
武藤 患者さんの側に立てば,切られるのはいやなものです。したがって,外科とは最終的な治療であり,なるべく外科的な治療ではない方法でやるのが理想ではあります。これからの外科医は,外から診た状態だけではなくて術後の患者さんのQOLを考えながら,内科的なものも含めてトータルな治療戦略を考えることができなければならないということですね。そのためにはやはり教育が重要になります。
医学教育の問題点
武藤 そこで,教育について話を進めたいと思います。今日の教育の問題点からご指摘ください。杉町 まず,卒前教育について反省しなければならないのは,教官たちが,どちらかというと自分の研究分野,研究成果に偏った講義を行なってきたということです。本来は,医師として患者さんに医療を施す上で必要な知識を教育していただかなくてはなりません。
武藤 まったく同感です。学生に聞いてみますと,基礎を回ってくる時には,どこでも分子生物学を学び,公衆衛生に行っても分子生物学で,それにはもう飽き飽きしているんですね。熊本大学はいかがですか。
小川 私も同感です。今日の医学教育では,卒前に対しても卒後に対しても,ここまで行なう,ここまでは教える,あるいはここまではマスターさせる,というような目標設定が欠けています。
武藤 私自身の反省でもありますが,そういう教育を受けていない人が教育しているんですから,うまくできるはずがないんですね。
イギリスやアメリカの実態を知りますと,これは大学生と幼稚園ぐらい違うなと感じます。例えば最近,シラバスを作成するようになりましたが,実はアメリカのシラバスと日本のシラバスはまったく違うのです。私たちはシラバスの作り方を習ってないですから,これは学生にとって申し訳ない。これからの人はそこからしっかり学んでいってもらいたいものです。
杉町 教授の選考基準も再検討する必要があります。教育への熱意や教育能力が評価されず,ペーパーの数ばかりにウエイトが置かれた教授選考のあり方では,ややもすると学生に対する教育がおろそかになってしまう。研究,教育,臨床にバランスのとれた人材を選ぶための工夫が必要だと思います。
小川 まったくその通りです。そして,教育を充実させるのに,いまの大学は教官数が少なすぎると思います。日常の診療をやり研究もやり,そして教育もやるというとなると,どうしてもどこかがおろそかになります。ですから,教育を担当する専門家を育てなければいけない。どこかに専門家を置くことは,いまの大学の定員制度ではなかなかできませんから,この数年行なわれるようになった臨床教授,あるいは臨床助教授,といった制度を積極的に利用すべきです。臨床教授・臨床助教授は,名誉職の称号であってはなりません。教育に熱心な方を選んで,十分に教えていただけるようなシステムにしなければいけないと思います。
杉町 私も教授会の席では,臨床教授について「日常診療に熱意があり,教育熱心な人を選んでください」とよくお話しています。業績目録は一応出させますが,ペーパーゼロでも臨床教授になれるようにしています。
小川 いま,大きく変えないと,21世紀の医療をやっていける医師が育ちません。臨床教授・臨床助教授の制度をしっかり根付かせなければなりません。
新しい卒後研修システム
武藤 さて,卒後の教育のシステムに話題を移しますが,昔は先輩の話を聞いたり,そのやり方を見て黙って学ぶという,いわゆる徒弟制度そのままでしたが,最近ではそれが随分変わってきました。 杉町 これまでの卒後教育とは,各医局独自に,本当にいろいろなやり方がなされています。研究面に力の入るところ,逆に臨床のほうに力が入るところなど,バラツキがあります。しかし,卒後教育とは,外科医としてのミニマム・リクワイアメントを身につける場であるということも忘れてもらっては困るのです。ある程度の共通した,必要最低限のメニューはあるはずです。厚生省指導型で卒後の必修化云々という話もありますが,ある程度カリキュラムを標準化し,必要最低限の技術を身につけられるようなシステムを構築していく必要があるでしょう。
杉町 これまでの卒後教育とは,各医局独自に,本当にいろいろなやり方がなされています。研究面に力の入るところ,逆に臨床のほうに力が入るところなど,バラツキがあります。しかし,卒後教育とは,外科医としてのミニマム・リクワイアメントを身につける場であるということも忘れてもらっては困るのです。ある程度の共通した,必要最低限のメニューはあるはずです。厚生省指導型で卒後の必修化云々という話もありますが,ある程度カリキュラムを標準化し,必要最低限の技術を身につけられるようなシステムを構築していく必要があるでしょう。
卒後の教育をしっかり行なうことは,国民の利益に直結しますので,腰をすえて取り組まねばなりません。
武藤 2年間の卒後臨床研修の法制化は次期国会で成立の可能性があると言われていますが,これは国民の側から見れば当然のことで,いままで行なわれていなかったのが不思議なぐらいです。また,大学病院としても教育システムをきちっとしていかなければなりません。
小川 ご指摘の通りです。しかし,これは1つの医局や1つの大学でやれることではないと思うのです。米国のACGME(Accreditation Council for Graduate Medical Education:米国医学卒後研修認定委員会)のような研修のプログラムを管理する公的機関を設置し,研修プログラムを公表し,また,プログラムごとにどこまで到達できるかということをはっきりさせ,研修を受ける者が選択をできるようなシステムを作らなくてはなりません。もちろん,その公的機関が常にそれを評価し,結果が公表されるようにしたり,各研修プログラムに対して指導できるようにしなければなりません。
また,初期研修の必修化はもちろん必要ですが,本来これは卒前教育でやっておくべきことではないかと思います。それを前提にして外科のトレーニングを始めないと,例えば,いま検討されつつある日本外科学会の専門医制度を5年のカリキュラムとすれば,最初の2年間はローテーションとなるわけですから,3年間でどれだけのことができるかとなると,かなり限られてしまうと思います。
武藤 外科学会の新しい専門医制度の根幹にある考え方というのは,外科医としてある年限が経った時に必要な経験をきちっと持つべきだということです。試験よりもまずそれが重要であって,それがなければ受験資格がないという形になってくると思います。しかし,これまでの各医局単位での教育システムでは,あるところでは教育陣が不足していて経験を十分に詰めないという弊害も指摘されています。外科医として十分な経験を積んでいただくために,ある程度,流動性を持ったシステムが必要になると思います。これは一方でマーケットのオープン化でもあります。米英のほとんどの病院では,1-2年の短期のコントラクトで医師が動いており,いい人がセレクトされていくわけです。日本はそれがまったく行なわれていない状況です。
杉町 話は少し変わりますが,卒後の大学院をどうするかという問題も大切ですね。
武藤 大学院には,研究する能力のある人,あるいは研究に興味を持つ人がいくべきところです。東大でも,全員大学院に来てくれとは誰も言ってないんですが現状は,「みんなで渡れば……」ということで全員が来るわけです。全国公募しているのですが,よそからまだあまりいらっしゃらないので,進学したい人はほぼ全員進学できるような状態です。
杉町 九大は,学生はアンダーグラジュエートで1学年100名です。ところが大学院は1学年136名なんです。その定員を満たすためにはかなり……。
武藤 東大もそうですが,本当はそんなにたくさん必要ではないのです。その人たちを本当に大学院の学生として教育し研究させるためにはものすごいお金がかかるし,ものすごいエネルギーも必要です。
杉町 私も同感で,こんなにたくさん研究者を養成しなければいけないのだろうかという疑問は持っています。大学院にいっている4年間というのは,臨床の力がどうしてもおろそかになりますから,研究指向型に拍車がかかり,日本の医療がいびつな方向にいかなければいいのだがと危惧してます。
武藤 医療の現場というのは多様な能力が求められます。教育の場ではその認識が薄いような気がしています。
小川 いまお話があったように,皆が大学院に行くから自分も行こうというような制度は論外ですが,臨床医がある期間,問題提起,問題解決というものを学ぶには,大学院がよい場所ではないかと思っています。つまり,臨床で抱いた問題について,なぜだろうかと問い,その解決にどのように取り組んでいくべきかを考えるということが,ある一定の期間あってもいいのではないかという考えです。絶えず考えながら,後輩を教えながら,もちろん臨床の場でも学べるとは思うのですが,指導者にそういうトレーニングを受けた者が少ない現状では,臨床医にとっても一定の研究期間というのは必要だろうと思います。
武藤 将来の指導者として科学の目を持った外科医――サージカル・サイエンティストなどの養成は確かに必要ですね。大学院の存在意義というものをより明確にしていく作業が必要でしょう。
これからの「教授」の役割とは
武藤 教授のあり方も変わってくることが予想されます。これまでのように教授の「背中で育てる」というパターンが特に外科では通用してきたのですが,今後はそうはいかなくなりそうです。いままでは教授が,卒前の教育者として,それから研究者として,そして臨床家として,1人で3役をこなしていたわけですが,実際にはもうそれが不可能であるということで,役割分担の方向に進みだしています。 小川 卒前教育は担当の教官が行なう,あるいは地域内の関連病院で臨床教授や臨床助教授が行なう。技術的なこと,臨床的なことはもっともっと任せていって,これからの外科教授は特に精神的な面,人間的な面の教育に力を発揮しなければなりません。いたわりの心や,克己心,見識,連帯感,そういう心を育てるように常に気を配る必要があります。そして,管理者としての能力も強調されるようになるのではないでしょうか。
小川 卒前教育は担当の教官が行なう,あるいは地域内の関連病院で臨床教授や臨床助教授が行なう。技術的なこと,臨床的なことはもっともっと任せていって,これからの外科教授は特に精神的な面,人間的な面の教育に力を発揮しなければなりません。いたわりの心や,克己心,見識,連帯感,そういう心を育てるように常に気を配る必要があります。そして,管理者としての能力も強調されるようになるのではないでしょうか。
もう1つは,研究についても,ここに宝物があるから行けとか,山賊の大将ですね(笑)。ここに宝物があるけれどこれはもう止めたほうがいいとか,これからはこういう方向に宝物があるからそちらに行けとか示唆を与える。あとはよくやったと拍手をしてあげる。そのように変わっていくのではないでしょうか。
杉町 まったく賛成です。若い人たちが方向性を間違えないように,教育・研究の方向の舵取りを行なうのが,教授のいちばん大事な仕事になってくるかもしれません。
武藤 野球やサッカーのチームの監督に似てますね。いいコーチをつかまえて任せ,全体の舵取りを行なっていくということですね。
生涯学習しつづける外科医に
不可欠な知識の更新
武藤 さて,これからの外科医の修練のあり方ですが,私はやはり仕事の合間を縫って,本を読んで勉強することは忘れてほしくないと思います。最近の人はあまり本を読まない傾向にあるようです。時間がないということも原因の1つではあるでしょうが,コンピュータに張りついてしまい,特に,大きな成書というものを読まない傾向にあるようです。杉町 私は学生に,ぜひ学生時代に1度でもいいからしっかりした成書を買って全部に目を通すように教えています。学生時代に一度読んでおくと,あの教科書のあの辺にこう書いてあったということが頭の中に入っていますから,臨床に出てから問題にぶつかった時に,もう一度それをひもとき,確認することができます。やはり,学生時代にしっかりとした教科書を読んでおくことは大切です。
小川 私は研修医に「必ず何年かおきに学生の教科書を買え」と言っています。「最低でも外科学の教科書,あるいはその周辺の麻酔学などの教科書を買って読め」と言っています。いま,身につけておくべき知識が指数関数的に増加しています。それをいちばん簡単に学べるのは,実は教科書ではないかと思うのです。最新の教科書をいつも置いて読む習慣をつける。それは学生の教科書でいいし,研修医の教科書でもいい。そういう教科書をいつも読んで新しい知識を吸収する,医師は生涯学習をしていこうという意欲を持っていなければなりません。
例えば,古い教科書から同じ肝臓癌のページをコピーして何年かおきに見ますと,ある時代に習ったものは,CTもなければ腫瘍マーカー,α-フェトプロテインもない肝臓癌を勉強している。この段階で止まってはいけないし,知識は必ず更新していかなければなりません。「外科学のすべての領域に目を通すつもりで,学生の教科書を何年かおきに必ず買って読め」と言っております。
このたび,医学書院より『新臨床外科学』が刊行されましたが,このような成書は大切です。折りに触れて見るようにしています。教える側も,知識は更新していかなければなりません。「理由がわからないけれどわしはこう習った」などという教え方は通用しない時代です。何年かおきに改訂されるこういう成書は非常に価値があります。実は私は,『新臨床外科学』ではなく『標準外科学』(医学書院刊)のほうをこれまで何年かおきに買ってきました。いまは執筆させていただけるようにもなりましたが(笑)。
武藤 そうした教科書が充実してきた一方で,最近,小川先生たちがおまとめになられた『外科分子病態学』(医学書院刊)はまったく新しい考え方の本ですね。
小川 この10年間に外科医が行なう研究には分子生物学的手法が大きく取り入れられてくるようになりました。この本は外科医が治療に当たっている病態を,現在の分子生物学の視点で見直し,それをインテグレートすることを目的にしています。教科書の範囲を超えた,外科に関連した基礎科学の進歩の学習はこの本で補っていただければ幸いです。
外科医としての心構え
武藤 最後にお1人一言ずつ,これから外科医になろうとする方,あるいは若い外科医に対してメッセージをいただきたいと思います。小川 やはり,外科医というのは大変です。技術も知識もなければならないし,いたわりの心や克己心,見識を持ち,決して自分勝手に振る舞うのではなく,チーム医療の中でリーダー的な役割が果たせなければならない。
「君たちは士官である」と私は研修医に言うんです。君たちはいまは見習いであるけれども,士官である。士官に任官したら自分よりずっと年上のコメディカルの方たちと一緒に仕事をしていかなければならない。そのためにはやはり強い責任感が必要だと。
それを要求する以上,その道を選んだ者に対してはそれにふさわしい社会的評価が得られるように,私たちはもっともっと動かなければなりません。いまは外科よりも他の科のほうがずっと経済的に評価されているという面もありますが,外科が適正な評価を得られるように変えていくことは,私たちの責務であると思います。
武藤 杉町先生,いかがでしょうか。
杉町 医学というのは患者さんを取り扱う学問ですから,工学や理学,農学とは根本的に異なります。「心」を持つ人間を対象とするところに医学・医療の最大の特徴があるということを私たちは肝に銘じなければなりません。特に外科医というのは,患者さんに大きな侵襲を加える場合があるわけですから,他の科の先生方以上に,患者さんの心を大事にするように心掛けなければいけないだろうと思います。
武藤 私も両先生のご意見に賛成です。時間は少しかかるかもしれませんが,「専門医制度」もいずれできるようになります。将来的にはそういう専門医に対して特別な給与がつくということも検討されることでしょう。また,医師-患者関係などのコミュニケーション能力を重視した教育も始まりつつあります。21世紀は夢が実現する可能性をもつ時代であって,外科の仕事というのは一層やり甲斐のあるものになっていくのではないかと思います。
本日はありがとうございました。


