連載 クリニカル・クラークシップ
-新しい医学教育への挑戦 第4回
学生は診療チームの一員になれるか
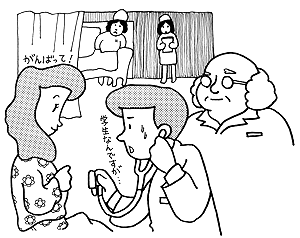
初仕事
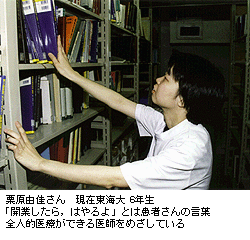 「担当の患者さんのところへ行ってカルテの1号用紙を記入してきなさい」
「担当の患者さんのところへ行ってカルテの1号用紙を記入してきなさい」
栗原由佳さんは,配属された診療チームの医師(シニア)に,突然告げられた。クリニカル・クラークシップ(以下,クラークシップ)が始まった第2日目,これが診療チームの一員としての初仕事だった。
栗原さんが診療チームの一員として担当するということを患者は了解していた。チーフやシニアと呼ばれる診療チームのリーダーが,予め学生が担当することを説明し,同意を得ているからだ。ところが病室に入るや否や,栗原さんは「あがってしまった」。患者だけでなく,そこに家族もいたからだ。患者にどう接するか,そして自分が何をすべきか。そこまでは頭の中でイメージできていた。だが,家族が来ているとは想定外だった。
頭に血が昇っていくのを感じながら,「患者さんを診るのは初めてですが,それでもよければお話を聞かせてください」そう挨拶したのは覚えている。が,後は何を聞いたかよく覚えていない。「あまり長居しては悪い」と思い,診察するには至らず,話だけを聞いて切り上げてしまった。
「失敗でした」と,苦笑いを見せながら栗原さんは話す。彼女は現在,東海大医学部の6年生。クリニカル・クラークシップが導入された初年度の学生だ。4年生の時にクラークシップが始まり,初めて担当したのがこの患者だ。
「でも,この失敗はいい教訓になりました」栗原さんは,この失敗にめげずに「どうしたら患者さんとうまくお話ができるだろう」,「どうしたら,医療チームの一員として信頼してもらえるだろう」と,自分なりに考え工夫をしていったという。「ご家族が来ている時などはお邪魔をしないように避けたり,長居しすぎて迷惑をかけないように気をつけながら」,足繁く患者さんのもとへ通った。「自分が少しでも(患者さんの)役に立ちたいんだということをアピールしたい」その一心からだった。
いつしか,その患者は自分の身の上話や,娘や家族のことについてまで,栗原さんに話すようになっていた。ある時,患者は自分の家族に笑顔を見せながらこう言ってくれた。「この先生はいつも熱心に診てくださるのよ」喜びと感謝の気持ちがこみ上げた。
学生が診察をすることとは……
東海大のクラークシップでは,4年次には各内科および一般外科を各4週間ずつ,5年次には内科・外科以外の診療科(産婦人科,整形外科など)および救急などを各3週間ずつローテーションする。かつて,いわゆるポリクリ(ベッドサイドラーニング)を行なっていたころは,各2週間ずつで全診療科をローテーションしていたが,「2週間では診療チームの一員になれない」ことから,「(クラークシップ導入にあたり)それぞれの診療科への配属期間を大幅に延ばした」(長村義之副学部長)ためだ。また,学生が担当する患者さんは,各配属先ごとに2-4人程度となっている。栗原さんは「1人の患者さんに長くつき合える」ことが,クラークシップの大きなメリットだと考えている。「いきなり学生が患者さんのところへ行って『はい,診せてください』とはとても言えない」いくら医学部のカリキュラムの中に制度的に位置づけられたとしても,医療は人間同士による営みである。「患者さんとの信頼関係がなくては診察をさせてもらうことはできない。医師免許のない学生であればなおさらです」栗原さんは,じっくり患者とつき合えるからこそ,学生でもそれなりの信頼関係を築くことができると考えている。
ある鼠径ヘルニアの男性患者は,「この学生なら(下半身の診察をされても)いいと思った」という。栗原さんがいつもしっかりした挨拶をすることが印象的で,「いい医療をやりたい」というやる気が伝わり,「この学生なら任せられる」と信頼したのだ。患者の手術は脊髄麻酔で行なわれ,手術中にも意識があった。「リーダー格の医師が学生に教えながら丁寧に手術を進めているのがわかった。次代を育てようとする指導者の熱意と,良医をめざす学生の熱意が伝わり,自分もそれに協力したいと思った」患者はこう振り返る。
待っていても与えられない
こまめに患者さんのところへ行くのはクラークシップの基本だ。ある時,別の男性患者は「小水が出にくい」と栗原さんに訴えた。症状から前立腺肥大を疑い,直腸診の必要性を感じた。栗原さんは「私が(直腸診を)してもいいですか」,思いきって訊いてみた。「ぜひ,お願いします」こう答えてくれた。ゼリーや手袋など器具や材料を取りに行くときに,チーフの医師に報告し,診察を見守ってもらいながら,初めて患者に直腸診を行なった。診察・治療を行なう機会は待っていても与えられない。もちろん,ごく基本的なものまでは教員の側がお膳立てをする。だが,ある一定以上の手技を学ぼうとすれば,学生が積極的にそのような環境をつくらなければならない。だから,実は同じ診療科,同じチームに配属されても,学生の取り組み方によって学習量は大きく異なってしまう。受け身の学生はそれなりのものしか学べない。
チームの中で何に貢献できるか
「(患者さんと)信頼関係を築いた上で,患者さんが『この学生を育ててやろう』と思った時に初めて,私たちは一定以上の手技を学ぶことができる」,こう話す栗原さんはクラークシップにあたりながら,「チームの中で学生は何に貢献できるか」を考えたという。その答えの1つは「話相手」だった。学生は診療を一人前に行なうことはできないが,「患者さんにとって一番話しやすいチームスタッフ」にはなれる。診療に忙しく,たくさんの患者を抱える大学病院の医師は,患者個別の課題に必ずしも十分に応えているとはいえない。患者とじっくりつき合える立場にある学生が,「患者さんと医師との橋渡しに力を発揮することはできるのではないか?」そう栗原さんは考えた。そして,「医師と患者さんの狭間で私は学んできたような気がする」と話す。
患者とのつき合い方には,各々の学生の間で大きな違いがある。「患者さんの話相手は,医師の仕事ではない。看護婦さんたちの仕事だ。もっと診療に関わる医師らしいことをすべきだ」ある学生はこう考えている。つまり,クラークシップは「臨床現場で点滴や動脈血採取,尿道カテーテルなどの医師として不可欠な手技を学ぶもの」という割り切った考え方だ。「でも,これは看護婦,これは医師,これは学生,などと単純に分けられる役割ばかりではないだろう。患者さんの立場からすれば,話した内容が療養生活の改善にしっかりつながりさえすれば,話を聞くのは誰でもいいはずだ。大切なのは患者さんの訴えを誰かがしっかり受け止めること」。むしろ,「資格も技術もない私たちが,一定以上の診察手技を行なうことを許してもらうためには,自分も患者さんをよく知り,患者さんにも自分を知ってもらうことが必要だ」栗原さんはこう反論する。
大人の学習
 今年も新学期がやってきた。東海大の新4年生たちにはクラークシップが始まろうとしている。今年は,クラークシップのオリエンテーションに米国ブラウン大学内科クラークシップの責任者であるマーク・フェイガン氏が招かれた。
今年も新学期がやってきた。東海大の新4年生たちにはクラークシップが始まろうとしている。今年は,クラークシップのオリエンテーションに米国ブラウン大学内科クラークシップの責任者であるマーク・フェイガン氏が招かれた。
「大人の学習(Adult Learning)をしよう」フェイガン氏はやや緊張気味の学生たちにこう語りかけた。「自分で考え学ぶことは,受身で教えてもらうことよりも,ずっと効果的だ。みんなで同じことを同じように学習するのはもうやめよう。当たり前のことだけれども,学習の仕方は学習者それぞれで異なるんだ。医学において学習は一生続けなければならない。もう,受身の学習からは訣別しよう。自分自身で学習すべき課題を見出し,積極的に周囲の力を借りて乗り越えていこう」。
この中でフェイガン氏が用いた“Learners are not all the same(学ぶ者は皆決して同一ではない)。”という言葉は,学習というものの本質を突くと同時に,クラークシップにあたる学生たちの現実をも表現している。クラークシップの成功はなによりも,個々の学生が「大人の学習」ができるかどうかにかかっているのだ。
「大人の医師」をめざして,今年もそれぞれの学生がそれぞれの苦闘を始めようとしている。
