特集 第25回日本医学会総会
パネル「21世紀の医学課題」
5つのキーワードから21世紀を展望する
第25回日本医学会総会は今世紀最後の総会となったが,パネル「21世紀の医学課題」(司会=昭和大 黒木登志夫氏,国立感染症センター 竹田美文氏)では,ヒトゲノム解析,がん,脳神経疾患,感染症,老化の5つのキーワードから次世紀の疾病と医学研究の展望が試みられた。2003年までにヒトゲノムの全シークエンス決定が達成される
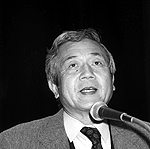 榊佳之氏(東大)は,「HGP(Human Genome Project)によるヒトゲノムの全シークエンス決定は当初の予想より早まり,2003年には達成できる」と報告。その成果として以下の事項を指摘した。
榊佳之氏(東大)は,「HGP(Human Genome Project)によるヒトゲノムの全シークエンス決定は当初の予想より早まり,2003年には達成できる」と報告。その成果として以下の事項を指摘した。
(1)医学・医療への貢献((1)遺伝子による診 断-予防医学,オーダーメードの治療,(2)新しい治療法・治療薬の開発-遺伝子 治療,医薬品開発)
(2)ヒトの生命観への影響((1)ヒトの体の成 り立ちの理解-発生・分化,老化,(2)ヒトの由来に関する理解-人類の進化)
次いで榊氏は,シークエンス決定に続くHGPの主要課題は,(1)10万種と言われるヒト遺伝子の機能の解明,(2)個体間の遺伝子(ゲノム)の多型性と表現型のvariationの相関関係の解析にあり,「それらの研究成果を土台にして,医学面では(1)生活習慣病など多因子疾患の遺伝要因の解明,(2)それに基づく疾患の発症メカニズムの解析が進み,医療面では(1)ゲノムに基づく新薬の開発,(2)個々人のゲノムタイピングに基づく医療法の最適化や予防法の確立が進展すると期待される」と述べた。
21世紀のがんとがん研究
 「がん研究」を展望した黒木登志夫氏は,まず20世紀のがん研究のあゆみをレビューし,“遺伝子の病気”がんの要因となる「がん遺伝子」「がん抑制遺伝子」「転位遺伝子」「DNA修復遺伝子」を平明に解説。特に「がん遺伝子」と「がん抑制遺伝子」について,「前者は(1)一段階変異,(2)活性化,(3)新しい機能の獲得,(4)優性変異であり,後者は(1)二段階変異,(2)不活化,(3)機能の喪失,(4)劣性変異である」と対比した。
「がん研究」を展望した黒木登志夫氏は,まず20世紀のがん研究のあゆみをレビューし,“遺伝子の病気”がんの要因となる「がん遺伝子」「がん抑制遺伝子」「転位遺伝子」「DNA修復遺伝子」を平明に解説。特に「がん遺伝子」と「がん抑制遺伝子」について,「前者は(1)一段階変異,(2)活性化,(3)新しい機能の獲得,(4)優性変異であり,後者は(1)二段階変異,(2)不活化,(3)機能の喪失,(4)劣性変異である」と対比した。
また,両者を分離する過程を“図書館から本を探索する作業”に喩え,「前者は目的の本を,後者はなくなった本を探すことである。後者の場合は“蔵書リスト”が必要で,これが現在進行中のヒトゲノム解析計画に当たる。この研究が進んでいない間は,“遺伝性がん”の家系解析によって原因遺伝子の染色体座位の見当をつけたわけで,これは“部分的なヒトゲノム解析”と言える」と概説。
さらに黒木氏は,「21世紀にがんを克服できるか」と設問し,「米国のがん死亡率・罹患率の減少(1990年代に入って毎年それぞれ0.5%,0.7%減少している),日本における5年生存率の向上から可能である」と強調し,“21世紀のがんとがん研究”を次のようにまとめた。
(1)ヒトゲノム解析の結果,遺伝子レベルの研究は飛躍的に進展する
(2)研究の結果は,診断・治療に反映される(遺伝子診断,分子標的,個人的な感受性,遺伝子治療)
(3)予防や早期発見により,がん死亡率・罹患率の低下が期待できる
(4)がんの治療成績は向上しつつある
(5)進行がん,難治性がんへのブレークスルー的研究が必要である。
21世紀は“脳の世紀”に
 「脳研究」について,中西重忠氏(京大)は,「感覚,認知,記憶・学習,行動,言語,思考,それらを支える意識と情動をきわめて多岐にわたる高次脳機能の研究の最大の特徴は,学際的・総合的な解明が必須であること」と指摘し,そのアプローチを(1)認知行動科学(イメージ法,電気生理学),(2)システム神経科学(神経ネットワーク),(3)神経発生学,(4)神経分子細胞生物学,(5)脳病態学(アルツハイマー病,パーキンソン病,てんかん,精神病,脳血管障害,遺伝病,痴呆など),(6)理論脳科学に分類して概説。中西氏は,「遺伝子工学の発展によって,がん・免疫・遺伝病などのメカニズムが次々に明らかにされた20世紀後半を“遺伝子の世紀"と呼ぶならば,脳研究は,ほとんどすべての学問を統合する必要があり,このことが21世紀は“脳の世紀”と呼ばれる由縁である」と強調した。
「脳研究」について,中西重忠氏(京大)は,「感覚,認知,記憶・学習,行動,言語,思考,それらを支える意識と情動をきわめて多岐にわたる高次脳機能の研究の最大の特徴は,学際的・総合的な解明が必須であること」と指摘し,そのアプローチを(1)認知行動科学(イメージ法,電気生理学),(2)システム神経科学(神経ネットワーク),(3)神経発生学,(4)神経分子細胞生物学,(5)脳病態学(アルツハイマー病,パーキンソン病,てんかん,精神病,脳血管障害,遺伝病,痴呆など),(6)理論脳科学に分類して概説。中西氏は,「遺伝子工学の発展によって,がん・免疫・遺伝病などのメカニズムが次々に明らかにされた20世紀後半を“遺伝子の世紀"と呼ぶならば,脳研究は,ほとんどすべての学問を統合する必要があり,このことが21世紀は“脳の世紀”と呼ばれる由縁である」と強調した。
新興・再興感染症
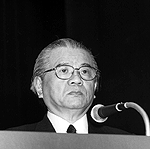 1980年代から,従来知られていなかった新しい感染症(新興感染症)が次々に出現する一方,制御に成功したかと思われていた感染症の再出現(再興感染症)が大きな問題になっている。「感染症」をキーワードとして21世紀を展望した竹田氏によれば,1970年以降だけでも30種類以上の新興感染症が出現し,主なものはレジオネラ症,新型コレラ,病原性大腸菌O157,クリプトスポリジウム症,HIV感染症,Helicobacter pylori感染症,C型肝炎,わが国で発見された成人T細胞白血病や一昨年英国を中心に話題になったウシ海綿状脳症などがある。また,再興感染症としては,(1)細菌感染症(劇症A型レンサ球感染症,ペスト,結核など)(2)ウイルス感染症(狂犬病,デング熱・デング出血熱など),(3)寄生虫・原虫感染症(マラリア,住血吸虫症など)を例示。
1980年代から,従来知られていなかった新しい感染症(新興感染症)が次々に出現する一方,制御に成功したかと思われていた感染症の再出現(再興感染症)が大きな問題になっている。「感染症」をキーワードとして21世紀を展望した竹田氏によれば,1970年以降だけでも30種類以上の新興感染症が出現し,主なものはレジオネラ症,新型コレラ,病原性大腸菌O157,クリプトスポリジウム症,HIV感染症,Helicobacter pylori感染症,C型肝炎,わが国で発見された成人T細胞白血病や一昨年英国を中心に話題になったウシ海綿状脳症などがある。また,再興感染症としては,(1)細菌感染症(劇症A型レンサ球感染症,ペスト,結核など)(2)ウイルス感染症(狂犬病,デング熱・デング出血熱など),(3)寄生虫・原虫感染症(マラリア,住血吸虫症など)を例示。
新興・再興感染症が出現する原因は,世界的な人と食材の動きの活発化,人口の増加,貧困,低栄養,地球の温暖化,難民の増加,人口の高齢化,人間の行動の変化,人口の都市集中化などが考えられるが,竹田氏は遺伝子の変化によって新型菌が出現することが証明された例として,自ら1992年に体験したO139 Bengal型という新型菌コレラを上げ,「問題はこのような遺伝子の変化(欠失・獲得)がなぜ起こるかであるが,現在のところまったく五里霧中である」と指摘。「感染症治療・研究は大きな負債を抱えたまま21世紀を迎えようとしており,さらなる蔓延が予想される。研究者は病態解明にもう1度立ち返るべきである」と強調した。
老化
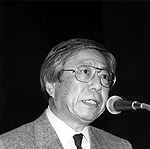 「老化」の問題を報告した折茂肇氏(都老人医療センター)は,老化の機序を「プログラム説」と「エラー説」(遺伝子変異蓄積説,テロメア説,フリーラジカル説)に分けて概説した。特にヒトの寿命を決定する候補遺伝子としては,(1)他の種(線虫など)の寿命に影響する遺伝子に相同性を持つ遺伝子,(2)細胞の維持や修復に関与する遺伝子(早老症候群の原因遺伝子),(3)老年病の発症に関係する遺伝子,を指摘した上で折茂氏は,線虫の長寿命突然変異体としてDAF-2,AGE-1,DAF-2;DAF-12を,短寿命突然変異体としてMEV-1を上げてその機能と機序を解説し,ともに「酸化ストレス抵抗性が重要」と指摘。
「老化」の問題を報告した折茂肇氏(都老人医療センター)は,老化の機序を「プログラム説」と「エラー説」(遺伝子変異蓄積説,テロメア説,フリーラジカル説)に分けて概説した。特にヒトの寿命を決定する候補遺伝子としては,(1)他の種(線虫など)の寿命に影響する遺伝子に相同性を持つ遺伝子,(2)細胞の維持や修復に関与する遺伝子(早老症候群の原因遺伝子),(3)老年病の発症に関係する遺伝子,を指摘した上で折茂氏は,線虫の長寿命突然変異体としてDAF-2,AGE-1,DAF-2;DAF-12を,短寿命突然変異体としてMEV-1を上げてその機能と機序を解説し,ともに「酸化ストレス抵抗性が重要」と指摘。
早老症候群の遺伝子異常については,「(1)Werner症候群とCockayne症候群は,その欠損遺伝子がともにDNA/RNAヘリカーゼファミリーに所属する,(2)DNA/RNAヘリカーゼは2本鎖のDNAまたはRNAを1本鎖にしてDNAの複製,修復,組み替え,転写,翻訳に関わる酵素である,(3)DNAの複製,修復エラーは染色体の不安定性→悪性腫瘍の発生となり,転写,翻訳エラーは異常な機能の蛋白生成→老化という機序を示す」とまとめた。
また折茂氏は,1997年にわが国の研究者が報告した老化抑制遺伝子「Klotho(生命の糸を紡ぐギリシャ神話の運命の女神)遺伝子」や,老化におけるアポトーシスの役割の重要性をも指摘した。
