連載
「WHOがん疼痛救済プログラム」とともに歩み続けて
武田文和
(埼玉県県民健康センター常務理事・埼玉医科大学客員教授・前埼玉県立がんセンター総長)
〔第5回〕がん・痛み・モルヒネ(5)
できあがったガイドライン
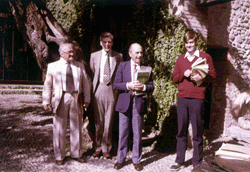 |
| WHO協議会が終了し,ホッとした表情で会場から出てきた出席者。左からBonica教授(米),Twycross博士(英),Swerdlow教授(英),Rane博士(スウェーデン) |
昼寝をあきらめての勉強時間
昼休みが2時間もあるなら,午後に必ずやってくる時差ボケ睡魔の予防に食事を急いでとって,残りの時間を昼寝にあてようと考えたが,ホテルに1つしかないレストランには時間をかけてサービスするコースメニューしかなく,食べ終わると2時間がすぎてしまうのであった。しかし,この2時間が私にとり絶好の勉強時間となった。私の隣の席はFoley博士,前の席はTwycross博士という具合であった。日本で読んだ文献からは汲み取りにくかった微妙なニュアンスの部分が直接専門家に質問でき,理解を深めるのに十二分に活用できた。
隣り近所にもレストランがない。ホテル滞在客は協議会出席者だけという状況である。同じレストランで3食とも全員が一緒にとり,夕食後は夜半まで団らんするのだが,話題は痛みのことばかり。協議会は合宿同様で,「缶詰になる」との予測ははずれなかったが,1年も2年も海外留学した以上に貴重な勉強の日々となった。
辞書の要らないガイドラインを
Working papers(討論資料)による討議が終わった午後の後半から,4つのサブグループに分かれ,それぞれ課題を与えられてのガイドライン第1稿の作成が始まった。時差ボケ睡魔など気にしている時間はなくなってしまった。私はFoley博士やRane博士らとともに,「strong narcotics(strong opioidsと同意語として当時は使っていた)」の章の起案グループに入った。日本語の文章書きも大変な私なのに,英語の原稿を英語を母国語としているその分野の第一級の専門家とともに書くとは思わなかった。
「さあ大変。だけど,なるようにしかならない」と開き直った。
グループでは,主としてFoley女史が口述役,Raneが筆記役,私は意見を言う役回りだが,非英語国の人々にはわかりにくい表現が出てくる。非英語国の医師や看護婦が英語がわかるとしても,辞書を必要とする回数が多いと読んでくれないと私が言ったところ,Foley女史が私の意見に賛成し,それではと,私に「原稿のチェックを任せる」こととなった。それがよいとBonica教授も大賛成であったが,かえって大変な役目を引き受けることになった。私の乏しい英語力とボキャブラリの報告書となってしまうとの心配が募った。
ともあれ,こうして草案の第1稿がとにかく3日目の夕方には完成したが,清書ができていない。他の項目の討議も終了していない。そこで協議会は翌日の正午までの会期延長となった。
日本での適応に不安が
翌朝,Ventafridda教授がガイドライン案をbriefingした。その時非オピオイド(代表薬;アスピリン),弱オピオイド(代表薬;コデイン),強オピオイド(代表薬;モルヒネ),鎮痛補助薬と黒板に書いた。それを線でつなぐと3段の階段となった。これが後に「WHO three-step analgesic ladder(WHO3段階除痛ラダー)」と呼ばれる有名な図(第4回,2328号参照)に発展(WHO編:がんの痛みからの解放,第2版,金原出版,1996)した。また鎮痛薬の使用に関するキーコンセプトとしてby the clock(時刻を決めて規則正しく)とby the ladder(除痛ラダーに添って効力の順に)の2つが採用された。このキーコンセプトは10年後には5つとなるのである。
ガイドラインの試行はいろいろな国に要請することになったが,病院施設に所属している協議会出席者は必ず試行に参加しようとなった。アメリカから参加した人々は,ことのほか日本での試行に熱心で,武田が埼玉で行なうことで了解してくれた。各自が帰国したらWHOプログラムについて自国内での広報に努め,マスコミにも伝えること,などの要望があったが,私は,「マスコミを動かす力はない。WHO自身が大声で広報すべきだ」と主張した。私としては納得して作成したガイドラインであるが,できあがってみれば,日本の医師のほとんどが使用していないアスピリン,コデイン,モルヒネが主役を果たす治療法である。帰国してからの広報に振り向いてもらえるだろうか,叱られることまであり得るのではないか,世界が先に変わってきていることをどうわかってもらおうかなどと考えてしまい,不安な気持ちに陥ったのである。
正午に散会,昼食をとりながらの別れの挨拶となり,とにかく山を下りてミラノ市内まで戻り1泊した。翌朝,ホテルの玄関でオランダ国立がんセンターからの出席者van Dam博士に会った。彼は,来年2月に日本に行くのだが,いろいろと世話をしてほしいと言う。「オーケー,連絡してくれ」と伝えて別れた。そのvan Dam博士の肩書きは「WHO consultant on quality of life」であった。当時の日本ではあまり聞かない言葉の肩書きであった。
(この項つづく)
