看護介入と科学/駅伝シンポ II

2日目に行なわれた駅伝シンポジウム IIでは,癌患者への看護介入など,さまざまな介入方法から,共通するケアがあるかを論議することを目的として4人の演者が登壇し,それぞれの考えを提示した(下表参照)。
乳癌患者へのケア介入
 同シンポでは,まず最初に,パトリシア・ラーソン氏(兵庫県立看護大)が登壇。「アメリカでは,30-50歳を中心に毎年2万人が早期の乳癌に罹患している。日本でも同様な傾向がみられるようになったが,幸いにも多剤併用の化学療法(ACTX)などにより再発は少なくなってきた」と前置きし,下表(1)を口演。
同シンポでは,まず最初に,パトリシア・ラーソン氏(兵庫県立看護大)が登壇。「アメリカでは,30-50歳を中心に毎年2万人が早期の乳癌に罹患している。日本でも同様な傾向がみられるようになったが,幸いにも多剤併用の化学療法(ACTX)などにより再発は少なくなってきた」と前置きし,下表(1)を口演。
ラーソン氏は,「ACTXは,副作用として卵巣機能を著しく低下させることから,閉経前の女性では性生活の満足度や人間関係が損なわれるというデータが出ている」と述べ,生物行動学的変化に視点を置いた乳癌患者のACTX治療の影響を報告。閉経前・後の女性のFSH(卵胞刺激ホルモン)量測定比較などの結果については,現在まだ集計中のため全部が解明されたわけではないとしながら,「治療中の患者は閉経後の女性が示す数値と合致し,同年齢の女性よりも上回った」と発表した。
またACTX治療に関して,「閉経前の女性でも,のぼせ,寝汗など更年期障害と同様の症状がみられることから,より若い患者へは,早い時期からの継続的なサポートケアが重要になる」と指摘した。
術後早期離床の看護支援効果
数間恵子氏(東医歯大)は,「Nuring Intervention」を「看護介入」と訳すには違和感があるとのことから「看護支援」という表現を用いて,下表(2)を口演。その上で,「看護支援は,科学的な問題解決過程の一部として評価する必要がある」として,看護支援の効果を検証する指標として用いることができ,文化を超えて使える「同心円モデル」を紹介。理論的根拠については,上腕部計測,大腿部測定などの実例を提示し証明した。
一方で,「術後早期離床の効果については,これまで肺合併症の予防,腸管麻痺の回復・促進,イレウスの予防,下肢筋力低下の防止などが指摘されてきたが,下肢筋力の低下は文献では数量的に検討されてはいなかった」と述べ,同心円モデルを用いての重回帰分析などから,「大腿筋の減少は,早期離床に向けた看護支援によって抑えられることが明らかとなった」と述べた。
さらに,胃癌術後患者の回復と栄養状態の影響について,術後の看護支援の影響は摂食行動に現れることを数量的に明らかにするとともに,「同心円モデルは,運動学および栄養に関する科学理論に基づいており,このモデルから得られたデータは信頼性があり,データを得る看護のツールとしても重要である」と結論づけた。
ホリスティック介入法の有効性
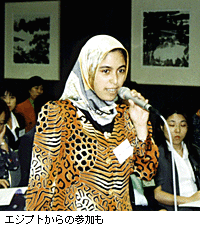 荒川唱子氏(福島医大)は,「リラクゼーション療法,イメージ療法,自立訓練,セラピューティックタッチ,ユーモア,音楽などのホリスティックな介入法の有効性は,これまでの看護実践の中で示されてきた」と解説し,下表(3)を口演。
荒川唱子氏(福島医大)は,「リラクゼーション療法,イメージ療法,自立訓練,セラピューティックタッチ,ユーモア,音楽などのホリスティックな介入法の有効性は,これまでの看護実践の中で示されてきた」と解説し,下表(3)を口演。
また,「ホリスティックな介入法が,科学的な研究を通じて証明されているのか,その効果は文化を超えて普遍的なものとなり得るのか」の2つの視点に注目し,日米の文献からの比較を行なった結果も発表した。それによると,「アメリカではリラクゼーション療法が心理学的,生理学的指標において,臨床症状などで有効であったことが認められた。また,日本のリラクゼーション療法の研究論文からも,アメリカ同様,有効性が確認できた」と述べ,さらに日米差においては,アメリカでは多種多様な調査対象者が母集団であり,施設も多様なことを指摘。一方,日本における研究では対象者に幅がないことや化学療法患者の例はなかったことを報告した。
また,「日本は比較的入院期間が長いためにリラクゼーション療法を習得するには十分な時間があり,日常ケアの中にリラクゼーション療法を取り入れることが可能。科学的な知識に基づいたリラクゼーション療法は,看護専門職が自立的に機能を果たせる」と示唆した。
看護介入としての「タッチ」
「世界を通じて,音楽療法,マッサージ,イメージ療法,アロマセラピー,タッチング,行動療法などの総合的な治療(Complementary Therapy)への関心が高まっているが,これらは看護の分野においては古くから行なわれてきているもので,看護に根ざしているものと喧伝してもいいのではないか」と述べたマリア・シュナイダー氏(ミネソタ大)は,下表(4)を口演。看護介入の分類のプロジェクトとして,International Council of Nursing(ICN)project, National Intervention Classification(NIC)project,Ohama projectなどの看護介入分類システムを紹介。「看護介入を定義,分類することで,ケアの報酬の対象となる看護婦の行動を見極めようとする意味合いも持つ」ことにも触れた。その上でシュナイダー氏は,看護介入としての「タッチ」に言及し,(1)意図したタッチ,(2)マッサージ,(3)セラピューティックタッチに分類しての科学的基盤に基づいた考察を行なった。
シュナイダー氏は,「これらの療法は,身体的,物理的な側面だけでなく,心理的,精神的な影響もみられる。知識体系の確立は,看護の信頼性を高めることにつながるが,現在の知識体系はバラバラであり,一貫した測定尺度がみられないという欠点がある。これからは積み重ね研究が必要であり,介入の有効性を立証するには,さらなる研究が必要」と述べた。
| 演者(所属)/発表演題名 | |
| (1) | Patricia Larson氏(兵庫県立看護大)
Symptoms and Problems of Premenopausal Women with Breast Cancer Receiving Chemotherapy |
| (2) | 数間恵子氏(東医歯大)
A Concentric Circle Model as Indicator of Outcome Followed by Intervention |
| (3) | 荒川唱子氏(福島医大)
Exploring the Scientific Bases of Holistic Nursing Intervention |
| (4) | JMariah Snyder氏(米・ミネソタ大)
Nursing Intervention and Science : Types of Touch |
