看護ケアシステムと文化/駅伝シンポ I
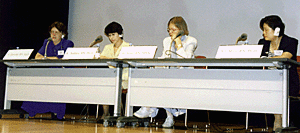
駅伝シンポジウム I「ナーシングケアシステムと文化」では,「看護職は在宅ケアを促進し,その実践と研究から得られた蓄積を在宅ケアの企画立案と提供に発揮しうる特異な立場にある」(司会者)との認識から,在宅看護の組織化とサービス提供のあり方について,それぞれ在宅看護の第一線で活躍する4つの国のシンポジストが,それぞれの現状と課題,今後の展望などを報告した。
拡大する在宅看護
Y.I.Shyu氏によれば,台湾の高齢者人口は1951年の2.5%から1996年には7.8%まで上昇し,2030年には20%に達すると推計されている。台湾では1971年にホームケアプログラムがキリスト教病院によって始められ,1987年に独立した在宅看護提供機関(エージェンシー:看護婦のみにより構成される。日本の訪問看護ステーションに相当)が台北看護協会により設立された。1995年には国民健康保険制度からの償還を受けるようになり,在宅看護サービスが急速に広まりつつあるという。Shyu氏は在宅ケアにおける看護職の課題として,(1)在宅ケアへの国民健康保険による償還枠を広げるための働きかけ,(2)標準的な患者アセスメント,看護計画,看護記録の整備し,質の管理と償還払いのためのデータベース構築,(3)質の評価とモニタリングシステムの確立,(4)包括的なサービス提供のため他職種との連携,(5)不足している在宅看護婦数の解決,(6)訪問看護婦の再教育,などを指摘し,将来的には,(1)地方での在宅ケアの普及(現在,50%のエージェンシーが台北に集中),(2)国民健康保険の改革による在宅ケアへのシフトの促進,急性期ケアからの引き受けネットワークの整備,(3)在宅看護の発展のための共同の在宅看護センターの創設,などの必要性を示し,今後の展開に意欲を見せた。
系統だった看護ケアの提供
H.Soini氏は,北海道奈井江町との交流で知られるフィンランドのハウスヤルビ町を含むRiihimaki地区の婦長である。奈井江町は1995年よりハウスヤルビ町と姉妹都市関係にあり,福祉・文化の交流事業を続け,特に高齢者福祉の分野では福祉先進国フィンランドに学び,進んだ町づくりで知られている。Soini氏自身もすでに2度,奈井江町を訪問し,福祉施設の視察,関係者との意見交換を行なったという。Soini氏によれば,フィンランドでは現在,65歳以上の高齢者は全人口の14.5%,75歳以上では5.9%を占め,今後は,85歳以上の後期高齢者が急増することが見込まれているという。高齢者の多くは,障害や疾病を持っても在宅での生活を希望しており,「患者の健康状態を評価した上で,(本人の力も借りつつ)生活上のすべての問題に対処(トータルケア)していかなければならない」と指摘した。
在宅ケアにおいては「高齢者が自ら意思決定し,健康増進できるようにすること」,「正確に高齢者の身体的機能について評価すること」の重要性に触れ,医師や看護婦の指示を受け,患者が自ら行なう「ホームホスピタル」という考え方を提示した。また,「在宅における個々の看護介入の成果評価」「健康およびQOL等の評価」については,今後十分な研究を行ない,系統だった看護ケア提供の必要性を強調した。
葛藤生む新旧の価値観
麻原きよみ氏は日本の現状について口演。「日本社会は伝統的に家族介護という価値観を維持してきた。『家』自体が複数の世代により構成され,高齢者が嫁と暮らす場合が多く,親と子どもの同居率は先進国の中ではもっとも高いと思われる。家族介護への責任から他人を家に入れたがらない風土も存在する」と述べ,在宅ケアをめぐる文化的要因に着目。介護者27名へのインタビューの結果から,(インタビューの対象である)村の人たちは「介護することが(家族の)能力の証」であり,「親の面倒をみる嫁は偉い」という価値観を強く持っていたとの結果を示す一方,家族が介護するより他に手だてがなかったこと,また,家族介護の伝統的価値観に政府が甘え,公的介護の政策が遅れてきたことも厳しく指摘。「価値観や国民性」の名の下に家族介護への依存を放置することは許されるべきではないとの立場を示した。また,「家族の介護者の多くには個人主義的な価値観と,伝統的な家族主義的価値観との間の葛藤もみられ,それらの意識は年齢や地域に規定される要素が多い」と指摘した。麻原氏は世界各国から集った看護婦たちに,昨年成立した介護保険制度を紹介し,「新しい仕組みの中では,伝統的価値観も変わっていくかもしれない。日本は大きな転換点にあり,その中で『すべての高齢者と家族のニーズに応えるシステムの開発』こそ,私たちの挑戦だ」と結んだ。
援助は依存を生むか
米国からはJoyce V. Zerwekh氏が口演。米国文化の背後に潜む10の誤解を指摘した。特にその中で興味深いことは,「(病んでいる,あるいは貧しい)人を助けることはできない」,「(彼らは)自ら苦しみを作り出しているのであり,自業自得だ」という根強い考え方が存在することである。同時に自助努力を重んじ,「援助は依存を生む」という見方が支配的で,在宅ケア推進の弊害になっているという。Zerwekh氏はこれに対して,「看護の介入の成果評価を示す」,「援助を行なうことのセルフケアへの効果を示す」等によって,反論していくことの必要性を示した。また,「在宅ケアに看護婦はいらない」,「訪問看護はコストが高すぎる」など,在宅ケアにおける看護の役割を否定的に捉える風潮もあり,「看護婦の実践的,専門的知識を示すと同時に,費用対効果を考えた質の高い看護を提供していかなければならない」と今後の方向性を示した。
本シンポジウムでは,高齢化の進展と効率的資源配分への圧力という各国共通の時代背景が示される一方,別個の文化と歴史を持ち,取り組み方や今後の可能性にも差異が示されるなど興味深いものとなった。
| 演者(所属)/発表演題名 | |
| (1) | Yea I. Shyu氏(台湾・Chang Gung大)
Home Nursing Services in Taiwan |
| (2) | Helena Soini氏(フィンランド・ツルク大)
Home Care System in Finland, Espesially in Riihimaki District |
| (3) | 麻原きよみ氏(長野看護大)
Home Care and Culture of Famiry Caregiving in Japan |
| (4) | Joyce V. Zerwekh氏(米・フロリダアトランティック大)
Challenges Facing Nurses Providing Home Care in the US |
