〈短期集中連載〉
激変するアメリカ合衆国医療事情(最終回)
日野原重明 (聖路加看護大学名誉学長・聖路加国際病院名誉院長)
米国におけるレジデント教育方針の大転換
W. オスラー教授に始まる世界に冠たる卒後教育
米国のインターン,レジデント研修制度は,100年前にジョンズ・ホプキンズ大学病院においてW. オスラー内科教授により始められたものである。すでに第1次世界大戦後には,米国の臨床医学教育はドイツより優れたものと評価され,第2次世界大戦後には米国はドイツや日本とのレベルを大きく引き離したのは,アメリカで開発されたこのレジデント・システムのためであると考えられている。以前は医学校卒後1年で病棟でトレーニングする研修生をインターンと呼んだが,最近はインターンと呼ぶ大学は少なく,多くは1年目のレジデントと呼び,それ以降は2年目あるいは3年目のレジデントと呼んでいる。アメリカで3年間の内科レジデントを経験した者の臨床能力は,日本の大学の内科医局に10年も在籍した者に勝っているということは誰もが疑いようもない事実である。アメリカの医学校の教授は,アメリカの卒後教育が,世界に冠たるものであることを誇っている。
過剰な医師数と財政問題
ところで,今回,私は学部学生の医学教育ならびに医師の卒後医学教育の責任者に会って,その様子が大きく変貌した説明を詳しくうかがうことができた。これまで米国は世界中からそれぞれの国の医学校出身者を数多く迎えて,米国式の卒後研修を政府の補助金を用いて提供してきた。ところが,米国では医師がすでに過剰になり,医療費がGDP(国内総生産)の13.6%(国民1人当たり3094ドル,1992年)と驚くほどの高率を示していることから,近年になり大きな政策転換を迫られてきた。これは医学教育にも波及している。
すなわち,米国の医学校に入学する学生数を制限し,教育病院のレジデント採用をも大きくカットするなどし,米国の医学校の卒業生へのレジデント研修費を絞るという方策がとられ始めてきたのである。つまり,卒後研修制度は米国に籍を置く,米国の国民のために働く医師の養成を目的とし,他国の医師の教育は抑制しようというわけである。したがって今後日本の医学校出身者が米国でレジデント教育を受けるのは至難のわざとなることは間違いない。医学研究者として米国留学をすることは可能であっても,臨床医学能力を高めるために有給でレジデントとして採用される機会はなくなる見通しである。
レジデントの教育に関してもサラリーと福利厚生費とは別に,政府から医学教育のためにメディケアから教育病院にレジデント1人あたり,8万ドルが支払われることになっていた。これまでは,NIHからは研究費,メディケアからは教育費が間接的に支払われていたために,アメリカの教育病院のプログラム拡張がなされてきたのであるが,マネージドケアは研究や教育への間接的コストをまったく払わないので,これが拡大するにつれて,診療報酬の切り下げ,価格破壊が進行し,米国の研究的なメディカル・センターは非常に苦しくなってきた。先に述べたような教育病院の統合で経営規模を大きくすることにより,コストを削減し,患者を取り込むといった生き残り作戦が熾烈になっているわけである。
R.ウッド教授は連邦議会において,将来の卒後教育に関する問題点について次のように演説したと報じられている。
「米国においては医師の供給過剰と医師の国内分布の偏在とによって国家の財政および医療サービスに大きな問題が生じた。医師を活用するために,第2次世界大戦後,今日までの60年間に連邦政府が卒後教育に投じてきた金額は,今や米国の医療が直面する経済的困難の中で早急に見直されなければならない。米国がこれまで維持してきた高い水準の医療を国民に提供するには十分な経済的サポートが必要とされるのは当然であるが,もっと効率的な医師の卒後研修がなされなければならない。経済的サポートとはレジデントの生活給(手当て)と上級医がレジデントを指導するための教育費,それに関連した事務処理の費用をまかなう財源である。そのためにはメディケア(高齢者のための公的医療保険)が病院へ支払う保険料の一部を卒後教育の費用に当てるべきである」
ここでついでに報告するが,私がボストン滞在中に聞いたことは,ペンシルベニア州の大学病院に検察庁の取り調べが入って病院は大変だとのこと。それは,公的保険の患者が入院した時に,指導医(Attending physician)が診察したり,手術を行なうことに対して公金が支払われることになっているが,実際にはレジデントに任せきりになっていたり,サインはされていても上級医が診察に参与した証拠がないことなどが問題になっていて,その結果,病院が取得した公金を返済する額が何百万ドルにも上るのだという。
政府の資金を外国人レジデントに払うことにも問題がある
米国では過去20年以上にわたり,米国の125の医学校の卒業生は年間約1万7000人(日本は約7000人)にも上るが,それに対してレジデントとしての受け入れのポジションは,毎年2万5000人以上の口がある。米国の医学校卒業生はこの2万5000人分の70%を占め,残りの8000人分のレジデントの職場を米国以外の医学校を出たものが占めるという構図になっている。この数は1980年代初期の米国の55の医学校の全卒業生の総数に匹敵するという。つまり米国は55の医学校を輸出していることに相当する。米国のレジデント教育システムがこのように膨れ上がったことは大問題で,これに政府としてメスを入れなくてはならず,外国人レジデントの数を20年前の状態にまで戻すというのである。
そのためには病院勤務のレジデントの数をカットすることが必要になってくる。次に,外国の医学校を出たものをアメリカ国内に受け入れる範囲を縮小すべきであることが叫ばれている。外国人のレジデントを採用した場合にも,その研修が終われば必ず母国に帰国させ,学んだことは母国に持ち帰って臨床医の能力水準を高めるような人材になってもらうことが望まれている。
つまり,レジデント育成のための政府の資金を外国人のために使うことはここで中止するほかないと主張するのである。政府が国民の税金として得た資金は,公費として国内の医療を健全にさせる目的に限って使われることが妥当だと考えられるに至ったのである。
外国人レジデント流入を法的に制限
米国では今後,国内で働く医師の養成に重点を置き,それに公費を使うべきであることが政府と民間との共通意思とされるに至った。ウッド教授の報告書にあるような鎖国的意見が議会に出された一方,アメリカ医学校協会(Association of American Medical College,本部はワシントンDCにある)のジョーダン J. コーヘン会長は,「外国の医学校を卒業した外国籍の医師が米国に研修に来ることを全面的に拒否するといった考えは行きすぎであり,米国の経済,その他の事情が許す限りは,外国からの医師にも門戸を開くべきである」と議会で演説している。コーヘン博士はウッド教授の議会での演説に対して反論をしている。難しいのは,その限度はどこかということであろう。
最近,米国では医師の従事する地域的分布の調査が行なわれた。その結果報告によれば,米国内の医療に恵まれない地域で生涯にわたり働く外国人医師の数は,そこで働く米国の医学校を卒業した医師の数とあまり変わらないか,あるいは米国生まれの方が僻地医療に従事するものがむしろ多いとのことである。
今後,日本から卒後教育を目的に留学したいと望んでも,就職口はひどく制限されていることを日本側の教育者はわきまえなくてはならない。
ところで,米国で医療を行なうには,在来からEducational Commission for Foreign Medical Graduate(ECFMG)の資格がなければならないとされてきた。かつては,日本でもこの認定試験を受けることができたが,1996年半ばから改定され,不可能になった。つまり,この資格試験の第1の基礎医学と第2の臨床医学のテストのほかに,病歴の問診や診察術,患者や家族とのコミュニケーションなどを模擬患者などを用いてテストし,またさらに実地で英語のヒアリング能力をテストする試験方向に変わったからである。これは外国人のレジデントの米国入国をできるだけ制限しようとする政府の法的制限が加味されているものと考えざるを得ない。
基礎医学に力点置く米国の科学研究費
連載第2回(2290号)で米国の科学研究費の助成の仕組みの一部を述べたが,クリントン米大統領が1998年2月上旬に議会に提出した1999年度予算案(1998年10月から1999年9月まで)によると,民生分野での科学技術研究予算の大幅な伸びが発表されている。それは今後5か年間継続的な増加を見込んでおり,その中には21世紀の科学技術の進歩の主導権を米国がとりたいという意図をうかがうことができる。民生部門の研究費は,「21世紀研究基金」としてまとめられ,1999年度は310億ドル,5年間を通して1700億ドルに達するという。この予算の中で特に力点が置かれているのは基礎医学の研究であり,NIHでは前年度の8%増となった。これは過去最高の伸びで,1999年度は148億ドル(1.77兆円)になり,5年先にはその50%増にもなる。その中の重要テーマは遺伝子治療などである。全米科学財団(NSE)も過去最高の10%増しで,38億ドルになるという。その他,エネルギー省(DOE)の研究費も72億ドル。新しい感染症対策には37億ドル。また科学技術分野の人材教育に7500万ドルが向けられるという。
短期間のボストン滞在中の週末
臨床教育の場は外来棟へシフト
私は12月25日の夕刻ボストンに着き,その夜はラブキン先生夫妻のクリスマスディナーに招かれたが,その席でも上述のようなボストンにおけるマネージドケア(管理医療)のために患者のQOLがレベルダウンされる危険が話された。また,米国の医療や医学教育は,DRGその他の理由で入院期間が極端に短縮されたことによって,病気の診断と治療に関する学生やレジデントへの教育の場は,入院病棟から外来棟へと重点がシフトされてきたことが強調されている。外来患者が増えた場合,日本のように大勢の初診・再診の外来患者を受け入れて3分診療を余儀なくされている弊害を避けるため,米国ではあらゆる努力が払われ,そのためにベス・イスラエル・ディーコネス・メディカルセンターはすばらしい外来棟を1996年に建てたのであった。
12月26日と27日は,出雲教授の配慮で先に述べたような各部門のトップと面会し,大きく変化を遂げつつある医療システムとその影響下にある医学・看護教育の現状を実際に見ることができたが,これは私にとって大きな収穫であった。
12月26日の夜は,年末恒例のボストンバレエ団によるチャイコフスキーの「くるみ割り人形」に招待された。上演されたウォン劇場はたいへん素晴らしかったが,富豪の中国人ロレーヌ C. ウォン夫人(現・名誉理事長)の寄付になるものだという。これは在米中国人の文化的貢献の1つでもある。
翌27日の午前,ボストン美術館で開催中のピカソの10歳代の時の絵画を見た。オーソドックスな写実的描写技術を学んだ修練時代の作品である。また午後はハーバード大学のキャンパスにあるMuseum of Cultural National Historyを訪れ,興味深い数々の動植物の展示を見て楽しんだ。そして夕刻には,出雲教授のお宅に招かれ,研究室の若手スタッフと歓談した。若者と心を割って話をすることは何と楽しいことか。
29日(日)の夕刻にはボストン空港を発ち,ペンシルベニア州フィラデルフィア市に飛び,夕刻はダウンタウンのホテルに1泊した。
30日の午前10時には州立ペンシルベニア大学医学部とならび伝統のあるジェファーソン大学のゴネラ医学部長室を訪ね,ここで外科の名誉教授でアメリカオスラー協会の古参会員のF.ワグナー夫妻と歓談した。オスラー博士の資料などのあるこの学部長室で,当大学とオスラーとの深い関わりについて聞くことができた。大学の医学部の玄関を入った突き当たりの壁には,Old Blockley(フィラデルフィア総合病院)の前庭で医学生やナースたちと野外診療に従事しているオスラーの大きな絵が掛けられている。この絵を私は自著『医学するこころ――オスラー博士の生涯』(岩波書店・1991年絶版)のカバーに許可を得て使わせていただいた。この岩波のオスラー伝は,私が1948(昭和23)年に出版した『アメリカ医学の開拓者 オスラー博士の生涯』(中央医学社)の復刻版であった。
ワグナー教授は,今は強度の視力障害を持ち不自由な生活をしておられるが,医学史の大家であり,かつパイプオルガン奏者でもある。ご夫妻とホテルで昼食をご一緒したあと,午後2時に同市内のビルにあるINCLENの事務所を訪ねた。ここでは医師で事務局長のデイビッド・フレイザーと次のような用件で話し合いを行なった。
国際臨床疫学ネットワーク(INCLEN)
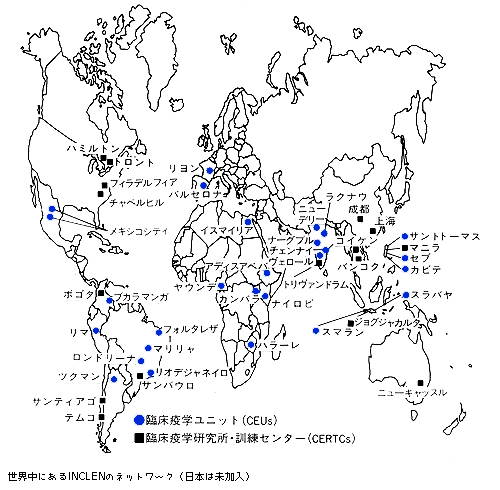
INCLENとはInternational Clinical Epidemiology Networkの略で,臨床疫学を世界に広め,臨床医の力で医療を合理的に行ない,かつ信頼性と説得性のある応用科学としての臨床医学を発展させるとともに,国民の健康づくりの基礎を築きたいとの発想から作られたものである。これは1980年にロックフェラー財団の事業として取り組みはじめられ,そのあと1988年には非営利の財団としてINCLENが設立された。
臨床疫学
臨床疫学という言葉は,決して新しいものではなく,早くは1938年にエール大学の内科・予防医学のジョンP.ポール教授が臨床研究学会の会長講演で初めて使っている。彼は臨床判断分析(clinical decision analysis)を重視し,患者のQOLを確保するためにも検証に支えられた信頼性の高い臨床研究が必要だと主張し,それをclinical epidemiologyと呼んだ。その後,この学問はハーバード大学の公衆衛生学部で取り上げられ,1980年には“Clinical Decision Analysis”と題したテキストが出版されている(日野原・福井次矢監訳『臨床決断分析』,医歯薬出版)。
福井先生と私が監訳した原本の“Clinical Decision Analysis”がボストンから出版された当時,日本の医学出版社は臨床疫学関係の新領域の成長をよく知らず,当時この翻訳出版を引き受けるところが大手の医学出版にはなかった。私と福井次矢教授が医歯薬出版に交渉してこれがやっと出版されたのは,原著出版から12年後の1992年7月であった。この訳本が日本で出版されたのをきっかけに,日本の医学校出身者の中で,臨床判断分析や広義の臨床疫学を専攻する同志が少しづつ増えてきたのである。今日,日本では総合臨床部門を持つ医学校が中心となり,200名近くが集まる総合診療研究会が5年前に発足し,1998年2月には第6回研究会が川崎医科大学で催されている。
臨床疫学という学問は,医療の利用度,有効性,効率性に関する研究を統計学的手法を用いて研究し,医師や医学生に正しい科学的文献の読み方を教え,臨床判断技法を教授し,臨床医学を検証したデータに基づいた科学として発達させ,国民の疾病予防に導くという学問である。これには医師のほかに,統計学者,経済学者,社会学者,看護専門職などが参与することによって医療の質を高め,またQOLを中心に全人的医療を考えようとする学問でもある。最近は,日本でもEvidence Based Medicine(EBM)またはEvidence Based Nursing(EBN)として流行し始めたが,それらはこの臨床疫学の重要な項目となるものである。
条件整え早期に加入を
INCLENの理事会については,その本部(フィラデルフィア市)を持つ米国からは5名の理事が,またカナダ,メキシコ,バングラデシュ,シンガポール,タイ,および英国からは1名ずつの理事が選ばれている。INCLENは,「人々の健康をよくするためには,資源を最も効率的に利用して実地医療のレベルを上げることを目的とする。これを達成するには世界中の医師,統計学者,社会科学者たちが一緒に働くことにより,臨床医学の優位性と確実性とを保持すること」という目的で発足した集団である。INCLENの支部は,米国はじめ,カナダ,フランス,ブラジル,メキシコ,チリ,エジプト,インドのほかに,東南アジアの国々にあり,各地で毎年学習セミナーやワークショップがもたれている。1998年2月にはメキシコで第15回年次総会が開催された。日本はまだ正式に加入していないので,私が理事長を務める聖ルカ・ライフサイエンス研究所が,事業の1つとしてこれに参与し,何らかの経済的・人的貢献をしたいと望み,その折衝のために今般私がこの本部を訪れたのである。
日本でも,総合内科臨床の講座がある大学に臨床疫学を指導できる専門家が2人以上いれば,INCLENの日本支部としてこの国際的組織に関わりを持つことができる。日本の何か所かにユニットが作られそれが公認されれば,新しい臨床医学の基礎となる研究や実践を世界的レベルで行なえる機構が整うわけである。この時が1日も早く来ることを私は期待して止まない。
むすび
私は,12月31日の午前11時にワシントンDC郊外のダレス国際空港を発ち,元日の午後2時に成田に帰国した。飛行機の中で私はこう考えた。米国におけるマネージドケア,これは経済的には制限的管理医療であるが,これが日本にじりじり近づいているものと私には思える。日本の医療費は1997年には27兆円にも上り,これは今後ますます急カーブで上昇することが明らかである。当然,マネージドケアは日本にも早晩政府の手によって手が着けられる気配が濃厚であり,すでに国立病院群を対象にその調査がされつつある。
対岸の火事ではない
米国では,各大学病院または優秀な教育病院のそれぞれが先端医療を取り扱うことには経済的にも人的にも非常に無駄があり,それぞれの病院がそれを採算性を持って行なうには無理があると誰もが合意するに至った。在来の方向で先端医療にことが進むと,米国の病院は遂には経済的破綻を来すことは明らかなのである。公立と私立の大学病院の統合や,ユダヤ教とプロテスタント派,またはカトリック派などの病院が公立私立の別や宗教の枠を乗り越えて合併または統合する。そのことによって先端医学への方向に進みつつ,かつ病院経営を合理化する施策が考えられつつあるのが現状である。これまで専門医指向で進歩してきた米国の近代医学が,数の上ではプライマリ・ケア医を主体とし,そこがゴールキーパーとなって2次,3次ケアの新病院システム形成をめざすという方策を病院経営者も,また政府も考えているのである。英国のNHS(National Health Service:公的医療制度)のとってきたような医療が米国でも始まっているといえよう。
それが果たして日本にはいつ上陸するか。米国での医学,医療,看護の動きは,これまでは日本に伝わるには10年ないし20年かかってきたというのが過去にたどった道である。それが21世紀には10年先の日本に来ないと誰が言えるだろうか。先人の轍を踏まずという賢い政策の立て方で,果たして先人の軌道を修正しつつ日本に最適な医療行政が打ち立てられるだろうか。
とにかく,医療先進国のアメリカが現在このような大波に洗われているのだという事実を,私たちは厳粛に受け止めて,これを対岸の火事と考えず,21世紀への合理的な医療改革のために米国のデータをEvidence Based Medicineの方法論で早期に検討すべきだと思う。
私は,科学としての医学が正しく発展するためには,医学を人間を尊重するという方向にもっていくことを忘れてはならないと強調したい。そうでなければ,科学としての医学は内部から破壊するのではないかと懸念するのである。
私の医の哲学を述べて筆を擱く。
「科学の進歩が人類の進歩と同意義となりうる道を探求しよう」
(おわり)


