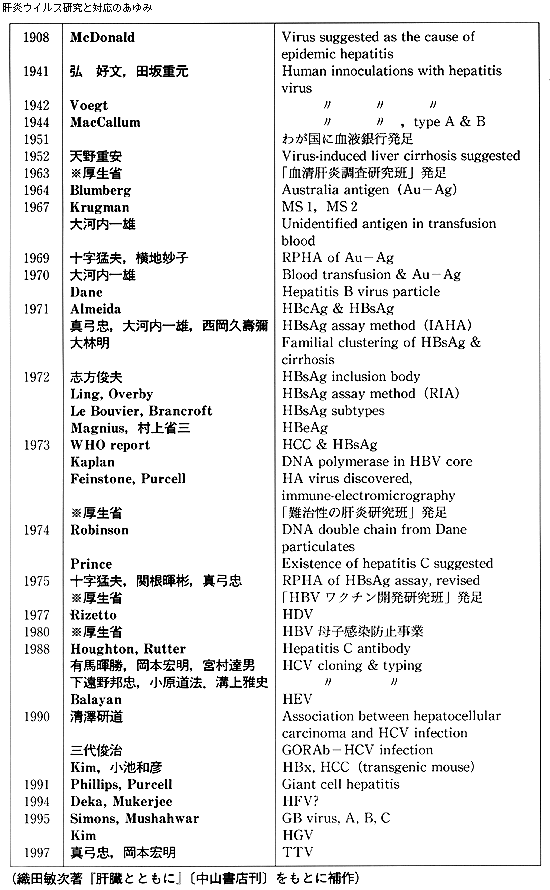【鼎談】
肝臓病学の新しいストラテジー
 | ||
| 戸田剛太郎氏 東京慈恵会医科大学教授 第1内科 | 織田敏次氏 日本赤十字社医療センター 名誉院長 | 清澤研道氏 信州大学教授 第2内科 |
「肝炎ウイルス発見」の夜明け
“血清酵素の診断への導入”と“ウイルス・ハンティング”の時代
戸田<司会> 本日は『肝臓病学の新しいストラテジー』と題しまして,大先輩であると同時に,また大いなる先達でもある織田敏次先生にご出席をお願いしまして,肝臓病学をめぐる諸問題や今後の展望をお話しいただければと思います。ご存じのように,わが国の疾病構造は大きく変化しておりますが,とりわけここ半世紀における肝臓病の増加,特にウイルス肝炎の増加には瞠目すべきものがあります。さらに,肝硬変や肝癌などが働き盛りの年代の死亡率の増加の原因として指摘され,社会的な問題になっています。
一方,肝臓病学の研究はこの30年の間に基礎の面においても臨床の面においても長足の進歩を遂げております。現代の肝臓病学はGOTやGPTを始めとする血清酵素を診断に導入することから始まったと言えると思います。また最近は,診断や病態把握に先端的な医用機器や遺伝子解析手法が導入されており,治療面でもウイルス肝炎に対するインターフェロン療法や肝腫瘍に対する内科的治療など,治療面での進歩も目覚ましいものがあります。
さらに病因追究という面における進歩の1つに,HBV(B型肝炎ウイルス)の発見に始まる肝炎ウイルスの分離・同定があります。肝臓病学におけるいわゆる“ウイルス・ハンティング”の時代はこれからも続くでしょうが,1989年のHCV(C型肝炎ウイルス)の同定によって1つの大きな山を越えたようにも思います。
しかし,肝臓病は肝炎ウイルスに対する生体の反応によって起きてくるものです。その意味で,これからの研究は病態成立のメカニズム解明が大きなテーマになってくると思います。
『肝臓-構造・機能・病態生理』の発刊と「血清肝炎調査研究班」の発足
戸田 今回『肝臓病学Basic Science』『肝臓病学Clinical Science』という2冊の成書を医学書院から発行する運びになり,本日ご出席をお願いしました清澤研道先生と私が両方の編集に当たりましたが,実は私どもの念頭には常に高橋忠雄先生が監修され,織田先生と三浦義彰先生,斎藤守先生が編集された著書『肝臓-構造・機能・病態生理』(1968年第1版,1976年第3版,医学書院刊)がありました。そこで,まず織田先生からこの本を出版された当時のお話をお聞かせいただければと思います。 織田 戸田先生が言われたように,当時はとにかく血清酵素による診断がつくようにはなったのですが,残念ながら肝炎ウイルスはまだ発見されておりません。しかしながら,戦前は尾去沢,そしてその少し後に猿島,そして岡山で肝炎の大流行がありましたし,1941年には北大の弘好文先生が人体接種経験を発表して,子どもに濾過性病原体が感染すると黄疸になるということだけはわかりました。
織田 戸田先生が言われたように,当時はとにかく血清酵素による診断がつくようにはなったのですが,残念ながら肝炎ウイルスはまだ発見されておりません。しかしながら,戦前は尾去沢,そしてその少し後に猿島,そして岡山で肝炎の大流行がありましたし,1941年には北大の弘好文先生が人体接種経験を発表して,子どもに濾過性病原体が感染すると黄疸になるということだけはわかりました。
ちょうど私が東大へ入学した年の秋,それを新聞で知ったのですが,それがどれほどの意味を持つものか,それにはまったくの無知でした。しかし,ウイルスが関与しているようだということがわかったわけですから,それを発見することが急務という認識は皆さんが持っていました。
培養に成功した例としては,現在,「由良三郎」という筆名でもっぱら推理小説を書いている吉野亀三郎先生が1956年,one day chick embryoに人間のヘルペスウイルスを植えたのが話題になっていました。そこで吉野さんに声をかけて,肝炎ウイルスの探索をお願いしたのが1964年,ちょうどBlumbergがオーストラリア抗原を発見して話題になった頃です。
そしてまた厚生省に「輸血をするたびに黄疸が起こるのはまずいので,国が研究体制をとるべきである」と提言して,「血清肝炎調査研究班」が発足することになるのが1963年です。
中毒性肝障害:アサリ・カキ中毒事件
織田 そもそも私が肝臓病の研究に進む契機となったのは「中毒性肝障害」という問題,つまり戦後すぐに起こった浜名湖のアサリ・カキ中毒事件でした。高橋先生と一緒に1949年に浜名湖へ行きましたが,剖検した肝組織は真っ黄色ながら,リンパ球の浸潤はまったくと言っていいほどありません。当初考えたウイルス起因説はこれで否定されました。それでは何が原因なのかと調べた結果,辰野高司先生が中毒因子「エリスロスカイン」を見つけ,中毒性肝障害ということになりました。その結果,戦後の肝臓病学は当面ウイルスをスキップして中毒性肝障害をターゲットにしたわけです。
しかし,ウイルス培養が必要であることに変わりはありません。そこに登場するのが大河内一雄先生で,彼はBlumbergの発見した“オーストラリア抗原”が輸血による肝炎と密接な関係があることを1970年に証明して,Blumbergにノーベル賞をもたらしたことも事実です。
戸田 それでは『肝臓-構造・機能・病態生理』の初版は,血清酵素が診断学に導入され,肝臓病学が今後あらたな展開をみせるという展望や期待のもとに作られたのですか。
織田 そうですね。
大河内一雄先生の門を叩いて:“SS血清”の登場
戸田 私は肝臓病学を専攻する以前は,生化学を研究していましたが,当時の生化学は主として肝臓が使われており,自然な流れで肝臓病学に興味を持つようになりました。その頃はGOTやGPTの他に,アルカリホスファターゼも揃ってました。また,G6PaseやICDHなどの酵素も,肝疾患の診断に導入され,織田先生はアルカリホスファターゼやフォスフォモノエステラーゼの研究に力を入れていらっしゃったことを憶えています。清澤先生はどのような契機で肝臓病の研究を始められたのですか。
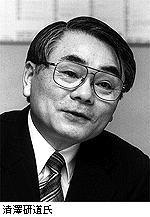 清澤 私が研修医の頃に,さきほど織田先生がおっしゃったように,大河内先生によってBlumbergが発見したオーストラリア抗原が血清肝炎と密接な関係があることが明らかにされました。私はこのオーストラリア抗原に興味を抱き,当時の小田正幸教授に紹介状を書いていただいて,1970年の秋,東大輸血部に移っておられた大河内先生の門を叩きました。
清澤 私が研修医の頃に,さきほど織田先生がおっしゃったように,大河内先生によってBlumbergが発見したオーストラリア抗原が血清肝炎と密接な関係があることが明らかにされました。私はこのオーストラリア抗原に興味を抱き,当時の小田正幸教授に紹介状を書いていただいて,1970年の秋,東大輸血部に移っておられた大河内先生の門を叩きました。
その頃の東大輸血部には,現在世界にその名を馳せていらっしゃる真弓忠先生が助手として在籍し,両先生は朝から晩まで赤血球粘着反応によるオーストラリア抗体の測定に汗を流していました。わずか1週間の短い滞在でしたが,私にとって文字どおり一生忘れられない“ゴールデン・ウイーク”となりました。そして松本に帰る時には,当時オーストラリア抗原を検出するのに最も抗体値の高い「山川血清」と,スタンダードの抗原を含んだ血清を分与していただきました。
実はその前に,Sさんというスルフヘモグロビン血症の患者さんを診ていた私は,東大に行く時にその血清を持参したのですが,松本に帰って間もなく大河内先生から電話があり,それが「山川血清」にも優る高力値のオーストラリア抗体を含んでいることが判明したとのことでした。大河内先生は,「今後は1滴たりともおろそかにしないように」とおっしゃり,即座に「信州のSさんの血清だから,“SS血清”だ」と命名されました。
それ以来,Sさんの血清は欠けることなく保存しています。
“ウイルス・ハンティング”の時代
“HBV" に次ぐ“HCV" 発見のインパクト
 戸田 肝炎ウイルスはいずれもオーソドックスなウイルス病学からは若干外れていますが,1970年頃から活発な“ウイルス・ハンティング”の時代を迎え,まずHBVが発見され,そのワクチンもできました。
戸田 肝炎ウイルスはいずれもオーソドックスなウイルス病学からは若干外れていますが,1970年頃から活発な“ウイルス・ハンティング”の時代を迎え,まずHBVが発見され,そのワクチンもできました。
そして,やや遅れましたがHAV(A型肝炎ウイルス)も,FeinstoneやPurcellたちがMS-1由来の肝炎を発症したボランティアから抗体電顕法によって確認することができました。また冒頭に申しましたように,HCVの発見および同定がウイルス・ハンティングの時代の1つの大きな山になりましたが,その間のエピソードをお聞かせいただけますか。
織田 あれは1988年の5月頃でしたが,Chiron社のRutter所長から「HCVのクローンが採れたので,NIHまでご足労願いたい」という内容の手紙が届きました。
早速出かけてみますと,「Dr.HoughtonがHCVのクローンを釣り上げることに成功した。ついては,日本の肝炎患者について,その正当性を試してほしい」というものでした。そしてその年の秋には,Rutter所長自ら来日しましたので,西岡久壽彌さん(現・日赤中央血液センター技術顧問)とともに朝食をとりながら,C型の抗原蛋白(c-100)を早く送ってくれるように頼みました。
清澤 そうですね。Chiron社がHCVのクローン化成功を発表した半年後の11月に,カナダのトロントで国際肝臓研究会が開かれましたが,そこでNIHのDr.Alterが「Chiron社がHCVの抗体として開発したものが,HCVにぴたりと反応する」と発表しました。
私は偶然この会議に出席していて,その講演を聞く僥倖に恵まれましたが,非常に感激した記憶があります。おそらく,私の生涯の中でも最も思い出に残る講演の1つになると思います。まさに,長いトンネルから抜け出して,眩しいばかりの光を感じた瞬間でした。
肝炎ウイルス発見が果たした役割
戸田 現在,ウイルス肝炎はAからGまで6種類あると言われていますが,日本に多いのは第1にC型肝炎,次いでB型肝炎です。また最近はG型肝炎に関しても盛んに議論されていますし,わが国の研究者が世界に先駆けて発見した新型肝炎ウイルス「TTV(TTウイルス)」に関して,厚生省は感染率や発症率の全国拠点調査,肝硬変や肝癌などとの関係を調べる本格的な研究をスタートさせようとしています。先ほども申しましたが,肝炎ウイルスの発見までは肝病態の研究に大きな役割を演じたのは生化学でした。しかし,わが国の肝臓病の原因の大部分が肝炎ウイルスであることを考えると,本来,肝炎ウイルス感染の結果として生じた肝疾患の病態が研究対象でなければならなかったとも言えます。そういう意味でも,肝炎ウイルスの発見によって肝疾患の病態発現の原因が明らかにされたことは肝臓病学の研究に大きな進歩をもたらすものと思います。当然のことではありますが,原因が明らかにされた後,つまり肝炎ウイルス発見後における肝臓病の研究は,それ以前の研究とは明らかに異なったものになるでしょう。
織田 ウイルスの探索も第1世代は培養,第2世代が抗原抗体,第3世代が遺伝子・核酸が対象に選ばれて,ようやく弱いウイルスも見つかってきたのです。培養では宿主細胞を殺してしまうほど強いウイルス以外は見つけられませんでした。
肝臓病学の新しいステラテジー
肝細胞障害のメカニズムの解明
戸田 肝臓病の最も大きな原因である肝炎ウイルスがある程度明らかになってきた現在,今後はいかにして肝細胞障害が起こるのか,その病態メカニズムの解明も大きな研究テーマになってくると思いますが,いかがでしょうか。肝細胞障害の機序は決して単一ではなく,細胞死にネクローシスとアポトーシスがあるように,細胞障害のメカニズムも多様です。肝炎ウイルスによる肝細胞障害機序の解明に大きな役割を演じたのは免疫学の進歩で,細胞障害の実行者としてのパーフォリン,Fas/Fas Ligands系,サイトカイン,活性酵素,フリーラジカルなどの同定があります。これらは肝細胞障害の阻止にもつながる重要な成果と言えると思います。 そしてさらには,「類洞壁細胞」の肝の恒常維持や肝細胞障害への関わりも最近明らかにされた重要な知見ですね。
清澤 そうですね。類洞壁細胞の機能として,「Kupffer細胞(Kupffer cell)」や「伊東細胞(肝星細胞:Ito cell)」,「類洞内皮細胞(sinusoidal endothelial cell)」,また肝内リンパ球など網内系の機能は,これから注目されてくるでしょうし,今後もさらに研究を深めていかなければならない分野でしょうね。その辺は今回の『肝臓病学Basic Science』では,かなり詳しく掘り下げて記述してあります。
第1回犬山シンポジウムにおける慢性肝炎分類の提唱
清澤 ところで,私たちが肝炎の研究を始めた時に,一番最初に習ったのが肝臓病理学でした。ちょうどその頃(1967年9月),第1回犬山シンポジウムが開かれて,日本肝臓学会慢性肝炎委員会によって慢性肝炎の分類が提唱されました。ヨーロッパ分類が提唱されたのが1968年ですから,ほぼ同時期に偶然慢性肝炎の分類を作ろうという気運が盛り上がって,CPH(慢性持続性肝炎)やCAH(慢性活動性肝炎),persistent hepatitis(持続性肝炎)などが議論されました。そしてご存じのように,「Staging(Fibrosis:線維化の程度)」,「Grading(Activity:炎症の程度)」の定義のもとに両者ともに改定がほどこされました。
織田 そうですね。犬山シンポジウムは慢性肝炎の概念・分類を討議することを目的に犬山に集合したもので,私はその幹事役を仰せつかりましたが,輸血による血清肝炎が慢性化する事実を知って,何とか対策を立てなければと大いに慌てさせられたことを憶えています。つまり,肝臓病学は慢性肝炎の研究から始まったわけですが,当時はウイルスによって慢性化するということは考えられませんでした。
自己免疫性肝疾患について
戸田 結局,ウイルスの持続感染が慢性肝障害の原因だったわけですが,そこにたどり着くまでが非常に大変で,長い道のりが必要だったわけですね。そしてその一方では,欧米の「自己免疫性の機序」という観点,つまりウイルスが見つからない慢性肝障害を説明するものとして,「自己免疫性肝疾患」という概念が出てきたように思います。
清澤 日本でもウイルスがわからない時代に,慢性肝炎の治療としてステロイドを使ったりしていた時代がありますが,あの頃はアメリカ学派はAIH(autoimmune hepatitis:自己免疫性肝炎)とウイルス性肝炎をはっきり区別していませんでした。
戸田 しかし,HCVの同定によってウイルス性肝炎とは別にAIHという病態が存在することが明らかになりました。最近では,アメリカからもAIHに関する研究報告が見られますから,AIHを取り巻く状況はだいぶ変わってきていると思います。
また,HCVの同定によってわが国と欧米のAIHの臨床像の違いは,免疫遺伝学的背景の違いに由来すると考えられています。
織田 欧米ではアルコール性肝炎の存在が大きいですし,日本ほどに肝障害が多くないですね。ことに欧米とわが国の肝癌の発生率は桁違いでしょう。
ウイルス肝炎発症のメカニズムの解明
戸田 自己免疫性肝疾患だけでなく,肝疾患はかなり民族や国によって差があると言えます。アメリカでもC型肝炎が増える可能性がありますね。織田 実際に増えているようですね。現在は400万人と言われています。そこでエマージング・ディジイズの中にC型肝炎を入れたわけです。原因はコカインなどの静脈投与で,これが重大な問題になっており,急遽研究費を回し始めています。エイズがやや下火になって……。
清澤 私どもは「C型肝炎の場合,肝癌になるのにだいたい30年近くかかるのではないか」というレポートを1984―1985年頃に出していたのですが,最近はアメリカからも同じような報告が出るようになりましたね。
戸田 C型肝炎の治療に関しても,インターフェロンの投与によってHCVが排除され,トランスアミナーゼが正常化する人もいますが,一方ではHCVが排除されないにもかかわらず,トランスアミナーゼが正常化する人もいます。そうしたことからも,これからはウイルス肝炎発症のメカニズムの解明という問題もまだまだ研究していかなければならないでしょうね。
織田 その通りです。そして,もっと木目の細かい治療を行なうためのデータを出していかなければなりません。
清澤 抗ウイルス剤だけに頼っていいかどうかというのは大きな問題だと思います。ワクチン療法や免疫機構を利用した治療というようなものが必要でしょう。
戸田 肝炎の治療は現在はウイルスを排除することに目標が置かれていますが,肝炎の鎮静化が図れればよいのではないかという考え方も成立すると思います。
清澤 公衆衛生学的な面から言えば,明らかに若い世代の患者さんは減りつつありますが,やはり現実にまだC型肝炎やB型肝炎に羅っている人がいるわけですから,予防医学的な観点からも解決しなければなら問題だと思います。
織田 話は飛びますが,この間『ジュラシック・パーク』を書いたマイケル・クライトンの『5人のカルテ』を読みましたが,彼はその中でアメリカ医療の破産を指摘していました。人件費が60%を超してはどうにも……,と言っていました。医療経済学的な意味合いからも,予防医学の問題がこれから重要になるのではないでしょうか。癌もある面では予防の問題と言えるのでしょう。
癌克服のモデルケースとしての肝癌発症のメカニズム解明
戸田 もう1つは,肝細胞障害が持続した場合,最終的に肝硬変へも進展するわけですが,肝硬変になるときわめて高率に肝細胞癌が発生します。肝硬変の母地としてどのような機序で肝細胞癌が発生するのかがこれから大きなテーマになると思います。現在は肝硬変で食道静脈瘤破裂や肝性脳症で亡くなる人はほとんどいなくなって,大多数は肝癌で亡くなっています。多くの癌の中でも原因が明らかにされ,しかも発生母体が明らかにされているのは肝癌しかないわけです。そういった意味で,肝癌の発症のメカニズムを研究することが,すなわち癌克服のためのモデルケースになるという気がします。
織田 Kimと東大第1内科の小池和彦君が見つけたB型肝炎のX遺伝子がそのよい例だと思います。C型肝炎でも彼のトランスジェニックマウスが,現在は脂肪肝まできています。この脂肪肝というのはかなり曲者で……。発癌の1つのプロセスであるとも考えられるのではないでしょうか。
清澤 早期癌のところには脂肪細胞がありますからね。
織田 もう一歩のところまできていると私は思っています。大いに期待していますが。
戸田 もう1つは肝炎の持続,つまり炎症と発癌との関連性についても,肝炎は非常にいいモデルケースになると思います。
ウイルス感染の予防やウイルスを排除するという方法以外でも,肝炎を抑えれば必然的に肝癌の発症は減ってくるわけですから,次の手段としては,肝炎の発症を抑えることによって肝癌の発症を抑えるという考え方が出かかってます。肝癌の発癌予防という観点からも,将来の展望として重要だと思います。
免疫学や分子生物学の研究成果の導入を
織田 先ほど戸田先生が「肝細胞障害の機序の解明に免疫学の進歩が大きな役割を演じた」と言われましたが,観点を変えて見れば,肝臓病学そのものが免疫学を臨床応用するには最適な場であると言えますね。免疫学という分野は,学問そのものが若く,それこそ日進月歩の世界ですから,先生方がこれから実際のデータを示してリードしていけば,肝臓病学もさらに魅力あるものになるはずです。肝臓とは代謝の機能もさることながら,生体防御機構の第2の砦にもなります。母親の母体の中では血液やリンパ球を造っていたのですから。
戸田 そうですね。先ほど炎症と肝癌との関連や肝細胞癌の発生の話が出ましたが,免疫学と同時に分子生物学の研究成果を取り入れることも重要です。現にそれらのこと抜きにしては肝臓病学という学問を考えることができない時代になりました。
清澤 最近よく言われているのは,免疫とからめたサイトカインです。
肝細胞・類洞壁細胞の調節因子としての役割,肝炎劇症化との関連,また発癌のレベルにまでサイトカインが登場してきました。その辺の研究は非常に大事ではないかと思います。
戸田 レセプター,セカンドメッセンジャーなどの細胞内情報伝達系の研究の進歩も目覚ましいですね。また,癌遺伝子・癌抑制遺伝子の発見もその後の発癌メカニズムの解明にもたらした功績は計りがたいものがあります。
肝臓病研究における「基礎」と「臨床」
清澤 それに関連して私があえて強調したいのは,肝臓病学における基礎医学と臨床医学のコンビネーションのよさです。戸田先生が指摘されたように,ウイルス肝炎に対するインターフェロン療法や肝腫瘍に対する内科的治療の進歩は目覚ましく,難治性肝疾患に対する肝移植法も生体肝移植例数が昨年末には全国で520例を超し,いまや確立された治療法になりました。また,昨年10月には脳死肝移植の法的な整備がなされました。今回『肝臓病学』を編集しながら痛感しましたのは,ここ半世紀近くの肝臓病学の進歩は,基礎医学研究陣と臨床医学研究陣が2人3脚でコンビネーションよく着実に成果をあげてきた結果によるものだということでした。このような研究形態は他の領域では見ることのできない特異なもので,わが国の肝臓研究陣が世界をリードしてきた源にもなっていると思います。
なす術もなく,不幸な転帰をとる多くの患者さんを目の前にした臨床家から切実な問題提起がなされ,それを基礎研究者が究明し,その成果が臨床研究に還元される。そして,当然のことながら臨床診療に反映され,予防医学にも恩恵をもたらす。そういう肝臓病学における基礎医学と臨床医学の表裏一体の共同作業は,まさに医学研究の真髄ではないかという思いを強く感じました。
戸田 まったく同感です。本日は,『肝臓病学Basic Science』と『肝臓病学Clinical Science』の発刊を機に,“肝炎ウイルス発見”をターニング・ポイントとした「肝臓病学の新しいストラテジー」をお話しいただきました。お忙しいところをどうもありがとうございました。