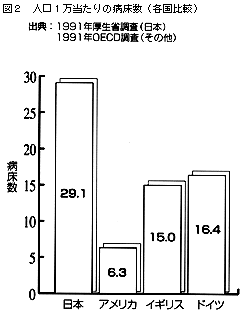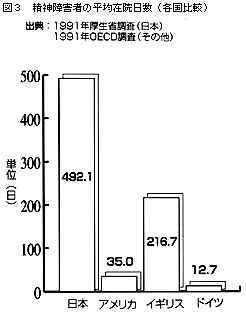〈インタビュー〉
精神保健福祉士法制定と日本の精神医療
荒田 寛氏(陽和病院ソーシャルセンター課長,日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会常任理事)に聞く


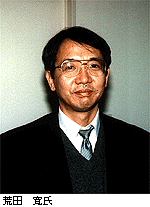 昨年12月12日の臨時国会で参議院本会議は「精神保健福祉士法案」を全会一致をもって可決,「精神保健福祉士法」が成立した。同法は本年4月1日より施行。来年の初めには第1回国家試験が実施され,「精神保健福祉士」が誕生する。
昨年12月12日の臨時国会で参議院本会議は「精神保健福祉士法案」を全会一致をもって可決,「精神保健福祉士法」が成立した。同法は本年4月1日より施行。来年の初めには第1回国家試験が実施され,「精神保健福祉士」が誕生する。
精神保健福祉士とは,その名称を用い,精神病院などで精神障害の医療を受けている患者や,社会復帰施設などを利用している方の社会復帰に関する相談に応じて,助言や指導,日常生活へ適応するために必要な訓練,その他の援助を行なう専門職であり,名称独占の国家資格である。
精神保健福祉士のモデルとなっている精神科ソーシャルワーカーとして,精神障害者やその家族の相談,援助等に従事している者は,現在約2600人ほどである。しかし,精神病院へ入院している患者のうち数万人は地域社会に受け入れ体制があれば退院可能な,いわゆる「社会的入院」と言われており,精神障害者の福祉の増進を図る上で,社会復帰を促進することは喫緊の課題となっている。厚生省はこうした状況を解消するために必要とされる精神保健福祉士の最低限度の数として1万人を掲げ,当面の養成の目標としている。
本紙では,日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会常任理事を務める荒田寛氏にインタビューを行ない,精神保健福祉士法制定の意義,日本の精神医療の課題,今後の展望などについて話をうかがった。


精神保健福祉士とは
―― 精神保健福祉士法制定の趣旨とは?荒田 私たちが国家資格に取り組んできた理由の1つには,閉鎖性が強い日本の精神医療を少しでもよくしていきたいということがありました。また,現在,精神保健福祉の中心的課題としては(1)精神障害者の社会復帰対策の促進,(2)よりよい精神医療の確保,(3)適切な精神医療をいつでもどこでも受けられる体制の整備,(4)予防対策や社会復帰の基盤整備などがあげられます。
長期入院者の社会復帰を促進
荒田 特に,精神障害者の長期入院,社会的入院の問題は強く指摘されています。今入院している34万人の方の50%が5年以上,全体の3分の1が10年以上入院しています(図1参照)。平均在院日数を諸外国と比較すると,日本は492日,イギリスはやや長く216日ですが,アメリカは35日,ドイツと,カナダが12日。日本の入院期間が極端に長いことがわかります(図2,3参照)。その人たちの社会復帰の援助を進めなければなりません。そのためには,精神科の医師をはじめとした医療従事者が行なう診療行為に加えて,退院のための環境整備などを積極的に進めること,精神障害者や家族,地域住民の保健福祉を生活問題として捉え,これら心理社会的問題の解決を図ることが必要です。これを担う専門職として精神保健福祉士が必要だったわけです。
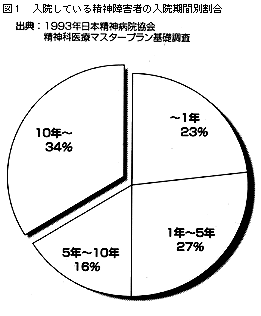
精神保健福祉士の具体的業務
―― 精神保健福祉士はすでに存在する精神科ソーシャルワーカー(以下PSW)が国家資格化されたものですが,その業務とは具体的にはどのようなものですか。荒田 基本的には,病気の心理・社会的な側面を理解して,精神障害者の入院生活を含む社会生活を援助するのがPSWの役割だと思っております。
精神病院における精神保健福祉士の業務を表にまとめてみました。この中でも,今回の国家資格化によって特に期待されているのが,(7)退院援助と,(10)地域との連携と退院後の援助です。その過程で(4)経済的援助や,(5)家族調整援助,(6)就労・就学・住居に関する援助なども行なうことになります。
住居の確保や受け入れるべき家族の相談に応じながら,家庭に戻っていくための援助をしたり,経済的な基盤が弱い方が多いので,生活保護をどう受けたらいいか,年金をどうもらったらいいか等,各種社会保障制度をどう利用していったらいいかという経済的な相談にものります。
精神病院に長く入院なさっていた方は,地域で暮らそうとしても,対人関係や具体的な日常生活に自信を持てない場合が多いと思います。電気釜の使い方から,ガス器具の使い方。場合によっては,電車やバスの乗り方から覚えなければいけないこともあります。地域生活を送るために,地域の受け皿を作ったり,対人関係の練習をしたり,具体的な生活の助言指導とともに,自らの障害を受容して,「あたり前」の生活を自分らしく送れるように援助する専門職としてPSWが国家資格化されました。
PSWの業務は,主に病院の入口と出口のところであり,その窓口としての役割は非常に大きいです。もちろん,入院中であれば,患者さんの心理的な面や,生活歴の中の社会的な面,人間関係の面でのその人の経験や病気の背景などの対象者の問題点を「生活レベル」で捉えて,看護や医師の方たちと一緒にチームを組んで仕事を進めていくことになります。
また,私たちはグループ援助の方法も学んでいます。他の職種はグループを対象とした援助方法を学ぶ機会は少なく,個別援助を基本に学ぶと思います。ですから私たちは入院中の生活技能訓練(SST:Social Skills Training)や集団精神療法的な業務はもちろんのこと,退院後のデイケア,ナイトケア等のグループを対象とする業務についても特別な役割を発揮できるのではないかと考えています。
―― 退院援助,そして退院後の患者さんの生活を支えるために必要な援助を継続して行なうのですね。
荒田 そうです。以前は退院前後に訪問しても無報酬で,病院でPSWを雇うということは,ある面では不採算部門を抱えることだったのです。けれども,患者さんの退院援助,社会参加援助の必要性によって,雇っていただいていたわけです。これも10年前に診療報酬点数にのりました。PSWの業務の中には資格ができる前からかなりの部分が診療報酬上に位置づけられています。精神科訪問看護・指導料のほかに,精神病院の精神科急性期治療病棟入院料,精神科デイケア,ナイトケアなど10項目以上にわたり「精神科ソーシャルワーカー」の配置が診療報酬算定にあたっての従事者として規定されています。ただ,資格がなかったので自称すれば,誰でもできることになり,援助の質を担保することが困難でした。
| (1)受診・受療援助
精神保健福祉士は,受診したほうがよいか,病気かどうか判断しかねている患者や家族の病気や生活上の相談に応じ,病気と生活の状況に適切に対応した医療の受け方について援助し,どのような医療サービスが提供できるのかオリエンテーションする。 (2)インテーク
(3)療養中の指導援助
(4)経済的援助
(5)家族調整援助
(6)就労・就学・住居に関する援助
(7)退院援助
(8)人権の擁護に関する援助
(9)集団への援助
(10)地域との連携と退院後の援助
|


国家資格化で何が変わるのか
―― 精神保健福祉士として国家資格化されたことによって,精神医療,PSWの業務などにどのような影響があるとお考えですか。荒田 現状では全国の精神病院の約3分の1がPSWを配置していません。それが資格化されることによって,PSWの配置が促進され,より多くの患者さんや家族の方が相談できるようになるでしょう。また,私たちの援助行為に質の担保ができる。今までは,だれが行なってもいいことだったのが,今後はしっかりとした教育的背景を持った者が行なうことになります。どの精神保健福祉士に相談しても,一定の援助,訓練が保障してもらえるようになると思っております。
チーム医療の中で力を発揮
荒田 チーム医療の中でもより明確な役割を果たせるようになるでしょう。精神障害者の多くは,身体障害者や知的障害者の方々と障害のあり方が異なり,社会で受け入れてもらえなかったり,自分の能力が落ちていることによって,病気が再発する可能性を持っています。機能障害が固定化したものではなく,生活上の変化,人間関係や社会関係の変化もきちんと見ておかないと再発をする。あるいは,病気が再燃して障害がもっと深くなってしまうということもあるのです。そのような患者さんたちの特徴から,病的な部分,病気の症状や問題行動の部分だけではなく,心理的な背景や生活の中での経験,例えば職場や学校,友人など人間関係の経験を重視し,総合的に1人の患者さんをみて,援助の方法を組み立てていくようなチームアプローチが可能になります。ただ,実際には,PSWの数が足りない中でチームに参加するといっても無理でした。多くの民間病院で1名ないし2名の単独配置というのが現状で,病院全体の医師や看護婦とチームを組んで協力関係を結んでいくには限界があります。PSWとしてのアイデンティティそのものが希薄な段階から,期待だけが膨らんでいて,それにこたえられなくてつぶれていくケースも一方でありました。
今後,配置が促進されてこそ,チームの中で自分たちの役割が発揮できるのではないかと期待しています。
―― 現在,PSWはほとんど病院に配置されているわけですが,国家資格化はPSWの活動の拠点を地域へ広げる要因になるのでしょうか。
荒田 精神障害者生活訓練施設,精神障害者授産施設,精神障害者福祉工場などの精神障害者社会復帰施設の運営要綱にはPSWの配置が規定されています。
また,保健所では精神保健福祉相談員の配置が精神保健福祉法により規定されています。この精神保健福祉相談員はPSWがモデルとなっており,精神保健福祉士は名称独占の資格ですが,将来任用職種として規定されることが考えられます。すでに,千葉や神奈川,埼玉,大阪などではPSWを各保健所に配置し,保健婦さんとチームを組みながら,精神保健福祉の相談にのるという仕事をしております。それがさらに促進されると思っております。


高齢社会の中の精神医療・保健・福祉
―― 精神福祉士法に先立って先の臨時国会では介護保険法が成立しました。高齢社会の中でのPSWの果たしていく役割にはどのようなことが考えられるでしょう。荒田 まず,精神病院に入院されている方の高齢化の問題があります。すでに入院患者の平均年齢は60歳を超えています。10年以上入院されている方が34%もいますから,長期入院の方々の中には,自分の人生の多くを精神病院で過ごしてこられた方がたくさんいます。
この人たちが一生精神病院で過ごすことが許されていいのか
荒田 私は今の病院に来て15年になりますが,勤めはじめた頃に出会った患者さんの中の1人に,いわゆる「赤線」で働いていた年配の方がいらっしゃいました。家が貧しく,兄弟を食べさせるために東京に出てきてそういう仕事をしていたそうです。自分の人生が崩壊していく中で,どう生きていっていいのかわからず,自分を見失って精神病になられたのです。その方は20年以上も入院なさっていました。売春防止法ができたのが昭和30年代ですからね。その時代に入院された方々の多くは,すでに帰る家もなく,精神病院で一生を過ごすケースが多いのです。
私はこの人たちは一生精神病院で過ごしていいのだろうか。そういうことが許されていいのだろうかと真剣に考えました。早速,退院援助に取り組んだのですがアパート探し1つをするにしても,保証人の問題もあれば,生活技術の遅れもあり大変でした。その当時,私が退院援助した方の何人かは,今も社会で暮らしていらっしゃいます。つまり,PSWが援助しなければ,病院で一生過ごす方が,全国にたくさんいらっしゃるということです。
精神病院の中で高齢化していく方々への援助としては,まず,社会,地域での受皿をつくりながらの退院援助が必要となります。また,一方で病棟で私に手を合わせて,「ここで一生過ごさせてくれ。異常者扱いされるから社会に出たくない。偏見のある社会は厳しい」とおっしゃる方もいます。病院で一生過ごされる方に対して,よりよい療養環境をどうつくっていくのか。これはPSWだけでなくて医師や看護の方々と一緒に考えていかなければならない課題です。
痴呆性老人と精神医療施設
荒田 また,痴呆性老人の方々も私たちのかかわる対象だと思っております。いま多くの痴呆性老人の方々は行き場がありません。家族制度が崩壊していく中で,家族の介護力が落ち,老人福祉施設(養護老人ホームや特別養護老人ホーム)にも入れない,老人保健施設にもすぐには入れない方々がいらっしゃる。そのようなときに精神病院に相談に来られるのです。残念ですが,結局,精神病院に入院なさる方は非常に多いのです。精神病院の中に痴呆性老人病棟をつくって痴呆症の方々への対応をするところも出てきています。私たちもかかわる必要があります。
―― 今後,精神病院の病床数削減となれば,痴呆老人を積極的に受け入れていかないと経営的にも難しいと思いますが,現在の療養環境を見ると,特養や老健に比べるとずいぶん劣るようです。そのような状況についてはどのようにお考えですか。
荒田 精神科に長期入院しておられていて,病状に変化がなく,社会復帰するには難しい方々のための病棟をなんとかと考えるべきだということで,「精神保健福祉施設」あるいは「心のケアホーム」と呼ばれるものをつくる計画があります。
その療養環境は,一人当たりの広さとか,明るさ,スタッフも含めて……,これはまだ試案でしかありませんが,非常に広く,アメニティを重視したものになっています。現在,精神病棟での患者さん1人あたりの空間は,8m2が基準となっている老健施設の約半分,つまり,4.3m2あればいいことなっています。とても十分な広さとは言えません。「心のケアホーム」をつくるときには,老健に相当するような広さ,療養環境を用意する必要があると思います。


幅広く連携し精神医療を変革すべき時代
チーム医療と地域との連携プレイ
荒田 地域における医療機関の役割も変化しつつあります。東京都内では,心療内科も含めて精神科クリニックは400ぐらいできているんです。生活の場の近くで精神科的対応を求めたり,相談することが可能になってきています。ですから,病院の役割が,以前のように隔離収容ではなくて,病状に振り回されていてしんどいときに一休みして,また社会に戻っていく場に大きく変わりつつあると思います。一方で,大きな問題は合併症の患者さんが非常に増えてきていることです。年をとられることで,高血圧や糖尿病,心疾患等を合併されても精神病院にいるということや,精神障害者であるということだけの理由で,なかなか一般科で診てもらえない現状があるのです。
あるいは一般病院に入院されても,病棟で大きな声を出されるなどのトラブルや入院費の支払いの問題,家族がいない単身者の方が手術をなさる場合に,その手術をする同意書を誰がするかというようなさまざまな問題が起こってきます。
PSWのいる単科の精神病院と提携を結んで,合併症の患者さんを診てくださる病院がもっと増える必要があります。私たちも一般病院と精神病院のお互いの合併症の患者さんたちの治療をうまく進められるように調整をする役割を果たしていきたいと思います。
―― 最後に今後チームを組んでいく医療職の方々へのメッセージをお願いします。
荒田 ある程度の数のPSWが配置されるまでは,有効な役割が果たせるかどうか正直自信がありません。定着するまで長い目で見ていただきたいというのが本音です。
しかし,私たちも精一杯がんばりますから,チーム医療の一員として温かく迎えていただいて,社会生活を支え,生活の視点で見るPSWの役割を認めていただければと思っております。
今までも,退院援助の他,社会復帰施設,小規模共同作業所など地域の受け皿をつくるお手伝いも,医師,保健婦,家族の方たちとチームを組みながらやってきました。「チーム医療」と「地域との連携」は,これからの精神医療の必要不可欠な課題です。
精神医療はものすごい勢いで変革の時代を迎えています。日本経済における福祉・医療そのものが狭められてきている状況の中で,精神医療も変革を求められています。病院に入院していればいいという状況から,地域に生活を準備し,援助していく方向にシフトしていかなければなりません。長い目で見てくださいと言いながら,私たちの期待されている役割は目の前にあるのです。この5年,10年間で,わが国で精神保健福祉士が本当に必要かどうか試されてしまうという厳しい状況でもあります。
(了)