米国臨床留学研修のすすめ
寄稿 津田 武 米国財団法人野口医学研究所常務理事“Nothing is easy”
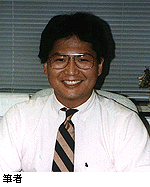 今,私がアメリカで何をしているのかということから述べようと思う。「アメリカ臨床留学の道」(照屋 純編;メディカル・サイエンス・インターナショナル社)という本の中の1章を執筆していたときには,7年間のJ-1ビザが今年(1997年)の6月一杯で切れる予定で,最悪の場合は日本へ帰らなければならない事態も考えられた。当然日本での職はない。
今,私がアメリカで何をしているのかということから述べようと思う。「アメリカ臨床留学の道」(照屋 純編;メディカル・サイエンス・インターナショナル社)という本の中の1章を執筆していたときには,7年間のJ-1ビザが今年(1997年)の6月一杯で切れる予定で,最悪の場合は日本へ帰らなければならない事態も考えられた。当然日本での職はない。
私としては,フィラデルフィア小児病院のCardiologyのフェローの2年目から始めた心臓発生に関する基礎研究がおもしろくなり,ぜひともこのままアメリカに残って基礎研究を続けたかった。今年は,幸いAmerican Heart AssociationからResearch Grantも得て,ますます研究に没頭しようとしていた矢先だったので,このビザの制約は目の前に立ちはだかる大きな難関であった。ECFMGを訪ねたところ,これ以上面倒は見られないので基礎研究を続けたいのなら自分で弁護士を雇って新しいビザを申請するように言われた。
フィラデルフィア小児病院等での計6年間の臨床研修で,一般小児科学,小児循環器科の専門書に出てくるような疾患はほとんどすべて経験した。教科書にでてくるような複雑心奇形の初期診断・治療は言うに及ばず,左心低形成症候群のThree Stage Reconstructive Surgery,WPW症候群等のCatheter Ablasion,心臓移植・肺移植・心肺移植も何例か術後CICU(Cardiac Intensive Care Unit)で直接管理する機会が持てた。先天性心疾患に対して現在人類が利用可能な治療法は,ほとんどすべて直に経験したと思う。
基礎医学の重要性を痛感
それでも,1997年現在,先天性心疾患の病因は,まだまったく解明されていないのである。心臓移植にしても,先天性心疾患に対する最終的な回答と呼ぶにはほど遠く,現地点では循環動態の異常を医原的免疫異常とトレードしたに過ぎないと言える。60歳の拡張型心筋症の患者に心臓移植するのと,新生児・乳児への心臓移植とではまったく意味が違うのである。小児科医の最大の存在意義は,子どもたちの正常な成長Growthと発達Developnentをさまざまなを病気(急性,慢性;先天性,後天性)から守ることである。ただ病気を治せばよいのではない。内科医が,人間の加齢・老化現象の中で病気を扱うのと対照的である。免疫抑制剤の成長と発達に与える長期的影響がまだ十分に解明されていない現在,小児領域における移植医療はまだ実験的医学の領域を出ない。誤解のないように言うが,私は小児領域における移植医療は意味がないと言っているのではない。移植医療が安全に行なわれるためには,まだまだ多くの研究が必要であると言っているのである。Pediatricsとは,一言で言えば,「成長と発達の科学Science of Growth and Development」である。加齢・老化を扱う内科学とは基本的には別個の学問なのであり,内科学とは一味違う実にダイナミックで魅力あふれる医学領域なのである。これは,アメリカでは常識の概念であり,われわれ小児科医以外に一体誰がこの生命現象の謎を解明できるというのであろうか。解明しなければならない問題が,この領域ではまだまだ残っている。小児科学が内科学に比べて,依然Second Class Citizenとしての扱いしか受けていない日本の現状を非常に情けなく思う。
何はともあれ私は,6年間のアメリカの臨床研修の後,意外にも臨床医学を支えるべき基礎医学の重要性を痛感するに至り,大胆にも先天性心疾患の病因解明のための何らかの端緒を見つけ出したいと思った。現在は専ら早期心臓発生における細胞生物学的ならびに分子生物学的な研究に没頭している。そんな熱い思いがINS(米国移民局)に通じたのか,はたまた弁護士の腕が良かったのか,2year ruleに束縛されることなくO-1ビザがJ-1に引き続き発給され,研究の中断は免れた。O-1ビザとは,教育,科学,芸術,スポーツ,ビジネス等の分野において特に秀でた能力が認められ,その人が滞在することでアメリカ合衆国が何らかの利益を得ると考えられた場合に与えられるビザ(Outstandingの“O”)である。このビザは,最長3年間まで延長可能であるが,要はこの間に永住権(Green Card)が取れるか取れないかが次の問題となってくる。NIH等のMajorなGrant申請のためには,永住権が必要となる場合が多い。
1989年に渡米して以来,一難去ってまた一難,次々と立ちはだかる難題を目の前にしている。アメリカでの滞在が長くなれば長くなるほど,誰もがこういった問題に直面する。“Nothing is easy”である。
これまでの臨床研修の反省
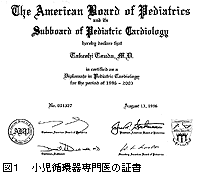 1996年6月,フィラデルフィア小児病院での3年間のCardiologyのフェロー研修を終え,8月には2つ目の専門医試験に合格して,アメリカでBoard Certified Pediatrician(小児科専門医)の他に,堂々とBoard Certified Pediatric Cardiologist(小児循環器専門医)と名乗れるようになった(図1)。アメリカでは,あらゆる分科専門医Subspecialistは,小児科に限らずまず3年間のGeneralな研修(レジデント研修:ただし外科は5年から7年)を終了し,そのBoardと呼ばれる専門医試験を合格して初めてSubspeciality Boardの受験資格が与えられる。アメリカで臨床研修を始める前は,レジデントとフェローと両方を終了すればどんなにえらい臨床医になれるのだろうかとものすごい期待をしてアメリカに乗り込んで来たが,終わって見ればこんなものである。正直に言って,特に自分が格別偉くなったとは思えない。知識の量など知れたものである。医師として一番大切なことは,相対的な知識の量ではない。医師として正しい判断ができるということである。教科書や最新の専門誌に書かれている知識が必ずしも正しいとは限らない。どうしてその記載が正しいのか理解できて,初めてその知識が意味のあるものとなる。
1996年6月,フィラデルフィア小児病院での3年間のCardiologyのフェロー研修を終え,8月には2つ目の専門医試験に合格して,アメリカでBoard Certified Pediatrician(小児科専門医)の他に,堂々とBoard Certified Pediatric Cardiologist(小児循環器専門医)と名乗れるようになった(図1)。アメリカでは,あらゆる分科専門医Subspecialistは,小児科に限らずまず3年間のGeneralな研修(レジデント研修:ただし外科は5年から7年)を終了し,そのBoardと呼ばれる専門医試験を合格して初めてSubspeciality Boardの受験資格が与えられる。アメリカで臨床研修を始める前は,レジデントとフェローと両方を終了すればどんなにえらい臨床医になれるのだろうかとものすごい期待をしてアメリカに乗り込んで来たが,終わって見ればこんなものである。正直に言って,特に自分が格別偉くなったとは思えない。知識の量など知れたものである。医師として一番大切なことは,相対的な知識の量ではない。医師として正しい判断ができるということである。教科書や最新の専門誌に書かれている知識が必ずしも正しいとは限らない。どうしてその記載が正しいのか理解できて,初めてその知識が意味のあるものとなる。
アメリカでの6年間の臨床研修で私が最も鍛えられたのは,一言で言えば問題解決能力の錬磨である。もっと詳しく言うと問題解決能力とは,まず(1)基本たる病態生理を理解し,(2)臨床における論理を組み立て,そして(3)自分の行なった医療行為の是否を判断できることである。そのためには基本の繰り返しが常に重視された。
Boardそれ自体は,学生時代の東日本医科学生体育大会(東医体)の金メダルのようなものである。(1981年,駒沢での東医体で信州大医学部サッカー部は5年ぶりの7回目の優勝を果たした。引き続き同年秋,慈恵医大国領グランドで行なわれた全日本医科学生体育大会王座決定戦でも決勝で宿敵広島大を破り,同じく5年ぶりで日本一に返り咲いた)医学生時代に学んだ最大の教訓,それは,「勝つことは大切である。しかし本当に大切なのは勝つまでの努力の過程である」と。わがサッカー部では,皆卒業のときにこの言葉を後輩たちに贈って卒業していく。あと2年たらずで40に手が届きそうになった今も,不思議とあの時と同じ感慨を彷彿とさせる。
私にとっての最大の財産は,アメリカでの臨床研修を生き抜いたという事実である。その中で得られた数少ない勝利は,次の闘いへの勇気と自信になっていく。これは,なにも特別なことではないであろう。人間として生きるために誰もがしなければならない闘いを,たまたま私も1人太平洋の向こうでしているにすぎない。Boardも東医体の金メダルも,私にとってそれらは存在するだけで十分なのである。
|
なぜアメリカへ臨床留学するのか
日本の医学教育向上のための提言
この6年にわたるアメリカでの臨床研修生活(レジデント・フェロー)で学んだものは,先端の知識や日本ではまだ行なわれていない手技やそのノウハウ(外見・現象)でなく,なぜそういった進んだ医学・医療が生まれて来たのかという必然性・哲学・文化(中身・精神)である。内科・小児科における基本とは,まず患者を目の前にした時の病態生理を理解する能力である。言い換えれば,何が問題であるのかを理解する力である。どんな最新の知識でも,基本となる病態生理の理解なくしては問題解決のための力となり得ない。ここが,日本の医学教育の中でまず第1に欠落していると思われる領域である。病態生理を理解することにより,初めて意味のある病歴聴取(History Taking),身体所見(Physical Examination)を取ることができる。日本の卒前教育でも卒後教育でも,病態生理の理解の基づいたHistory & Physical Examinationの取り方をしっかり教えているところは,ほとんどないようである(これは,私自身の経験から生まれた偏見ではなく,アメリカ臨床留学を希望する多くの医学生,研修医と話して知った事実である)。一番の問題は,この事実を事実として認識していない指導医が多いということ,また認識していてもアメリカの臨床指導医がするような教育ができる人材が日本には極めて少ないということである。
病態生理はある程度理解できた。問題解決のために次に大切なのは,物事を論理的に筋道を立てて自分の意見としてまとめる力である。同じ症状・兆候の中でも,何がprimaryで,何がsecondaryであるのかを病態生理の立場から理解し整理できなくてはならない。相矛盾する2つの事実がある時は,なぜそれらが矛盾するのか説明できなくてはならない。どちらか一方の事実が誤っているのか,自分の論理が誤っているのか証明できなくてはならない。1つひとつのステップが理路整然と説明できない限り,次のステップには進めない。臨床検査も,これらの筋道を助けるために存在するものなのである。もっとも,患者の容態が差し迫っている時は,時間を考えて要領よくこれらの考えを進めていかなければならない。数多くの事象の中から何が一番大切なのか,その次に大切なのは何なのかという優先順位(Priority)は,常に頭の中に整理しておく必要がある。このプロセスが研修医時代に優れた指導医にしっかりトレーニングされていないといわゆる自己流になってしまう。いったん身についた自己流は,修正するのに時間がかかる。私自身もこのために相当な苦労をした。
自らの医療行為を評価する勇気
最後に大切なのは,自分が医師として患者に施した医療行為が本当に意味があったのかということを厳しく評価(evaluation)できることである。ただ心の中で評価するだけでなく,すべての医師は,医師としての良心と倫理観に基づいてその評価を勇気を持ってはっきりとした形で公表する義務と責任が求められる。本来そのために学会というものが存在するのである。日本の医療の中でなぜこういったものが今なお依然として存在しているのかと疑問に思うことが数多くある。
例えば,神経芽細胞腫のマス・スクリーニングは,世界中で日本だけ依然として行なわれていると言われる。私は,Oncologyの専門家ではないが,多くのアメリカでのoncologistらと同様この検査はまったく意味がなく無駄な検査だと考えている。意味のない検査に意味づけをするという点で,ただ無駄なのではなく有害であるとも言える。
またアメリカの小児科医で喘息の大発作時に,テオフィリンの点滴静注をする小児科医はまずいない。この治療法は,フィラデルフィア小児病院でも私が2年目のレジデントの時まで頻繁に使われた治療方法であったが,Doubleblind studyでテオフィリンが喘息患者の入院期間短縮にまったく影響を与えていないと報告されてから,大学病院でも市中病院でも以後一切用いられなくなった。喘息の発作は,ごく一部の重症例を除いてβ2agonist(albuterol)の吸入とステロイドで十分管理できる。
さらに日本では,誰もが疑っていないソリタの第1液(T-1),3液(T-3)という輸液方法は,厳密な輸液の理論からすれば必ずしも正しいとは言えない。特に成長期の小児の骨の成長著しい時期には,T-3(維持液)のナトリウム含有量は少なすぎる。NPO(経口不可)の状態でT-3(維持液)で輸液を維持すれば,10歳以上の児では,翌日血清ナトリウムは下がっていることが多い。成長期における1日のナトリウム必要摂取量から計算すれば答えは明らかである。こんな例はあげればきりがない。
日本では,いったん始まってしまって確立された医療は,後に意味がないとわかっても,なぜ修正したり止めることができないのであろうか。結局は責任の所在が明確でないために,物事の軌道修正が著しく遅れてしまうのであろう。医師が自分の医療行為の批判的評価ができなくて,誰がすればよいのであろうか。医療行為の結果の正当な評価・批判は,研修医時代にぜひとも学ばなければならない,医師として最低限必要な能力である。自分の行なった医療行為の善悪の判断・意味づけを責任を持ってできない者たちが,どうやってこの先臓器移植や遺伝子医療,胎児医療などの先進医療を取り入れていけるというのであろうか。
無意味なものを廃止する勇気
また必要のなくなった無意味な医療は,再評価し必要なら廃止する勇気を持つべきである。そのために科学Scienceが存在する。医師として最も大切な能力は,倫理観Ethicsと科学Scienceに基づいて物事の良否を判断できる力である。こういったものは,本来なら卒前・卒後教育の中で正しく教育されるべきものである。現在の日本の医学教育の中にこういった指導項目が位置づけられているであろうか。残念ながら私は,こういった考え方を医学生時代・日本での研修医時代に学ぶことはなかった。ただ,これは医学界だけの問題ではないように思える。日本には,意味のない(あるいは時代の変化により意味を失った)法律・規制が数限りなく存在し,それらが再評価されることなく依然として存在し続ける。あの矛盾に満ちた「少年法」然りである。これらは,何も官僚や政治家たちだけの責任ではない。日本人全体の問題ではないかと思う。現代の日本人は,物事の本質を原点に帰って厳しく批判・評価する勇気を失ってしまったのであろうか。
読者の皆様で私の考えが誤っていると思う人があれば遠慮なく教えてほしい。
臨床医学留学のすすめ
最近,アメリカに臨床研修を受けたいと希望する医学生や若い研修医が増えてきている。なぜだろうか。皆,日本の現状に危機感を持ち始めてきているからではないかと推察している。私もかつてそうであった。しかし残念ながら時代は,そういう人たちにとってますます厳しくなっている。アメリカでも深刻な医師過剰時代を迎え,外国人医師のレジデント研修に対して厳しい規制が課せられるようになった。その証拠として,1つは本年7月から始まるECFMG CertificateのためのClinical Skill Assessment(CSA)の導入であり,もう1つは外国人レジデントの採用のための連邦政府の大幅な予算削減である。私がレジデントに応募した1989年に比べ,状況は明らかに難しくなって来ている。これは,動かし難い事実である。もともとECFMGを介した医学交流制度は,アメリカでの絶対的な医師不足を補うために作られた制度であり,事実1950年代から60年代にかけては外国人医師たちの存在なしではアメリカ医学界が成り立っていかなかったとまで言われている。この間,世界各国から夥しい数の医師がアメリカで臨床研修を受けることになり,多くの医師がそのままアメリカに残留した。現在,アメリカでは深刻な医師過剰時代を迎え,特に専門医のポジションはかなり厳しくなってきている。したがって医師不足解消のために作られたこの制度の歴史的役割は終了したと考えるべきである。もっとも,歴史的な意義の喪失と現実の制度の廃止との間には若干のタイムラグがあり,今はその過程にあると言えなくもない。
では,本当にこの国はこのまま安易に,海外からの医師を閉め出して鎖国状態になってしまうのであろうか。私見だが,まずそれはないと思う。なぜなら,この国の医学の水準の高さは,外国から来た医師たちの死にものぐるいの努力によるところが大きいからであり,アメリカでも多くの識者はそのことを十分認識しているはずだからである。医学の領域に限らずこの国を世界のリーダーたらしめたのは,優秀な人材が世界中から集まって,そういった人たちがひたすら頑張ったことによる。もちろん,医学の発展に第1のPriorityをおいたアメリカの国家政策も相まってのことである。1776年に建国された自由と機会均等の実験国家アメリカ合衆国が今後もこれまでどおりの発展してくためには,この国家の大原則を変えることはしないであろう。アメリカは今後も,世界中から熱意のある優秀な医師たちを必要とするであろう。もし道を誤れば,第2のソビエト連邦になりえないとも言えない。存在意義を失った制度,文明,国家が時代の波に淘汰されるのは,世界史の常識である。
対話と相互理解
アメリカへのレジデント留学は数年前に比べてかなり厳しくなったが,まったく可能性がなくなったわけではない。それどころか日米医学交流の意義は,これからますます重要になってくるであろう。一方的に技術や知識を輸入するだけの医学交流の時代は終わった。これからの医学交流のテーマは,「対話」と「相互理解」と言えよう。日本に大きな問題があるのと同じように,後述するがアメリカも大きな問題を抱えている。どの時代にもその時代の持つ困難があり,その困難を克服することがその時代に生きるエリートに課せられた宿命であると思う。そして,それが次の時代の人たちへの貴重なメッセージとなる。これからアメリカでの臨床研修をめざす人たちは,どうか勇気を持って初志を貫徹してほしい。私が君たちに送るメッセージは,1人の日本人として「日本」を思う偽らざる心の叫びである。今ほど君たちの存在が強く必要とされていることはない。そして日本の医学界の将来のために,1人でも多くの有為な若者にアメリカの医学を体験させることこそ「野口医学研究所」の存在意義と考えている。確かにアメリカの医学教育は,20世紀にアメリカが成し遂げた世界に誇れる素晴らしいシステムである。しかし現在,その素晴らしい教育システムが時代の大きな試練に立たされている。Managed Careの台頭である。
健康保険会社が次々と市中病院・大学病院を買収し,その統制の中に組み込まれた経済原理最優先の医療が行なわれ始めた。具体的には,アメリカ中のあらゆる病院でリストラの風が吹き荒れている。また,前述した個々の医師の良心と倫理観に基づいた判断は,少なからず経営の原理の影響を免れなくなった。当然のことながら,医学教育にもこのことが幾分反映されるようになった。あるHMO(健康維持機構)では,その配下の医師に1時間に10人の新患を診ることを要求している。日本で昔言われた3分間診療と五十歩百歩であり,これではよい医療ができるわけがない。
誤解してほしくないのだが,私は,Managed Care自体が悪いと言っているのではない。Managed Careは,医療費が国家予算の大きな割合を占めるに至ったアメリカ社会が生んだ必然の産物なのである。
アメリカでは多くの医療関係者が,矛盾と葛藤と価値観の目まぐるしい変動の中で今未曾有の産みの苦しみを味わっている。もしかしたら5-10年後には,何らかの新しい解答が見えてくるのかもしれない。私もアメリカの医学・医療の世界に生きる専門医の1人として,この激動の中に参加している。それが医師としての私の義務だからである。やがて何らかの解答が見つかった時,その喜びを皆と一緒に分かち合いたいと思うし,そのときはまた日本の皆様にも報告したい。考えてみれば,日本での臨床経験(5年)よりも,アメリカでのそれのほうが既に長くなっている(今年9年目)。
それは日本にいるときから始まっている
野口医学研究所では,毎年1回東京でアメリカ臨床研修のための面接選考を行なう(今年度は昨年12月14日に実施)。人を選ぶための試験ではない。この面接は,君たちにこの「医学交流」に参加する機会を与えるために行なわれるものである。そのためにはアメリカでの医学領域のプロフェッショナルとしての常識・価値観を知ることがまず第一歩である。今年は,初めての試みで前日(13日)の午後半日を使ってアメリカ臨床留学準備のためのセミナーを行なった。何が必要なのか,何を準備すれば次のステップに進めるのか,こういった内容のことを紹介した。「医学交流」は,実は君たちが日本にいる時から始まっているのである。日本人として
アメリカにどれだけ長く住んでいようと自分が日本人であり,日本人の医師であることは変えがたい事実である。そして,今になって日本での5年間の卒後臨床研修は決して無駄ではなく,私はむしろそのことを誇りに思えるようになってきた。最後に,私からこれからの若い人たちへのメッセージは,今という時代,そして次の時代に何が本当に必要なのか,真剣に考えてほしい。常に偏見のない眼で,そして勇気を持ってその問題に立ち向かってほしい。“Knock and it will be opened to you(求めよ,さらば与えられん)”である。


