第39回日本消化器病学会大会開催
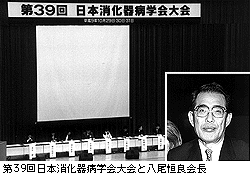 日本消化器病学会の秋季大会である第39回日本消化器病学会大会が,八尾恒良会長(福岡大筑紫病院)のもと,さる10月29-31日,福岡市のアクロス福岡,他において開催された。
日本消化器病学会の秋季大会である第39回日本消化器病学会大会が,八尾恒良会長(福岡大筑紫病院)のもと,さる10月29-31日,福岡市のアクロス福岡,他において開催された。
大会では,会長講演「Crohn病500例の臨床像」,特別講演(1)「犬山シンポジウム-30年の歩み」(新潟大名誉教授 市田文弘氏),(2)「世界的視野からみた早期大腸癌の問題点」(新潟大 渡辺英伸氏),(3)「膵胆道疾患のMRCP診断」(順大 有山襄氏),そして招待講演(1)「Hepatic Fibrogenesis」(カリフォルニア大 D.M.Bissell氏),(2)「Inflammatory Bowel Disease-Susceptibility Gene and Clinical Patterns」(オックスフォード大 D. P. Jewell氏),(3)「Medical Therapy of Inflammatory Bowel Disease;From Evolution to Revolution」(シカゴ大 S.B.Hanauer氏)の他,宿題講演,シンポジウム4題,パネルディスカッション5題,ワークショップ8題が企画された。


シンポジウム「H.p 除菌後の消化性潰瘍の臨床経過」
H.p 感染と消化性潰瘍
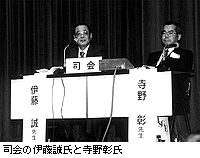 1983年にWarrenとMarshallによってHelicobacter pylori(以下=H.p)が分離・培養されてから15年たった今年は,ヨーロッパ(Maastricht Consensus)とアメリカ(DDW)が相次いで治療ガイドラインを発表,8月にはその全遺伝子が解読され,H.p 感染症治療に向けて節目の年になったと言えよう。しかしその反面,H.p 感染から潰瘍の発生に至る機序の詳細については不明な点が多く,またH.p に感染していない(陰性)消化性潰瘍患者や,H.p を除菌した後に再発する消化性潰瘍が存在することも事実である。
1983年にWarrenとMarshallによってHelicobacter pylori(以下=H.p)が分離・培養されてから15年たった今年は,ヨーロッパ(Maastricht Consensus)とアメリカ(DDW)が相次いで治療ガイドラインを発表,8月にはその全遺伝子が解読され,H.p 感染症治療に向けて節目の年になったと言えよう。しかしその反面,H.p 感染から潰瘍の発生に至る機序の詳細については不明な点が多く,またH.p に感染していない(陰性)消化性潰瘍患者や,H.p を除菌した後に再発する消化性潰瘍が存在することも事実である。
榊信廣氏(都立駒込病院)は,その編著『ヘリコバクター・ピロリ除菌治療ハンドブック』(医学書院刊)の中で,「消化性潰瘍をめぐる問題は何もH.p ばかりではないが,臨床の場において,特に治療に関してはH.p の重要性がますます認識されてきている。そのような現在,病態生理面の不明確さや矛盾を議論していくだけでなく,優れた除菌法を早急に確立して,除菌治療を開始する時期にきていると思われる」と述べているが,そうした背景を反映して今学会では,シンポジウム「H.p 除菌後の消化性潰瘍の臨床経過」(司会=名市大 伊藤誠氏,獨協医大 寺野彰氏)が企画され,9名のシンポジストが討議に参加した。また,フロアを交えたシンポジスト相互の討論の後,「日本消化器病学会H.p 治験検討委員会」の委員長である下山孝氏(兵庫医大)が特別発言に指名されてシンポジウムを締めくくった。
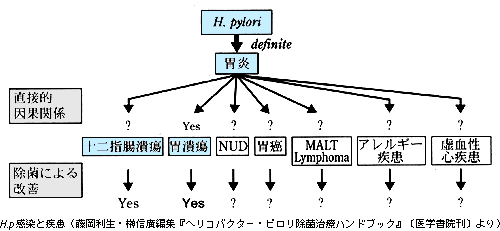
顕著な除菌治療効果
まず木平健氏(自治医大)は,胃潰瘍および十二指腸潰瘍におけるH.p 除菌治療後約3年にわたる再発例の実態や要因,除菌後のfollow-up法,疾患別差異について検討した結果,「今後,H.p 陽性の消化性潰瘍を取り扱うにあたって,除菌成功例には維持療法が必要なく,除菌不成功例には,速やかに菌の感受性を検討した上で,再度除菌治療に踏み切るべきであると考える」と報告した。さらに,「H.p 陽性の十二指腸潰瘍に除菌治療を行なうと潰瘍の治癒の質(QOUH:Quality of ulcer healing)を向上させ,潰瘍の再発が抑制されることが示唆される」(福岡大 城谷拓郎氏),また「H.p 感染は十二指腸潰瘍では主たる発生因子であり,再感染があると易再発性につながるが,胃潰瘍症例においては再増悪または再感染によっても直接潰瘍再発にはつながらず,潰瘍治癒過程では除菌による潰瘍瘢痕の質の改善も再発防止に有用であることが示唆される」(兵庫医大 澤田幸男氏)との報告が続いた。
組織学的および薬剤耐性菌からの検討
一方,根引浩子氏(大阪市立総合医療センター)は,NSAIDs(non-steroidal anti-inflammatory drugs;非ステロイド性抗炎症薬)使用例を除外した症例に対する除菌後の再発・非再発胃潰瘍について,(1)除菌成功再発群,(2)除菌成功非再発群,(3)除菌不成功再発群,(4)除菌不成功非再発群,(5)非除菌再発群,(6)非除菌非再発群,に分けて組織学的に検討。その結果,除菌成功群では,その後の再発の有無にかかわらず,除菌後の潰瘍瘢痕の好中球浸潤は消失していたが,(2)は(1)よりも除菌前の潰瘍辺縁の好中球浸潤が有意に少なく,これらの症例の潰瘍形成にH.p 以外の因子が関与している可能性が示唆され,(3)は(4)よりも除菌治療後の瘢痕部好中球浸潤が有意に多いことから,「胃潰瘍の再発には,H.p が除菌できたか否かのみでなく,H.p 感染に伴う炎症細胞浸潤の程度やH.p 以外の因子の関与もあると考えられた」と発表した。また,高橋信一氏(杏林大)は前掲書の中の「ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の実際-私の除菌方法(1)」において,(1)mono therapy,(2)dual therapy(常用量),(3)dual therapy(倍量),(4)triple therapyの除菌療法の成績を報告しているが,このシンポジウムでも薬剤耐性菌からH.p 感染症の除菌法を検討し,「(1)H.p のより適切な除菌法には,治療前の薬剤感受性試験が必要であり,(2)耐性菌出現の予防のためにより強力な除菌法が要求され,(3)二次療法の薬剤選択には薬剤感受性試験が不可欠である」と報告した。
H.p 除菌治療の功罪
加藤元嗣氏(北大)は,「H.p の除菌治療の意義についてはかなり明確になってきたが,一方では除菌治療後に生じてくる病態についても注目されており,除菌治療の功罪が問われる時代になってきた」と述べて,除菌判定には組織,培養,尿素呼気試験,迅速ウレアーゼ試験のうち2つ以上を施行し,経過中いずれも陰性が持続した場合を除菌成功として,除菌後に発生する上部消化管の疾患について検討した。加藤氏らが対象とした除菌成功例のうち,消化性潰瘍の再発が認められた症例は2.3%で,その80%が胃潰瘍であり,さらにその50%がNSAIDsの短期間使用で同部位に再発を来たしたものである。また,除菌後に生じた急性の十二指腸びらんは除菌治療施行例の約8.1%に,逆流性食道炎は約3.8%に認められ,両者を経時的に検討した結果,H.p 除菌後にみられる両者の発生機序は異なることが推測されることから,「H.p 除菌治療を施行するにあたっては,上部消化管疾患については,急性十二指腸びらんや逆流性食道炎の発生,またNSAIDsの使用に対する注意が必要である」と強調した。


シンポジウム「ミリサイズ肝細胞癌診断へのアプローチ」
 胃癌や食道癌などの管腔臓器の癌では,深達度から「早期癌」の定義がある。一方,実質臓器である肝細胞癌には早期癌という明確な定義はないが,日本癌研究会では,切除または剖検時に得られた最大径2cm以下の単発した肝癌を「細小肝癌」(small liver cancer)と定義し,この細小肝癌という概念が早期肝細胞癌として意識されながら臨床的に用いられている。
胃癌や食道癌などの管腔臓器の癌では,深達度から「早期癌」の定義がある。一方,実質臓器である肝細胞癌には早期癌という明確な定義はないが,日本癌研究会では,切除または剖検時に得られた最大径2cm以下の単発した肝癌を「細小肝癌」(small liver cancer)と定義し,この細小肝癌という概念が早期肝細胞癌として意識されながら臨床的に用いられている。
シンポジウム「ミリサイズ肝細胞癌診断へのアプローチ」(司会=筑波大 板井悠二氏,山口大 沖田極氏)では,肝細胞癌の早期発見と早期治療として注目を浴びている細小肝癌の診断が取り上げられた。
その病理形態学的特徴
細小肝細胞癌の中でも高分化型肝細胞癌(well-differentiated hepatocelluler carcinoma)は境界不明瞭なものが多く,これらは肉眼分類では「境界不明瞭型」として分類される。中島収氏(久留米大)は,腫瘍径別(5~10mm, 11~15mm, 16~20mmの3群),および肉眼型別(境界不明型と境界明瞭型の2群)に肝癌の病理形態学的特徴について検討し,「境界不明瞭型肝癌は,(1)早期肝癌に相当し,ミリサイズ肝癌の特徴的な肉眼像とみなされる,(2)高頻度に脂肪化をともなうために,脂肪を反映する画像所見に注意を要する,(3)血管造影や腹部CTで描出されにくい理由は明瞭な被膜がなく,動脈性腫瘍血管に乏しく,結節内に種々の程度に門脈を含み,増殖先端部は置換性増殖を示す高分化型肝癌で構成されるためである」とまとめた。
各種の画像診断法を検討
続いて,細小肝癌に対する各種の診断方法の検討が発表された。まず戸原恵二氏(福岡大筑紫病院)は,非侵襲的なUS-D(超音波ドプラ)とD-MRI(Dynamic MRI)で約半数が質的診断ができ,侵襲的なDSA(血管造影)やCO2-US(CO2-microbubblerを肝動脈へ注入する造影エコー)を追加しても新たに質的診断される結節は1結節のみであることから,「US-DやD-MRIで細小肝癌と診断されない結節には,侵襲的なDSAやCO2-USを省略し,腫瘍生検を行なうことが効率のよい診断手順である」と報告。
また黒川典枝氏(山口大)は,10mm以下の肝癌はUS, CT, MRIでは鑑別診断が困難であり,血管造影が最も特異性の高い画像診断法であるが感受性に劣り,かつ侵襲性を考慮すれば腫瘍生検が最も効率的な診断方法であると報告。さらに東克謙氏(名大)は,US, CT, MRI,血管造影の画像所見と組織所見を比較検討し,10mm以下の群の55%,11mm~20mm群の33%は画像所見のみでは診断が困難であることから,腫瘍生検の必要性を指摘。杉岡篤氏(藤田保衛大)は,AHCT(Dual phase angio-helical CT)は最も診断能力の高い画像診断法であり,特に肝切除の治療効果の高い症例および結節に対して診断能力が高いことを報告した。
腫瘍マーカーによる診断
AFP(α-fetoprotein)は,PIVKA(protein induced by vitamin K antagonist)-IIと並ぶ肝細胞癌の腫瘍マーカーで,AFPは約70%に,PIVKA-IIは約50%以上に高価を示す。また,前者は陽性率は高いが疾患特異性が低く,後者は陽性率が低いが疾患特異性が高いとされているが,最近の画像診断の進歩・普及は相対的に腫瘍マーカーの診断面での意義を後退させるとともに,診断可能になった細小肝癌ではAFP価の上昇していない症例が増加している。松村雅幸氏(朝日生命成人病研)は,これを克服するために,血中AFPmRNAを検出して検討し,「流血中の肝癌細胞の存在を示す指標としてのAFPmRNAの検出は,細小肝細胞癌の補助診断としての可能性を秘めていることを示唆する」と報告した。また小峰文彦氏(日大)は,腫瘍生検による病理組織的な診断およびテロメラーゼ活性測定の有用性を指摘した。
