第33回国際生理科学連合会議に参加して
桑木共之(千葉大医学部・生理学第2)
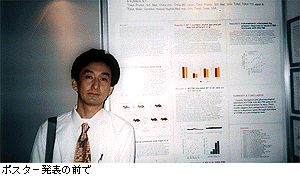 金原一郎記念医学医療振興財団第11回研究交流助成金(1996年度)を得て,6月30日から7月5日まで,ロシアのサンクトペテルブルグ(旧レニングラード)で開催された標記学会に参加した。本学会は1889年の第1回会議から実に100年以上の歴史を誇り,アジア,アフリカのいわゆる開発途上国からも多くの参加者が集う,まさに国際の名にふさわしい会議で,最近は4年に1度開催されている。今回は,「統合生理学:分子からヒトへ」という標語の下,11題の特別講演,それぞれが4-10人のシンポジストの口頭発表からなる100題以上のシンポジウムと,2000題以上のポスター発表が行なわれた。日本から特別講演に選ばれた京都大学の中西重忠氏は,脳のグルタミン酸レセプターの役割について最新のレビューを行なった。
金原一郎記念医学医療振興財団第11回研究交流助成金(1996年度)を得て,6月30日から7月5日まで,ロシアのサンクトペテルブルグ(旧レニングラード)で開催された標記学会に参加した。本学会は1889年の第1回会議から実に100年以上の歴史を誇り,アジア,アフリカのいわゆる開発途上国からも多くの参加者が集う,まさに国際の名にふさわしい会議で,最近は4年に1度開催されている。今回は,「統合生理学:分子からヒトへ」という標語の下,11題の特別講演,それぞれが4-10人のシンポジストの口頭発表からなる100題以上のシンポジウムと,2000題以上のポスター発表が行なわれた。日本から特別講演に選ばれた京都大学の中西重忠氏は,脳のグルタミン酸レセプターの役割について最新のレビューを行なった。
サンクトペテルブルグの夏
会場となった陸軍軍医学校は市の中心を流れるネバ川に面し,帝政ロシア時代の宮殿の一部であり,今では美術館として有名なエルミタージュの対岸に位置する。残念ながら私は訪問する機会に恵まれなかったが,条件反射の発見で有名なパブロフの研究所は,会場からバスで1時間の距離にあり,見学ツアーが企画されていた。さて,サンクトペテルブルグに到着してまず最初に驚かされたのは,綿のようなポプラの花が,吹雪のように街中飛び交っていることであった。今年は夏の訪れが遅く,6月中旬になってやっと暖かくなり,一斉に飛び始めたとのことだった。花粉症で悩む人が増えために,最近では順次,菩提樹に植え替えており,ロシア人も鼻を押さえて歩いていた。 次に印象深かったのは,社会の安定と人々の活気だった。確かに旧西側諸国に比べれば商店に物は少なく,旅行者には見えない部分も多くあろうが,人々は陽気で親切であり,自由を楽しみ,将来の発展の希望に満ちているように見えた。また,3時間しか陽の沈まない白夜のおかげで,夜の危険も存在しようがなかった。
生理科学はあまりにも広い分野をカバーしているために,以下の発表内容の紹介は著者の専門分野に限局していることをご容赦願いたい。
動脈化学受容器による低酸素検出機構の調節
一酸化窒素(NO)と一酸化炭素(CO)が動脈化学感受性を修飾するという,ケースウエスタンリザーブ大のN. R. Prabhakar氏の発表があった。頸動脈小体の神経線維には神経型NO合成酵素(nNOS)が存在し,NO産生量は酸素分圧に比例する。タイプII細胞にはCO合成酵素であるheme oxygenase(HO)-2が存在する。また,NOとCOは頸動脈小体による酸素検出を抑制し,nNOS阻害剤のL-NMMAは増進させる。そこで彼らは,ウサギの頸動脈小体から単離したタイプI細胞にNOドナーを与えて細胞内カルシウムを測定したところ,70%の細胞で減少が,30%で増加がみられた。阻害剤を用いた実験から,細胞内カルシウムの減少は,NOがguanylate cyclseを活性化した結果であると考えられた。一方,HO-2の阻害剤のZnPP-9は細胞内ストア由来のカルシウムを増加させた。さらに,nNOSノックアウトマウスの横隔神経活動の酸素感受性は,野生型マウスに比べて増大していた。これらの結果から,NOとCOは,頸動脈小体における酸素検出能を抑制的に修飾していると結論された。中枢性呼吸調節
低酸素に関する情報は中枢神経でも検出されている。特に,動脈化学受容器が十分に発達していない新生児では,これが唯一の酸素センサーといってよい。一般にほとんどの神経細胞は低酸素で抑制されるので,エネルギーの節約を図る合目的的反応と考えられているが,ごく一部の神経は反対に興奮することによって酸素センサーの役割を果たしている。ニュージャージー医大のJ. A. Neubauer氏は,この中枢神経の酸素感受性について講演した。低酸素で興奮する神経細胞は,吻側延髄腹外側部(Rostral ventrolateral medula: RVLM),橋,視床下部などに見いだされているが,彼女はRVLMに注目した。その理由は以下の2点である。1)個体レベルで低酸素刺激を長時間与えると,横隔神経活動は一過性の増大の後,抑制・消失に至るが,さらに低酸素刺激を続けているとあえぎ呼吸(gasping)と呼ばれる特徴的な発火パターンを示すようになる。RVLMのpre-Botzinger neuronにNaCNまたはホモバニリン酸を投与すると,同様にパターン変化を引き起こすことができる。すなわち,RVLMはgasping centerと考えられる。
2)コーネル大のSun,Reis両氏によって,RVLMのsympathoexcitatory vasomotor neuronが低酸素刺激で興奮することが示されている。
そこで彼女は,in vitroの実験系として,ラット新生児のRVLM neuronのprimary cultureを用いて,そのNaCN感受性を調べた。その結果,60%のニューロンが発火頻度を増大させ,40%のニューロンは抑制された。反応の異なるこれら2種のニューロン間の差異は,形態や遺伝子発現(後述)に関して,今のところ見いだされていない。さらに,酸素感受性に関与する分子種を同定する目的で,HOの遺伝子発現について調べた。HO-2はRVLMを含むいくつかの脳部位に常に発現していたが,HO-1は慢性に低酸素に暴露してはじめて,RVLMに発現が誘導された。以上の結果から,RVLMの一部のニューロンは中枢による低酸素検出機構に関与しており,通常はHO-2が,慢性低酸素ではHO-1がその役割を担っていると推測された。
動脈圧受容器による血圧の検出機構とその調節
血圧という物理量が神経活動という生化学過程に変換されるメカニズムはまだ完全には解明されていない。一般に,壁の伸展により活性化される陽イオンチャンネルを介してナトリウムまたはカルシウムが細胞内に流入することによって興奮が始まるとされているが,その機械刺激感受性チャンネルの実体は明らかでない。アイオワ大のF. M. Abboud氏はこの候補分子を同定した。線虫の機械刺激受容に必須の蛋白質であるdegenerinは,哺乳動物の上皮細胞ナトリウムチャンネル(epithelial sodium channel: ENaC)および脳ナトリウムチャンネル(BNC)-1aと高い相同性を持つ。そこで,このENaCスーパーファミリー分子がラット動脈圧受容器の本体ではないかとの仮説を検証した。まず,大動脈神経の細胞体が存在する節状神経節に,ENaCとBNC-1aのmRNAが発現していることをRT-PCRで確認した。次に,抗ENaC抗体を用いて,ENaCが大動脈弓の大動脈神経終末と,培養大動脈神経細胞に存在することを確認した。培養大動脈神経細胞は,トレーサー色素のDiIを大動脈弓部に投与してから数日後に取り出した節状神経節から,色素でマークされたものを選び出すことによって得た。また,培養大動脈神経細胞にピペットから液を吹きかけることによって機械刺激を与えると,細胞内カルシウムが上昇した。細胞内カルシウム上昇反応は,ENaCの阻害剤であるAmilorideや,植物細胞の機械刺激感受性チャンネルの阻害剤であるGadoliniumで抑制された。これらの結果から,彼は大動脈神経の機械刺激感受性チャンネルは,ENaC/BNC-1aファミリーに属する蛋白であろうと結論した。
同じくアイオワ大のM. W. Chapleau氏は,プロスタサイクリン(PGI2)およびNOが,同様に単離した培養大動脈神経細胞の機械刺激感受性活動を修飾することを報告した。PGI2の安定なアナログを投与しておくと,機械刺激によって引き起こされる活動電位の回数が増加したが,これは機械刺激感受性チャンネル自体が修飾を受けたのではなく,protein kinase Aによるリン酸化によってK+チャンネルの活性が低下したからであると考えられた。一方,NOの投与は機械刺激感受性を低下させたが,これはナトリウム電流の抑制よることがパッチクランプによって明らかになった。また,NO scavengerのヘモグロビンを投与すると,ナトリウム電流は増加した。他方,NOが培養大動脈神経細胞自体で作られることがNOの定量により明らかになり,これはNOSの阻害剤で減少した。さらに,アデノウイルスをベクターとして内皮細胞型NOSを培養大動脈神経細胞に発現させると,対照のβ-Galactosidase導入細胞と比較して,機械刺激感受性が低下したことからも,NOの機械刺激感受性修飾作用が証明された。
