レポート 第2回国際地域看護学会
世界的にニーズ広がる地域看護
斉藤 恵美子 東京大学 地域看護学助手 狭川 庸子 東京大学 地域看護学助手 さる8月13日から15日の3日間,英国スコットランドのエジンバラ郊外,Heriot Watt大学James Wattカンファレンスセンターにおいて,第2回国際地域看護学会(2nd International Conference on Community Health Nursing Research)が開催された。「Making a Difference-using community health nursing research toward 2000 and beyond(違いを生み出す:地域看護研究を用いて,2000年とその先に向けて)」をテーマに,英国看護協会と学会企画委員会の主催により,全体集会,分科会などが繰り広げられた。
さる8月13日から15日の3日間,英国スコットランドのエジンバラ郊外,Heriot Watt大学James Wattカンファレンスセンターにおいて,第2回国際地域看護学会(2nd International Conference on Community Health Nursing Research)が開催された。「Making a Difference-using community health nursing research toward 2000 and beyond(違いを生み出す:地域看護研究を用いて,2000年とその先に向けて)」をテーマに,英国看護協会と学会企画委員会の主催により,全体集会,分科会などが繰り広げられた。
欧米を中心に世界22か国から360人余りの参加者があり,口演・示説を合わせて約270の一般演題が発表された。日本からも各地から約30名が参加し,12演題(口演3,示説9)の発表があった。日本やアメリカ,カナダからは教育・研究関係者の参加が多かったが,他国,とりわけ主催地の英国からは本学会への参加が卒後教育のポイントに換算されることもあって地域,施設内を含めた臨床家の参加も多かった。3日間の日程をとおして,6つの全体集会と3つのマスタークラス(定員40名,1テーマの小セッション),79の一般演題分科会が行なわれた。
違いを生み出すもの
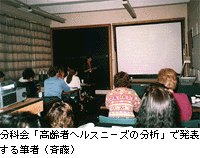 13日午前,開会式に引き続き第1回全体集会が「地域看護研究:違いを生み出す(Community health nursing research : making a difference)」をテーマに,学会の学術委員会長を務める英国バッキンガム州大学のSally Kendall教授の挨拶にはじまり,WHOヨーロッパ地域事務局,看護・母子担当Ainna Fawcett-Henesy氏による講演「欧州における地域看護活動の新しい役割の展開」と続いた。
13日午前,開会式に引き続き第1回全体集会が「地域看護研究:違いを生み出す(Community health nursing research : making a difference)」をテーマに,学会の学術委員会長を務める英国バッキンガム州大学のSally Kendall教授の挨拶にはじまり,WHOヨーロッパ地域事務局,看護・母子担当Ainna Fawcett-Henesy氏による講演「欧州における地域看護活動の新しい役割の展開」と続いた。
質と効果をめぐって
分科会をはさんでの夕刻の全体集会では「どこに違いを生み出すか(Where do we make a difference)」をテーマに,アメリカ合衆国コロラド大学学校保健部門教授Judith Igoe氏が「保健室」という場で違いを生み出すことを長年の研究成果より語り,続いてロンドン,ナイチンゲール研究所のJill Macleod教授は地域看護の質や効果を何で評価したらよいのか,どこに違いを見いだしていくことをめざすのかについての見解を述べた。翌日の第3回全体集会「どのようにして違いが生み出されていることを知りうるか(How do we know we are making a difference)」では,さまざまな視点で広範囲に行なわれている地域看護研究の結果の本質とそれをどう用いていけるのかをSally Kendall教授が,そして質的研究を通した実践と研究との関係を,コロンビア,アンチオカイア大学のCarmen de la Cuesta氏が述べた。
ディベート等で幅広い議論
 第4全体集会はディベート形式で行なわれ,立論者は「プライマリケアは看護婦によって先導されるべきである」との主張に立って見解を述べた。4人のディベート参加者の構成は,地域看護学の教授,看護協会の看護理念と実践部門の部長,健康教育局の長,医師会からの代表者であった。
第4全体集会はディベート形式で行なわれ,立論者は「プライマリケアは看護婦によって先導されるべきである」との主張に立って見解を述べた。4人のディベート参加者の構成は,地域看護学の教授,看護協会の看護理念と実践部門の部長,健康教育局の長,医師会からの代表者であった。
第5全体集会は質疑応答の時間であったが,2日目までに参加者から寄せられた質問をいくつか選び,BBC(英国放送協会)の保健医療関連の記者が司会を務め,質問・疑問に対して6人のパネルの意見も聞きながら参加者からの意見,パネルの意見を聞いての質問者の反応などを交えながら,建設的な議論がすすめられた。
最終の第6全体集会では,メインテーマに沿って英国グラスゴーカレドニアン大学のJean McIntosh教授がまとめの講演をし,最後に本学会名誉会長であるLisbeth Hockey氏が締めくくった。
研究テーマに類似性
各分科会のテーマは「病院ベースの在宅サービスの評価」,「地域看護の役割変化/倫理的問題」,「知識と態度の開発:HIV関連問題」,「多国間の視点による戦略的計画」,「質的研究:デザインの問題」,「創傷ケア向上に研究を用いる」など,多岐にわたっていた。多く取り上げられ目立っていたテーマとしては,「実践の評価」,「ヘルスニーズのアセスメント」,「実践と研究のリンク強化」,「質的研究」,「コンピュータの利用」などがあり,わが国の地域看護領域の最近のテーマと類似している印象を受けた。各研究・報告の対象としている集団は,小児,女性,高齢者,介護者,貧困層,癌患者など幅広く扱われていた。学術集会を縁取る催し物として,第1日目の夕方には歓迎レセプションがあり,スコットランドのバグパイプ演奏が披露され,参加者の歓談が進んだ。2日目には,歓迎ディナーがあり,エジンバラ市長の挨拶,バグパイプ演奏に合わせてスコットランドの民族舞踊の披露があり,参加者も踊りの輪に加わり,よい汗をかく楽しいひとときであった。
日本でも地域看護学会旗揚げ
学会は第1回目のカナダのエドモントに引き続いて,まだ第2回目ということで,現在学会の組織作りに乗り出している。日本においても本年10月15日,横浜パシフィコにて日本地域看護学会が設立総会を開き,スタートした。日本でも世界でも医療や保健のシステムの変化の中で地域看護研究へのニードが高まり,早急な対応が求められている。学会をとおして,研究活動がさらに活発化し,研究・教育と現場との交流がますます深められて,相互によい変化をもたらしていけるように,国際学会の発展と合わせて期待したい。
|
