IRMA VIII(第8回国際リハビリテーション医学会)印象記
「21世紀への架け橋」をテーマに,全世界より京都に集う
IRMA VIII(The 8th World Congress of the International Rehabilitation Medicine Association:第8回国際リハビリテーション医学会世界大会)が,上田敏組織委員会委員長のもと,さる8月31日-9月4日の間,「Across The Bridge Towards The 21st Century」をテーマに,京都市の国立京都国際会館において開催された(2259号既報)。
本号では,多彩なプログラムが企画,進行されたIRMAの印象を,シンポジウムおよび一般演題発表の座長を務めた2氏に記していただいた。


●「電気診断学1」に参加して
椿原彰夫(川崎医科大学リハビリテーション科教授)
注目を集める電気診断学
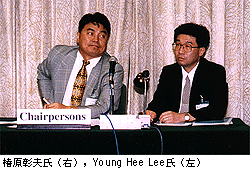 電気診断学が,リハビリテーション医学において重要な位置を占めていることはいうまでもない。リハビリテーション医療の遂行にあたっては,その科学的な診断・評価と治療効果の判定,生理学的な機序の解明などの観点から,電気診断学は欠かせないものとなっている。この理念は,欧米諸国をはじめとして国際的に受け入れられており,本学会では多くの電気診断学に関するセッションが開催された。
電気診断学が,リハビリテーション医学において重要な位置を占めていることはいうまでもない。リハビリテーション医療の遂行にあたっては,その科学的な診断・評価と治療効果の判定,生理学的な機序の解明などの観点から,電気診断学は欠かせないものとなっている。この理念は,欧米諸国をはじめとして国際的に受け入れられており,本学会では多くの電気診断学に関するセッションが開催された。
今回行なわれた電気診断学のセッションは,4つのシンポジウムと一般演題3セッションに加えて,教育講演が4題と特別講演・セミナーがそれぞれ1題であった。その他にも各疾患単位のセッションで,電気診断学を利用した報告がいくつか行なわれた。特に好評だった話題は,経頭蓋的磁気刺激による運動誘発電位の計測,運動単位の解析,末梢神経における伝導ブロックの計測などである。運動誘発電位は,脳血管障害や外傷性脳損傷などによる運動麻痺の予後を推測するには最適であり,新しい解析法として注目を浴びている。
各シンポジウムの内訳は,電気診断学のトピックスが5題,神経可塑性の臨床研究が4題,磁気刺激が3題,電気生理学的評価が4題であった。一般演題は,電気診断学が15題,筋生理学が5題であった。
質の高い発表があいつぐ
私とYoung Hee Lee氏(Yonsei大)が座長を務めた担当した一般演題「電気診断学1」のセッションでは,8演題のうち7題が日本人による発表で,他の1題は韓国からの報告であった。欧米から一般演題の参加がなかったのは,欧米の研究者の報告がシンポジウムにおいて行なわれたことにも起因している可能性がある。しかし,医療経済などの変革から,米国医療が徐々に研究しにくい体質となっていることを反映しているのかもしれない。「電気診断学1」の内容は比較的高度なものが多く,学術的な見地において質の高い報告が目立った。
近藤国嗣氏(慶大)は筋線維伝導の不応期を研究し,筋線維タイプによる差異を実証。廃用性筋萎縮の評価に利用可能であるかどうかが議論の的となった。加藤弥生氏(横市大)は,表面電極による非侵略的診断法を紹介。電極の大きさを小さくすることが有用であることを示したが,脱神経電位の記録の可能性が今後の課題となった。赤星和人氏(慶大)は,運動単位の発現様式と筋出力との関係を調べた。Hennemanによるサイズの原理をヒトにおいて明らかにした研究であり,好評であった。原行弘氏(国療村山病院)はF波を用いた運動単位数の新しい計測法によって,廃用性筋萎縮の病態解明に貢献した。
北村純一氏(日本医大)は運動関連電位を用いた片痳痺の予後予測に関する研究を報告し,臨床上における利用価値を示した。発症早期の本検査により,麻痺の良好な回復が得られるかどうかを知ることはリハビリテーション医療において有用と考えられた。鈴木俊明氏(関西鍼灸短大)は痙縮とH反射の振幅との関連を論じた。持続伸張によるH反射抑制を検討する研究であったが,有効な持続伸長の時間が話題となった。J.K.Na氏(Korea大)は,新生児の体性感覚誘発電位について報告。数少ない貴重な報告であったが,N17以下の短潜時に関する検討が今後の課題となった。私たちは,macro-EMGに使用するspike triggered averaging法を利用した筋線維伝導速度の計測について報告。他に類を見ない方法で,臨床への利用に期待が持たれた。
一般演題では活発な討議が行なわれ,海外からの参加者と演者とのやり取りのみでなく,日本人同士の質疑応答も英語で的確になされた。しかしながら,同一時間に多くのセッションが行なわれたことから,シンポジウムの参加者数が40名前後であったことはやや物足りなさを感じさせられた。
●脊髄損傷と脳外傷シンポジウムに参加して
大橋正洋(神奈川リハビリテーション病院)
 IRMA VIII(第8回国際リハビリテーション医学会世界大会)は,参加者および演題数が過去最大であり,初めてアジアで開催,そしてIFPMRと統合され新組織ISPMRとなる(2259号1面記事参照)ために,IRMAとしては最後の開催となる記憶されるべき会議とのことである。
IRMA VIII(第8回国際リハビリテーション医学会世界大会)は,参加者および演題数が過去最大であり,初めてアジアで開催,そしてIFPMRと統合され新組織ISPMRとなる(2259号1面記事参照)ために,IRMAとしては最後の開催となる記憶されるべき会議とのことである。
学会での各々の発表は,多数の会場で同時に行なわれたため,全体の様子を把握することが難しかったが,脊髄損傷と脳外傷2つのシンポジウムの様子をIRMA VIIIの一端として紹介する。
脊髄損傷治療における問題と可能性を論議
シンポジウム「脊髄損傷リハビリテーション-最近の進歩」は,スイス脊損センターDiez氏,神奈川リハ病院 大橋,米国Dittuno氏,国立リハセンター 矢野氏,横市大 水落氏の6名が発表者として登壇し,座長はDietz氏と大橋が担当した。まずDietz氏は,中枢神経損傷後の痙性不全麻痺患者に運動機能が改善する過程を,神経内科医の立場から考察した。すなわち痙性麻痺の下肢筋は,麻痺による筋力低下だけでなく,多シナプス反射の減衰による筋トーヌス低下が伴っている。そこで筋トーヌスが改善して歩行可能になるためには,大脳でなく脊髄レベルの中枢神経組織の再編成が必要と述べた。
続いて大橋は,神奈川リハセンターのリハ工学サービスが,機能訓練プログラム作成支援や福祉機器開発・製品化などを通して脊髄損傷者のQOL改善に役立っていることを報告した。
Dittuno氏は,脊髄損傷リハの第一人者にふさわしく,現状と展望を概括する興味深い報告を述べた。例えば米国では,脊髄損傷者の機能および能力改善の経過を,主要なリハセンターの協力を得て全国的なデータベースに集約している。そのデータベースが,残存最下位機能C6完全四肢麻痺者では,手背屈筋は受傷6-8週後に最大限の筋力を回復することを明らかにした。ところで米国の医療環境は,頸髄損傷のリハ治療に長期入院を許さない。そこで,このレベルの頸髄損傷者に限っては,入院リハの開始を遅らせるべきではないかと提案。これは早期リハを強調してきた従来の考え方と異なるものであり,会場から疑問も述べられた。
ところで今回のIRMAに参加した米国の会員からは,入院期間短縮に対する工夫や十分な治療ができない問題点について,リハのさまざまな疾患を対象に発言があり,米国の医療環境の激変ぶりがうかがわれた。Dittuno氏が述べたC6四肢麻痺者の問題もその一例である。
さてDittuno氏はその他に,不全両下肢麻痺者の体幹をハーネスで吊って免荷しながらレシプロカル歩行を訓練する研究を紹介した。これはDietz氏が述べた脊髄レベルの神経機能再編成のテーマと,矢野氏の下肢装具開発と訓練成果につながるコメントになった。Dittuno氏はさらに将来展望として,脊髄損傷へのさまざまな薬物治療が実用化する可能性を指摘。また米国で脊髄空洞症の治療として,他人から採取した脊髄を移植する実験が行なわれたことを紹介した。この治療の意義はまだ確定していないが,今後脊髄移植がしばしば行なわれるとすれば,リハ医学で確立された機能障害および能力障害の評価方法を用いた科学的検証を行なうべきと述べた。
一方矢野氏は,国立リハセンターにおいて完全両下肢麻痺者の新しい歩行用下肢装具が開発されたことを発表。水落氏は,大学病院で経験した非外傷性脊髄損傷患者の経過をまとめ発表した。高齢の不全麻痺が多く,リハ治療に長期を要し,機能回復や社会適応に問題を有する例が多いと指摘したが,水落氏の発表には聴衆からの質問も多かった。
多岐にわたる脳外傷リハを紹介
シンポジウム「脳外傷リハビリテーション」は3日目の午後に行なわれ,イスラエル Groswasser氏,オーストラリア Smith氏,米国 Mayer氏,英国 McLellan氏,タイ Tongpiputn氏,横市大 安藤氏の6名が発表者となり,座長はGroswasser氏と大橋が担当した。今回のIRMAでの脳外傷関連は,初日に一般演題8題,2日目にセミナー3題,教育講演2題があり,リハの分野で国際的に関心の高いテーマであることがうかがわれた。
さてシンポジウムの発表であるが,Groswasser氏はリハ病院退院時にスタッフが一般就労可能と判断した重症脳外傷患者について,実際の職業的予後の調査結果を報告した。就労困難であった患者は,脳振盪患者でよく見られるような眩暈,不眠,混雑した場所での疲労などを共通の症候として示したと発表した。
Smith氏は,オーストラリアの一地域のさまざまな脳外傷プログラムを現地調査し,地域資源が適切に活用されていることを述べた。Mayer氏は,脳損傷者の麻痺手に対する手術や神経ブロックなどの効果を,ビデオによって示した。McLellan氏は,脳外傷患者の家族が,患者の行動や認知機能の変化を受け入れられずに苦労していると指摘し,脳外傷リハプログラムの一環として家族へのアプローチが重要であると述べた。Tongpiputn氏は,脳外傷患者の急性期のGlasgow Coma Scaleと,慢性期Glasgow Outcome Scale値が相関すると報告した。
日本側の演者である安藤氏は,大学病院の救命・救急センターで脳外傷患者に対する身体面および認知面へのリハ治療を提供した経験を報告。受傷後1か月の臨床所見から長期的予後を判断することは困難であるとして,脳外傷患者に対しては急性期から慢性期まで,医療と福祉にまたがる組織的対応が必要と示唆した。
一般にシンポジウムは,パネルディスカッションのようにテーマを絞り込んで演者が討論を交わす場ではなく,各演者がそれぞれの問題意識を持って研究成果や経験を披露する場である。この脳外傷リハシンポジウムにおいて各国の演者が選んだテーマは,就労,地域,麻痺手の治療,家族への対応,障害評価,脳外傷リハシステムと多岐に及んでいた。
Groswasser氏は脳外傷リハのエキスパートとして,それぞれの発表に座長席で小声の発言を繰り返していたが,結局時間がなく意見を控えることになった。例えば脳外傷リハ先進国では,予後評価法としてGlasgow Outcome Scaleを使用しなくなっていることがあげられる。脳外傷者の家族に,障害受容の問題があるとすれば,家族の反応を科学的に調査すべきことなどの意見があったようである。関連して,米国Mayer氏の痙性手の治療の発表は,脳外傷に独自の問題でなく意表をつかれた感があった。しかし考えてみると米国では,すでに評価方法や,脳外傷リハのモデルシステム,医療から職業までさまざまな脳外傷リハプログラム,脳外傷患者組織,インターネットなどを利用した豊富な情報源が整っており,これらの事柄が関心事となった時期は過ぎているのかもしれない。このあたりを実感することも国際会議に参加する意義であると感じた。
