ペンシルベニア大学留学日記
長浜正彦(日本医科大学6年)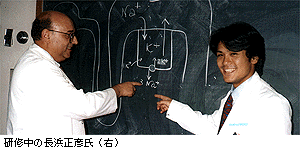 私は日本医科大学の6年生である。1997年7月,私は母校に1年間の休学届けを出して米国東海岸にあるフィラデルフィアにやって来た。ペンシルベニア大学医学部で交換留学生として1年間,臨床実習と臨床研究のプログラムに参加するためである。
私は日本医科大学の6年生である。1997年7月,私は母校に1年間の休学届けを出して米国東海岸にあるフィラデルフィアにやって来た。ペンシルベニア大学医学部で交換留学生として1年間,臨床実習と臨床研究のプログラムに参加するためである。
私が留学を決意したのは約1年前の夏で,それ以前は,自分が学生の間に留学しようなどとは夢にも思っていなかった。4年生の冬に,たまたまアメリカ旅行をした旅先でペンシルベニア大学医学部の浅倉稔教授と出会い,フィラデルフィア小児病院の血液科の回診に加わらせてもらった時,アメリカの医学教育のすごさに“電気ショック”を受けたのがすべての始まりである。
学生時代はもっぱらラグビーに専念していたので,医学の面でも,英語の面でもアメリカに行く準備は何1つできていなかった。その私がこの1年間,どのように準備をしてきたか,また現在アメリカでどのような教育を受けているか書いてみたい。
■留学準備編
英語,英語,英語
まず,何といっても英語である。1年前の私の英語は,決してアメリカへ行ける実力ではなかった。浅倉教授に頼んで5年生の夏に,もう1度フィラデルフィア小児病院に行き,感染科のローテーションに加わらせてもらったが,彼等の言っていることはほとんど理解できなかった。アメリカの臨床現場を見学する機会を2回持ち,相当の語学力を身につけなければアメリカで臨床実習するのは不可能だと感じた。
それからというもの私は,参考書は英語で読み,試験も英語で解答するようにした。しかし,すぐには努力は実らないもので,それは再試の山を築いていくに過ぎなかった。また,臨床実習の間も回っている科のジャーナルや文献を英語で読むように努めた。その科に特有の単語だとか言い回しがあるもので,それをまねてケースレポートは英語で書いて提出していた。しかし,書きっぱなしではあまり意味がなく,できれば添削してもらい間違いを訂正する必要がある。幸い私にはネイティブのアメリカ人の友人がいたので,英語に関しては彼に添削してもらえたし,また,どの科にも私の書いたレポートを熱心に添削してくださるドクターが誰かしらいるものである。
こうして読むことと書くことに関しては,少しずつできるようになった。問題は話すことである。私は機会があればプレゼンテーションなども英語でやらせてもらった。人前で英語を話すのに必要なのは語学力ではなく,繰り返し練習することによって得られる自信と度胸である。発表前日には夜遅くまで何度も練習した。英語でプレゼンテーションをさせてくださった先生方には本当に感謝している。
アメリカで臨床実習をするには,英語による患者とのコミュニケーション,ケースプレゼンテーション,ドクターとのディスカッションが必要不可欠となる。英語放送のラジオを聞いたり,2か国語放送の映画を英語で見たりしたが,臨床実習中はなかなか思うように時間がとれなかった。
私の場合は幸い先に述べたネイティブのアメリカ人に3か月間,わが家に滞在してもらい英語で寝食を共にした。その間に相当に鍛えられたと思う。3か月間,彼の滞在を許してくれた両親に感謝している。
日本での臨床実習
アメリカの医学生がとてつもなく優秀であることを知っていたので,この1年間で少しでも追いつかなければと臨床実習では真面目に勉強もした。私の場合は教科書的な知識からして不足していたため,病棟や手術室は勉強の材料をいただくところで,そのあとすぐに図書館に行って最新の文献等も含めて徹底的に勉強するというスタイルであった。同じ卓上での勉強でも単に教科書を読むのと,実際に患者やカルテを目の当たりにしてから勉強するのとでは当然,印象も能率もちがう。私には治療の手技や診察の技術を身につける余裕はなかったし,学生が完全にお客さんである日本の臨床実習では限界があると思う。
■渡米後編
渡米後の1週間
浅倉教授から「学校の授業は9月から始まるが,7月からフェローの教育が始まり,毎日そのレクチャーに出席させてもらえるようにしたので早めにアメリカに来たらどうか」という連絡を受けたので,1997年7月8日,私は期待と不安の入り交じった複雑な気持ちでアメリカへ出発した。
ペンシルベニア大に到着して私はまず大学の大学院生用の寮に行った。寮とはいっても16階建てのホテルのような建物で,入り口で名前を言うと鍵などが用意されていた。部屋は清潔で勉強机もあり,非常に快適でほっとした。
到着2日目,私はまだ時差ボケ気味の赤い目をしたまま,副学長であり,この交換留学プログラムのボスでもあるSilverberg教授に挨拶にいった。教授はとても温かく迎えてくださり,寮のこと,安全面のことなど気にしてくださった。日本の医学生が1年間という長い期間留学するのは稀なことであり,母校の日本医大のこともいろいろと聞かれた。私は母校が日本で最も歴史のある私立医大であること,5つも病院を持っていることなどたくさんアピールした。アメリカに来て“謙遜”などという言葉は通用しないからである。
翌日,腎臓内科のMedio教授にも面会し,これから当分の間,アテンディング・フェローと学生からなるチームの回診に加わらせてもらえることが決まった。思いがけなく教授に白衣をいただいた時は,正直言って跳び上がるほど嬉しかった。
こうして私は,渡米5日目から腎臓内科の白衣を着て,聴診器片手に病棟で過ごすこととなった。前日には白衣を着て,何度鏡の前でポーズをとったことだろう。後から知ったのだが,学生は皆ジャケットタイプの白衣を着るもので,私のいただいたロングコートを着ることはドクターであることの象徴であるらしい。それを聞いて私がジャケットタイプの白衣を買いに走ったのは言うまでもない。
病棟での1日
病棟では,まず最初に腎臓に関するコンサルテーションを行なうグループに加わった。アメリカの病棟には日本のような,いわゆる“受け持ち”制度はない。どんな患者もまず,主にレジデントからなるプライマリ・ドクターのチームによって診察・検査される。そのうえで各科の専門家のチームがコンサルテーションの依頼を受けて患者の診断や治療を指導するのである。例えば,心筋梗塞で入院した患者は病棟の医師団によって管理されるのと同時に,循環器のチームによってもフォローされる。この患者が心不全を起こして体液管理がうまくいかなければ腎臓のチームがコンサルトを受ける。そのうち呼吸困難が肺炎によるものであると判明すると呼吸器科と,そして感染科も診察に加わる。このようにしてあらゆる専門家が,網の目のようになって1人の患者を診ている。
私の属する腎臓チームは助教授以上のアテンディング・ドクター1名,医学部を卒業して3年間のレジデントを終了したフェロー・ドクター1名,医学部4年生(日本の医学部6年生にあたる)1名,それに私の4名であった。回診はこのメンバーで毎日行なわれ,日本のような大名行列はない。
朝8時からフェローのための講義に出席することから1日が始まる。その後,病棟へ行き,フェローとともに患者を診て回るのだが,彼は朝7時から来てすでに一部の患者の診察を終了している。カルテで患者の状態を把握し,コンピュータでその日の検査値をチェックしてから一緒に患者のもとへ行く。フェローはしばらく患者の訴えを聞いたあと,慣れた手つきでまさに頭のてっぺんから爪先まで全身の診察を始める。
私の印象としてはアメリカの医師は手と聴診器だけで患者の病状をかなり正確に把握する技術を持っている。日本では見たこともない診察方法を見るのもめずらしいことではなく,その手つきたるや,まさに芸術の域に達している。ビデオで撮って家で練習したいくらいであった。
ひと通り診察を終えて病室から出ると,「何か質問は?」ここで黙っているわけにはいかない。基本的なことであろうと何であろうと,つたない英語で必死に質問を浴びせた。たまに,「それはいい質問だ」と言われると嘘でもうれしいものである。
午前中にひと通り患者の診察を終えると,これまた英語しか話せない気の抜けないランチが待っている。フェローからはレジデントプログラムのよい病院や外国人の受け入れられやすい科の話,学生からは黒人社会の話やスラングなど,ここでも学ぶことは多い。午後にはアテンディングと再び回診するが,そこでのディスカッションについては後で述べることにしよう。
アメリカのメディカルスチューデント
アメリカの医学生は優秀である。優秀というのは,単に教科書的な知識があるだけでなく,疾患に対する臨床的なアプローチができるということと,何よりも彼等は診察の仕方を熟知している。日本で聴診器をきちんと使いこなせる医学生がいったいどれだけいるだろうか。4年生(最高学年)ともなれば一人前の医師のように診察でき,知識も経験も日本のレジデントを凌ぐであろう。アメリカの医学部4年生は日本のレジデント2,3年生と同じレベルであると聞いたことがあるが,これは本当である。
病棟における医学生は単なるお客さんではなく,忙しいフェローの完全な戦力として患者の診察にあたっている。フェローは忙しいながらも熱心に学生の指導にあたり,自分の片腕として活躍してくれる学生を信頼している。そして,学生もその期待に応えるべく一生懸命仕事をする。お互いに助け合うことにより,日本の堅苦しい上下関係とは違う,さわやかな関係を築いていくのは見ていて羨ましかった。
英語も不自由で臨床経験もないに等しい私は,そんな彼等の一挙手一投足をまねているだけである。どうやって病歴をとるのか。どうやって診察するのか。どうやってカルテを書くのか。どうやって症例報告するのか。どうやってディスカッションするのか。彼等に追いつくにはひと筋縄ではいかないが,それこそトイレにまで付いて行く勢いでくっついている。
アメリカの医学教育
アメリカには英語を母国語としないで頑張っている人たちがたくさんいる。したがって,異国から来たドクターに会うのもめずらしくなく,統計ではアメリカのドクターの12%が外国の出身者である。彼等は英語を母国語としない人間の不安や困難を理解していて,概して私に優しく,適切なアドバイスをしてくれる。例えば,カルテは略語と記号ばかりで外国人のわれわれには,まるで暗号文のように見えるが,それを一緒に解読しながら読んでくれたりした。アメリカのドクターは教えることやディスカッションをすることを楽しんでいるようである。廊下で,階段で,エレベーターで,教室と同様の講義が展開される。こちらが質問すると逆に何倍にもなって質問し返されることもあるが,日本と決定的に違うのは基礎医学に裏打ちされた理論があり,最後には必ず納得する答が返ってくることである。
たびたび前日に診た患者に関する論文のプリントが渡されるが,著者がわれわれのアテンディングであったりすることには圧倒された。つまり,名著の筆者であるドクターに直接教えてもらっているわけである。世界的に有名なドクターに会うこともめずらしいことではない。
そして,教育システムが素晴らしい。教育の題材は常に入院してきた患者である。毎日行なわれる回診者の前にミーティングがあり,そこで個々の患者についてディスカッションがなされる。フェローが患者の病状,検査所見についてひと通り述べるとアテンディングが学生に質問する。「ここまで聞いて何を考える?」,「最近の尿量減少,体重減少,そして嘔吐から急性腎不全による尿毒症を考えます。降圧薬の服用も,起立性低血圧もないので腎性か,腎後性だと思います」,「よし。それでは,この後どういう検査をする?」,「尿の性状を調べます」
ここでフェローから尿検査の所見が述べられた後,「さあ,軽度の蛋白尿,高度の血尿はあるが,円柱はなかったようだ。何を考える?」,「円柱がないので腎性の急性尿細管壊死は考えにくいです。白血球がやけに多いのに熱もないし,尿が停滞しているのかなあ……。」,「高齢の男性が腎後性の病状を呈したら考えなければならない原因があるだろう。」,「あ,前立腺か」
こういった具合にして疾患を把握していき,前立腺肥大症では尿路の通行障害を解消した後でも場合によっては透析が必要となること,しばらくは膀胱からの出血があること,そして腫瘍マーカーを必ず検索しなければならないことも体験していく。
私が同じように質問された時は絶句した。しかし私が的外れの回答をしても,なぜその検査をする必要がないのか,なぜ別の考え方をしなければならないのかを丁寧に教えてくれるので,病気へのアプローチの仕方がだんだんとわかってくる。
コミュニケーションがうまくいかないときは,図を描きながら説明してくれる。多少知っていることや,聞いたことがある内容ならば理解可能だが,聞いたこともない電解質の複雑なメカニズムをその場で理解するのは非常に難しい。たいてい,家に帰ってから教科書を読み,翌日質問して初めて理解できる。
プレゼンテーション
こちらに来てから,週に1回のペースでプレゼンテーションをさせてもらっている。プリントを作ったり,発表の練習を繰り返してしたりと楽ではないが,そういう訓練は日本でも何度かしてきてはいたが,こちらのプレゼンテーションのほうがはるかに膨大な準備を必要とする。まったくもって当たり前のことであるが,正確な英語の発音をしないと通じない。日本で使っているカタカナがいかにいい加減か思い知らされる。英語を,しかも医学的な複雑な内容を,相手の反応に注意しながら決して一方通行にならないように発表するには相当の労力がいる。
プレゼンテーションも2回目までは,どんなに下手でもアテンディングは黙って開いてくれ,最後には必ず誉めてくれた。しかし3回目は違った。少しでも不明な箇所があると即座に指摘され,矢継ぎ早に質問された。フェローがアテンディングに尋ねたことでさえも,彼はまず私に答えさせた。こうして私は2時間ほどの集中攻撃を受けたが,あれは「もうお前はお客さんではないぞ」という手厚い洗礼だったのだろうか。その後から彼等との距離がやけに縮まった気がする。
現在の状況
アメリカで臨床をするのは,覚悟はして来たものの,正直言って相当にハードだ。1年間かけて日本で準備してきたが,率直な感想は,英語の準備も医学の知識も不十分であった,ということである。日本ではかなり理屈っぽく勉強したつもりだが,最新の文献を読んでいる暇があったら,基礎医学の病態生理をもっと把握しておくべきだった。基本も知らずに目新しいことを覚えてもまったく意味がないということを今さらながら痛感している。
英語も,もう少し通用すると思っていたが,甘かった。いろいろ反省点もあるが,日本での準備期間がなければアメリカで臨床をするのは確実に不可能であった。私が言いたいのは準備してしすぎることはないということである。英語はもうひたすら訓練するしかないのであろう。たちまち上手くなる方法があるのならば私が教えてもらいたい。よく言われる。「3か月経てばどうにかなる」というのを信じてただ待つのみである。それ以上深く考えても滅入るだけで,私の場合は,3か月経って状況が変わらなければ日本に逃げ帰ろうと開き直ることにしている。
辛いことも多く,歯を食いしばって頑張っている自分に気づく時もある。99%がタフでも,残りの1%で勇気づけられることや感激することがあれば,そちらに集中することによって何とかやっていけると信じ,念じて言い聞かせている。
人間は不思議なもので,あまりに大変なことが多いと少々のことを大変に思わなくなってくる。いちいちストレスを感じていたら,とっくに寝込んでいるであろう。
しかし,同時にアメリカという国はエネルギーとかパワーを私に感じさせてくれる国でもある。ドリームやチャレンジという言葉の似合う国である。しなければならないことや,できるようにならなければならないことを考えると気が遠くなるが,毎日がエキサイティングであり,刺激に満ちている。目の前のことだけに集中して,昨日より今日,今日より明日と,少しずつ前進していこうと思う。
以上アメリカ留学1か月の感想を書いたが,日本の学生諸氏の参考になればと思っている。昨日,アデンディングから,「見学は今週で終わり。来週から君1人で患者を診るのだ。」と言われているのでその様子は,次の機会に書いてみたいと思う。
最後に,私の留学に際していろいろと温かく御尽力いただいた母校の早川弘一学長,小川龍教授,飯野靖彦助教授,それから今回の留学をアレンジしてくださり,このような素晴らしい経験をするチャンスを与えてくださった浅倉稔生教授に心から感謝したい。
